冬期講習面談:中学受験をしない小学生保護者様面談を成功させる「見せる」面談手法
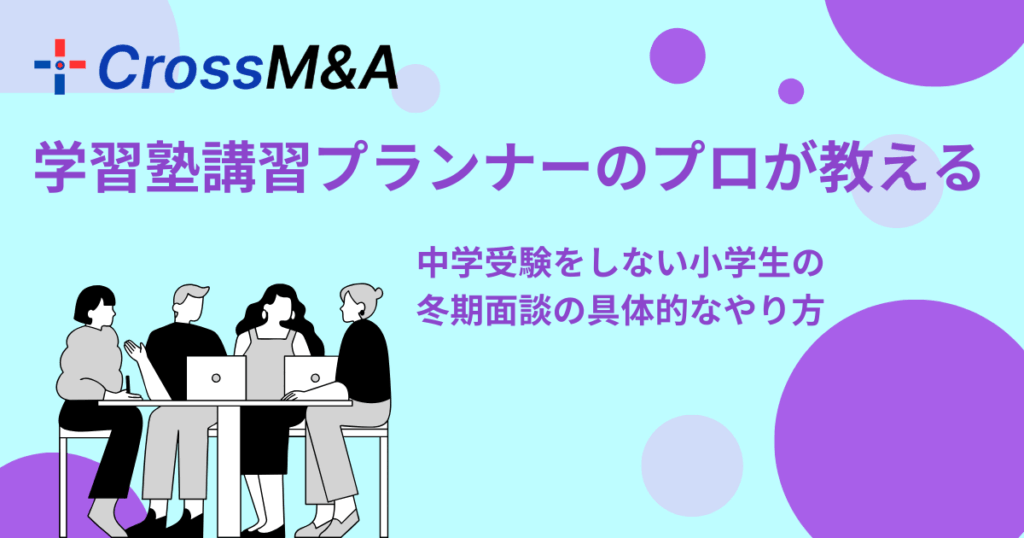
冬の足音が聞こえ始めてから・・ではなくて、残暑が厳しくある中で、塾業界では冬期講習の準備が本格化します。
まさに9月、今です。
多くの学習塾にとって、冬期講習は新規生徒獲得と既存生徒の継続学習を促す重要な機会です。今回、本記事では「中学受験をしない小学生の冬期講習前の面談」にスポットを当てて参ります。
保護者の関心を引き、受講に繋げるためには、繊細なアプローチが求められます。
例えばよくあるのが、教室で新しい講座が開始されたとします。その案内をしたいがために、単に「新しい講座があります」と伝えるだけでは、保護者の心には響きません。
なぜなら、保護者が求めているのは、短期的な学力向上だけではなく、もっと広範で長期的な子どもの成長だからです。この面談を成功させる鍵は、ただの商品説明ではなく、子どもの成長を共に描くストーリーを提示することにあります。
変わる小学生の学習環境:保護者の「なぜ?」に答える
小学生の面談のときに注意しなくてはいけないのは、中学受験をされる生徒さんの保護者との面談と、中学受験をされない、あくまでも学校補習目的の保護者との面談は全く異質で、全然違うアプローチであるという点です。
言葉に出して言われるか、心の中で思われるかは別として
「うちの子は中学受験をしないから、そこまでの学習は必要ないのでは?」
首都圏小学生の82%は中学受験をしません。つまり小学生のほとんどは中学受験をしないものだという前提からストーリーを考えていく必要があります。
ここで皆さんに質問です。
・A:中学受験をされるお子さんの保護者面談
・B:中学受験をされないお子さんの保護者面談
さて、お聞きします。
現在、学習塾を経営されているオーナーさん、または教室長、塾長という立場の方がご縁あって本記事をご覧いただいているかと存じます。
どちらの面談のほうがやりやすいと思いますか?
長く運営をされている方、去年、一昨年と一連のお仕事を経験されたオーナーさん、教室長、塾長であれば、すぐに答えを「A」のほうがやりやすい!とお答えいただけるかと存じます。
そうですね、私も同感ですし、感覚以上に、実際そうです。勘でモノ言っているわけではありませんので、まさしくA、これが答えです。
さらに、この答えのなぜかに回答する形式をとりますとさらに長い文章になってしまいますので、ここでは話をシンプルに答えはAとだけお伝えしておきます。
Bの方、中学受験は考えていないという生徒さんの保護者様とは面談での話で、よほどしっかりと想定したストーリーを作っておきませんと、下手したら面談で伝えるべきないようが20分ぐらいで終わってしまって、「これ以上話すことがない」という事態になり、聞き手の保護者も「いったいこの面談はなんだったのかしら」という感想しか残りません。
対して、中学受験となれば冬期前のこの時期の面談は、いよいよ志望校を確定させて、受験日となる12月から1月(2月前半)までの学習計画を提示するなど、話す内容が多くなるためそれなりに面談も盛り上がります。
中学受験をしないお子さんの保護者様に対して、学校の先生が行うような面談だとしたら、そこに価値観は見いだせないので、だんだんと
「今回、うちの場合は面談はパスでいいです」
なんていうことになってしまうこともあります。
この言葉が出てきたら、イエローカードが発せられたと思っていいです。それは何故かというと、前回実施(例えば夏の面談)が、つまらない内容だったからなのです。
したがって、中学受験をしない生徒さんの保護者様との面談をとても有意義なものにしていけるかどうかは、オーナーさん、教室長、塾長の取り組み、事前の面談準備次第、トーク次第ということになります。
現代の小学生を取り巻く学習環境がどのように変化しているかを理解し、それを保護者に分かりやすく伝えていけるようにしたいものです。
では具体的に、どんな内容をお話するといいのかを以下示してまいります。
1.小学校の学習内容の変化(※マクロ要素)
まず、小学校の学習指導要領が大きく変わっていることを伝えましょう。プログラミング教育の必修化、英語教育の早期化、道徳の教科化など、教科の枠を超えた「生きる力」を育む教育へとシフトしています。
特に注目すべきは、思考力・表現力・判断力を問う問題が増加している点です。
従来の「知識の暗記」だけでは太刀打ちできない問題が、算数や国語の教科書に散見されるようになっています。これは、その先の高校入試や大学入試、ひいては社会で求められる力が変化していることに起因します。
たいていの場合、こういうマクロ要素のお話というのは、退屈です。
退屈がゆえに、この内容を「言葉だけ」で伝えようとしたら、余計に退屈で聞くことさえも面倒な話となってしまいます。
ですから以下絶対に必要なこととして、
①根拠となる資料を用意する
②資料の出所を明確にする(※例えば、文部科学省など)
③線を引きながら、読む
④数字面のデータがあれば、それを強調材料として使う
この4つを是非、試してみてください。そうすると、マクロの退屈なお話が、少なくとも注目すべきお話に切り替わります。
2.小中接続の重要性(※マクロ要素)
「小中接続」とは、小学校と中学校の学習内容や学習方法のスムーズな移行を指します。昔は、中学校に入ると一気に学習内容が難しくなる「中1ギャップ」が問題視されていました。しかし現在では、小学校で学んだ内容が、中学校の学習の土台となることがより明確になっています。
例えば、小学校の算数で学ぶ「割合」や「速さ」は、中学校の数学で方程式や関数を学ぶ上で不可欠な概念です。国語では、小学校で習う要約力や論理的思考力が、中学校での複雑な文章読解や小論文作成に直結します。
この「小中接続」という言葉を使って、小学校で身につけるべき基礎力が、中学校での学習成果を左右することを伝えましょう。冬期講習は、このギャップを埋め、スムーズな移行をサポートするための絶好の機会です。
これもマクロなお話です。いわゆる背景であるとか、そうなって原因はこうですよというような内容となります。
若干ヒントめいた形で書いたのが、上のオレンジ色で書いた具体例です。
さて、ここでもこんな準備をしておくとよいですよ!というものを紹介しておきます。
①小中接続についてのわかりやすい記事
②小学校高学年の生徒の保護者様向けであれば、中学の内申点の仕組みも有効
③実際に教科書や教科書準拠教材の「目次」部分のコピーと実際の難易度が高めの問題のコピー
小学校4年生ぐらいまでなら何とかご自宅でのフォローもできていた保護者様も、4年後半とか5年、6年になると、一転内容がかなり難しくなったりします。
昔の小学生内容とは一線を画すどころか、かなり昇華し内容的に、「え、これって・・・中学で習う内容じゃないの?」ぐらいのものも登場します。
ですから、その「実態」を面談のときに「言葉だけじゃなく」資料として提示するのです。
上のマクロ内容のことでも言葉だけで伝えたならば、記憶にもインプットされない、ただの素通りされる世間話になってしまいますが、しっかりと権威ある機関などが書いた記事を用意したり、実際に目次や問題を見せて、今はこんな風になっているというところを目で見てもらうことで、
「小学校の内容なんて、学校の授業を聞いてさえいたら何も困らないだろうに」という感覚をもった保護者様に、新しい理解を植え付けることが出来るのです。
お疑いであれば、赤字で書いた関連資料を用意して、トークを考えてみてください。もしそのトークが思いつかない場合などはいつでも連絡いただければ、資料にそったトークスクリプトを面談に間に合うように即時作成いたします。
↓ ↓ ↓
上に書いた内容は、マクロっぽいことです。塾の責任者がある程度、オーソリティのある話をする際には、多少マクロも入れたほうがいいのです。
小学生のお子さんの面談でそこまで?と思わないでください。
対応するのはお父さんかお母さん、またはご両親ですよね。つまり相手は大人です。さて、続きまして、軽くストーリーと言いますか、話す順番についてです。これは人それぞれ自由ですが、相手が話に乗っている状態にするためには、いきなり本題ではなく、本題にスムーズに移行できるような流れにしたほうがいいです。
ストーリーで引き込む面談構成
面談の冒頭で、いきなり冬期講習のパンフレットを見せるのは得策ではありません。まずは保護者の関心を惹きつけ、子どもの学習に対する課題意識を共有することから始めます。
1.オープニング:共感と現状の把握
- 共感の言葉:「〇〇さん、お忙しい中お越しいただきありがとうございます。〇〇君(ちゃん)も毎日学校と習い事を頑張っていらっしゃいますよね。今日は、〇〇君(ちゃん)の今の頑張りを、さらにその先の成長に繋げるお話ができればと思います。」
- 現状のヒアリング:「最近、学校の勉強で何か気になることはありますか?」「特に算数や国語で、どんな問題に躓きやすいと感じますか?」
2.課題の提示とストーリーの導入
ヒアリングを通じて得た情報をもとに、具体的な課題を提示します。
- 例(算数):「〇〇君(ちゃん)は、計算は速いのですが、文章問題になると少し時間がかかりますね。これは、問題文を正確に読み解く力と、そこから必要な情報を抜き出す力に課題があるのかもしれません。これからの時代、ただ計算できるだけではなく、『どのように考え、答えを導き出したか』を説明する力が重要になってきます。冬期講習では、この考える力を養うことに重点を置いた授業を行います。」
- 例(国語):「読書は好きなようですが、感想文や要約が苦手なのは、文章の全体像を捉える練習が足りないからかもしれません。この冬に、論理的に文章を読み解くトレーニングをすることで、中学校の国語だけでなく、他の教科の文章問題も得意になります。これは、将来、自分の考えを明確に表現する力に繋がります。」
この段階で、保護者は冬期講習が単なる復習ではなく、子どもの将来に繋がる意味のある学習機会であることを理解し始めます。
上手く言えませんが、講習のための講習ではなくて、子どもの将来のために今のうちにというような感覚でいいと思います。
学習塾ですので、やはり教科学習のことがメインになるのですが、中学受験をしない小学生の場合、理科とか社会を話題にするよりも
「算数」「国語」「英語」を主軸においたほうが、保護者との意見が一致しやすいです。
個別提案:教科ごとの追加提案方法
冬期講習の基本コースに加えて、保護者の課題意識に応じた追加提案は必須です。ただの「追加」ではなく、「より良い学習のために必要な選択肢」として提示しましょう。
1.算数の追加提案:思考力を鍛えるコース
多くの保護者が、子どもの計算力向上を望んでいます。しかし、提案すべきはそれだけではありません。
- 提案内容:「思考力・応用力養成講座」や「論理パズル・文章題特訓」といった講座を提案します。
- 提案方法:「〇〇君(ちゃん)は計算力は素晴らしいので、冬期講習ではさらに応用力を伸ばす講座を一緒に受講しませんか?この講座では、頭の中で考えを整理する『思考の組み立て方』を学びます。これは中学の数学で難解な図形問題や関数問題に取り組む上で、大きな強みになります。」
- 保護者のメリット:単なる計算力向上に留まらない、真の算数力を身につけられると納得してもらえます。
またはズバリ、単元強化の内容にすると、上記の新感覚学習の提示よりも受け入れられやすいです。
例えば、「速さの問題」「比の利用」「図形」の3分野です。この3つは、たいてい、どの保護者にも「ああ~確かに」と受け入れられます。
苦手な子が多いからです。図形についていえば、女子生徒の場合は9割は苦手意識をもっていることが多く、「例えば図形など・・・」このワードを発するだけでも保護者様は「あああ~~~」と言います。
つまりうちの子は確かに図形は苦手だわという思い当たるフシがあるからです。
このようになると、面談もそれなりに盛り上がる内容に変化します。
2.国語の追加提案:読解力・表現力を磨くコース
国語は「勉強方法が分かりにくい」と保護者が感じやすい教科です。そのため、具体的な学習方法を示すことが重要です。
- 提案内容:「物語文・説明文読解講座」や「表現力アップ!作文・小論文講座」。
- 提案方法:「〇〇君(さん)は読書が好きなので、その強みを活かして、さらに深く文章を読み解く力をつけましょう。この講座では、筆者の意図を読み取るコツや、自分の考えを論理的に表現する方法を学びます。中学に入ると、どの教科でも長文を読み解く力が求められます。冬休みを利用して、今のうちに差をつけることができますよ。」
- 保護者のメリット:国語の勉強が「ただ読書をするだけ」ではなく、具体的なスキルとして身につけられることを理解し、将来に繋がる投資だと感じてもらえます。
サブアドバイスとして申し上げると、国語の追加提案は、算数や英語よりもちょっと難易度が高いです。例えば、うちの子は読解力が弱いと保護者が認識をしていたとしても国語を追加講習するというのは、抵抗があるようです。(そこまでして・・・)という感覚かもしれません。
ところが、もっとも琴線に触れやすいのが次の英語ですので、英語の項目はよく確認しておいてください。
3.英語の追加提案:早期スタートの重要性(※ここの項目は超重要)
小学校での英語教育が必修化されたとはいえ、中学校の本格的な英語学習についていけるか不安を感じる保護者は少なくありません。
- 提案内容:「聞く・話す・読む・書く、総合英語講座」。
- 提案方法:「中学校の英語は、一気に語彙と文法が難しくなります。冬休みの間に、『英語って楽しい!』という体験をすることが、中学での学習意欲を維持する上で非常に重要です。この講座では、ゲームや歌を取り入れながら、聞く・話す力を中心に、英語に親しむことができます。中学校で良いスタートを切るための準備として最適です。」
- 保護者のメリット:単なる英単語の暗記ではなく、英語の楽しさを知ることで、子どもの学習意欲が自然と高まることを期待してもらえます。
どのような生徒さんにも「英語」の話題は振り向けていきましょう。オーソドックスに総合英語という形で英語を教科としてしっかりと学んでいく通常授業へのいざない的にやるのが一番なのですが、
英語に興味をもっている保護者の場合、英語は「英会話塾に通わせている」ケースも多いのです。その際は、英会話教室を否定しないで、英会話を学ぶことと、文法や単語、熟語、読解を主体にした英語学習との相違点をソフトに伝えていくようにします。
究極は、会話などのSpeaking をテスト項目にする時代はもっと先になるという話をしてもいいです。
Speakingのテストは試験的に都などが行ったりしていますが、採点はどうするのかという点と音声データを保存しなくてはいけないため、その膨大なデータをどう格納していくのかという課題などがあって、実用化はまだまだ先です。
今の受験はほとんどがreading ですから、読む力が重視されていること、そのためには文法が理解されていて、熟語がわからないと解けないこと、語彙力も以前も格段に求めらえていることなどを伝えていくとよいです。
この場合も、口頭で、こうこうこうなんですよ、と言うのではなく、資料を用意して線を引きながら伝えるようにしましょう。
そして、こうもっていきます。
「お母様、太郎君に英語を学んでもらいましょう。英検をとったほうがいいです」
はい、英検の話に全部もっていくといいでしょう。
小学生で英検4級取得、始めるのが早ければ3級取得までは普通の小学生でも十分いけます。
そしてここで「中学受験のお子さんの勝つ方法」を教えるのです。
中学受験の生徒さんはたいてい4科目(算数、国語、理科、社会)の受験がオーソドックスです。中には英語を選択できる学校もありますが、中学受験の英語は難しくないのです。ですから差が出ません。
そもそも中学受験で英語を試験科目選択するのは、よけいにいばらの道になるので、4科目受験を推奨するのが普通です。
中学受験向けのすごい学習をしている子供たちも英語になると、かなり弱いことが多いです。
従って、中学受験をしない、だけど勝てる方法として英語を先行学習してしまいましょう!という内容で話をもっていきます。
締めくくり:子どもの「今」が創る「その先」
最後に、面談全体を総括し、保護者の背中を押す言葉をかけます。
- 総括:「本日ご提案させていただいた冬期講習は、〇〇君(ちゃん)が今持っている力をさらに伸ばし、中学校での学習をスムーズに進めるための準備です。中学受験をしないからこそ、この期間を有効活用し、焦らず、着実に基礎学力と応用力を身につけていくことが、その先の高校受験、そして社会で活躍するための土台となります。」
- クロージング:「私たちはお子様の『今』の頑張りを最大限に引き出し、『その先』の可能性を広げるお手伝いをしたいと考えています。ご検討いただけますよう、よろしくお願いいたします。」
この面談は、単なる冬期講習の勧誘ではありません。子どもの将来を真剣に考える保護者に対し、寄り添い、共に子どもの成長を応援する姿勢を示すことが何よりも重要です。ストーリー性を持たせた丁寧な説明は、保護者の信頼を勝ち取り、冬期講習の受講、そしてその後の継続学習へと繋がる、強力な第一歩となるでしょう。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目

2025年09月26日
塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について
#入塾面談
#塾の成功
#塾経営
#塾講師
#学習塾
#学習塾運営
#期限厳守
#生徒指導
#良質顧客
#顧客育成