学習塾経営の真髄:突飛な企画より、塾として求められる普通の企画が一番
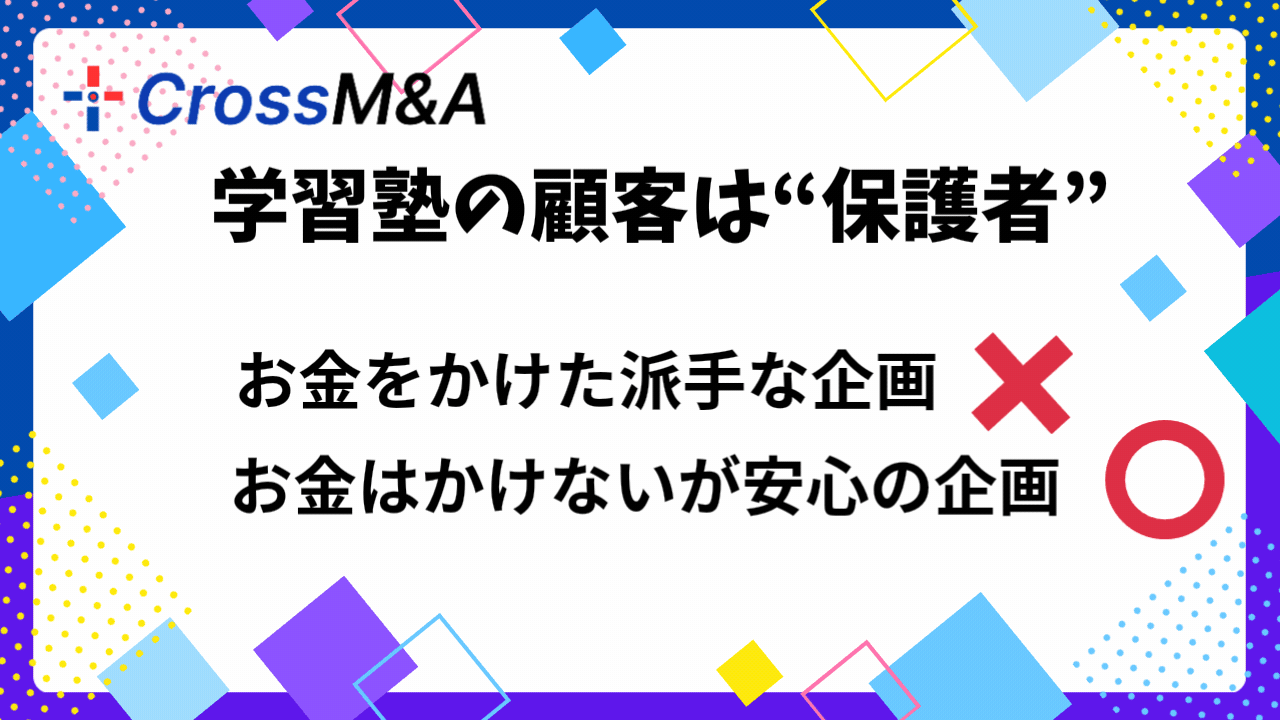
学習塾の経営と聞くと、最初のうちは右も左もわからないことが多いため、基本に忠実にしかも遮二無二運営に向き合います。ところが慣れてくると多くの人が「生徒を惹きつける斬新なアイデア」や「他の塾にはないユニークなイベント」を想像しがちです。
確かに、新しい風を吹き込むアイデアは重要です。CROSS M&A(クロスマ)のアドバイザーも塾経営時に同じように考えました。
長年、アレやコレやとやっていくと、企画した内容が「あたり」の場合もあれば、「はずれ」の場合もあります。
そして一つの結論に達します。
本当に塾を成功に導くのは、そうした華やかなアイデアではなく、むしろ地道で泥臭い、日々の積み重ね、企画であれば普通の企画が一番であると断言します。
「自分はアイデアマンだ」と自負する塾長や教室長は少なくありません。私自身もそのきらいがあるかもしれません。そして、実際に湯水のように溢れ出すアイデアは、時に人を魅了しますし、自分に酔います。
夏期講習で特別企画のイベントを実施したり、季節の変わり目にSNSで目を引くキャンペーンを打ち出したり。これらの企画を立てることは、非常にクリエイティブで楽しい作業です。
しかし、その楽しさが、本来の目的である「生徒の学力向上」や「保護者との信頼関係構築」から逸れてしまうと、それは単なる自己満足に過ぎなくなります。
華やかなアイデアの落とし穴
例えば、生徒を飽きさせないようにと、突拍子もないイベントを企画したとしましょう。それは、もしかしたら一時的に生徒の関心を引き、話題になるかもしれません。しかし、そのイベントが単なる「人寄せパンダ」的なものであれば、その効果は一過性のものです。
なぜなら、保護者が学習塾に求めるものは、エンターテイメントではなく、確かな学力の向上と安心感だからです。
奇抜なイベントで一瞬盛り上がっても、生徒の成績が上がらなければ、保護者は「この塾は遊びばかりしている」と評価するでしょう。
結果として、生徒は定着せず、口コミも広がりません。そのアイデアは、塾のブランド価値を高めるどころか、かえって信頼を損ねる原因にもなりかねないのです。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
学習塾のチラシや、ネット上で出ているリスティング広告、または塾関連のフリーペーパーなど、関連性があれば、ランダムで紐解いてみてください。
どこを見ても、何を見ても「真面目」な感じがします。
どこを見ても、遊びの要素はありません。学習一本、勉強一本です。
私がかつて関わった塾で、生徒を獲得したいがための遊び要素を入れた企画がありました。グループで話し合って、どうしたら「この企画が盛り上がるだろう」というテーマで話し合ったりもしたようです。
この最初の発想となる「企画を盛り上げるため」という着眼点がそもそも間違っていたのです。今から思えば「確かにこれは大失敗」だとすぐにわかることですが、当時はそれが間違いだとは思わず、「きっとみんな楽しむだろう、きっと盛り上がるだろう」というところに終始してしまいました。
喜ばせる企画には飛びつかないし、ほぼ誰も喜ばない
例えば、
何かしらキャンペーン的なものを実施して、〇〇賞として〇〇というプレゼントを合計〇名様へ!というものであったり、先着〇名様に〇〇を進呈!というようなもの、このような企画は、だいたい成功しません。
コストをかけた企画は、コスト倒れになることが多い
経営をしていると予算だとか、予算差異分析だとか、そういう言葉を耳にすることがあります。「予算」というのは、一定の目的のために計画を立てた費用のことを言います。
要するに「お金」です。
お金をかければそれなりの効果が・・・というのは、こと学習塾関連企画の場合には、期待するほどの効果はありません。
例えば、今、入手が難しいゲームコンソールが抽選でゲットできる!そんなイベントを学習塾でやったとします。そのゲーム機は、一台5万円だとします。
これを何とか5台用意して、25万円の予算計上をして実際にそれにまつわる企画を催したとします。さて、この企画は成功するでしょうか。
当然ながら切り口としては、
いついつまでに〇〇をしてくれた人に抽選で5名様に今話題のゲーム機〇〇をプレゼント!
こんな感じでしょうか。
結論から言って成功しません。
何故かというと、
学習塾の契約者は大人だからです。親御さんだからです。
例えば、10月までにご契約の方、抽選で5名の方に今話題のゲーム機〇〇をプレゼント!といくら声高にメッセージングしても失敗しますということです。
ただし、これが「もれなくプレゼント」でしたら、また違うかもしれませんが、そんなコストを出せる学習塾なんてそうそうありません。ましてや入手困難なゲーム機をそんなに簡単に、裏ルールがあるわけでもないのに入手できるはずがありません。
いずれにしても失敗するのです。
先の話に戻りますと、
子どもは「抽選」でもちょっとだけ盛り上がるかもしれません。(ほんの微量です)
しかし、学習塾を検討する大人はプレゼントを重視などしないのです。
今、これだけ多くの広告が湧き出る水のようにあちこちにあり、湧き出る泉のSNSにはどれが本物でどれが偽物なのかが区別判別がつかないぐらいの事態になっています。
こういう眉唾系に、ポンポンと飛びつく大人はどんどん少なくなっていますし、飛びつきません。
したがって、「お金をかけたらからこれは何かしらの成果が出るだろう!」ということにはならないのです。
さらに、とんでもなく重要なことがあります。
そして大人はわかっています。
「学習塾は月々にお金がかかる月額料金のかかるサービス」なのだということをです。
その計算をしっかりとしているので、「モノ」がもらえることに特段の感情は生れないことを是非知っておいてください。
視点と切り口は全く違いますが、2万円の給付を受けるのと減税と・・みたいのが議論されていましたが、この問題と少々似ています。
それよりも!
子どもの学力向上のための地道な企画のほうが100倍いい!
お金をかけなくても(塾側として無理に経費を使わなくても)よい企画というのは、やはり学習塾の学費をベースにしたお得感を見出せるかどうかです。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、
例えば月々35,000円の月額月謝の塾があったとします。これは保護者が支払うコストです。毎月に月額費用です。
お金に対しての感覚から見ると「モノを買うお金」と「サービスを受けるお金」は異なります。
35,000円で35,000円のものを買う
35,000円で35,000円のサービスを受ける
モノは目に見えて、尚且つその金額相当のものが手元に残ります。しかし、サービスは、油断しているとフワッと過ぎ去ってしまうかのような霞のようなものです。
実感がモノよりも希薄になってしまうのです。
ですから、サービスという金額イメージの中に「いかに付加価値的なものを印象づけられるかどうか」で企画を決定するときっとうまくいきます!
例えば、あるとき・・・35,000円で45,000円のサービスが受けられる企画があったとします。
これは保護者の琴線に触れるのです。
あくまでも
プレイヤーは子供、お金を払うのは大人です。
世の中のサービスであるとか、世の中の仕組みがわかっている大人の保護者をモノで何とかしようとするのは、そもそもが間違っているということです。
教室としてコストカットは徹底すべきです。
この企画をやれば、コストは20万円かかるけれど、顧客が〇名ゲットできるぞ!・・・・
誰が保証するわけでもないけれど、その掛け声が妄想的に闊歩したときに、一気に視野が狭くなってしまうのですね。
例えは、全く違いますが、「恋は盲目」みたいな状態になってしまうというです。投資したら倍返しできっと返ってくる「にちがいない」という妄想レベルのことなのです。
この企画をやれば、きっとこうなる!きっと子供が喜ぶ!
わかります。
私もその魔術にかかったことがありますので。
しかし成功はしません。
それよりコストをかけないで(コピー用紙と印刷代はかかりますが)当たり前のことを丁寧にやってあげたほうが長い目で効果が出ます。
はい、間違いなくです。

伝統的な「当たり前」の価値
では、学習塾の真の成功は何によってもたらされるのでしょうか。それは、華やかさとは真逆にある、「当たり前」を丁寧に、そして徹底的に行うことです。
学習塾は、そもそも「勉強を教える」場所です。その本質を忘れてはなりません。
生徒一人ひとりの学習状況を把握し、つまずいているポイントを特定し、個別最適な指導計画を立てる。そして、その計画に基づき、日々の授業で丁寧に解説し、演習を徹底的に繰り返す。定期テスト前には、出題範囲の分析を行い、生徒が確実に得点できるよう対策を練る。これらのルーティンワークは、決して派手なものではありませんが、生徒の学力向上に直結する最も重要なプロセスです。
考えてみてください。
保護者が学習塾に期待するのは、「うちの子が、あの塾に通ってから勉強の習慣がついた」「テストの点が上がった」という具体的な成果です。
この期待に応えるためには、奇をてらう必要はありません。むしろ、誠実で真摯な学習指導こそが、最も強力な武器となります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
これは、私が運営している学習塾の近隣の「とある進学塾(仮称A塾)」のお話しです。独立系で、多店舗展開もしているため、地元ではそれなりに名前が知られています。
塾ナビなどの塾探しポータルサイトにも登録していませんので、口コミ主体です。
A塾の紙媒体の広告も見たことがありませんので、本当に口コミ、紹介メインの塾なのでしょう。A塾の強みは、
◆授業が終わった後も、生徒が納得するまで質問対応を続ける姿勢
◆保護者からの連絡には必ず当日中に返信する、という徹底したルーティンワーク
◆定期テスト前は徹底した定期テスト過去問演習(10回はやるとか・・・)
塾長は「特別なことは何もしていません。生徒と保護者の信頼を裏切らないように、当たり前のことを当たり前にやっているだけです」と語っていました。
しかし、この「当たり前」を徹底することは、並大抵のことではありません。
その地道な努力が、地域に深く根ざした信頼となり、口コミで生徒が集まる好循環を生み出していたと言えます。
とにかく「教育一本!」という筋の通った方です。
自分の指導方針に自信を持っていて、上位高校への合格実績は毎年積み上げられています。
ポータルサイトに掲載しない、紙媒体の広告もやらない、しかし集客はしっかりと出来ているというその秘訣的なものとして私が感じ取っているのは、
◆上位層の生徒獲得
◆上位高校への進学実績
なのではないかと思っております。
定期テストベースで、450点以上ぐらい取れる生徒が多い塾ですので、そういう生徒さんが入塾をするような紹介連鎖を意図して狙い、結果上位校への合格者が出て、それが塾のサブ看板になっているというループだと思うのです。
そして、とても大きな事実に気づきました。
保護者が塾に対して信頼を抱く瞬間、信頼を失う瞬間を「成績」という部分で考えると、
それは、「定期テストの結果」が第一だということです。
通知表の4とか5の、微妙に曖昧な部分がある評価よりも「点数」はだれでも簡単に良し悪しが判断できるものじゃないでしょうか。
したがってA塾は、入塾の生徒さんにさらに勝ってもらうために、「定期テストの過去問」を10回解かせているのです。
入試の過去問ではありません。「定期テストの過去問」です。
ここに大きなポイントがあるように思います。
そして、この「地道だけれど徹底した作戦」は、決して「モノ」とか「楽しいもの」で釣ろうとはしていないということです。
この事例からも是非、
「そういうことか!」と気づきを得てもらえたらと思います。
ルーティンを回す仕組みづくり
「当たり前のことを丁寧に」と言うのは簡単ですが、それを継続するには仕組みが必要です。
特に、学習塾では、生徒の学習進捗、保護者とのコミュニケーション、講師の育成など、多岐にわたる業務があります。
これらをすべて属人的な努力に頼るのではなく、誰もが同じ品質のサービスを提供できるようなルーティンワークとして確立することが重要です。
1. 学習管理のルーティン化
生徒の成績や学習状況をデータとして一元管理し、定期的に振り返る仕組みを構築しましょう。例えば、毎日の宿題提出状況をチェックリストで管理する、週に一度は小テストを実施して理解度を確認する、といったルーティンです。これらを徹底することで、生徒のつまずきを早期に発見し、手遅れになる前に手を差し伸べることができます。
2. 保護者コミュニケーションのルーティン化
保護者との面談を定期的に実施するだけでなく、日常的な報告体制を構築します。毎日、生徒の様子をまとめたメールを送る、何か特別なことがあればすぐに電話で連絡する、といったルーティンです。これにより、保護者は常に塾との繋がりを感じることができ、安心感を持つことができます。
3. 講師育成のルーティン化
アルバイト講師に依存しがちな学習塾では、指導の品質を均一に保つことが課題です。これを解決するためには、指導マニュアルの作成や、定期的な勉強会の実施をルーティン化することが有効です。例えば、週に一度、授業のフィードバックを行う時間を設ける、季節講習の前には必ず指導内容のすり合わせを行う、といった取り組みです。
これらは、どれも地味で目立たない作業です。しかし、このルーティンを徹底することで、塾全体のサービス品質が向上し、生徒と保護者からの信頼が厚くなります。そして、この信頼こそが、地域での磐石な地位を築く上で最も重要な要素となるのです。
企画力は「地道な努力」の先にこそ活きる
もちろん、私は「アイデアは不要だ」と言っているのではありません。
むしろ、地道な努力によって築かれた強固な土台の上にこそ、アイデアは最大限に活かされると信じています。
例えば、生徒の学力が着実に向上し、保護者からの信頼も厚い塾があったとします。その塾が、学習成果を称えるための「成績向上発表会」を企画したとしましょう。
これは、一見すると地味なイベントです。しかし、日々の地道な努力があるからこそ、この発表会は生徒にとって「自分の努力が報われた」と感じる貴重な場となり、保護者にとっては「この塾に預けてよかった」と確信する機会になります。
また、受験対策においても同じことが言えます。過去問演習、苦手単元の克服、志望校の傾向分析といった地道な作業があって初めて、より効率的な学習プランや、モチベーションを維持するためのユニークな取り組みが意味を成すのです。地道な努力がなければ、どんなに素晴らしいアイデアも、空回りするばかりで終わってしまいます。
塾経営は、マラソンである
学習塾の経営は、短距離走ではなく、マラソンです。一発逆転を狙うような華やかなアイデアに飛びつくのではなく、一歩一歩、確実に前に進むことが重要です。その道のりは、時に退屈で、地味に感じられるかもしれません。
しかし、どうやら経験や関係者に話を伺うと、変哲のないその地道な積み重ねが、やがて強固な信頼という大きな財産となり、地域社会に深く根ざした、揺るぎない学習塾へと成長させてくれるということがわかります。
さあ、あなたの塾の「当たり前」をもう一度見つめ直してみませんか。地道な努力をルーティン化し、その土台を固めることから、真の成功への道は始まります。そして、その先に、生徒の成長と、保護者の感謝の笑顔という、かけがえのない報酬が待っているはずです。
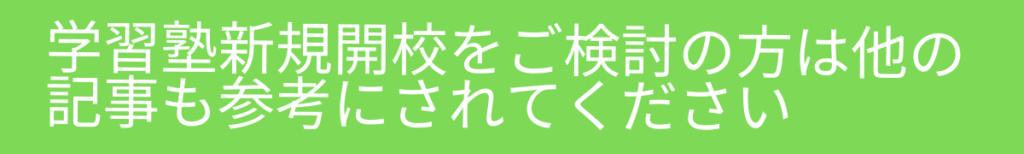
立地選定について
最適な物件選びの秘訣とは?
内外装計画と工事について
統一感のある什器・備品
教室長一日密着レポート徹底解説
失敗しない採用のための求人
見落としがちな掲示物の重要性!
開校時に用意しておく事務用品
商圏分析とネットリサーチ徹底攻略
塾講師採用 効果的な募集から採用
学習塾は単月赤字でも経営できる!
話し上手より「聞き上手」
テキスト選定と教材会社の選び方
塾の「儲けの仕組み」を徹底解剖!
学習塾選びの鍵!自習室の有無
立地で選ぶ塾の重要性
掲示物、パンフレット、のぼり旗
学習塾・習いごとの看板は集客の要

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備