個人塾の閉鎖、費用はいくら?知らないと損するコストと賢い節約術
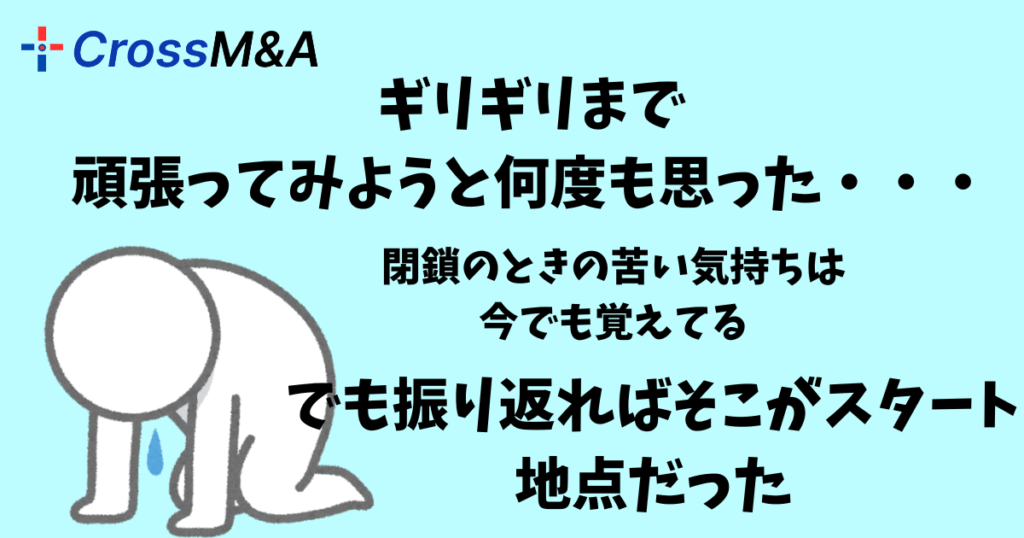
1. はじめに:個人塾の閉鎖は「終わり」ではなく「次」へのステップ
個人塾の経営、本当にお疲れ様でした。
少子化、学習方法の多様化、競合の激化など、様々な要因が重なり、塾の閉鎖を検討されていることと存じます。しかし、「閉鎖」と聞くと、ネガティブなイメージを抱きがちですが、これは決して失敗ではありません。むしろ、これまでの経験を活かし、次なるステップへ進むための大切な決断です。
しかし、その決断の前に立ちはだかるのが「閉鎖にかかる費用」という現実的な問題ではないでしょうか。漠然とした不安を抱えながら、どこから手をつけて良いか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、個人塾の閉鎖にかかる費用の全貌を明らかにし、それぞれの項目でどのようなコストが発生するのかを具体的に解説します。さらに、少しでも費用を抑えるための賢い節約術や、閉鎖後に後悔しないための注意点まで、あなたの疑問を解消し、安心して次の一歩を踏み出せるよう、徹底的にサポートします。
2. 個人塾閉鎖にかかる費用の全体像:主な発生項目と相場
個人塾の閉鎖にかかる費用は、塾の規模、立地、契約状況、閉鎖のタイミングなど、様々な要因によって変動します。一概に「いくら」とは言えませんが、ここでは主な発生項目とその相場感を解説します。
表にしてまとめてみました。
| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |
| 原状回復費用 | 賃貸物件の場合、入居時の状態に戻すための費用 | 坪単価2万円~10万円(広さや内装の状態により大きく変動) |
| 什器・備品処分費用 | 机、椅子、ホワイトボード、教材、コピー機などの処分費用 | 数万円~数十万円(量や品目、買取の可否により変動) |
| 解約違約金・通知義務 | 賃貸契約の期間内解約や、通知期間の不足による違約金 | 家賃数ヶ月分~1年分(契約内容による) |
| 生徒・保護者への対応費用 | 謝礼、教材費返金、転塾支援など(ケースにより発生) | 数万円~数十万円(生徒数や対応内容による) |
| 未払金・債務整理費用 | 従業員の給与、仕入れ代金、借入金など(必要であれば弁護士費用) | 数十万円~数百万円(債務状況による) |
| 専門家への依頼費用 | 行政書士、弁護士、税理士などへの相談・手続き代行費用 | 数万円~数十万円(依頼内容による) |
| 広告・告知費用 | 閉鎖の告知、移転先の案内など(必要であれば) | 数千円~数万円 |
| その他雑費 | 交通費、通信費、消耗品費など | 数千円~数万円 |
上記はあくまでも目安ですが、大小問わずコストがかかるのが、「原状回復費用」と「什器・備品処分費用」です。
これらの項目を合計すると、小規模な個人塾でも数十万円、大規模な塾であれば数百万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。漠然とした不安を解消するためにも、まずは上記を参考に、ご自身の塾でどの項目にどれくらいの費用がかかりそうか、概算を出してみることをお勧めします。
3. 各費用の詳細と注意点:想定外の出費を防ぐために
3.1. 原状回復費用:賃貸契約の落とし穴と交渉術
賃貸物件で個人塾を経営されている場合、閉鎖時に最も大きな費用となるのが「原状回復費用」です。これは、借りた時の状態に戻すための工事費用のことで、壁紙の張り替え、床の修繕、間仕切りの撤去などが含まれます。
注意点と対策:
- 契約書を熟読する: 賃貸契約書には、原状回復義務の範囲が明記されています。入居時の写真や図面などがあれば、それも確認しましょう。
- 「通常損耗」の範囲を確認する: 通常の使用によって生じた汚れや傷(通常損耗)については、借主の負担ではない場合が多いです。しかし、特約で借主負担になっているケースもあるため注意が必要です。
- 複数の業者から見積もりを取る: 不動産会社から指定された業者だけでなく、複数の原状回復業者から相見積もりを取ることで、費用を比較検討し、適正価格を見極めることができます。
- 交渉の余地を探る: 内装の状況によっては、交渉次第で費用が下がる可能性もあります。例えば、次のテナントが内装を大幅に変更する予定がある場合などは、貸主も融通を利かせやすいかもしれません。
- スケルトン貸しの場合: スケルトン貸し(内装が全くない状態)で借りた場合は、スケルトンに戻すのが原則です。工事費用が高額になる傾向があるため、特に注意が必要です。
一番厄介なのが、最後に書いたスケルトン渡し物件です。今は人件費が高くなっている時代ですから、業者の見積もりは信じがたいぐらい高い場合があります。
また、不動産会社が指定した業者などは、ことのほか高い場合がありますので、なるべく独自で相見積をとったほうが無難です。
契約書について書きましたが、そこに書かれた内容も解釈をどう捉えたらいいのか、よくわからないものもあります。特約で書かれたとしても物件契約というのは、通常は事細かにしっている宅建士と全く知らない素人の契約ですので、主張できる要素も出てくる可能性があります。
その胆となるのが、
「通常損耗」です。
CROSS M&A(クロスマ)では、諸々の意味合い、自分自身の苦い経験もあることから、新規開校時などの物件選定ではスケルトンは避けるべし!という方針を皆さんにお伝えしています。
借りるときはいいのです。夢が膨らみ、かかったコストもなぜかすぐに回収できるように思えてしまうからです。
兎に角、スケルトン状態に戻す必要があるときのコストは想像以上であることを覚えておいてください。
さて、蛇足的ですが、もし不動産を解約する際に管理会社とか物件オーナー側と何等かのことでもめた場合とか、敷金や保証金がほとんど戻されないなどの理不尽なことが起った場合には、お問合せください。
内容によっては、取り戻すことができます。
どんな場合でも泣き寝入りはしないでください。
3.2. 什器・備品処分費用:売却・譲渡でコスト削減
塾で使用していた机、椅子、ホワイトボード、本棚、教材、コピー機、パソコンなどの什器や備品も、閉鎖時には、そのすべてを自宅に持っていくのは大変でしょう。
私物として引き取るものと、処分するものがあるはずです。
特に個別指導などで使っていた机などは、それ単体では相当の重量があります。そのままの形のまま、どこか別のところに移送するにしてもコストはかかります。
かえって現場で壊して内部解体して持って行ってもらったほうがコスト的には安いかもしれません。
注意点と対策:
- 不用品回収業者に依頼: 大量の不用品がある場合、専門の不用品回収業者に依頼するのが一般的です。料金は量や品目によって変動します。
- 買取サービスを利用: 比較的新しいものや状態の良いもの、需要のあるものは、オフィス家具専門の買取業者やリサイクルショップ、フリマアプリなどで買い取ってもらえる可能性があります。査定を依頼し、少しでも費用を回収しましょう。
- 譲渡や寄付も検討: 周囲の塾やNPO法人などに、無償で譲渡したり寄付したりすることで、処分費用を抑えられるだけでなく、社会貢献にも繋がります。
- 産業廃棄物と一般廃棄物の区別: 塾から出る廃棄物は、産業廃棄物として処理しなければならないものもあります。事前に専門業者に確認し、適切な方法で処分しましょう。
この解体、不要品処分においてもかかるコストは業者によって雲泥の差です。当方は千葉県ですが、東京・神奈川・千葉・埼玉あたりでしたら、CROSS M&Aが「きっとこれ以上安いところはないだろう」というところを紹介できます。
作業スピードが半端じゃなく早いですし、若くて溌剌としたスタッフたちで、閉校の寂しさとを感じる間もなくキレイにしてくれます。
イメージ的には、見積差が2~3倍違う可能性があります。
この件でもご入用でしたら遠慮なくお問合せください。
3.3. 解約違約金・通知義務:契約書を再確認!
賃貸契約には、通常「解約予告期間」が定められています。一般的には数ヶ月前(たいていは3か月前まで)までに解約の意思を通知する必要があり、これを守らないと解約違約金が発生する場合があります。
注意点と対策:
- 契約書を確認する: 解約予告期間、違約金の有無、違約金の算出方法などを必ず確認しましょう。
- 早めに通知する: 閉鎖を決めたら、できるだけ早く貸主に解約の通知を入れましょう。通知が遅れると、余分な家賃を支払うことになりかねません。
- 中途解約特約の有無: 契約によっては、一定期間内の中途解約を禁止する特約や、高額な違約金が設定されているケースもあります。
後ろ髪引かれるかもしれませんが、不動産会社への通知はとにかく早めに行ったほうがいいです。不動者会社としても早めに次の借主を見つけなくてはいけない使命感があるため、広告を出すてはずを整える時間が必要なのです。
しかしながら、「閉鎖」ではなくて、「譲渡」という手段の場合には話がまったく変わってきます。仮に、
譲渡先が期限内に見つかれば譲渡
見つからなかったらやっぱり閉鎖
こういう形になるケースもあるでしょう。
この場合も、不動産会社にその旨を伝えるといいです。不動産会社、物件オーナーとしてもこのまま閉鎖になるよりは、事業譲渡が決まって、新しいオーナーと物件計約できたほうがいいのです。
正直に実情を伝えることで、不動産会社も色々と応援してくれるようになったりします。
3.4. 生徒・保護者への対応費用:誠実な対応が次につながる
塾の閉鎖は、生徒や保護者にとっても大きな影響を与えます。誠実な対応を心がけることで、トラブルを回避し、将来の信頼関係にもつながります。
注意点と対策:
- 返金対応: 未消化の授業料や教材費の返金は必須です。返金規約に基づき、速やかに対応しましょう。
- 転塾支援: 提携している塾があれば紹介したり、近隣の塾の情報を提供したりするなど、生徒がスムーズに次の学習環境に移れるようサポートすることも検討しましょう。
- 説明会の開催: 保護者向けに閉鎖の経緯や今後の対応について説明会を開催することで、不安を軽減し、理解を得やすくなります。
- お詫びの品や謝礼: 義務ではありませんが、これまでお世話になった感謝の気持ちとして、ささやかな品や謝礼を渡すことを検討するのも良いでしょう。
閉鎖となれば、顧客との関係性もすべて清算しなくてはなりません。この作業が一番精神的に突き刺さる部分になります。
ひとりひとりの保護者に伝えていく過程で、色々な声掛けもあるでしょうし、惜しむ声もあるはずです。
大手塾ですと、本部の決定でそういう人とのお別れもドライに行われるかもしれません。しかし個人塾の場合には、ずっと密接につながってきた保護者とか生徒とのお別れがありますので、ドライになれない部分もあるでしょう。
それは人としての気持ちですから、最後まで丁寧に接していったほうがよいでしょう。
3.5. 未払金・債務整理費用:専門家への相談を視野に
もし、従業員への給与未払いや、仕入れ業者への代金未払い、金融機関からの借入金などがある場合は、これらを清算する必要があります。
注意点と対策:
- 優先順位を明確にする: 従業員の給与は最優先で支払うべき債務です。
- 早期に相談する: 債務の状況が複雑な場合や、支払い能力に不安がある場合は、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。自己破産や任意整理など、状況に応じた最適な解決策を提案してもらえます。
- 従業員への説明: 従業員がいる場合は、閉鎖の意向と今後の対応について、丁寧に説明し、理解を求めましょう。
3.6. 専門家への依頼費用:安心して閉鎖を進めるために
個人塾の閉鎖は、様々な手続きや法律的な知識が必要となる場合があります。専門家に依頼することで、時間と手間を省き、安心して閉鎖を進めることができます。
依頼を検討すべき専門家:
- 行政書士: 廃業届の提出、各種許認可の返納などの手続きを代行してくれます。
- 弁護士: 賃貸契約のトラブル、債務整理、従業員とのトラブルなど、法的な問題が生じた場合に相談できます。
- 税理士: 最終的な確定申告、事業廃止に伴う税務処理について相談できます。
費用を抑えるポイント:
- 無料相談を活用する: 多くの専門家が初回無料相談を実施しています。まずは相談してみて、必要なサポート内容と費用を確認しましょう。
- 必要な範囲で依頼する: 全てを依頼するのではなく、自分では難しい部分や、特に専門知識が必要な部分だけを依頼することで、費用を抑えられます。
差し出がましいですが、もしこの件でも頼れるひとがなかなか思い浮かばないときには、クロスマのアドバイザーまでご連絡ください。
当然無料でご相談承ります。
4. 賢い節約術:閉鎖費用を最小限に抑える方法
ここまで、閉鎖にかかる費用の内訳を見てきましたが、これらの費用を少しでも抑えるための具体的な節約術をご紹介します。
4.1. 計画的な閉鎖スケジュール:早期着手が最大の節約
閉鎖の意思決定から実行までの期間が短いほど、焦って費用がかさんでしまう傾向があります。できるだけ早めに閉鎖の計画を立て、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
- 解約予告期間の遵守: 賃貸契約の解約予告期間を遵守することで、余分な家賃の発生を防げます。
- 事前準備の徹底: 什器・備品の売却先の検討、原状回復業者の選定など、早めに準備を進めることで、比較検討の時間も確保でき、費用を抑えることに繋がります。
4.2. 補助金・助成金の活用:意外な支援があるかも?
個人塾の閉鎖に直接適用される補助金や助成金は少ないかもしれませんが、従業員の再就職支援に関する助成金や、事業転換を支援する制度など、間接的に利用できるものがないか、各自治体や国の制度を調べてみる価値はあります。
- ハローワーク: 従業員の雇用調整助成金や、再就職支援の制度について相談できます。
- 中小企業庁、各自治体の商工会議所: 廃業に関する相談窓口や、事業転換支援の制度について情報提供を行っています。
4.3. 自力でできることは積極的に行う
専門家に依頼する費用を抑えるためにも、自分でできることは積極的に行いましょう。
- 不用品の処分: 粗大ごみとして出す、フリマアプリで販売する、知人に譲るなど、できるだけ費用がかからない方法を検討しましょう。
- 簡単な清掃や補修: 原状回復工事の前に、自分でできる範囲の清掃や簡単な補修を行うことで、業者の作業量を減らし、費用を抑えられる可能性があります。
- 情報収集: 閉鎖に関する手続きやノウハウを事前に情報収集しておくことで、専門家への依頼範囲を絞ることができます。
4.4. 複数業者からの相見積もり:比較検討で適正価格を
原状回復工事、不用品回収、その他依頼する可能性のある業者については、必ず複数の業者から相見積もりを取りましょう。
- 見積書の内容を比較する: 単に総額だけでなく、内訳を詳しく確認し、不明な点があれば質問しましょう。
- 実績や評判を確認する: 価格だけでなく、業者の実績や評判も参考にしましょう。安かろう悪かろうでは意味がありません。
5. 閉鎖後の後悔を防ぐために:大切なこと
個人塾の閉鎖は、多大な労力と費用を伴う決断です。後悔しないためにも、以下の点を心に留めておきましょう。
5.1. 生徒・保護者との良好な関係を保つ
閉鎖は、生徒や保護者にとって大きな出来事です。誠実で丁寧な対応を心がけることで、感謝の気持ちと共に終わりを迎えられます。これは、あなたの今後の人生においても、かけがえのない財産となるはずです。
5.2. 確定申告の準備と税務処理
事業を閉鎖した場合、最終的な確定申告が必要です。事業廃止に伴う税務処理も発生するため、税理士に相談するなど、適切な対応を行いましょう。
5.3. 精神的なケアも大切に
事業の閉鎖は、経営者にとって大きなストレスとなることがあります。一人で抱え込まず、家族や友人に相談したり、必要であれば専門のカウンセリングを受けることも検討しましょう。
気持ちが不安定になって泣きたくなることもあるかもしれません。
閉鎖となったことは色々な事情があるとは思います。しかしながら、一生懸命やってきたのですからあまりご自身のことを責めてはいけません。
どんなに大きな会社でも、どんなに順風満帆に見える企業でも失敗経験のない会社などありません。どんなにとんとん拍子に見える他人の出世でも、そこに挫折経験がないということもほとんどありまえせん。
なんだかんだ言っても人間は皆何かしら悩みをもっています。
悩みがあるのが普通ですし、失敗経験などは生きてる年数が長いほど、いくらでもあると思います。
何かが終わってもそこで人生終わるわけではありませんから、また不死鳥のように蘇っていきましょう!
5.4. 次のステップへの準備
閉鎖は終わりではなく、次へのステップです。これまでの経験を振り返り、新たな目標を見つけるための大切な時間でもあります。ゆっくりと心身を休めながら、次の人生に向けて準備を進めてください。
6. まとめ:個人塾の閉鎖は、あなたの新たな門出
個人塾の閉鎖は、決して簡単な決断ではありません。
しかし、この記事で解説したように、費用についてしっかりと理解し、計画的に準備を進めることで、その負担を最小限に抑え、安心して次の一歩を踏み出すことができます。
- 費用の全体像を把握し、早めに概算を出す。
- 賃貸契約書を熟読し、原状回復費用や解約違約金に注意する。
- 什器・備品の売却や譲渡で費用を抑える。
- 生徒・保護者には誠実に対応する。
- 必要に応じて専門家を上手に活用する。
- 計画的なスケジュールと相見積もりで節約を意識する。
あなたの個人塾は、これまで多くの生徒たちの成長を支え、地域に貢献してきた素晴らしい場所だったはずです。その役割を終え、新たなステージへと進むことは、決してネガティブなことではありません。
この情報が、あなたの個人塾閉鎖における不安を少しでも解消し、希望に満ちた新たな門出を応援する一助となれば幸いです。
そして最後に、終わりにする・・閉鎖する・・・という決断があったとしてももう一つの「譲渡」という可能性についてもお時間あるならば、是非ご検討ください。
どんな場合でもご相談、承ります。
誠意をもって対応させて頂きます。
CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡