中学受験をしない小学生のための学習塾の選び方と学習戦略
多くの方が小学生対応の「学習塾」と聞くと、中学受験対策を思い浮かべるかもしれません。しかし、すべての小学生が中学受験をするわけではありません。
確かに首都圏の中学受験率18.1%と以前よりも高水準ですが、裏を返せば小学生の82%は中学受験をしませんので、「中学受験をしない率は約82%と高水準である!」と表現したほうが正しいのかもしれません。
実は近年、「戦略的に(作戦として)中学受験をしない」という選択をするご家庭「も」増加しているのです。
単純に円グラフで18%が中学受験をする、82%が中学受験をしないという2つの項目に分かれるのではなく、「中学受験をしない」ということを作戦として意図的に選択している保護者が一定数出てきているということです。
中学受験をしないという82%の中には、考えがあって中学受験をしないという方針にしたということです。
それは、「中学受験をしない」というだけでなく、その先の高校受験、さらには大学受験を見据えた戦略的な選択肢として捉えられています。
この記事では、中学受験をしない小学生のための学習塾の選び方、効果的な学習戦略、そして学習塾をM&Aで買収を検討している方にも参考にしてもらえるように心がけました。将来的な学習塾業界の動向についても説明していきます。
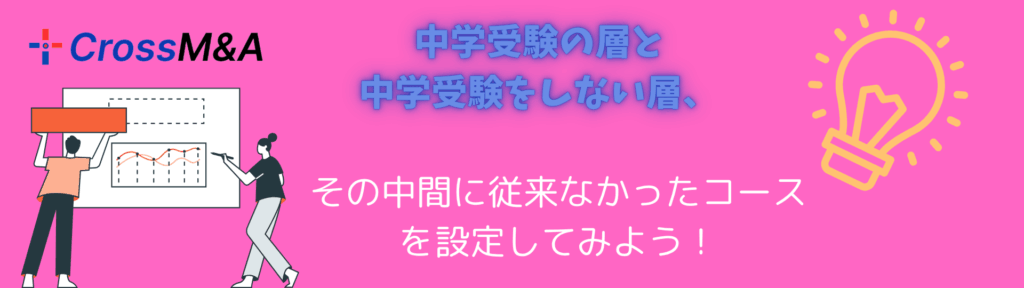
なぜ今、「戦略的に中学受験をしない」選択肢が注目されるのか?
かつて、難関大学への進学を目指すなら、まず難関中学への進学が定石とされていました。しかし、近年、その常識が変わりつつあります。
推薦入試や総合型選抜の多様化
大学入試において、一般選抜だけでなく、推薦入試や総合型選抜(旧AO入試)の枠が拡大しています。これらの入試では、学力だけでなく、高校での活動実績や面接、小論文などが重視されます。つまり、中学受験で無理に難関校に入学しなくても、高校で着実に実績を積むことで、希望する大学への道が開かれる可能性が高まっているのです。
↑ ↑ ↑ この部分はとても重要ですので、塾関連の方もM&A検討の方も押さえておいてください。
公立中学校での「内申点」の重要性
公立中学校に進学した場合、高校受験においては「内申点」が非常に重要な要素となります。内申点は、日々の授業態度、定期テストの成績、提出物の状況などによって決まります。
中学受験のプレッシャーから解放された分、公立中学校で部活動や生徒会活動に積極的に取り組み、定期テストで高得点を取ることで、着実に内申点を積み重ねることができます。この内申点こそが、高校推薦入試の強力な武器となるのです。
中学受験で小4ぐらいから塾通いをして、合格に向けての努力をして見事栄冠を勝ち取ることもその後の人生にとても大きなプラスになりますし、公立中学に進学して定期テストだけは絶対に落とさないという決意で猛勉強して内申点を稼ぎ、上位高校へ進学することも大きなプラスになります。
道が二つに分かれて、当初の予定とは違う報告に舵を切り替えたとしてもそれは間違いとは言えません。
ではここで、恒例の実例(実話)として一つ紹介いたします。
【実例(実話)】
小学4年生から通ってくれていたS君の事例です。
S君のお母さんのスタンスとしては、中学受験で中堅の学校に通わせたいという意向でした。S君が住んでいるところは、塾のすぐそばということもあり、塾の日は必ず10分前には来てくれて、まじめに取り組んでいました。
5年生になったときに、最初の模試を受けましたが、算数はそこそこでしたが国語がよくありませんでした。漢字を覚えるのが苦手、読解問題で記述が苦手というのはわかっていましたので、授業カリキュラムでは読解を中心に組み立て、漢字の読み書きは鉄板の「漢字日記」で宿題を出しながら進めていきました。
かなり悪い状態から6年を迎え、国語には相変わらず四苦八苦でしたが、算数の実力は相当高まってきました。夏の講習では理科や社会も取り入れて総合的な演習に取り組みましたが、ある日国語の授業の時に、読解がわからない何を書いたらいいのかわからないという悔しさなのか、授業中に泣き出してしまったのです。
講師がきつい言葉を発したりすることはないため、状況をお母さんに伝え、少し国語についてはペースダウンしたほうがいいかもしれませんと相談しました。
国語だけが足をひっぱる状況をなかなか脱することが出来ずに秋を迎えたとき、お母さんから「中学受験をやめて中学生の勉強を先取りする形にしていきたい」という申し出がありました。
さらには、国語の受講をやめて「算数と英語」にしたいということも伺いました。
4年生の夏ぐらいからの開始で、ずっと中学受験を目指して頑張ってきたので、正直ショックではありましたが、保護者の判断に従いました。
ところが、これはS君にとっては最高にいい決断だったのです。
S君の授業を英語と算数(先取りで数学)に切り替えてからは、誰が見てもわかるように明るくなりました。9月、10月ぐらいから約半年間、徹底して先取り学習をしたことで、英語は中1の内容が終わってしまい、数学は正負の計算、文字式、一次方程式、比例反比例、そして平面図形まで進めてしまいました。
そこから中学デビューです。
はっきり言って余裕でした。
S君は最初のテストから高得点で、英語は100点、数学は98点、他の3教科も80点以上となり、学年順位も1桁で堂々のスタートを切ることが出来たのです。
それからも先行学習の手を緩めずに、進めていき、気づいたら5教科はオール5となっていました。運動は苦手で3でしたが、他、技術家庭、美術が4で、音楽も5ということで、9教科41というところが1年生の内申になったのです。満点が45ですから、そこそこいいです。
しかしながら、どうしても体育などは上にのびあがるのはちょっと難しそうだということで、こんどは英検と漢検、数検という検定受験を2年生から徹底してきました。
結果、英検、漢検、数検のすべて、3級に合格して、内申プラス(加点)が呼び込める状態になりました。
そして迎えた受験期、私立の推薦受験で、選べる推薦の一番いい学校に合格することが出来ました。
お母さんが我が子のポテンシャルを知った上で、途中戦略変更したことが全て当たった好事例です。
経済的・精神的負担の軽減
実際、中学受験は、高額な塾費用や精神的なプレッシャーなど、ご家庭にとって大きな負担となることがあります。
保護者が子のためにそれなりの費用を覚悟したとしても、中学受験に向かう子どもは、下手すると本来の明るさが消えうせ、メンタルで追い込まれてしまう可能性もあるのです。
中学受験をしない選択は、これらの負担を軽減し、よりのびのびと小学校生活を送ることを可能にします。その結果、子どもたちは自分の興味や関心を追求する時間を確保でき、より主体的な学習習慣を身につけることができるというメリットがあります。
中学受験をしない小学生のための学習塾選びのポイント
では、中学受験をしない小学生は、どのような学習塾を選べば良いのでしょうか? 「中学受験対策専門」ではない塾を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。
1. 基礎学力の定着と応用力育成を重視する塾
中学受験をしない場合でも、小学校で学ぶ基礎学力の徹底的な定着は不可欠です。算数、国語、理科、社会の各教科において、つまずきがないように丁寧に指導してくれる塾を選びましょう。
知識の詰め込みではなく、応用力を養うための思考力や表現力を育む指導を行っているかどうかも重要なポイントです。例えば、文章読解や記述問題に力を入れている塾は、将来の高校受験や大学受験にも繋がる力を育むことができます。
2. 公立中学校の学習内容に接続する指導
小学校の学習内容を土台に、公立中学校で学ぶ内容へとスムーズに接続できる指導を行っているかを確認しましょう。特に、数学や英語といった積み上げ式の教科では、先取り学習や基礎固めが効果的です。中学入学後に戸後れることなく、スムーズに学習を進められるようなカリキュラムを持つ塾が理想的です。
中学受験をしない選択にして先を見据えて戦略をとるならば、中学内容をいずれかの地点で先取学習することになります。小学生から中学の内容を?と思われるかもしれませんが、
この先取学習は、失敗する可能性限りなくゼロに近いです。トータル的に言えば中学受験での失敗確率と比べてたら、圧倒的に先取学習成功率のほうが高いです。
3. 個別指導や少人数制のクラス
集団指導だけでなく、個別指導や少人数制のクラスがある塾も検討に値します。中学受験をしない場合、一人ひとりの学習進度や理解度に合わせたきめ細やかな指導が、より効果的です。苦手分野の克服や得意分野のさらなる伸長など、個々のニーズに応じたサポートが期待できます。
4. 学習習慣の確立をサポートする塾
勉強の習慣は、学力向上に欠かせない要素です。宿題の管理、自習室の利用、定期的な面談などを通して、子どもが自律的に学習に取り組む習慣を身につけられるようサポートしてくれる塾を選びましょう。特に、家庭学習の習慣がない子どもにとっては、塾での学習習慣がその後の学習意欲を左右する可能性があります。
自習室(自習専用ブース)は非常に利用価値が高いです。
この自習室があるかないかも保護者からの質問には多く、さらには自習室の利用可能時間や、予約の必要が有無などを聞かれることもありますが保護者にとって、我が子の学習習慣が付けられる環境はかなり理想に近いと考えます。
5. 高校受験を見据えた情報提供と進路相談
中学受験はしないものの、将来の高校受験は考えているご家庭が多いはずです。そのため、高校受験に関する情報提供や進路相談を積極的に行ってくれる塾は非常に心強い存在です。地域の高校の情報や推薦入試の傾向など、具体的なアドバイスを受けられる塾を選ぶことで、より戦略的な学習計画を立てることができます。
6. 中学受験コースがない、または明確に分かれている塾
中学受験対策を主軸としている塾は、どうしても中学受験を目指す生徒向けの指導に重心が置かれがちです。そのため、中学受験コースがない、あるいは中学受験コースと明確に分かれており、それぞれに特化したカリキュラムが用意されている塾を選ぶことが重要です。これにより、中学受験をしない小学生でも、適切な指導を受けることができます。
ではここで少し、公立中学校に進学した後の流れ(作戦)についてご説明いたします。
公立中学校から難関高校への道筋:戦略的学習のススメ
「中学受験をしない」という選択は、決して「受験から逃げる」ということではありません。むしろ、公立中学校で内申点を着実に稼ぎ、高校推薦入試でランクの高い高校を目指すという、非常に有効な戦略です。
内申点UPのための秘訣
まずは内申点の仕組みを知っておきましょう。
小学生のカラーテストは、表面が「知識・技能」を問う問題、裏面が「思考・判断・表現」を問う問題です。
同様に中学では、解答用紙や問題用紙にわかりやすく、この問題は「知識・技能」この問題は「思考・判断・表現」を問う問題とわかるように書かれています。だいたい比率は6:4です。テストから評価されるのがこの2つの観点です。
これに「主体的・積極的に学習に取り組む態度」というもう1つの観点が加わり、全部で3つの観点別評価が為されるのです。それぞれがA, B, Cの3段階で評価され、5段階の評定が決定される仕組みです。
例えば、5になるためには、3つの観点ですべてがA評価を得る必要があります。
しっかりとテストで結果を出し、積極的な学習参加をする姿勢をしっかりとアピールすることで「5」がもらえるということです。
以下は少し具体的に書いてみました。
- 定期テスト対策の徹底: 定期テストは内申点に直結します。日々の授業内容を理解し、計画的に学習を進めることが重要です。塾では、テスト範囲に合わせた対策や、応用問題への対応力を養う指導を受けると良いでしょう。
- 提出物の期限厳守と丁寧な作成: 宿題や課題、レポートなどの提出物は、期限を守り、丁寧に作成することが評価に繋がります。
- 授業への積極的な参加: 授業中に発言したり、グループワークに積極的に参加したりすることも、内申点に良い影響を与えます。
- 部活動や生徒会活動への貢献: 勉強だけでなく、部活動や生徒会活動でリーダーシップを発揮したり、地域貢献活動に参加したりすることも、推薦入試の際に有利に働くことがあります。
塾を活用した戦略的な学習計画
上記の内申点UPの秘訣を実践するためには、塾の活用が非常に有効です。
- 苦手科目の克服: 公立中学校では、特定の科目が苦手だと内申点に大きく響きます。塾で苦手科目を克服し、平均点を底上げしましょう。
- 得意科目の強化: 得意科目はさらに磨きをかけ、高得点を安定して取れるようにすることで、全体の内申点を引き上げることができます。
- 定期テスト対策: 塾では、中学校の定期テストの傾向と対策を熟知している講師がいるため、効率的に高得点を狙うことができます。
- 英検・漢検・数検などの取得: 各種検定試験の取得は、学力の証明となり、推薦入試でアピール材料となります。塾で対策講座を受講することも有効です。
相当努力しても点数が少し不足になることは誰にもあり得ます。その際に不足分を埋め合わせ、さらに上の評価を勝ち取るのが、各種検定です。
特に英検はその先の大学受験の際にも役立つため一番オススメの資格です。
それではここで、少しM&Aにも触れていきます。
学習塾業界のM&Aと「中学受験をしない層」へのアプローチ
近年、学習塾業界ではM&A(企業の合併・買収)が活発に行われています。この小さなタイトルから、一体何の話になるのか、意味不明かと存じます。
「中学受験をしない層」へのアプローチという部分が特にです。
「中学受験をしない層」への新たなビジネスチャンス
学習塾のメイン顧客層は、小学生、中学生、高校生です。通塾率という観点で言うと、中学生がもっとも通塾率が高いです。
しかしながら、「中学生のみ」「小学生のみ」「高校生のみ」はそこに明確なターゲットを置いている点では、それが戦略ですからいいのですが、しかし市場は横に拡がっている昨今、そこまでターゲットを絞りこむのはリスクのほうが高いような気がします。
年齢層として考えれば、例えば「中学生のみ」でしたら、12歳から15歳という年齢のみがターゲットということになります。
せめて小中高生とフルで扱えるようになったほうがいいです。
ここで小学生というターゲットに目を転ずると、小学生は中学受験の生徒、または学校補習の生徒という2分割で考えると、単価や売上高は中学受験の生徒のほうが多くなります。
しかもほんの少し多くなるのではありません。かなり多くなる、相当の差が出る、下手したら3倍以上の売り上げ格差にな・・・と言っても全然過言ではありません。
でもパーセンテージとして見れば、中学受験をする生徒=18%、中学受験をしない生徒=82%です。
「中学受験をしない」という82%の中から、新しい価値を創造しよう!というのが本記事の主旨なのです。
- 公立中高一貫校対策: 公立中高一貫校は中学受験を必要としないものの、適性検査対策など特別な指導が必要な場合があり、これも「中学受験をしない」カテゴリーに含まれることがあります。
- 高校受験に特化したカリキュラム: 中学入学後、高校受験に向けて本格的に準備を進める生徒向けの塾が増加しています。内申点対策、定期テスト対策、高校別の入試対策など、特化したカリキュラムが求められます。
- 英語教育の強化: 大学入試改革により、英語の4技能(聞く、話す、読む、書く)が重視されています。小学生のうちから英語力を高めるための塾や、オンライン英会話などとの連携も活発化するでしょう。
- プログラミング教育など非認知能力育成: 学校教育でもプログラミング教育が導入される中、論理的思考力や問題解決能力を育むプログラミング教室なども、学習塾と連携したり、M&Aによって取り込まれたりする可能性があります。
このように中学受験をしない選択をした子供たち(たいていの決断は保護者ですが)の中に潜在的にある新しい需要を作り出せたならば、「中学受験をしない小学生」へのアプローチが多岐に渡るようになります。
↑ ↑ ↑
この部分、上手く伝わりましたでしょうか。
・中学受験をする小学生
・中学受験をしないけれど高校から先の戦略をもった小学生
・中学受験をしない小学生
そうです。今までは「する」「しない」というタイプ分けだったのをもう少し段階を増やすのです。そうすることで学習塾が売り込むコース設定に選択肢が増えることで、この間をとった価格設定も可能でしょうし、他にも
工夫する要素が出てくると思います。
学習塾のM&Aは、このように、新しい教育サービスや指導方法を生み出すきっかけにもなります。
「中学受験をしない」という選択をするご家庭が増える中で、この層のニーズを的確に捉え、質の高い教育サービスを提供できる塾が、今後の学習塾業界で優位に立つことができるでしょう。
実際、小学生の保護者対応をしていると、この第二段階目の層の顧客が一定数以上いるということに気付きます。
まとめ:戦略的な選択が未来を拓く
中学受験だけが唯一の選択肢ではない、という部分をチャンスに切り替えることが出来れば、M&Aは低コストで実施して中味の改革にコストを割くなど、いろいろ戦略を立案できそうです。
中学受験をしないという選択は、決して安易な道ではありません。むしろ、公立中学校進学後の地道な努力は必須です。
内申点を着実に積み重ね、高校推薦で希望する高校に進学するという、非常に戦略的で有効な道であっても空から降ってくるわけではありませんの大変ではありますが、その誘導が上手くできるのであれば、保護者も賛同してくれる人がきっと出てきます。
戦略を成功させるためには、小学生の段階から適切な学習塾を選び、基礎学力を定着させ、応用力を育むことが不可欠です。
学習塾業界のM&Aも進む中で、多様なニーズに応えられる塾が増え、子どもたち一人ひとりに最適な学びの場が提供される未来が期待されます。M&A後に明確なコンセプトを掲げ、今までなかった商品設計をして、その「今までなかった商品」が認知されるとそこからまた顧客が増加することでしょう。
CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略