新規開校を目指す教室長・塾長へ!一日密着レポートで業務を徹底解説
学習塾の新規開校を考えている皆さん、期待とともに「実際、どんな毎日を送るんだろう?」という不安を感じているかもしれませんね。
生徒たちの成長を間近で見られるやりがいのある仕事ですが、新規開校後の塾運営には多岐にわたる業務があります。
今回は、新規開校を目指す学習塾長の一般的な1日をご紹介し、具体的な業務内容や繁忙期について詳しく解説します。
意外と楽しい-1024x288.png)
塾長の一日:新規開校後の通常スケジュール
学習塾の業務スタートは午後からというケースが多いです。
13時〜15時頃から始まり、夜は21時〜22時頃までといったスケジュールが一般的でしょう。学習塾、習いごと教室ともに小学生から中高生を対象にしているところがほとんどですので、生徒が学校から帰宅しからということになれば、やはり授業時間も早くて15時台、16時台ぐらいからの開始になるところが多いのではないでしょうか。
それでは、イメージがわくように、一日の勤務スケジュールをお伝えしていきます。
開校前の準備:午後のスタートダッシュ
- メールチェックと情報収集(14:00〜)
- その日の業務は、まずメールチェックから始まります。(LINEなどのツールを利用する場合も多いと思いますが、やはりビジネス上の連絡のメインはメールになると思います)
なぜなら、昨晩から今朝の間に重要な連絡が入っているかもしれないからです。
既存の保護者の方々からの質問や相談、新規のお問合せ、教材業者からの連絡、FC加盟をしているならば、本部からの連絡など、多岐にわたるメールが届きます。
迅速な返信が必要なもの、後ほど対応が必要なものなどを仕分けし、優先順位をつけていきながら、一日の仕事の仕分けを計画していく時間になるでしょう。 - 同時に、当日の授業や面談の予定を確認し、その日にやるべきことをリストアップ。常に先の見通しを立てて行動することが、効率的な運営には不可欠です。
- その日の業務は、まずメールチェックから始まります。(LINEなどのツールを利用する場合も多いと思いますが、やはりビジネス上の連絡のメインはメールになると思います)

自分自身の日々のtodoはノートやメモで管理してもいいのですが、断然google カレンダーがオススメです!慣れてくると、紙のメモは使わなくなっている自分に気づくかもしれません。
続いて、
- 教室環境の整備
- 生徒たちが快適に学習できる環境を整えることは、塾運営の基本です。
教室内の清掃、整理整頓はもちろん、トイレ掃除も毎日欠かしません。清潔で気持ちの良い空間は、生徒たちの学習意欲を高めるだけでなく、保護者の方々への安心感にもつながります。
清掃箇所(机の上、タブレット端末、ホワイトボード、床、トイレ、外の教室前スペースなど) - 掲示物の作成と掲示も大切な業務です。塾からのお知らせやイベント情報、成績優秀者の紹介、学習アドバイスなど、生徒や保護者に役立つ情報を分かりやすく掲示します。
人間は称賛されたい欲求があるため、成績優秀者の掲示はとても有効です。
掲示の基準は教室によって異なると思いますが、なるべく褒められるポイントを見出してあげるのもいいですね。
例えば取れた点数は、50点だったけれど、前回の点数が30点であれば、「前回より20点UP!」という掲示もアリだと思います。
また、学校の成績以外にも模試であるとか、英検・数検・漢検やプログラミング検定なども称賛の材料になります。
これは内部にいる生徒さんのやる気アップだけが目的ではなく、
来校される保護者にもインパクトを与えるのです。
成績優秀者の掲示は断然オススメです!
- 生徒たちが快適に学習できる環境を整えることは、塾運営の基本です。
- 事務・教材関連業務
- 備品の発注も定期的に行います。文房具、プリント用紙、トナー、消毒液など、日々の運営に必要なものは多岐にわたります。在庫状況を常に把握し、計画的に発注することで、急な不足を防ぎます。
最も注意しなくてはいけないのは、「複合機」と「コピー用紙」です。
学習塾や習いごと教室は、タブレットのみで授業を実施している場合であっても、複合機とコピー用紙は使います。
複合機は、「トナー切れ」「トナー受け皿」この2つに注意です。どちらが切れても、以降の印刷が出来なくなるため、業務に支障をきたしてしまいます。
教室内は、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4つの色トナーとトナー受け皿(廃トナーボックスなどの名称)は、ひとつずつ在庫をストックしておくようにしましょう。
そしてコピー用紙、こちらも切れてしまうと支障が出ますので、ときおり予備チェックをしておくといいです。コピー用紙も値段が上がってきましたので、ミスコピーを裏紙として使うんどの工夫をして少しでもコスト削減してみてください。 - 生徒が受ける模擬試験などの申し込み手続きも重要な業務です。期限厳守で抜け漏れがないよう、細心の注意を払って進めます。
主に会場模試というと、受験学年での実施が多いです。非受験では教室内で実施しているところがほとんどです。
受験生向けの会場模試は、日程や会場、時間、持っていくものなどの注意事項を、保護者にもしっかりと伝えてあげるようにしましょう。
- 備品の発注も定期的に行います。文房具、プリント用紙、トナー、消毒液など、日々の運営に必要なものは多岐にわたります。在庫状況を常に把握し、計画的に発注することで、急な不足を防ぎます。
- 情報発信と広報活動
- 新規生徒の獲得や塾のブランドイメージ向上のため、ウェブサイトやブログ、SNSを活用した情報発信は欠かせません。日々の塾の様子、学習に役立つ情報、教育に関するコラムなどを定期的に更新し、塾の魅力を伝えていきます。
文章を書くのに、不慣れな人が、画像がメインのInstagramなどでもいいと思います。
今の時代は、多くの場合はネットからの情報入手です。SNSを主体に情報を得ている人も多く、口コミという要素の重要性が増しているといえます。
- 新規生徒の獲得や塾のブランドイメージ向上のため、ウェブサイトやブログ、SNSを活用した情報発信は欠かせません。日々の塾の様子、学習に役立つ情報、教育に関するコラムなどを定期的に更新し、塾の魅力を伝えていきます。
- 教材準備とカリキュラム作成
- 生徒一人ひとりのレベルや目標に合わせた問題作成や、全体の学習進捗を考慮したカリキュラム作成も、日中の重要な業務です。生徒の理解度を深めるためのオリジナル問題や、定期テスト対策プリントなど、質の高い教材提供を心がけます。
この対策プリントは、イメージ的には学校の先生みたいに、手作業で作るように感じるかもしれませんが、問題を作成するためのツールやシステムもありますので、積極的に活用していき、なるべく時間負担を軽減するようにするといいです。
- 生徒一人ひとりのレベルや目標に合わせた問題作成や、全体の学習進捗を考慮したカリキュラム作成も、日中の重要な業務です。生徒の理解度を深めるためのオリジナル問題や、定期テスト対策プリントなど、質の高い教材提供を心がけます。
- 講師への業務指示
- 授業を担当する講師への業務指示も塾長の役割です。生徒の学習状況や個別の指導方針を共有し、連携を取りながら質の高い授業を提供できるようサポートします。
生徒に指導するにおいて、講師たちが知りたいことは何でしょう。
生徒の属性的なものもそうなのですが、一番は「前回はどんなことをやったのだろう」ここです。生徒の担当が自分以外居ないのであれば自分が把握していればいいのですが、夏期講習や冬期講習などの講習期間になりますとなかなかそうもいきません。
講習期間はそれまでの通常期間よりも授業数が多くなるのが普通です。場合によっては、通常時期の10倍近い授業数になる場合があるのです。
さすがに・・・この生徒の担当は自分!ということをどこまでも通すことは難しくなります。この期間は複数の先生が生徒の担当を受け持つようになるのが普通だととらえておきましょう。
完全に担当制を維持できる・・・というのは、よほど生徒数が少ない教室ということで、逆の意味であまりよくない兆候かもしれません。
今日担当する生徒が前回どのような箇所を学び、どこで躓いていて、どこに課題があるのかを限られた時間で会得するには、その講師の慣れというよりも、システムでフォローしてあげる必要があると思います。

重要ポイント!講師への業務指示と共有のための時間コストを大幅に減少させるためのスペシャルツール!
クロスM&Aは、他社との差別化を徹底して図ってまいります。
その一つが、信じられないぐらいに手厚いアフターフォローなのですが、このシーンで役立つ(本当に、本当に、ものすごく役立つ)ツール作成のお手伝いをします。
ツールの作成!?
それって無料なの?
ご安心ください。ツールの作成補助及び料金はかかりません。人たち作成したら、必ず運営に役立ちますし、必ず気に入っていただけます!
具体的には、ここで こういうもので、ああいうものでと申し上げてもなかなか伝わりきらないと思いますので、
まずは学習塾への開校へのお気持ちが固まってきたら、弊社サービスの「モデルルーム」をご利用いただき、現場でデモをご覧ください。
多分・・・デモをご覧になれば、「うぉ」とかそういう声が漏れるかもしれません。
生徒対応と授業:夕方から夜にかけてのメイン業務
教室長(塾長)自らが生徒の授業に入ることが「ある」場合と「ない」場合と「たまにある」場合などで時間配分がちがうと思います。
自分自身が授業に入るメリットは、生徒の学習状況を自分自身が把握できる点と講師にかかるコストをカットできる点です。
デメリットは、その時間にもし保護者が来校された場合は、対応に苦慮します。また、その他の事務作業に滞りがでます。
とても悩ましいところですが、個人的には、教室長(塾長)は極力授業に入らないほうが良いと思います。ものすごくバイタリティ溢れる管理者でしたら、その限りではありません。
教科指導もバリバリできる!教室運営の経営要素も全部こなせる!ということであれば、かえってそのようにアレもコレもと、忙しく動いていたほうがいい!と感じる場合もあるでしょうね。
ただし、保護者の存在はとても大きいです。
保護者の来校、来塾をそっちのけにすることはなかなか難しいですし、ときに大きな機会損失につながる恐れもあるのです。
このあたりのバランスをどうとるか、を考えていくようにしましょう。
- 生徒との面談
- 必要に応じて生徒との面談も行います。学習の進捗状況の確認、悩み相談、進路相談など、生徒一人ひとりと向き合い、個別のサポートを提供します。生徒のモチベーション維持や学習意欲向上に直結する大切な時間です。
- 必要に応じて生徒との面談も行います。学習の進捗状況の確認、悩み相談、進路相談など、生徒一人ひとりと向き合い、個別のサポートを提供します。生徒のモチベーション維持や学習意欲向上に直結する大切な時間です。
- 保護者への授業報告
- 授業終了後には、保護者への授業報告を行います。生徒の学習態度、理解度、今後の課題などを伝え、家庭学習へのアドバイスも行います。保護者との密なコミュニケーションは、信頼関係を築き、生徒の成長をサポートするために不可欠です。
- 授業終了後には、保護者への授業報告を行います。生徒の学習態度、理解度、今後の課題などを伝え、家庭学習へのアドバイスも行います。保護者との密なコミュニケーションは、信頼関係を築き、生徒の成長をサポートするために不可欠です。
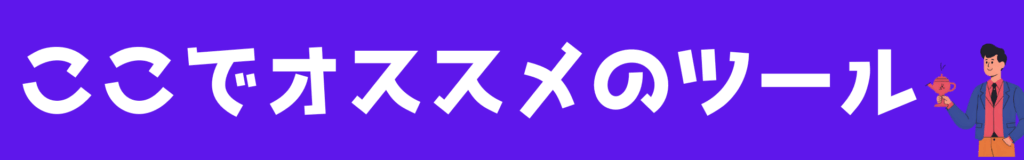
「またか!?」
そう思わないでください。
実はこの保護者への授業報告においてもクロスM&Aは、飛躍的進化を遂げた無料ツールの作成をお手伝いしております。
もちろん
有料で毎月うん万円というシステムコストだけど、まぁそれはふつうでしょ?と思われる経営者様は、本項目は無視していただいても大丈夫ですが、
毎月何千円、1万円でもコストカットはしたほうがいいという考えがクロスM&AのT部長の考えです。
一か月のコストとしてとらえるのではなく、年間でとらえると例え1万円のコストカットであっても年間12万円のコストカットで、ipadがうまくすれば3台買えます。
そんなスペシャルツールにおきましても、やはり百聞は一見にですから、モデルルールでぜひご確認ください。
繁忙期:塾長の腕の見せ所
通常業務に加え、時期によって発生する特別な業務も塾長の重要な役割です。これらの繁忙期をいかに乗り切るかが、塾の成長を左右すると言っても過言ではありません。
ところで皆さんは、特に学習塾における繁忙期はいつぐらいだと思われますでしょうか。
多くの方が
「7月とか8月でしょうか」と、夏期講習のメインとなる時期を想像されます。ですが、実際に業務を行っていきますと、そういう講習の実施時期よりも「実施前の時期」のほうが繁忙期であるということに気づかれるはずです。
それはなぜかというと、保護者との「面談」があるからです。
面談実施時期:生徒と保護者の未来を考える
保護者との面談は、業務の中でも重要度が一番高い位置にあると思ってください。なぜなら、生徒はプレイヤーですが、保護者は決断者だからです。
特に以下の時期は、集中的な面談期間となります。
- 1月〜2月:新年度に向けた面談
- 学年末を迎え、新学年での学習計画や進路について話し合う大切な時期です。新年度のカリキュラム作成や、生徒一人ひとりの目標設定のための準備に多くの時間を費やします。
- 5月〜6月前半:夏期講習前の面談
- 夏の長期休暇を活用した夏期講習の提案や、これまでの学習状況の振り返りを行います。夏期講習のカリキュラム作成や、講習内容の説明資料作成などもこの時期に集中します。
- 9月後半〜10月:冬期講習前の面談
- 受験を控える生徒にとっては特に重要な時期です。冬期講習での学習内容や、入試に向けた最終調整について話し合います。受験戦略の立案や、個別指導のプランニングなども行われます。
これらの面談期間は、カリキュラム作成や面談資料の準備など、通常業務に加えて多くの準備が必要となります。
保護者と生徒を交えた三者面談、または保護者との二者面談のいずれかになりますが、現状の課題点を浮き彫りにして、今後はこういう方針で進んでいきましょう!という方針のすり合わせの場になるのですから、口頭だけの話し合いよりも資料をしっかりと準備したうえでの対話になったほうが、印象にも残りやすいのではないでしょうか。
テスト対策期間:生徒の「できる!」を最大限に引き出す
定期テスト前は、生徒たちの成績向上を左右する重要な期間です。
- 徹底的なテスト対策
- 生徒のテスト範囲に合わせた対策プリントの作成は必須です。学校ごとの出題傾向を分析し、効率的な学習ができるような問題を作成します。
- テスト対策のためのイベントも考案し、実施します。例えば、集中勉強会、確認テスト、塾内での模擬試験、テーマ別集団クラスなど、生徒がテストで良い結果を出せるよう、あらゆる角度からサポートします。
- これらのイベントを告知するためのチラシ作成や、イベント内容の企画・運営も塾長の大切な業務です。
テスト後:次につながる振り返り
テストが終わればそれで終わりではありません。
- 結果分析とフィードバック
- テスト結果を分析し、生徒一人ひとりの弱点や課題を明確にします。
- 生徒や保護者との面談を通じて、テスト結果のフィードバックを行い、今後の学習計画に反映させます。
このフィードバックも非常に重要度が高いです。
それは、結果が良かった場合よりも悪かった場合のケアも必要になるからです。
とかく結果が良かった場合は、保護者へも「よく頑張りましたね!」と連絡はしやすいでしょう。
逆に、悪かった場合は連絡もしにくいかもしれません。
運営でのコツにもあたると思うのですが、
悪いことから逃げないこと!これは本当に重要だと思います。 - 改善点や次回のテストに向けた目標設定を行い、生徒の成長を継続的にサポートします。
まとめ:教室長(塾長)という仕事の魅力とやりがい
教室長(塾長)の一日は、生徒の指導から教室運営、広報活動まで多岐にわたります。特に新規開校となれば、これらすべての業務をゼロから立ち上げる大変さも伴います。しかし、生徒たちの「わかった!」「できた!」という喜びの声を聞いたとき、そして彼らが目標を達成し、成長していく姿を間近で見られることは、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。
今回ご紹介した一日の流れや繁忙期の業務は、あくまで一般的な例です。塾の規模や形態、地域性によっても業務内容は異なりますが、この記事が学習塾の新規開校を考えている皆さんの参考になれば幸いです。
学習塾の開校は、子どもたちの未来を応援する素晴らしい仕事です。ぜひ、情熱と覚悟を持って、この挑戦に臨んでください。


学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備