退塾の判断は?通知表より定期テスト!その心理と答え
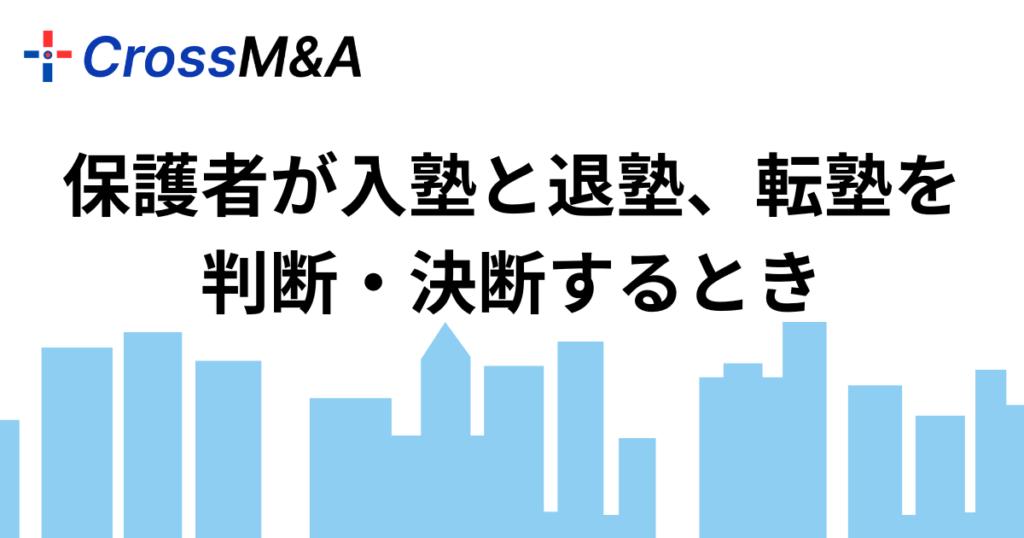
定期テストと通知表、どちらが子どもの「今」を映すものなのか?
通知表。 ドキドキしながら開く通知表に、一喜一憂した経験は誰にでもあるでしょう。 「よく頑張ったね!」 「もっと頑張らないとね…」 そんな親の声かけに、子どもたちはどんな感情を抱くのでしょうか。
一方で、定期テストの結果はどうでしょうか? テストが返ってきた日、点数を見て思わずため息をついたり、ガッツポーズをしたり。 通知表の評価とは異なり、その場で明確な数字として結果が突きつけられます。
では、子どもの成長を測る上で、通知表と定期テスト、どちらをより重視すべきなのでしょうか?
多くの保護者が、通知表よりも定期テスト(※小学生であればカラーテスト)の結果に注目しがちです。
それでは、
①保護者が塾に行かせるべきだと判断するときはどんなときなのでしょうか?
②また、現在すでに通塾しているけれど、転塾すべきだと判断するときはどんなときなのでしょうか?
この記事は、現在 学習塾を経営されているオーナー、教室長、塾長向けの内容です。
この①と②の回答そのものが、退塾というものを考えるときに非常に重要な視点となります。
通知表が示すのは「先生から見た姿」、テストが示すのは「絶対的な実力」
子どもたちの学校生活を客観的に評価する通知表は、その学期の学習態度や提出物、授業中の発言、そして定期テストの点数などを総合的に判断して作成されます。 通知表の評価は、先生が子どもたちの学校生活を丁寧に観察し、多角的な視点から判断したものです。 つまり、通知表は「先生から見た子どもの姿」を映し出しています。
一方、定期テストはどうでしょうか? 定期テストは、その学期に学んだ内容をどれだけ理解しているかを測るためのものです。 テストの点数は、その時点での学力や知識量を客観的な数値で示してくれます。 満点が100点である場合が多く、保護者自身も経験しているため、点数を見ただけで子どもの理解度がどのくらいか、直感的に判断しやすいという利点があります。
なぜ通知表はわかりにくいのか?
通知表の評価がわかりにくいと感じる背景には、各学年における評価方法の違いがあります。
小学生:数字では測れない成長
多くの小学校では、通知表に5段階評価のような数字の評価は使われていません。 代わりに、「よくできました」「もう少しです」といった言葉による評価や、具体的な項目ごとに細かく記載されるのが一般的です。
これは、まだ学習習慣や生活習慣が定着していない小学生にとって、数字で評価することが適切ではないという考えがあるからです。
「先生の話をしっかり聞けているか」「友達と協力して活動できているか」「自分の考えをしっかり発表できているか」といった、学習態度や社会性を評価する項目が中心となります。
しかし、保護者からすると「結局、どのくらいできているの?」という疑問が残りやすく、客観的な判断が難しいと感じる要因となります。
中学生:3から4、4から5…見えにくい「歩み」
中学生になると、5段階評価が主流になります。 しかし、この評価方法が保護者の悩みの種になることも少なくありません。 例えば、前回は3だった科目が、今回は4になったとします。 もちろん、これは素晴らしい進歩です。
しかし、「3から4に上がるために、具体的に何をどのくらい頑張ったのか?」が、この数字だけでは見えにくいのです。
テストの点数が10点上がったのか、提出物の質が上がったのか、授業中の発言が増えたのか。 「3」と「4」の間にある、子どもたちの努力や成長の過程が、数字に集約されてしまうことで見えにくくなってしまいます。
さらに、内申点に影響するため、「どうすれば5が取れるのか」というプレッシャーが、子どもたちにかかることもあります。
高校生:評定平均の壁
高校生になると、通知表の評価はさらに複雑になります。 大学入試の合否に影響する「評定平均」は、各科目の評定を合計して科目数で割ったものです。 そのため、特定の科目で高得点をとっても、苦手な科目の評定が足を引っ張ってしまうことがあります。 個別の科目の評価を見ても、その科目のテストで何点取ったか、文系理系やその他コースなどもあるため、学校内でどのくらいの順位なのかが分かりにくく、全体的な学力レベルを把握するのが難しくなります。
評定値の計算は、たいていは別紙での説明書が渡されるか、個票内に書かれてあり、自分で計算して算出するタイプ、または学校側が計算して記載してくれているタイプがあります。
とは言え、科目数も多く保護者がパッと見てイメージがしにくくなっています。
また、算出された評定値ではなく、実際に使われる指標は評定平均値となるため、1年のときからの積み重ねが必要です。
この意味合いを高校入学時からしっかりと理解し、目的をもった学習継続が出来ている生徒はさほど多くありません。(高校1年生の通塾率は中3と比較して大きくダウンする)
テストの結果はなぜ判断しやすいのか?
通知表がわかりにくいと感じる一方で、定期テストの結果が多くの保護者にとって「子どもの今」を測る基準となっているのには、いくつかの明確な理由があります。
1. 誰もが知っている「100点満点」という共通の尺度
多くの定期テストは、昔も今も変わらず100点満点で採点されます。 この「100点満点」という尺度は、時代や地域、そして学校が違っても共通の理解を得やすい基準です。 保護者が子どもの頃に経験したテストと同じ形式であるため、子どもが取った点数がどのくらい「良い」のか、直感的に判断することができます。 例えば、70点という点数を見れば、「もう少し頑張れば80点、90点に届くかな」という具体的な目標をイメージしやすいのです。
2. 目に見える「数字」が与える安心感と納得感
テストの点数は、紛れもない「数字」です。 100点満点中85点、75点、50点。 この数字は、子どもたちの努力や理解度を明確に示してくれます。 通知表の「よくできました」という言葉よりも、85点という数字の方が、保護者にとっては「この子はよく頑張ったんだな」という納得感を与えてくれます。 また、前回と比べて10点上がったという事実があれば、「この勉強法が効果があったんだ」と、次につながる具体的な手応えを感じることができます。
3. 「ライバル」との比較が容易
多くの学校では、定期テストの結果と同時にクラス内や学年内の順位が示されます。 これは、子どもたちの競争心を煽る一方で、保護者にとっては「うちの子は、全体の中でどのくらいのレベルにいるのか」を客観的に把握する手段となります。 友だちやライバルの点数と比較することで、相対的な位置を確認し、今後の学習計画を立てる上での参考とすることができます。

さて、ここからが主題です。
確かに通知表は若干漠然としていて、2と3の違い、3と4の違い、4と5の違いが少々ぼんやりしている感じがします。
実際には、
・知識、技能の面での採点
・思考、判断、表現の面での採点
・積極的な学習への取り組みの面での採点
この3つがあってその総合評価が通知表なのですが、それでも保護者から見たら少々ぼんやりしているため、その明確な基準がわかりにくいことも相まって、時に「何故5だったのに、4になったの?」「なんで3から4に上がったのだろう」「あの点数なら2は覚悟したのに、3をつけてくれたのかしら」
そんな不思議な思いを抱くことも多いでしょう。
しかし、テストの結果は違います。
ズバリ言えば、通知表よりもこの学校で実施されているテスト結果のほうを保護者は重視しています。小学生であればカラーテスト、中学生であれば定期テスト、高校生であれば定期考査です。
その他、例えば文科省主導の学力テストとか、学校で実施される実力テストなどは、成績には入らないことがわかっているため、さほど重視はしていないです。
この定期テストは、しっかりと結果を見ていて、次のアクションの大きなきっかけとなります。
①このままではまずい・・そろそろ塾に行かせないと!
②塾に行かせているのに、この結果?
③今回の結果から、早々に転塾したほうがいいだろう
保護者のアクションは定期テストの結果で決まります。
「心理」と「答え」:通知表とテストの真の価値
通知表と定期テスト、どちらをより重視すべきかという問いに対する答えは、「どちらも重要であり、両方を組み合わせることで子どもの本当の姿が見えてくる」というのが適性な答えだと思います。
しかしながら、保護者が何かしらのアクションを起こすきっかけとなるのは、圧倒的に「テスト結果」であることが多いのです。
保護者が定期テストの結果を重視する心理は、「客観的でわかりやすい評価を求めるから」に他なりません。 複雑で主観的な要素も含まれる通知表の評価よりも、明確な数字で示されるテストの点数の方が、安心感と納得感を与えてくれるのです。
確かに、テストの点数だけでは見えないものがあります。
それは、「子どもの努力の過程」や「学習への向き合い方」だったりします。
テストで満点を取ったとしても、その子が授業中に真剣に先生の話を聞いているのか、提出物を期限内にきちんと出せているのか、友だちと協力して課題に取り組めているのかは、テストの点数だけでは分かりません。この部分が学習への積極的な参加という評価項目です。
ここまでをしっかり見る意味で、通知表は真価を発揮します。
通知表の「言葉による評価」や「態度」に関する項目は、テストの点数には現れない、子どもの内面的な成長や学習への姿勢を示してくれます。 例えば、テストの点数が悪かったとしても、通知表に「授業に真剣に取り組んでいる」と書かれていれば、「今は結果が出なくても、真面目に頑張っているんだな」と、子どもを信じて見守ることができます。
つまり、定期テストは「結果」を、通知表は「過程」を映し出すものだと言ってもいいでしょう
保護者目線、親目線、及び 何らかの所感やコメントを発する必要がある教室長や塾長、オーナーの目線で言えば、
子どもの成長を真に見抜くためには、この2つ両方とも覗き込む必要があります。
テストの点数が悪かったとき、ただ「もっと頑張りなさい」と叱るのではなく、通知表の「態度」や「提出物」の項目を見て、「授業中は集中できているみたいだね。あとは、家での勉強方法を一緒に考えてみようか」と、具体的な改善点を話し合うことができます。
逆に、テストの点数が良かったときも、通知表を見て「授業中に積極的に発言できているみたいだね。その調子で、これからも頑張ってね」と、結果だけでなく過程も褒めてあげることが大切です。
子どもたちの成長は、テストの点数という一本の線だけで測れるものではありません。 通知表に書かれた言葉の一つひとつ、先生からのコメント、そして子どもの表情や態度。 これらすべてを総合的に見つめることで、私たちは子どもの「今」をより深く理解することができます。
そして最後に、
塾を「経営している」オーナー、教室長、塾長という目線で言うと・・・単に保護者への次はこうします!という意気込み表明であるとか、結果が悪かったときの謝罪など、起こった事実に対してのアクションが、もし表面的なものであったならば、
それは一気に退塾者が増加することになります。
したがって、定期テストの結果というのは、運営上の注力度合いで言えば、トップクラスなのです。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目

2025年09月26日
塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について
#入塾面談
#塾の成功
#塾経営
#塾講師
#学習塾
#学習塾運営
#期限厳守
#生徒指導
#良質顧客
#顧客育成