感じませんか?小学生たちの学習意欲の高まりと学習力そのものの高まり
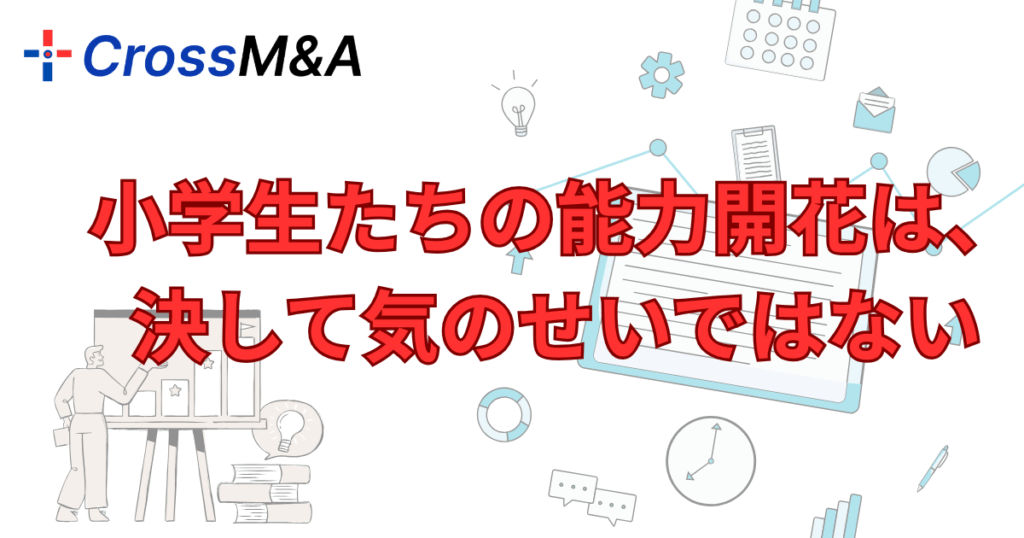
はじめに:現代小学生に見る「能力開花」の兆し
近年、小学生の持つ「学習意欲」と「学習力」の双方に高まりを感じるという声が、教育現場や保護者の間で散見されます。
これは気のせいではなく、実際に子どもたちの能力が「開花しつつある」かのような印象を受ける背景には、いくつかの社会的な要因や教育の変化が複雑に絡み合っていると考えられます。
正直なところ、「今の中学生よりもレベルが上がっている」と、塾運営のCROSS M&Aのアドバイザーもこの数年ずっと思っています。
本記事では、この「今の中学生よりもレベルが上がっている」という内見が何を意味するのかを深掘りしつつ、その要因となっている可能性のある「中学受験の加熱」「学習指導要領の改訂」「教育費の増加傾向」という三つの要素、そして「コロナ禍」の影響について考察します。
1. 「能力開花」を支える要因:三つの社会的背景
現代の小学生の学力や意欲が高まっているように見える現象は、以下の三つの大きな流れと無関係ではないでしょう。
1-1. 中学受験の加熱とその影響
近年、首都圏を中心に中学受験率が過去最高水準に達するなど、その加熱ぶりは顕著です。
2000年代以降、受験者数・受験率ともに増加傾向にあり、特に2020年代に入ってからはコロナ禍による公立校への懸念や、公立中高一貫校の増加なども相まって、その流れは加速しています。
【学習塾買収検討の方へ朗報】個別指導塾で中学受験生徒開拓が成功トレンド!
自信のない人が多いからこそ「商機」:中学受験における個別指導塾はヒットする
- 「思考型」入試へのシフト: 従来の知識偏重型から、「考える力」「記述力」「論理的な説明力」を問う「思考型」入試への変化が進んでいます。これに対応するため、受験塾のカリキュラムも早期から高度な思考力を養成する方向に進化しました。小学生が低学年のうちから抽象的な概念を理解し、多角的に物事を捉えるトレーニングを積むことで、必然的にその後の学習の「レベル」が底上げされている可能性があります。
- 早期教育と選抜効果: 受験準備の開始年齢が低年齢化しており、小学4年生やそれ以前から本格的な学習に取り組む層が増加しています。これにより、同年齢集団の中で特に高い意欲と能力を持つ層が、早期から集中的な英才教育を受けることになり、その学力レベルが「今の中学生」の平均を上回るように感じられる可能性があります。
1-2. 新学習指導要領と「主体的・対話的な学び」
2020年度から小学校で全面実施された新学習指導要領は、子どもたちの学習に対する姿勢と内容に大きな変化をもたらしました。その根幹にあるのは、「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の推進です。
- 探究活動の重視: 授業の中で「グループで調べたり考えたりする」「自分たちで決めたテーマについて調べる」「発表する」といった探究的な活動が増加しています。これにより、知識を一方的に受け取るだけでなく、「なぜ?」「どうして?」と考え、自ら課題を見つけ、解決する能力が養われつつあります。この能力は、従来の「知識・技能」だけでなく、社会で生きて働く「思考力・判断力・表現力」として評価されるものです。
- デジタル機器の活用: GIGAスクール構想により、児童生徒一人一台のデジタル端末が整備され、授業での活用が大幅に増加しました。デジタル機器を用いた調べ学習や表現活動は、学習への興味・関心を高め、「学びたくなる環境」を整備する一助となっています。
1-3. 1人当たりにかける教育費の増加傾向
子ども一人当たりにかける教育費、特に学校外教育費の増加傾向は、親の「教育熱心さ」の表れであり、学力向上の一因と考えられます。
- 学校外教育費の増加: ベネッセの調査(2023年時点)によると、小学生(小1~6生)の1人当たりの教育費は、2015年頃と比較してわずかに増加傾向にあります。特に高年収層(世帯年収800万円以上)での増加が顕著で、世帯年収による教育費の差が拡大している傾向が示されています。
- 格差の拡大と質の向上: この「教育費の増加」は、経済的な背景を持つ家庭が、塾や習い事などを通じて、より質の高い教育機会や早期からの専門的な指導にアクセスしていることを示唆しています。結果として、投資を受けた子どもの層が高度な学力を獲得し、全体的な水準を引き上げている可能性があります。ただし、これは同時に教育格差の拡大につながる懸念も示唆しています。
2. 意欲と学力の「高まり」に対する二つの視点
ご指摘の小学生のレベルアップは、上記の環境変化によって実際に起きている現象かもしれませんが、その解釈には二つの視点が必要です。
2-1. 「レベルアップ」の正体:知識量から思考力への移行
「今の中学生よりレベルが高い」と感じられるのは、単に知識量が増えたからではなく、彼らが「知識・技能」を「活用する力」という、新しい学力の形を身につけ始めているからです。
- 早期の抽象化能力: 中学受験や新指導要領の影響で、小学生のうちから物事を論理的に捉え、抽象化する能力が鍛えられています。これは、中学以降で学ぶより複雑な内容への対応力(接続)を高め、結果として「進んだ」学習をしているように見えるのです。
- 情報活用能力: デジタルネイティブとして育ち、GIGA端末にも慣れた現代の小学生は、情報収集・分析・発信といった情報活用能力に長けています。これらは学習活動全般の効率と質を向上させています。
2-2. 意欲の二極化:高まる層と低下する層
しかし、データによると、全ての小学生の学習意欲が一律に高まっているわけではありません。東京大学などの調査(2019年〜21年の3年間)では、「勉強しようという気持ちがわかない」と回答する子どもが半数を超え、学習意欲が低下した子どもが25.8%と、向上した子ども(11.2%)を大きく上回る傾向も報告されています。
これは、上述の要因が「意欲・能力の高い層」をさらに引き上げ、そうでない層との格差を広げている可能性を示唆しています。高いハードルと競争意識の中でモチベーションを保てる子どもは伸びますが、そうでない子どもは「ついていけない」「わからない」と感じ、かえって意欲を低下させているのかもしれません。
3. コロナ禍の影響:学力と世代間の特異性
ここで、あなたの疑問である「コロナの発生時に受験生だった子たち」の学力への影響について考察します。
2020年、21年、22年、この辺りで小学5年、6年、中2、中3、高校生だった子たちの学力は今よりも若干低めなのでは!?
この懸念は、複数の研究や調査によって裏付けられている部分があります。
3-1. コロナ禍による学習遅延と格差の拡大
2020年春の一斉休校は、日本の学校教育に大きな影響を与えました。多くの地域で数週間から数ヶ月にわたり授業が停止し、その後の短縮授業や行事削減をもってしても、学習時間の完全な補填は困難でした。
- 学力低下の懸念: 尼崎市の行政データを用いた分析(2023年公表)など、一部の研究では、休校から約1年半経過後も、特に国語の低学年、算数/数学の全学年で学力が依然として低下したままであることが示されています。
- 世帯年収による格差の拡大: 休校期間中、学習時間を確保できたか否かは、家庭の経済状況(世帯年収)と密接に関係していました。年収の高い世帯では、学校外の勉強時間(塾、オンライン教材など)を増やし、学習の遅れを積極的に取り戻そうとする傾向が見られました。一方で、低い世帯ではそれが難しく、結果として学力格差が拡大したことが示唆されています。
3-2. 「コロナ世代」の特異性
2020年・21年・22年に、学校の中核的な時期(小学高学年、中学・高校の受験学年など)を過ごした世代は、以下のような特異性を持ちます。
| 年代の区分 | 該当する学年(2020年頃) | コロナ禍の影響 |
| 小学生(低学年) | 小学1〜4年生 | 学校行事の中止・縮小、集団活動の制限はあったが、純粋な学習内容は休校明けの補填やデジタル導入で比較的巻き返しやすかった層。現在の小学生はこの世代の直後であり、ICT活用などはスムーズに移行できている。 |
| 小学校高学年・中学生 | 小学5・6年、中学2・3年 | 学習内容の習得に大きな遅延が生じた層。特に中学3年生は、受験直前に休校となり、学習指導と進路決定の両面で困難に直面しました。この世代は、基礎学力の定着にバラつきが生じている可能性があります。 |
| 高校生 | 高校生全般 | 部活動や行事の縮小(心理的影響)に加え、大学受験への影響も懸念されました。オンライン授業への対応や自律学習の経験が、かえって自己管理能力を高めた層もいる一方で、対人交流の機会が制限された層もいます。 |
結論として、
2020年頃に小学校高学年や中学・高校の受験学年だった世代は、学習機会の喪失とそれに伴う格差拡大の影響を最も強く受けた可能性があり、
その世代の平均的な学力は、影響が薄れ、新しい教育環境に適応した「今の小学生」と比較して、一部で「若干低め」であるという見方は、一定の根拠を持つと言えるでしょう。
4. まとめ:新しい学力の形と未来への課題
現代の小学生の「学習意欲の高まりと学習力そのものの高まり」は、中学受験の加熱、新学習指導要領による思考力重視への転換、そして教育への投資額の増加という三つの複合的な要因によって生み出された「新しい学力の形」と捉えることができます。
これは、従来の「詰め込み」型の学力ではなく、「自ら考え、探究し、表現する」という、社会が求める高度な非認知能力に基づいた学力の開花であると言えます。
しかし、この「能力開花」は、教育格差の拡大という影を伴っています。全ての児童が等しく恩恵を受けているわけではなく、高い水準を維持・向上させる層と、意欲を低下させる層の二極化が進んでいることも無視できません。
「今の小学生のレベルが上がっている」という実感は、最も意欲と能力が高く、充実した教育環境にいる層が、新しい学習要領と競争環境の中で、従来の世代よりも早期に高度な能力を開花させている、という現象を捉えているものと考えられます。
この流れをポジティブなものとして維持し、全ての子どもたちの可能性を最大限に引き出すためには、教育におけるICT活用と個別最適化を進め、経済的背景によらない学習機会の確保と、「意欲を低下させている層」への丁寧な支援が、今後の日本の教育における重要な課題となるでしょう。
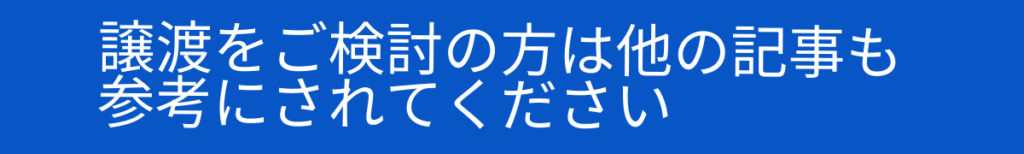
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月31日
なぜ「低単価・多人数」の塾は強いのか?長期繁栄を実現する経営戦略
#リスク分散
#一人当たり単価
#収益構造
#収益構造シミュレーション
#口コミの母数
#塾運営の標準化
#学習塾経営
#授業頻度の法則
#生徒数最大化
#経営の安定化
#講習平均単価

2026年01月19日
2026年1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト!ここから読み取る大学入試の変化
#2026年
#タイムマシン
#ベルサイユのばら
#入試改革
#大学入学共通テスト
#思考力
#探求学習
#文理融合
#新課程入試
#歴史総合

2026年01月13日
私立中学や私立高校で「大学へ直結する、思考型の学習」をテーマに学習カリキュラムを革新的に変更しようとする流れ!
#カリキュラム
#パラダイムシフト
#大学入試改革
#学習塾
#思考型学習
#探求学習
#教育の未来
#私立校
#総合型選抜
#非認知能力