生徒数を増やす!無料イベントで塾の魅力を伝える実践ガイド
塾の生徒数を増やすために、無料イベントは非常に効果的な手段です。
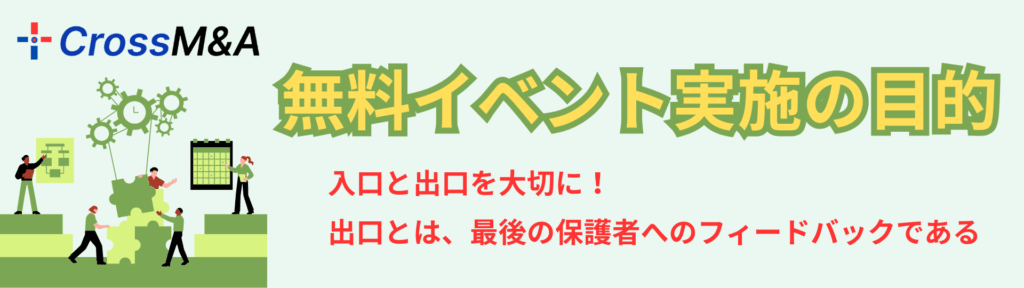
ただ漠然とイベントを開催するだけでは、期待したほどの成果は得られません。この記事では、私が過去の経験から学んだ、生徒募集につながる無料イベントの企画・運営方法を具体的にお伝えします。
特に、上記画像内でも書きました「出口とは、最後の保護者へのフィードバックである」という部分。このラストが非常に重要です。
開校2年目以降の教室長、塾長、オーナーに是非ご確認頂ければ幸いです。
塾運営、習いごと運営での肝は、「保護者」だと思います。
本記事は、アレコレと色々試し、成功も失敗も・・・みっともないぐらいの大失敗も経験したクロスマのアドバイザーが、背伸びした言葉ではなく、実際に成功するために必要な「素直な気持ち」と「シンプルな思い」を大切にした内容となっております。
どうして無料イベントは必要なのか!?
「生徒を増やすために、なぜわざわざ手間と時間をかけて無料イベントを開く必要があるのか?」
そう思われる方もいるかもしれません。
無料イベントを「集客のための手段」・・・・と考えてしまうと、若干違和感を抱かれるかもしれません。
・直接的で且つ即効的効果がなければ、無料イベントはあまり意味がない
・無料イベントを実施しても生徒が集まらない
などの疑問を持たれる教室長さんも多いことでしょう。
しかしながら、授業以外の無料イベントは、塾の存在を地域に根付かせ、未来の生徒たちとの信頼関係を築く上で、なくてはならない重要な役割を担っています。その理由を、3つの観点からお伝えします。
1. 塾の教育理念と価値を「体験」してもらう場
無料イベントの最大の目的は、塾の教育理念や取組みの本質、スタンスを、保護者と子どもたちに直接「体験」してもらうことです。
どれだけ素晴らしい教育方針を掲げ、充実した教材を用意していても、それを言葉だけで伝えるのには限界があります。
体験談や口コミは参考になりますが、実際に自分自身の目で見て、肌で感じなければ、本当の価値は伝わりません。
無料イベントは、その壁を打ち破るための最適な機会です。
例えば、通常の授業では体験できないような、単元を絞り込んだテーマ演習や、理社を中心とした講座などを実施することで、「この塾の授業は面白い」「先生は子ども一人ひとりにしっかり向き合ってくれる」といった、ポジティブな第一印象を与えることができます。
この「体験」が、保護者の方に「この塾なら、うちの子を安心して任せられる」という確信を与え、入塾への強い動機付けとなるのです。
2. 地域コミュニティとの接点をつくる
無料イベントは、塾と地域社会をつなぐ大切な接点でもあります。
普段、塾に通っていない方々にとって、塾は「入りにくい場所」かもしれません。しかし、無料のイベントを開催することで、塾の扉を開くきっかけを提供できます。
イベントを通して、保護者の方々と直接顔を合わせ、言葉を交わすことで、塾が地域の一員として、子どもたちの成長を応援しているというメッセージを伝えることができます。
イベントを通じて交流が生まれることで、保護者の方々が持つ「塾=勉強ばかりで厳しい場所」という固定観念を払拭し、「地域の子どもたちのための、開かれた学びの場」というイメージに変わっていくのです。
これにより、イベントに参加した方が、近所の方に「あの塾のイベント、良かったよ」と口コミを広げてくれることも期待できます。地域に根ざした活動を続けることで、塾は単なる学習塾ではなく、地域になくてはならない存在へと成長していくことができます。
3. 将来の塾生との出会いの場
無料イベントは、単発の集客イベントではなく、将来の塾生との「出会いの場」です。
イベントに参加した子どもたちは、塾の先生や雰囲気に触れることで、塾に対する親しみを感じてくれます。たとえイベント直後に入塾しなくても、「〇〇塾の先生、面白かったな」「また行ってみたいな」という良い記憶が残ります。
そして、彼らが学年が上がり、本格的に塾を検討する時期になったとき、最初に頭に浮かぶのが「あの時の塾」になる可能性が高いです。
私たちは、無料イベントを通して、「未来の生徒の芽」を蒔いているのです。その芽を大切に育て、継続的なコミュニケーションを取ることで、数年後の入塾に繋がることも少なくありません。
目先の生徒数だけでなく、将来の生徒数を増やすための「種まき」として、無料イベントは不可欠なのです。
企画は1ヶ月前、アナウンスも1ヶ月前からが基本
無料イベントを成功させるためには、十分な準備期間が不可欠です。
結論から言うと、企画と告知はイベント開催の1ヶ月前から始めましょう。
なぜ1ヶ月前なのか? それは、保護者の方々が「予定を立てる」のにちょうど良い期間だからです。
開催直前に告知しても、すでに他の予定が入っていて参加できない可能性が高まります。かといって、あまりにも早く告知しすぎると、イベントの存在自体を忘れられてしまうこともあります。1ヶ月前という期間は、参加を検討する時間、他の予定を調整する時間として、最もバランスが取れているのです。
【具体的なスケジュール例】
- 1ヶ月前:
- イベントのテーマ、日時、場所、対象学年、定員を決定
- 告知物の制作開始(チラシ、ポスター、Webサイト、SNS用の画像など)
- 塾内での役割分担(当日受付、質問対応、講師担当など)
- 3週間前:
- 告知スタート。チラシを近隣に配布、WebサイトやSNSで告知
- 予約受付開始
- 2週間前:
- 予約状況を確認し、必要に応じて追加告知
- イベント内容の最終調整、使用する教材や資料の準備
- 1週間前:
- 参加者へのリマインダー連絡(メールや電話)
- 当日のシミュレーション、備品の最終チェック
このスケジュールを徹底することで、余裕を持った運営が可能になり、当日のトラブルも未然に防ぐことができます。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
今までたくさん実施してきた中で、成功したイベント、実施したら確実に人を呼び込めるイベントをいくつか紹介いたします。
①塾内模試
受験生向けの塾内実施の模試を実施する場合には、受験生にとっても大切な「定期テストの前」の時期を外した時期に開催するとよいです。
会場模試が開催する5月に実施すると、参加者はほぼ全員になるでしょう。
(6月は英検や、二学期制の学校の定期テストがある。三学期制の学校は5月が中間テストなので、またそれよりも前がいいかも)
②理社特訓
普段の授業で、「英語」と「数学」の受講をしている生徒が多い場合には、理社特訓はとても効きます。やり方は、特訓ですので、暗記が苦手な子でもついてこれるような内容にすると評判もよくなります。
③テーマ別勉強会
こちらは、数学でお勧めの手法です。
どの学年であっても方程式が終わった後は、関数に入ります。例えば中学1年生は「比例・反比例」、中学2年生は「一次関数」、中学3年生は「二次関数」このように実施単元を決めて、講義の時間も決め、実施する内容も基礎確認、標準、利用問題とすれば、かなり実のある勉強会になります。
ちなみに、5教科で一番質問が多い教科は、ダントツで「数学」です。それがゆえに「数学」絡みのイベントはヒットしやすいです。
④学校ワークチェック
どの都道府県でも一緒ですが、定期テストの前に学校が指定したワークからの課題が出されます。今は、学校のワークをやっていれば点数が取れると言い切れる時代ではありませんが、少なくとも課題で出されているワーク範囲は提出期限を守り、提出しなければなりません。
家庭ではなかなかできない、課題チェックを塾が率先して実施し、質問も受け付けます。ワークの出来ない問題をその日のうちに解決していく目的があるため、参加者は安定して多いです。
「勉強とかけ離れたイベント」は失敗する
「生徒を増やすためには、まず塾に興味を持ってもらわなければ」と考え、勉強とは関係のない、たとえば工作教室やゲーム大会などを企画したくなるかもしれません。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
あるとき、耳を疑う提案がありました。
「教室で祭りをやりたい」という・・・。
これは許可を出した私自身に一番の責任があるのですが、学習塾の業務を行ってきた中で、一番の汚点だと今でも思っております。
結論から言えば、お菓子を準備、台となる机も買い(今から思えば本当に私自身がバカでした)、当日を迎えて 集客0人です。
穴があったら入りたい気持ちです。
ものすごく違和感を感じながらもなぜ許可を出したのかいまだに自分を呪うばかりです。
この経験から、絶対に学習塾のイベントでは遊び要素は1ミリも作らない!と心に誓いました。
後日ですが、今度は違う教室長から、人生ゲームみたいなゲーム(もう忘れてしまいましたが)を使ったゲーム大会をやりたいという申し出がありました。
私は心に誓った後でしたので、1秒で「やめてください」と決断を伝えました。
しかし、私の経験上、勉強とかけ離れたイベントは、生徒募集においては失敗に終わることがほとんどです。企画をしている段階では、企画をしている人、それが例えば教室長なのか講師なのかはわかりませんが・・・たくさんの生徒さんが来てくれる根拠のない妄想的なもので走りがちです。
学習塾です。
教室内でお祭りだとか、マインクラフトで一緒に遊ぼうだというイベントは、
客寄せパンダ的要素として良い企画と考えたかもしれません・・・・。
例えばくじ引きでお菓子がたくさん当たるとか、それに群がる子供たちはいないです。また保護者もそのイベントを重視することはありません。
なぜなら、塾に通わせようと考えている保護者が求めているのは、「お子さんの学力を向上させること」だからです。工作やゲームを楽しんでくれたとしても、「この塾は楽しそうだけど、本当に学力が上がるのかな?」という疑問が残ってしまい、入塾には繋がりません。
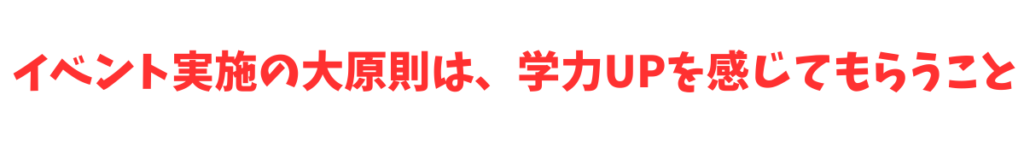
無料イベントは、「この塾に通えば、こんなふうに学力が伸びるんだ」という未来を具体的に体験してもらう場でなければなりません。
例えば、
- 「苦手な文章題がスラスラ解けるようになる数学講座」
- 「夏休みの宿題をサクッと終わらせるワークショップ」
- 「実験と観察に絡んだ問題 厳選20問特訓体験授業」
といった、「勉強」を主軸にしたイベントが成功しやすいです。
楽しいイベントを否定するわけではありません。(いえ、否定します)
しかし、その「楽しさ」は、あくまで「勉強の楽しさ」であるべきです。勉強の面白さを知ってもらうことが、塾の存在意義に直結するのです。
参加率を高めるための告知戦略
告知は単に情報を発信するだけでなく、「参加したい」という気持ちをいかに引き出すかが重要です。
まずは教室内の生徒へのチラシ配布、保護者への画像やPDF添付メールの送信、サイトへの記載、教室内の掲示、教室外向け掲示、教室の外用パンフレットラックへのセットと、内部の生徒さん向けに徹底します。
まず、最も効果的な告知手段は「手渡しできるチラシ」または「ポスティング」です。
チラシには、内部生向けであっても、「イベントの内容」「開催日時」「対象学年」「参加費(無料)」「問い合わせ先」を、簡潔かつ分かりやすく記載しましょう。
何故なら、内部生が友達へ案内をしてくれるかもしれないからです。
これらの案内は、「塾の生徒からの口コミ」となります。既存の生徒に「こんなイベントやるよ!」と声をかけ、友達を誘ってきてもらうのも非常に効果的です。信頼している友達からの誘いは、保護者にとっても安心材料になります。
また、保護者宛メールの添付画像、PDF、メール本文にも同様にしっかりと記載していくことをお勧めいたします。こちらも保護者が別の保護者へ案内をしてくれる可能性があるためです。
また、
WebサイトやSNSも活用します。特にSNSは、写真や動画を使ってイベントの雰囲気を伝えるのに適しています。たとえば、「前回のイベントの様子」や「講師の紹介動画」などを投稿することで、安心感や期待感を高めることができます。
。
告知の際に意識したいのは、「参加することで得られるメリット」を明確に伝えることです。
- 「参加するだけで、苦手な文章題の解き方がわかります!」
- 「〇〇中学用の対策問題集を進呈致します!」
- 「この夏休み、まわりと差をつける学習法を学べます!」
- 「イベント参加者には、入会金無料の特典があります!」
- 「ここだけしか知らない〇〇県公立高校対策 差し上げます!」
といったように、具体的なメリットを提示することで、参加へのハードルを下げ、申し込みに繋がりやすくなります。
テスト実施が圧倒的な反響を呼ぶ理由
数あるイベントの中でも、特に生徒募集に大きな反響を呼ぶのが上記にも書きましたが、なんだかんだ言っても塾内模試がナンバー1です。つまり「無料のテスト実施」です。
これは、保護者の「お子さんの現在の学力が知りたい」という根源的なニーズに応えることができるからです。
【テストイベントのメリット】
- 学力の可視化:
- テスト結果という客観的なデータで、お子さんの得意な分野、苦手な分野を具体的に知ることができます。
- 「現状」を把握できることで、保護者の危機感や学習意欲を高めることができます。
- 塾の教育力をアピールできる:
- テスト後の「個別フィードバック」は、塾の先生がどれだけ熱心に一人ひとりと向き合ってくれるかを直接伝えるチャンスです。
- テスト結果をもとに、具体的な学習プランやアドバイスをすることで、「この先生に任せれば、うちの子は伸びるかもしれない」という信頼感につながります。
- 入塾のきっかけが生まれやすい:
- テストで弱点が見つかった場合、「このままではいけない」という気持ちが強くなります。
- その場で「弱点を克服するための具体的な方法」として、塾のカリキュラムやコースを提案することで、スムーズに入塾を促すことができます。
テストイベントを実施する際は、「テスト結果を基にした無料個別学習相談会」をセットで企画するのがおすすめです。

逆を返せば、テストイベントを実施しても、保護者に対してのフィードバックが何もなければ、次回からの参加人数が減ってしまうことでしょう。
テストイベントは、参加してもらうための口実的なものではありません。
①実際にテストを真剣に受けてもらい
②どこが出来ていて、どこが出来ていないのかを生徒とともに確認し
③具体的にどのように学習すべきかを指導していく
④そして、保護者に一連の内容を報告する(重要!!:フィードバック)
さらに言えば、もしそのテストが受験生向けや、塾内模試的なものであれば、
テストの点数だけを渡すのではなく、保護者と直接対話する機会を設けることで、より深い信頼関係を築くことができます。
まとめ:シンプルに、正直に、塾の価値を伝える
生徒数を増やすための無料イベントは、奇をてらう必要はありません。
- 1ヶ月前からの計画と告知
- 勉強の楽しさを伝えるイベント内容
- 参加メリットを明確にした告知
- テスト実施による学力把握と個別相談
この4つのポイントをシンプルに、そして正直に実行することが、生徒募集成功への一番の近道です。
大切なのは、
塾の先生たちが「本気で子どもの学力を伸ばしたい」という思いを、イベントを通して保護者の方々に伝えることです。その熱意は必ず伝わり、生徒と保護者の心を動かします。
特別な言葉はいりません。ありのままの自分たちの想いを、イベントという形で表現していきましょう。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク
関連記事

2026年02月05日
学習塾において、春期面談時に押さえるべきポイント ◆◆◆8つの重要項目について
#会場模試
#保護者面談
#学習塾
#授業計画
#教材選定
#新受験生
#春期講習
#春期面談
#継続確認
#英検対策

2026年01月14日
学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)
#保護者面談
#個別指導提案
#入試情報提供
#受験生意識付け
#塾テキスト推奨
#学習塾経営
#新年度カリキュラム
#春休み学習計画
#春期講習
#継続率向上

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導