塾の「儲けの仕組み」を徹底解剖!新規参入・買収で高収益を目指す戦略(生データでリアル分析!)
はじめに:塾は本当に「儲かる」のか?そのカラクリを解き明かす
「塾は儲かる」という話を聞いたことはありませんか?
少子化が叫ばれる現代において、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。しかし、結論から言えば、塾は明確な「儲けの仕組み」を理解し、そのメカニズムを最大限に活用できれば、非常に高い収益性を実現できるビジネスです。
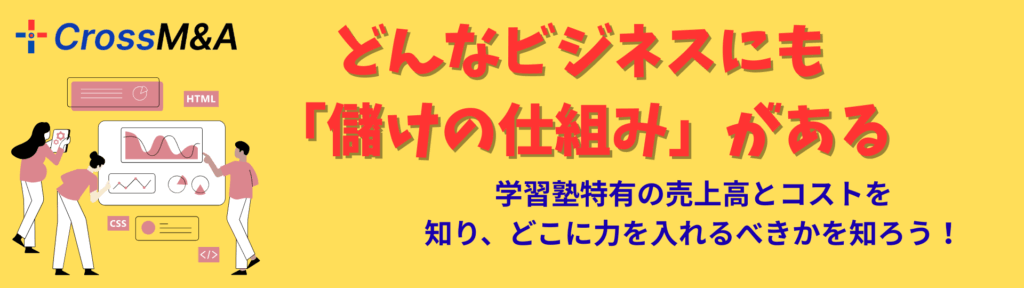
この記事では、
・これから塾の開業を考えている個人の方
・異業種からの新規参入を検討している法人
・そして塾の買収によって事業拡大を目指す方々
に向けて、塾がどのようにして「儲け」を生み出し、その利益を最大化するのか、その具体的なカラクリと戦略を余すことなくお伝えします。
単なる生徒集めではなく、いかに効率的に収益を上げ、持続的な利益を確保するのか、その秘訣を深掘りしていきましょう。
塾ビジネスの基本的な「儲けの仕組み」
塾の基本的な儲けの仕組みは、至ってシンプルです。生徒から授業料や各種費用(入塾金、教材費、季節講習費など)を受け取り、そこから運営にかかる様々な経費(人件費、家賃、広告費など)を差し引いたものが「利益」となります。しかし、このシンプルな構図の中に、利益を最大化するための重要なレバー(要素)が隠されています。
1. 売上の構成要素:儲けの「入り口」を広げる
塾の売上は、主に以下の3つの要素の掛け算で決まります。
売上=生徒数×生徒一人あたりの平均単価
そして、生徒一人あたりの平均単価は、さらに以下の要素に分解できます。
生徒一人あたりの平均単価=基本授業料+オプション費用(教材費、季節講習費、特別講座費など)
これを踏まえると、売上を最大化するための基本戦略は次の通りです。
- 生徒数を増やす: 新規生徒の獲得と既存生徒の退塾防止が鍵です。
- 生徒一人あたりの平均単価を上げる: 提供するサービスの付加価値を高め、より多くの費用を生徒から得られるようにします。
2. コストの構成要素:儲けの「出口」を絞る
売上を増やしても、コストがそれ以上に膨らんでしまっては利益は残りません。塾の主なコストは以下の通りです。
- 変動費: 生徒数や授業コマ数に比例して増減する費用です。
- 講師人件費: 特に個別指導塾では売上に占める割合が大きくなります。学生アルバイト講師の活用などで変動します。
- 教材費: 生徒数に応じて発生します。
- 固定費: 生徒数や授業コマ数に関わらず、ほぼ一定で発生する費用です。
- 家賃・共益費: 教室の立地や広さで決まります。
- 正社員人件費: 事務スタッフや教室長の給与など。
- 広告宣伝費: 生徒募集のための費用です。
- 設備費・減価償却費: 机、椅子、PCなどの購入費用や、それらの償却費。
- 光熱費・通信費: 塾運営に必要なインフラ費用。
儲けを最大化するためには、これらのコストをいかに効率的に管理し、削減するかが重要になります。特に、固定費をいかに低く抑えるか、あるいは固定費を上回るだけの生徒数を確保できるかが、損益分岐点(儲けが出るか出ないかの境目)を左右します。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
さて、今回も実例で示して参ります。
下の表は、とある教室の実際データです。縦長のため、パソコンでご覧頂いている場合は、表自体がスクロールできます。
・2025年4月から6月までの数値の平均値(※4月、5月、6月を足して3で割ったもの)
・項目により1000の位、または100の位以下は四捨五入
各項目の概要は表の下に記載します。
| 区分 | 項目 | 金額 |
| 売上高 | ①売上高 | 1,280,000 |
| ②売上戻り高 | 800 | |
| 純売上高 | 1,279,200 | |
| 販売管理費 | ③役員報酬 | |
| ④給料手当 | 440,000 | |
| ⑤法定福利費 | 45,000 | |
| ⑥広告宣伝費 | 8,000 | |
| ⑦交際費 | 7,500 | |
| ⑧旅費交通費 | 5,500 | |
| ⑨通信費 | 22,000 | |
| ⑩教材費 | 72,000 | |
| ⑪消耗品費 | 15,500 | |
| ⑫事務用品費 | 7,300 | |
| ⑬修繕費 | 11,000 | |
| ⑭水道光熱費 | 29,000 | |
| ⑮支払手数料 | 177,000 | |
| ⑯車両費 | 7,900 | |
| ⑰地代家賃 | 263,000 | |
| ⑱保険料 | 1,300 | |
| ⑲租税公課 | 7,800 | |
| ⑳減価償却費 | 42,000 | |
| ㉑雑費 | 16,300 | |
| 販売管理費合計(コスト) | 1,178,100 | |
| 営業外収益 | ㉒受取利息 | 0 |
| ㉓雑収入(※売却の際) | 0 | |
| 営業外収益合計 | 0 | |
| 営業外費用 | ㉔支払利息 | 0 |
| 営業外費用合計 | 0 |
①売上高・・・学費など営業上の売上高
②売上戻り高・・・ほとんどありませんが、一部返金など
③役員報酬・・・会社方式であれば、オーナー自身の給料項目
※役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内にしなければなりません。
例えば会社で学習塾を開始する場合の、オーナー自身の給料はこの項目になります。
※ちなみに、個人事業主の場合は、事業で得た利益は、事業所得として扱われます。この利益から、生活費や事業経費などを支払います。自分自身に給与を支払うという概念はありません。
④給料手当・・・社員とアルバイトの給与
⑤法定福利費・・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など、法律で定められた社会保険料を会社が負担する費用で、法定福利費は給与の約15~20%程度が目安
⑥広告宣伝費・・・※ここではポスティングを実施したようです。
⑦交際費・・・主に紹介入塾の場合のギフトカード
⑧旅費交通費
⑨通信費・・・電話、プロバイダ、Wi-Fi、切手代、レターパックなど
⑩教材費・・・生徒購入の場合は通常一緒に振り込まれたり、引落されます。また、この項目に会場模試の代金なども含めています。
⑪消耗品費・・・蛍光灯や電池、パソコン用品や工具、器具、備品、掃除用品などもこの項目です。
⑫事務用品費・・・コピー用紙、クリアファイル、生徒用ファイル、ペン類など。
⑬修繕費・・・カウンター形式の複合機の場合の項目
⑭水道光熱費・・・電気、水道、(※ガスは学習塾の場合は使わない=使わないほうがよい)
⑮支払手数料・・・フランチャイズの場合のロイヤリティ、問題作成システムや、塾用の管理システム、成果報酬型の講師採用コストなど
⑯車両費・・・ガソリン代など
⑰地代家賃
⑱保険料・・・※ここでは店舗総合保険を月間で案分
⑲租税公課・・・法人税、所得税、消費税、法人市民税など
⑳減価償却費・・・設備投資などの費用を一定期間に配分する会計処理のことです。
税務に関しては、法人に限り一定の条件下で、任意償却が可能です。 ただし、企業会計では認められていません。 税法会計(=税金に関する会計)では、法人の場合はある価額(=償却限度額)の範囲内で減価償却は任意に行えます(法人税法第31条)。
㉑雑費・・・トイレットペーパー、石鹸、洗剤、書籍、クリーニングなど
㉒受取利息・・・預金の利息
㉓雑収入・・・※事業譲渡などで、教室を売却した場合などの項目
㉔支払利息・・・日本政策金融公庫や銀行に借入がある場合の利息
◆こちらのデータからすると、4月~6月における月間利益は平均で101,100円です。しかも役員報酬を計算に入れていませんので、なんだ!赤字ではないか!そう思われるかと存じます。
ここでは偽りのないデータ提供をしていますので、その現実はそのままです。
しかし、期間が4月~6月という第一四半期の内容です。

特に
・7月からの入塾要素
・夏期講習
・冬期講習
などがまったく加わっていません。
当然ながら、これらが加われば、一教室あたりの売上とコスト面からして、許容できる範囲以上の収益になります。
また、④給料手当と⑮支払手数料は、まだ削減余地があります。
こちらの計算段階では、支払い手数料に問題作成システムが入っていますが、こちらをカットすると、約3万円、人件費でもAIの仕組みを取り入れると、20%程度はダウンできます。
3. 利益率の算出と目標設定
塾の収益性を測る重要な指標が「利益率」です。利益率は、売上高に対する利益の割合を示す指標です。売上高から費用を差し引いた利益を売上高で割ることで計算できます。具体的には、「利益÷売上高×100(%)」で求められます。
つまり、
利益率=(売上高ー販売管理費)÷売上高×100
この計算です。
上の表の状態から利益率を計算すると、
(1,279,200ー1,178,100)÷1,279,200×100=7.9
こちらのデータからすると、約8%です。
一般的に、塾業界の営業利益率は10〜20%程度と言われています。しかし、ビジネスモデルや運営効率によっては、これを大きく上回る高収益な塾も存在します。高い利益率を目指すには、売上増加とコスト削減の両面から戦略的にアプローチする必要があります。
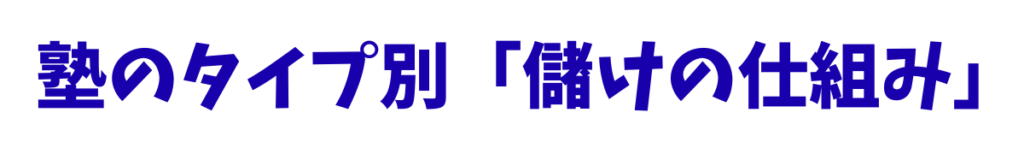
塾のタイプ別「儲けの仕組み」と利益最大化戦略
塾には様々な形態があり、それぞれが異なる強みと儲けの仕組みを持っています。
1. 集団指導塾:規模の経済で「量」を稼ぐ
- 儲けの仕組み: 1人の講師が同時に多くの生徒を指導することで、生徒一人あたりの人件費を極限まで下げるのが最大のポイントです。教室の家賃や設備費といった固定費は高めですが、生徒数が多ければ多いほど、その固定費が生徒一人あたりの負担として希釈され、利益率が向上します。
- 利益最大化戦略:
- 圧倒的な生徒数確保: 大規模な広告宣伝、高い合格実績のアピール、地域でのブランド力構築による口コミが重要です。
- カリキュラムの標準化: 教材や指導方法を標準化することで、講師の育成コストを抑え、どの講師でも一定の指導品質を保てるようにします。
- 高稼働率の実現: 教室の利用時間を最大限に活用し、昼間や土日なども講習を設定するなどして、教室の回転率を上げます。
- 季節講習の徹底: 夏期講習、冬期講習といった短期集中講座で、追加の収益源を確保します。
集団塾の特徴を最大に活かすとなれば講師1名あたりが受け持つ生徒数です。これが多ければ多いほど利益率は大きく異なってきます。
また、教材と指導方法が標準化されていないと、(タイプ分けが多すぎると)その分負担が増加するか、雇用が必要になってきます。
2. 個別指導塾:高単価で「質」を稼ぐ
- 儲けの仕組み: 生徒一人ひとりに合わせた手厚い指導を提供することで、集団指導塾よりも高い授業料を設定できるのが特徴です。人件費の割合は高くなりがちですが、高単価でその分をカバーし、かつ生徒数に応じて講師を柔軟に調整できるため、固定費を抑えやすい傾向にあります。
- 利益最大化戦略:
- 高単価設定と付加価値: 「完全個別」「オーダーメイドカリキュラム」「きめ細かい進路指導」といった付加価値を明確に打ち出し、料金設定を高くします。
- 講師の多能工化・シフト最適化: 複数の科目を教えられる講師を育成し、生徒のニーズに合わせて効率的にシフトを組むことで、無駄な待機時間を減らします。
- 自立学習スペースの活用: 講師が常に付きっきりではない自習スペースを提供することで、教室の付随的稼働率を増加させます。
- 成果の可視化と保護者へのアピール: 定期的な面談や学習報告を通じて、成績向上や学習意欲の変化を具体的に示し、保護者の満足度と継続意欲を高めます。
授業料設定では集団塾よりも安価設定にするのは難しいです。
そのかわり集団塾にはないメリットを前面に打ち出していくことがポイントです。料金の高いか安いかは保護者判断ですが、付加価値をつけることで、料金への納得が得られるようにします。
また、意外と軽視されがちですが、講師の力量、例えば複数教科指導可能な講師の存在はコスト削減に繋がります。
文系講師は主に英語、国語、社会系科目、理系講師は主に数学と理科、このように文理が分かれる場合が多いですが、5教科指導が可能な講師の獲得を進めると、非常に有効です。
特に個別指導の場合は、生徒側からの振替は、ある程度の生徒数がいればそこからほぼ毎日発生する可能が高いです。夏以降は頻発します。
その際、文系指導だけ、理系指導だけの講師よりも5教科フル対応が出来る講師が居れば、移動も楽です。
例えば、1:2の個別指導の場合、
A君とBさんが同一ブースでセットされていて、講師は1名。この状態がベストです。
しかしながら、突然Bさんが振替希望となり、別日設定されれば、A君1名と講師1名というかたちになりますので、その瞬間から、資金効率が悪い設定となります。
さらに悪いことに、Bさんの教科が理科だとします。
他に移動する場合には、移動先の講師の指導可能教科に「理科」が含まれていないといけないわけです。
3. 自立学習型塾(FC展開含む):低コストで「効率」を稼ぐ
- 儲けの仕組み: 映像授業やAI教材、タブレット学習などを活用し、講師の直接指導時間を最小限に抑えることで、人件費を大幅に削減するのが最大の強みです。生徒は自分のペースで学習を進め、質問対応などに少数の講師が対応するモデルです。フランチャイズ(FC)として展開すれば、ロイヤリティ収入も得られます。
- 利益最大化戦略:
- 徹底したコスト削減: 講師数を減らし、システムや教材への投資を重視することで、固定費・変動費の両面からコストを圧縮します。
- 多店舗展開によるスケールメリット: 1教室あたりの利益は小さくても、多数の教室を展開することで全体の収益を最大化します。FC展開はその強力な手段です。
- 月謝モデルの確立: 年間契約や月額定額制を導入し、安定的な収入源を確保します。
- 多様な生徒層の獲得: 低価格帯で気軽に始められることで、今まで塾に通っていなかった層や、複数の習い事をしている層も取り込みます。
高単価で尚且つ自立学習に向く層を取りこむことが出来れば、大きな利益につながりやすいです。高単価な層=高校生です。また、高校生が塾通いをする場合は、たいていは親から行かされるよりも自分の意思で塾通いをしたいという気持ちが強いため、自学に向いています。
4. オンライン塾:地理的制約を取り払い「リーチ」を稼ぐ
- 儲けの仕組み: 教室の家賃や設備費といった物理的な固定費がほとんどかからず、全国の生徒を対象にできるため、生徒数の天井がないのが最大のメリットです。講師も在宅で勤務できるため、人件費の効率化も図れます。
- 利益最大化戦略:
- 圧倒的な集客力: 全国展開のウェブ広告、SNSマーケティング、有名講師の起用などで、広範囲から生徒を募集します。
- システムの効率化: オンライン授業システム、学習管理システム(LMS)を導入し、生徒管理や学習進捗管理を効率化します。
- 多様なプラン設定: 月額定額制、ポイント制、短期集中講座など、多様な料金プランを用意し、幅広いニーズに応えます。
- コンテンツ販売: 独自開発の映像コンテンツや問題集を販売することで、追加の収益源を確保します。
この形式で新規開業や業態変更を考えるオーナーが増加しています。一番の魅力はオンラインであるがゆえに地代家賃が大きくカットできる点です。
ネット上の一等地(SEO対策やリスティング広告など集客のための施策にコストを割く必要があります)にかまえることが出来れば集客力がかなり高まります。
塾の「儲け」を最大化するための具体的な戦略
どのタイプの塾であっても、以下の戦略は儲けを最大化するために不可欠です。
1. 生徒一人あたりの「LTV(顧客生涯価値)」を高める
LTVとは、一人の生徒が塾に在籍している期間中に、塾にもたらす総売上を指します。例えば小学3年生のお子さんのご入塾があったとします。
この時点では、中学受験でもない限りは、恐らく季節講習の追加や週の授業回数を増やしていくことはかなりレアケースになります。しかしながらこの生徒さんが小学4年生、5年生、6年生・・そして中学と在籍してくれたとしてらどうでしょう。
相当息が長い顧客は、都度の講習売上高が初期段階で大きく期待できなくともLTVは大きなものになります。
LTVを高めることが、長期的な儲けに直結します。ポイントは以下の3項目です。
- 退塾率の低下:
- きめ細やかな学習サポート: 定期的な面談、学習成果の可視化、苦手克服に向けた個別対応など。
- 保護者との連携強化: 学習報告、進路相談、保護者会などを通じて信頼関係を築きます。
- 生徒のモチベーション維持: 勉強以外のイベント、成功体験の共有、居心地の良い環境作り。
- 在籍期間の長期化:
- 継続的なコース・レベルアップ提案: 学年が上がっても継続できるコースを用意し、次のステップへの移行を促します。
- 兄弟姉妹割引・友人紹介制度: 家族や友人単位での長期的な顧客化を図ります。
- オプション販売の強化:
- 季節講習の魅力化: 通常授業では扱わない発展内容や、弱点克服に特化した内容で、受講意欲を高めます。
- 教材・ツールの提案: 自社開発の教材や、学習をサポートするITツールを有料で提供します。
- 個別指導・特別講座の推奨: 集団指導の生徒にも、必要に応じて個別指導や特定のスキルアップ講座を推奨します。
2. コスト構造の最適化と効率化
無駄な支出をなくし、効率的な運営体制を構築することで、利益率を向上させます。
- 人件費のコントロール:
- 講師の稼働率向上: 生徒数やコマ数に応じて講師のシフトを最適化し、無駄な待機時間を削減します。
- 非正規雇用の活用: 学生アルバイト講師や業務委託講師を効果的に活用し、固定費を抑えます。
- 業務のIT化・自動化: 採点、宿題管理、出欠管理、請求業務などをシステム化し、事務スタッフの負担を減らします。
- 固定費の見直し:
- 適切な立地・規模の選定: 開業前に、ターゲット層のアクセスや家賃相場を徹底的に調査し、最適な物件を選びます。過剰な広さや設備投資は避けます。
- 居抜き物件の活用: 内装工事費を大幅に削減できる可能性があります。
- オンライン併用による教室規模の最適化: オンライン指導を導入することで、必ずしも大規模な教室は必要なくなり、家賃を抑えられます。
- マーケティング費用のROI(投資対効果)分析:
- 費用対効果の高い媒体への集中: チラシ、Web広告、SNSなど、どの媒体からの集客が最も効率的か(CPA: 顧客獲得単価)を分析し、無駄な広告費を削減します。
- 口コミ・紹介の促進: 最も費用対効果の高い集客方法である口コミを増やすために、生徒・保護者の満足度向上に努めます。
3. 多角的な収益源の確保
塾の授業料以外の収益源を確保することで、経営の安定化と利益の底上げを図ります。
- 教材販売: 独自開発の教材や、市販の良質な教材を有料で販売します。
- イベント・セミナー開催: 保護者向けの進路相談会や、受験対策セミナー、教育系イベントなどを有料で開催します。
- 自習室開放: 集中できる学習環境を有料で提供します。
- 他社サービスとの提携: 参考書販売、資格試験対策講座、留学支援など、生徒のニーズに応じた他社サービスを紹介し、紹介料を得ます。
- フランチャイズ展開(事業規模拡大時): 自身の塾のノウハウをフランチャイズパッケージとして提供し、加盟金やロイヤリティを得ることで、初期投資なしに収益を拡大できます。
新規参入者が「儲ける」ためのステップ
はじめに、これから塾を始める方が後発だからと言って、引け目を感じる必要はありません。また、業界経験がないからという理由で業績向上が難しいと考える必要もありません。
ここでは、新規で始める方が効率的に儲けを生み出すためのステップを段階で説明します。
Step 1: 徹底した市場調査とニッチなポジショニング
一般的な塾市場は飽和状態にあります。飽和状態だから難しいのでは?と考えるのが普通ですが、世界中を見ても「真似文化」は健在です。最初はニッチでもそのうち飽和になるのですから、結果同じです。先行者利益とまことしやかに言われますが、先走りしすぎても、後発すぎてもイマイチな結果になりますので、これも言い得て妙であります。
何にしても「アイディア」だと思います。
この少し飽和化した世界でで儲けるためには、明確なニッチ(特定のターゲット層や強み)を見つけ、差別化を図ることが不可欠です。
- 地域ニーズの深掘り: 周辺の学校のレベル、保護者の教育熱、通塾状況などを調査し、どのような塾が不足しているのかを把握します。
- 競合の徹底分析: 周囲の塾の料金体系、指導形態、強み・弱みを分析し、自塾が「なぜ選ばれるべきか」という明確な理由(USP: Unique Selling Proposition)を確立します。
- 例:「苦手科目克服に特化」「〇〇高校専門」「高専受験に強い」「学習習慣ゼロからのスタート支援」など。
- ターゲット層の明確化: 小学生、中学生、高校生、浪人生、特定の学力層(難関校志望、中堅校志望、基礎力向上など)を明確にし、その層に響くメッセージを発信します。
Step 2: 現実的な資金計画とコスト管理
儲けるためには、まず事業が破綻しないための資金計画が重要です。
- 初期投資の最小化: 高額な内装や設備は避け、必要最低限からスタートします。居抜き物件の活用や、オンライン指導の併用で教室規模を抑えるのも有効です。
- 運転資金の確保: 開業後、売上が軌道に乗るまでの期間(最低でも半年~1年)の運転資金(家賃、人件費、広告費など)をしっかりと確保します。
- 損益分岐点の明確化: 何人の生徒が集まれば利益が出るのかを把握し、そこを最初の目標とします。
- 補助金・助成金の活用: 国や自治体の創業支援制度や、教育関連の補助金・助成金を積極的に活用し、初期費用を抑えます。
Step 3: 高い集客力と顧客維持力の構築
儲けを生み出すには、生徒を集め、かつ長く続けてもらうことが不可欠です。
- 効果的なマーケティング戦略:
- オフライン: ターゲット層に届くポスティング、地域情報誌への掲載、学校近辺での広報活動など。
- オンライン: 魅力的なウェブサイト、SEO対策、SNS(Instagram、Xなど)での情報発信、リスティング広告など。
- 口コミ戦略: 生徒や保護者の満足度を高め、良い評判が広がる仕組み(紹介制度など)を構築します。
- サービス品質の確保: 指導の質はもちろんのこと、生徒や保護者とのコミュニケーション、教室の雰囲気作りなど、総合的なサービス品質を高めます。
- 退塾防止策の徹底: 生徒一人ひとりの状況を把握し、学習の悩みや進路相談に丁寧に対応します。
異業種からの新規参入・買収で「儲け」を最大化する戦略
既存の事業基盤や資金力を活かし、塾業界で効率的に儲けを出すための戦略です。
1. 異業種からの新規参入:自社の強みを活かす
- IT企業の参入: 自社の技術力(AI、システム開発など)を活かし、学習管理システムやオンライン教材開発で差別化を図ります。人件費を抑えた自立学習型塾やオンライン塾での儲けが期待できます。
- 不動産企業の参入: 自社物件を活用することで、塾の主要コストである家賃を大幅に削減できます。複数の教室展開もしやすくなります。
- 人材派遣・教育系企業の参入: 優秀な講師のリソースを活かし、質の高い指導を提供することで高単価な個別指導塾や特化型塾での儲けを狙えます。
- M&Aも視野に: ゼロから立ち上げるよりも、既存の塾をM&Aで買収することで、生徒基盤、ブランド、ノウハウを一気に獲得し、事業を効率的に立ち上げることが可能です。
2. 塾の買収(M&A):時間とリスクを短縮して「儲け」を獲得
M&Aは、既存の塾の「儲けの仕組み」そのものを手に入れる最も手っ取り早い方法です。
- M&Aのメリット(「儲け」の観点から):
- 既存のキャッシュフロー(売上・利益)の獲得: 買収直後から収入が得られるため、開業当初の資金繰りの不安が少ないです。
- 顧客基盤・ブランド力の継承: ゼロから集客する手間とコストが不要で、既存の生徒とその保護者の信頼をすぐに獲得できます。
- ノウハウ・人材の獲得: 成功している塾であれば、その指導ノウハウ、カリキュラム、優秀な講師・スタッフをそのまま引き継げます。
- 市場参入時間の短縮: 開業準備期間を大幅に短縮し、すぐに収益化を図れます。
- M&Aにおける「儲け」のための注意点:
- 正確なデューデリジェンス(詳細調査): 買収対象の塾の**「本当の利益体質」**を見極めることが最重要です。
- 財務状況: 過去数年間の売上、利益、キャッシュフロー、借入金、簿外債務などを徹底的に調査します。
- 生徒数と退塾率: 生徒数の推移、学年ごとの生徒数、季節変動、退塾理由などを詳細に分析し、将来的な売上予測の根拠とします。
- 講師の定着率と給与体系: 人件費の割合、講師の質と定着状況を確認します。買収後の人件費増加リスクも考慮します。
- 教室の賃貸契約: 家賃の妥当性、契約期間、更新条件などを確認します。
- 生徒・保護者の満足度: 顧客アンケートや口コミを参考に、塾の評判を確認します。評判が悪いと、買収後に生徒が流出するリスクがあります。
- シナジー効果の追求: 買収によって、自社の既存事業との相乗効果(例:自社のIT技術を導入して効率化、自社の不動産を活用して教室拡大など)が生まれ、より大きな儲けを生み出せるかを検討します。
- PMI(Post Merger Integration)の計画: 買収後の組織統合、システム統合、企業文化のすり合わせなどを円滑に進める計画を立て、買収効果を最大化します。買収後に既存の生徒や講師が離れてしまっては、せっかくの「儲けの仕組み」が機能しなくなります。
- 正確なデューデリジェンス(詳細調査): 買収対象の塾の**「本当の利益体質」**を見極めることが最重要です。
塾の「儲け」を阻害する要因と回避策
儲けを最大化するためには、儲けを阻害する要因を理解し、適切に対処することも重要です。
- 生徒数の減少:
- 原因: 少子化、競合の増加、指導品質の低下、口コミの悪化など。
- 回避策: 強力なマーケティング、指導品質の向上、生徒・保護者との密なコミュニケーション、退塾防止策の徹底。
- 人件費の高騰:
- 原因: 講師不足、最低賃金の上昇、優秀な講師の囲い込み競争など。
- 回避策: 講師の育成と定着支援、業務効率化による一人あたりの生産性向上、ITツール導入による人件費削減。
- 過剰な広告宣伝費:
- 原因: 費用対効果の低い広告への投資、効果測定の不足。
- 回避策: 広告媒体ごとの効果測定(CPA分析)、費用対効果の高い口コミマーケティングの強化。
- 固定費の負担:
- 原因: 高額な家賃、広い教室、過剰な設備投資。
- 回避策: 適切な物件選定、オンライン指導の併用による規模の最適化、居抜き物件の活用。
- ブランドイメージの毀損:
- 原因: 不祥事、指導ミス、生徒からの不満。
- 回避策: コンプライアンス遵守、講師の倫理研修、顧客満足度調査と改善、迅速な問題対応。
まとめ:塾の「儲けの仕組み」を理解し、高収益体質を築く
塾業界は、少子化という大きな変化の中にありますが、教育に対するニーズが多様化・専門化している現代において、明確な「儲けの仕組み」を構築できれば、非常に魅力的なビジネスとなり得ます。
塾の儲けは、単純な売上からコストを差し引いた「利益」という数字の裏に、生徒数、単価、コスト構造、そしてそれぞれのビジネスモデルの特性が複雑に絡み合って生まれます。
新規参入を考えている方は、まず徹底的な市場調査を行い、自社が「儲け」を最大化できるニッチなポジショニングを見つけることが重要です。そして、初期投資を抑えつつ、効率的な生徒集客と定着、コスト管理を徹底することで、利益を生み出す土台を築きましょう。
既存の塾の買収を検討されている方は、その塾が持つ既存の「儲けの仕組み」を正確に評価し、自社のリソースと組み合わせることで、さらなる高収益化を図るチャンスがあります。ただし、徹底したデューデリジェンスと、買収後のスムーズな統合が成功の鍵となります。
「儲けの仕組み」を深く理解し、常に市場の変化に対応しながら戦略を柔軟に調整していくことで、あなたの塾は持続的な成長と高い収益性を実現できるでしょう。教育という尊い事業を通じて、社会に貢献し、かつ経済的な成功を収めることを心から応援しています。
【関連】
学習塾経営は「儲かる」のか?「儲からない」のか?具体的な戦略で「儲かる」塾を目指す
学習塾経営で年収1000万円以上!買収で成功する秘訣を徹底解説

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク
関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備