塾経営で成功を掴むための唯一無二の正解:本音はメインターゲットを「中学受験」にしたい
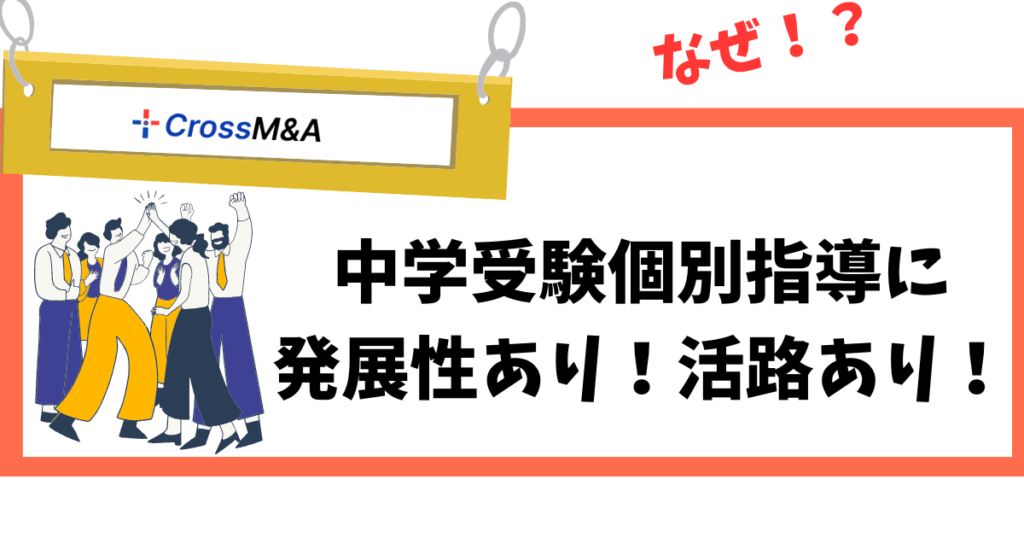
なぜ、中学受験はビジネスとして成り立ちやすいのか
今回も余すところなく、本音トークです。
買収による塾運営、脱サラ、異業種からの参入、あるいはセカンドライフの選択肢として。教育事業への関心が高まっている今、塾経営という選択肢は多くの人にとって魅力的です。しかし、成功を掴むためには、事業の根幹となるターゲット選定が非常に大切です。
ひとまず、ターゲット選定としては、学習塾ですので、小学生、中学生、高校生の3つの属性から考えてみることにしましょう。幼児とか、大学生、社会人は敢えて今回は外して考えてみます。
小学生、中学生、高校生。どの層に焦点を当てるかによって、経営の安定性も、得られる成果も、そしてやりがいすらも大きく変わります。
実は教室内の「盛り上がり方」も全く違うものになるのです。
もしあなたが「大学受験の予備校をやりたい」「地元の中学生を公立高校に合格させたい」と考えているなら、一度立ち止って考えてみましょう。
なぜ?大学受験の「予備校」が減少しているのか、なぜ中学生の高校受験準備はほとんどの場合、中3の夏が終わってからなのか・・・。
・1990年代と今とでは大学受験の制度が全然異なり、今は推薦と総合型選抜のほうが一般受験より多いのですから、予備校が減るのは当然の流れです。
・地元志向の公立高校の倍率は全体として1倍台、下手したら全体としても1倍割れ、さらに私立高校は内申基準で楽に推薦が通るので、勉強に燃える期間はかなり少なく済む時代です。
多くの人が見落としている、しかし成功者が必ず押さえている本質的な市場の真実をお伝えします。
結論から申し上げます。塾経営のメインターゲットは、中学受験をする小学生です。
形式は個別指導の中学受験(集団形式+個別でもいいと思います)なら、レッドオーシャンにならないでしょう。
これは決して感情論ではなく、市場の動向、顧客の特性、そしてビジネスとしての安定性を総合的に判断した、論理的な結論です。まずは、なぜ他の層がビジネスとして成り立ちにくいのか、その現実から見ていきましょう。
なぜ「大学受験」は今、塾経営の主戦場ではないのか?
大学受験は、多くの人が想像する「努力と根性の世界」とは大きく様変わりしました。現在の市場を深く理解せず、安易に参入するのは非常に危険です。
1. 顧客獲得のタイミングが遅すぎる
大学受験を本格的に意識し、塾や予備校に通い始めるのは、高校3年生になってからというケースが多数を占めます。もちろん、高校1年生から通う生徒もいますが、全体から見ればごく一部に過ぎません。
ちなみに通塾率という観点で言えば、中学3年生が一番多いのですが、高校1年になった途端、通塾率は思い切りダウンするのです。
そうすると、大手の学習塾はこう考え、現場の教室長のお尻を叩きます。
「中3から高校継続をさせるように誘導しなさい」と!
まず、このことを何度もしつこく言ってくる上長、またはフランチャイズであれば、スーパーバイザーが居たら、上手くリードしてこう言ってみてください。
「あなたのレベルは私より相当上なんでしょうね。でしたら、中3の生徒さんを継続させるための面談、トークを拝見したいので、是非やってみてください」と。
上長、SVとか言う人たちは、自分が出来もしないことを平気で指示してきます。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶと言いますが、上長及びSV各位でこのようにのたまう人は、経験もさほどなく、歴史上でも学んでいませんので、ここで現場へいざなって「お手並み拝見しましょうか」とやってあげると良いです。
恐らく、どんなに偉そうなことを言ってるこの手の人たちも勝率は10%もないでしょう。その指示をしてくる段階で、すでに結果が見えています。
勿論、とんでもないキャンペーンをぶち上げてやれば話は別です。
しかし、そこには必ず経営上の痛みを伴うことでしょう。
よくあるのが・・・
・高校継続したら〇コマ分の授業をプレゼント!
・高校継続したら何か月無料!
そして契約に縛りをつけることはできませんので、「継続」というワードの重みはほとんどありません。
ということは、ひとまず中間テストまではいるかもしれませんが、その後は部活動だ、学校での補習だとか、なんだかんだ理由をつけられて退塾していくのです。
表数字だけ、人の頭数だけいても、そこに売上が伴わない、または売上に変わらないサービスを毎年繰り広げていたら、それはサービスというものの本質を見失っているのと同義になってしまいます。
ボランティア・慈善事業ではなく、経営ですし、利益追求できなければそれは戦略として間違っているということになります。
さて、話を戻します。
ビジネスの観点から見れば、高校生は「顧客の在籍期間が短い」です。
以前も何度か触れていますが、学習塾は特殊なサービス業です。ストックビジネスのように見えても、在籍できるのは通常は高校3年生までです。
高卒生(浪人生)も対応できますが、それでもその先は「卒業」が待っています。
生徒一人あたりのLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)が低く、毎年新しい生徒を大量に獲得し続けなければ、経営が安定しません。これは新規参入者にとって、大きなリスク要因です。
2. 入試制度の多様化がもたらすビジネスチャンスの縮小
現在の大学入試は、一般選抜だけではありません。
総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜といった、学力試験以外の要素で合否が決まる入試方式が主流になりつつあります。これらの入試は、高校での活動実績、小論文、面接、プレゼンテーション能力などが重視され、対策も多岐にわたります。
「合格のためには、ひたすら勉強するしかない」という時代は終わり、多くの高校生が、学力一本勝負ではない道を選ぼうとしています。実際、総合型選抜や推薦は、一般選抜よりも合格率が高い傾向にあり、生徒や保護者もその現実を知っています。
この変化は、純粋な学力向上を目的とする従来の予備校の存在意義を揺るがしています。
顧客のニーズが「受験対策」から「多様な入試に対応できる総合的なサポート」へとシフトしているのです。
これは、大規模な資本を持つ大手予備校が生き残りをかけて事業転換を図っていることからも明らかです。
もしあなたが、大手予備校と同じ土俵で戦おうとするなら、その競争は非常に厳しいものになるでしょう。
高校生をメインターゲットにしたい場合には、大手予備校がやっていないこと、大手予備校がやろうと思っても出来ないことを軸に考えていくといいと思います。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
本記事は、これから学習塾を始めたい方、特に買収で成功させたい方向けの内容です。勿論、全くの初心者の方でも学習塾は開始できます。
そして意外に思われるかもしれませんが、私が本サイトで箇所箇所で書いている注意すべき事項を少しでもリストアップしてくださったならば、尚ありがたいですし、成功確率は高くなるはずです。
例えば、立地とか、教室長や講師のこととか、商品ラインナップ(コース)、です。その中の一つが「ターゲット」です。
ターゲットというと、まるでハンターが獲物を捕らえるときの表現に聞こえますが、ビジネスとして受け止めてください。
この高校生箇所で実例を出す内容は、やはり大っぴらではなく、こっそりメモしておいてほしいです。
さて、ここで質問です。
例えば個別指導塾の場合、小学生、中学生、高校生たちの「受験」がらみ入塾で一番遅いスタートを切るのは、どの属性だと思いますか?
まぁ、小学生は違いますね。
はい、そうすると2択となり、自ずと「高校生?」となります。
その通りです。
受験が非常に甘くなったことで、高3の春どころか、夏ぐらいにやっととか、下手すると夏が終わってからとか・・・けっこうあります。
そうすると、通塾期間は・・・・・・・・
数か月です。
上記ちょっと語弊があります。言い直します。
受験が非常に甘くなったのではなく、受験制度が非常に甘くなったに訂正です。
共通テストから一般受験は今まで通り、いや、センター試験時代より内容はハードです。
制度と書きましのは、総合型選抜(旧AO入試)と学校推薦型入試及び公募推薦入試の存在です。
共通テストがかなり難しく発展的になっている部分もあることから、受験生も高校側も下手したら全国的に塾側も、蛍の歌を歌っているということです。
「ほ、ほ、ほーたるこい」の歌です。
総合選抜、推薦のみ~~~ずはあ~~~まいぞ~~~
という替え歌になります。
この制度は、今後、もっと甘くなります。何故なら私大とか、下手したら定員が大きく割れるところもあるからです。そして、国立大学でも1倍割れあります。
学生獲得のため、こんなコースならインパクトあろう!という「え?」というコース、学科をつくって何としても学生を確保・・・そんな動きがあるからです。
ですから、高校生を生徒さんにするときには、違った角度からの戦略は必須です。それが奏功すると、今度は呼び込みがうまくなると思います。
続いて、中学生です。
この属性は、今も今後も需要は多いですが、変化が出てきていますので、その要点を下にまとめておきます。
なぜ「高校受験」は競争原理が働きにくいのか?
高校受験は、地域密着型のビジネスとして魅力的に映るかもしれません。しかし、こちらも大学受験同様、新規参入者にとってのハードルは決して低くありません。
実際、「通塾率」というデータからすれば、中2、3が多いのでターゲットにしやすいです。
しかし、それはAさんもBさんもCさんもDさんもEさんもFさんもGさんもHさんもIさんも・・・
Zさんも知っていますし、そう考えています。
さらにもっと言えば、
小学生(中学受験含む)、中学生、高校生、浪人生まで対応できます!ととりあえず看板には書いてあったとしても、実際には中学生の対応しかできず、中学受験の小学生、高校生、浪人生の対応は出来ない・・・という教室長もわんさかいます。
わかりやすく言えば、中学生ターゲットは、真っ赤な海です。
1. 顧客の動機付けが弱い
中学1年生、2年生から本格的に高校受験の準備を始める生徒は、ごく一部です。多くの生徒は、中学3年生になってから、あるいは部活動を引退してから、ようやく受験勉強を始めます。
これはなぜか? 高校受験は、学校の定期テスト対策をしっかり行い、内申点をきちんと確保すれば、特に私立校の推薦などは楽に進学できるからです。
いわゆる大学受験でいうところの専願、高校受験では単願です。
学校長の推薦がもらえたら、落ちることなどないのですから、正直これってコスト使ってわざわざ高校側もテストなんてやらずともいいのに・・と思えるぐらいです。
受かりやすい、誰でも受かる・・これは入試というネーミングとは違うものにしたほうがいいと思います。
定期テストは、中学受験のような応用問題は少なく、教科書レベルの基礎を固めれば高得点が取れます。学校のデータで個票が出てきたら是非生徒さんからコピーさせてもらってください。
500点満点のテストで400点オーバーの生徒など、うなるほどたくさんいます。
さらに、内申点には、定期テストの成績だけでなく、部活動、生徒会活動、委員会活動、各種検定の取得状況など、多岐にわたる要素が加味されます。多くの生徒が、勉強以外の活動も頑張れば評価されると知っているため、純粋な学力向上のための塾へのモチベーションが生まれにくいのです。
2. 私立高校の「基準」がもたらす問題
私立高校の多くは、内申点や偏差値に一定の基準を設けています。この基準は、中学受験のような激しい競争を経たものではなく、学校側が「この程度の学力があれば、入学後も問題なくやっていけるだろう」と判断する、いわば「最低限のライン」です。
この「基準」をクリアさえすれば、ほぼ確実に合格できるため、私立高校には中学受験や大学受験のような「落ちたら次」という厳しい競争原理が働きません。受験生は、基準を満たした複数の私立高校に安心して出願し、滑り止めとして利用します。
また、公立高校の倍率も全国的に1倍台、地域によっては1倍を割るケースも珍しくありません。高校受験は、以前に比べて「入学しやすい」時代になっているのです。
これは、ビジネスの観点から見れば、顧客の「危機感」や「切実なニーズ」が薄いことを意味します。切羽詰まった顧客が少ない市場で、高い学習効果やサービスを提供しようとしても、その価値を正当に評価してもらうことは難しいでしょう。
ちなみに、この記事は、そうそう・・
学習塾をこれからはじめてみようか!とする未来ある人達向けですので、ここまでの内容を見ただけであれば、
気持ち的に張り合いが失せてしまいます。
しかし!
ここからが本番です。
すべての要素が揃う「中学受験」市場の圧倒的な優位性
ここからは、あなたが塾経営で成功するために、なぜ中学受験をメインターゲットにすべきなのかを具体的に解説します。中学受験市場には、大学受験・高校受験市場にはない、数々のビジネス的な強みが存在します。
1. 顧客のLTVが圧倒的に高い
LTVとは、Life Time Value:顧客生涯価値のことです。
中学受験の準備は、ほとんどの家庭が小学4年生から始めます。遅くとも小学5年生の夏からは本格的な準備がスタートします。これは、小学生が中学受験を終えるまでの約2〜3年間、あなたの顧客であり続けることを意味します。
顧客を長期的に囲い込めることは、ビジネスの安定に直結します。毎年、新規顧客を大量に獲得する必要がなくなり、既存の顧客満足度を高めることに集中できます。教育ビジネスにおいては、顧客との信頼関係を長期的に築くことが、紹介や口コミを生む最も重要な要素です。
2. 保護者の熱意とコミットメント
中学受験を目指す保護者は、非常に熱心です。子どもに中学受験をさせようと決断する時点で、子育てや教育に対する強い熱意と、それに伴う経済的な投資への覚悟を持っています。
彼らは、情報収集に余念がなく、塾の合格実績や指導方針を徹底的に調べます。彼らがあなたの塾を選ぶということは、あなたのサービス内容や理念に心から賛同し、その価値を高く評価してくれた証拠です。
このような「熱心な顧客」は、教育ビジネスにとって最高の財産です。彼らは、子どもの成績向上を強く望み、あなたの提案に積極的に耳を傾け、協力してくれます。これは、生徒のモチベーションに大きく左右されがちな高校受験や大学受験とは根本的に異なる点です。
3. 顧客の意思決定が保護者主導である
小学生は、自分で塾を選ぶことはできません。最終的な意思決定は、保護者が行います。これは、塾経営者にとって非常に大きなメリットです。
なぜなら、保護者は「費用対効果」を重視するからです。高額な授業料を支払ってでも、子どもを志望校に合格させたいという明確な目的があります。あなたの塾が「この塾に通わせれば、合格できる」と保護者に確信させることができれば、ビジネスは成立します。
これは、自分で塾を選ぶ高校生や浪人生とは全く違う顧客像です。彼らは「安さ」「友達が通っている」「なんとなく」といった理由で塾を選ぶことも多く、ビジネスとしての安定性が低いと言えます。
4. 確固たる競争原理が働く市場
中学受験には、明確な「合格」と「不合格」があります。志望校に合格するためには、ライバルよりも高い学力を身につけなければなりません。これは、塾にとって、サービス価値を客観的に証明できる唯一無二の指標です。
中学受験を主戦場とする塾の多くが、驚異的な業績を上げているという事実は、この市場に明確な競争原理と高い顧客ニーズがあることを証明しています。合格実績という目に見える成果を積み重ねることで、口コミが広がり、さらに質の高い生徒が集まってくるという好循環が生まれます。(↑ ここ大げさに書いているわけではありません。事実です)
このサイクルは、一度軌道に乗れば非常に強力なブランド力となり、後発の追随を許しません。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
中学受験の生徒さんは、4年生であっても夏期・冬期・春期と講習を受講します。5年生でも当然です。受験前は5年生半ばからラストぐらいから6年生の受験が終わるまで、相当の受講です。
自習を見ていても、今の時代は中学受験の子が一番学習しています。
親御さんから学習については厳しく指示を受けている子も多いでしょう。
面談のときには、ほぼ必ずと言っていいほど講習受講は即決で決まるのです。
そして「とある学習塾」では講習は絶対受講です。
講習をやらない選択肢がないと豪語する方式ですが、それでも中学受験の生徒はたくさんいますし、白熱しています。
忘れてほしくないので、また再度言いますが、
中学受験と言えば、
SAPIX、日能研、四谷大塚と大御所が居ます。ここの正面から戦いを挑むような形ではなく、「個別指導の中学受験」を謳うのです。
皆さんがもしお時間あれば、
中学受験が得意です!という個別指導塾ってありますか?
是非近くの学習塾に電話で聞いてみてほしいのです。
「あの・・・お宅の塾は中学受験対応していますか」と。
その時にちょっとだけ意地悪な質問を用意して聞いてみるといいです。そこの教室長がしどろもどろになったり、「あまり自分は詳しくないんです」と言ったり、
「自分は中学の頃、中学受験をしていないのであまり詳しくないんですけど・・・」と言ったりするでしょう。
そして今、私はズバリ予想をします。
中学受験をガチっと押さえられる個別指導塾はそうそうない!
だ・か・ら!チャンスだということです。
買収のときには、その瞬間から「中学受験の個別でいこう」そう決めてもいいと思います。
具体的な中学受験個別指導塾の運営の仕方は、また機会を改めて記事にしていきます。
まとめ:成功への第一歩は、正しい市場選びから
塾経営は、教育という崇高な事業であると同時に、収益を追求するビジネスでもあります。事業の成功は、どれだけ熱意があるかではなく、どれだけ顧客のニーズと市場の特性を正確に理解しているかにかかっています。
大学受験市場は、入試制度の変革と顧客の多様なニーズにより、競争が激化しています。高校受験市場は、受験のハードルが下がり、顧客のモチベーション維持が難しいという課題を抱えています。
一方で、中学受験市場は、顧客のLTVが高く、保護者の熱意が強く、明確な競争原理が働いています。これは、新規参入者にとって、最も安定して成長できる市場であり、質の高い教育サービスを提供することで、顧客からも、そして事業としても、正当な評価を得られる場所です。
もしあなたが、本気で塾経営を成功させたいと願うなら、ぜひ中学受験をメインのターゲットに据えることを強く推奨します。そして、顧客である保護者の想いに真摯に向き合うことから、あなたの成功は始まります。
CROSS M&A(通称:クロスマ)は15年の運営キャリアがあり、最近動向も勿論押さえております。
学習塾を買収検討の方には、ホット!な案件もご提供できますので、お気軽にお問合せください。
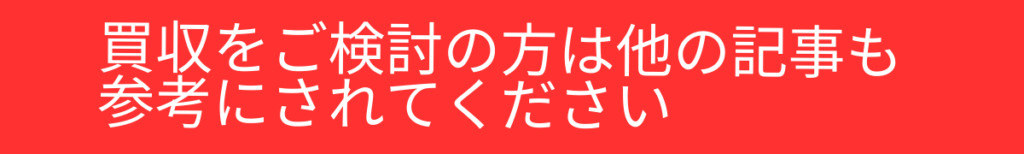
よい物件とのめぐり合い
顧客・従業員(講師)への最初の行動
フランチャイズと独自ブランド
なぜ今、学習塾がおすすめなのか?
見て触れて、深く理解するモデル教室
学習塾・習い事教室の運営は狙い目
学習塾の売上高は月間売上高の16倍
CROSS M&A(クロスM&A)の自信
学習塾とプログラミング教室のM&A
高校生指導ができる学習塾をM&A
60歳からの新しい挑戦!
国立大学最寄り駅の案件は即買い
小学生向け学習塾の料金相場徹底解説
M&A成功のコツ潜在的価値の見極め
【高収益案件を発掘!】小規模学習塾
あなたの既存スキルがM&Aで花開く
千葉県の学習塾買収
習いごとフランチャイズ買収ガイド
個別指導塾M&A成功秘訣と実践ガイド
人が変わると業績が変わる
未経験だからこそ成功率が高い!
簡易株価評価の算定方法(①)
簡易株価評価の算定方法(②)
デューデリジェンス基礎
労務リスクを見抜く専門ガイド
M&Aにおける不動産の基礎知識
保護者との信頼を築く授業報告
学習塾の新しい形:異業種参入歓迎
株式譲渡と事業譲渡、見極めポイント
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年02月03日
学習塾業界は変化を求めている:すべての受検で「安全志向」の時代へ突入!塾運営はこうなっていく!!
#バリューアップ
#リスク回避
#保護者ニーズ
#個別最適化
#塾M&A
#大学入試改革
#安全志向
#年内入試
#進路指導

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収