成約率を劇的に変える!学習塾面談の「交渉の終着点」を制する“たった一言”と“一枚の紙面提示”の極意
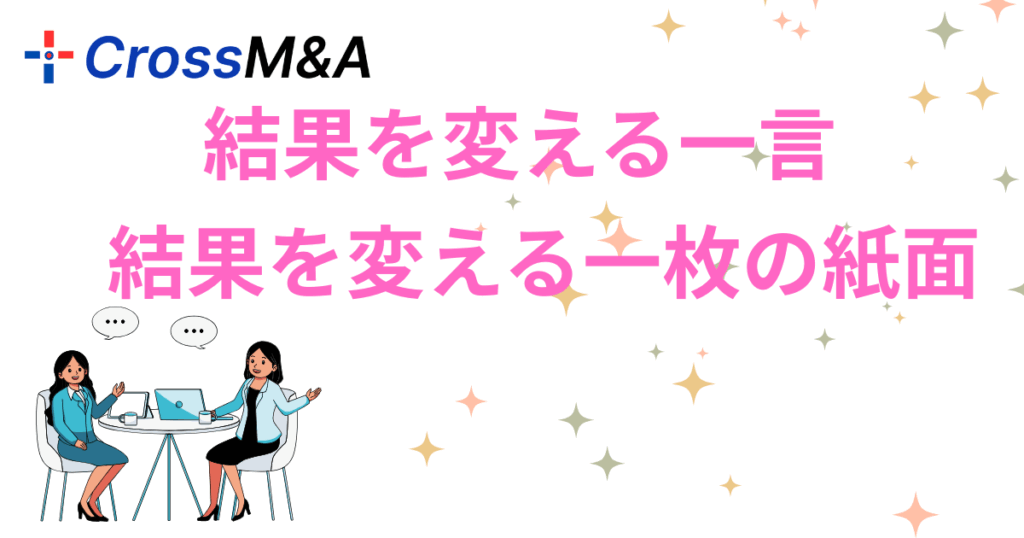
ほとんどの教室長が陥りがちな「親切な大間違い」の正体
多くの学習塾の教室長は、保護者の方々への配慮、いわゆる「相手を想い図る心」から、意図せず成約から遠ざかる行動を取っています。
これが、多くのケースで結果の差を生む決定的な敗因となっているのです。
これは、なかなか難しいことなのですが、言うなれば、契約を促す面談や実際の追加講習交渉時には、保護者が階段を自分で上がってくるのを待つのではなく、保護者の手を引いてグイッと引っ張り上げる、そんなイメージの言葉の発し方、紙面や資料提示が必要です。
癖がついてしまっているなら、どんなことがあっても封印すべき言葉集
さて、それでは、「言葉」についてです。
このサブタイトルのとおり、もし以下で示す言葉が、まるで慣用句のように、まるでしかるべき結びのように、自然と口から出てしまっているのであれば、思い切り口にチャックをして、その言葉が出なくなるまで、その部分のトークだけでも訓練したほうが良いでしょう。
「是非、ご検討ください」
「親切な大間違い」の代表格が、面談の結びで発する「是非、ご検討ください」という一言です。
「検討してください」という言葉は、相手に判断を委ねるという一見丁寧な表現に聞こえますが、実は成約率を劇的に落とします。この言葉を言えば言うほど、保護者の判断は宙に浮き、結論は引き延ばされます。
その瞬間に、面談で高まったはずの期待や感情は冷め始め、他の選択肢と並べられ、時間が経つほどに成約率は急降下するのです。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
「では前向きに検討しますね」
こう言われた後、どのように言葉でつなぎますか?つなげないですよね。この「検討します」を言われたら、終わった・・・と思っていいです。
前向きに検討しますと言われて心が躍りますでしょうか?
踊っている場合ではないですし、相手はとても言いやすい断り文句を言ってるだけですよ。
「検討します」は断り文句と全く同じです。
残念ながら保護者は、検討しません。あなたの学習塾、習いごと教室を一歩外に出た瞬間「検討」の文字、「検討」の言葉「検討」の気持ち、その全部がなくなります。
そう思って間違いない!それぐらい思ってていいです。
では、もう一度
「では前向きに検討しますね」
このように言われた後、その場でどのように言葉を返せますか?返せないですよね。場面を変える言葉に強引に変えていくのはものすごく難しく高度です。
ではどうしたらいいのか・・・・?
これらの断り文句の類を言わせない!ことが肝要なのです。
一例を挙げます。
「お母様、今説明させていただいた内容の通りですが、是非来週火曜日からスタートさせてください。まぁ、急な話で検討したいという部分もあるかと思うのですが、2週間後にはテストもありますので、どうしても私たちも結果を出したいので」
ここでのポイントは
「検討したいという部分もあるかと思うのですが」という言葉を入れている点です。
これ、どういうことかというと・・・
相手が心の中で思っている「であろう」言葉をこちらから先に口に出して言ってしまう!という心理トークです。
これを言われると、なかなか今度は反論が出来なくなるのですね。
是非今度試してみてください。
「お母さんも大変ですよね」
また、「お母さんも大変ですよね」とお金の面を労う言葉を百回重ねたところで、保護者の背中を押す力にはなりません。保護者が真に求めているのは、漠然とした労いではなく、「我が子の未来を確実に変えるための明確な道筋と、それを掴むための決断の後押し」なのです。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
そのご家庭のお金のことを心配するトークを出す教室長さんがいますが、それ・・・教室内に他の生徒さん、講師もいる中での発言として考えた場合・・・言っていいのでしょうか。そして子供がいる前でお金の話をシビアにし始めるのは、相手がしたら仕方ないですが、こちらから切り出すものではないと思うのです。
正義の味方的に、あなたのことを心配しているのです、という要素でしょうか。それともちょっとドラマの見過ぎで、そういえば保護者の心がぐらつくと思うのでしょうか。
経験則で言えば、それを一切言わずに
「あなたのお子さんの偏差値をここまで上げるためには、当然コストもかかります」というスタンスで接したほうがいいです。
そして、
「私、太郎君の計画を立てました。ここから2月までの計画で、太郎君用の計画です。ほかの生徒の計画ではなく、太郎君専用ですので、是非ちょっと聞いてほしいのです。今、太郎君は学校のテストで、平均点300点のテストで実質点数が〇点です。そうするとこれを平均点以上にもっていき、尚且つ学校内での偏差値として55ぐらいまでもっていく計画ですので、少し大変ではあります。
ですが、かなり細かく計画組んでありますので、この通りやっていただきたいのですが・・・」
このように、学習に関しての専門家なのですから、堂々と自分の計画を述べてみてください。お金のことを考えるのは保護者様です。我々が考えるのは学習面です。
「成績を必ず上げます」
そして、よくある勘違いが、「成績を必ず上げます」が決め文句だという誤解です。これは塾として当然の約束であり、「それが可能である明確な根拠や方法、そして『今すぐ始めるべき理由』」がなければ、保護者の心を動かす決定打にはなり得ません。
こ、これはもう
学習塾の教室長が言う内容ではないと思います。
日本全国でどのぐらいの塾があるかわかりませんが、確かコンビニの数以上?でしたか。
そこに存在する教室の数が例えば5万教室あったとします、全部「成績アップ!」うんぬんかんぬん!という売り出し文句があるのではないでしょうか。
「あなたの成績はこれをやれば必ず下がる!!」と言ってる塾などありませんし、
「成績上げますよ」という言葉を発するほどに、ちょっと格式というか、そういうものを思い切り下げてしまうことになります。
この点は事例をあげるまでもなく、何となくわかりますね。
さて、続いて保護者心理についてです。
多くの保護者は「結論の背中を押されたい」という真実
教室長は、契約や入塾の結論を「保護者ご自身が出すべきもの」として、全ての判断を相手に預けようとします。
確かに、最終的な決定権は保護者にありますが、こと学習塾、特に夏期講習や冬期講習といった「季節講習」においては、このセオリーが通用しないことが多々あります。
まず、
季節講習は、「期間限定」の「特別な成果」を約束するものです。
保護者は「受けさせたい」という気持ちはあっても、
「本当にこれで良いのか」
「もっと良い選択肢があるのではないか」
という迷いの段階から抜け出せずにいます。その迷いを断ち切るのが、私たち塾側の役割です。
結論を出すのが遅くなるごとに、保護者の「感情」は冷め、外部の「雑音」(他の塾の情報、家族の意見など)が入り込みやすくなります。この「結論の遅延=感情の冷却」が、成約を逃す最大の原因です。
季節講習の提案においては、特に「背中はすぐさま押さなくてはいけない」のです。
本来の商取引においては、結論を出すのは顧客側です。しかし、講習というのは、追加で実施する授業ですので、すでに授業契約を結んでいる顧客が追加するかどうかの判断をしてもらう内容ですので、新規契約の際の「結論出し」とは一線を画するものがあるのです。
そして、
講習は追加での授業ですから、追加でお金がかかることは保護者は全員わかっています。
でも保護者の感覚で、わが子の学習調整はなかなか難しいです。
特に受験を考えてみてください。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
追加の講習で提示した授業数から金額が20万円だったとします。それを安いととるか、高いととるかは別として、この金額20万円だけが保護者の印象に残る話し方をしたのであれば、これはあまりよくないです。
「なぜ?」20万円のコストがかかるのか?
この部分をしっかりと説明しなければ誰も納得はできないでしょう。
そして、金額のイメージというのは打ち出し方によって相手の受け方も変わる!ということを是非しっておいてほしいのです。
「お母様、これね、合計で講習金額が20万円となっていますが、5教科ですので、1教科4万円の追加だと思ってください。実際は、英数が少し多めになっていますが、イメージとしてはそんな感じです。先ほどの過去問を一緒に見ていきましたが、学校の定期テストレベルと同じような問題であれば、そんなに苦労しませんが、あきらかに学校のテストとは違いますよね?
あの問題をきちんと解けるようにしていくようにするための練習は必要だと思うのです。
そのためには、過去問とか模試の過去問なども使いますが、これを1年分、2年分やったところで、そんなに効果はありません。
私の計画では先ほども示しましたように、12年分はやりたいのですね。過去問のこの本ありますよね。これを2冊~3冊分です。特に数学は太郎君が苦手な教科ですし、どうしても偏差値をあと3~5ぐらいは上げていきたいのですね。
過去問もただ何も考えずにやれば効果は薄いですが、過去問を解きながら苦手な箇所を見出してすぐに復習する!というやり方で問題を解きながらインプットもしていくやり方でやっていきます。
本当はこれを太郎君が自主学習でやって、わからないところの解説+類題演習と言う形でやりたいのですが・・・おそらく性格的な面を考えてみると、お母さまが一番わかると思いますが、先生がしっかりとリードして道しるべというか、やるべき箇所を示しながらやったほうがいいと思うのですね。
なので、本当に目的ある学習をこの直前期にしていきますので、これは是非やってほしいのです」
こんな感じです。
どのように、いつ、背中を押すのか?(超重要)
背中を押す最適なタイミングは、面談中いつでも良いわけではありません。それは、面談の「最後の瞬間」と、その日のうちに送信する「お礼メール」の二つのフェーズに集約されます。
面談の最後で、全てのプログラムや金額の説明が終わり、保護者の理解と共感が最も高まっている瞬間に、明確なアクションを促さなければなりません。
決定的な差を生む「たった一言」と「一枚の紙面提示」
成約率を劇的に変える最大のポイントは、この「最後の瞬間」に何を伝えるかにかかっています。必要なのは、「検討」の余地を与える言葉ではなく、「決断」を促す明確な「期限」の提示です。
① 期限を伝える「たった一言」
あなたの口から発するべきは、「検討ください」ではなく、「先生がお預かりできる枠には限りがございます。今回の特別プランの適用と、お子様の席の確保のため、【〇月〇日(水)の午後6時まで】にお返事をいただけると、確実にご案内できます」といった、明確な期限と理由付けを伴う一言です。
この一言が、保護者の「迷い」を「猶予期間のある決断」へと変えるのです。
この内容、軽くサラリと言ってますが、意外と出来ていない教室長がわんさかいますので、絶対にその重要な意味をとらえて実施してみてください。
② 紙面でも期限が書かれたものを提示する
口頭での伝達だけでは不十分です。人間は忘れる生き物であり、特に複雑な情報は記憶から薄れます。
ここで投入するのが、「たった一枚の紙面」です。
その紙面には、料金、コース概要といった基本情報の他に、「お申込み期限:〇月〇日(水)18:00」といった明確な期限が、他のどの情報よりも目立つように記載されていなければなりません。
面談の最後にこの紙面を提示し、
「こちらにお子様の席を確保できる期限と、プランの適用期限を明記しております。この期限を過ぎますと、ご案内が難しくなる場合がございますので、必ずご確認ください」と、その紙面が持つ意味をしっかりと言葉で伝えるのです。
この「口頭での明確な期限の提示」と「紙面での視覚的な期限の明記」のセット運用ができているか否かだけで、保護者が持ち帰る情報と、その後の行動力はとんでもなく変わります。
「親切心」という名の優柔不断な態度を捨て、「お子様の成果のために、今、決断を後押しする」という強い心意気を、明確な期限という形で表現すること。これこそが、学習塾の面談で「交渉の結果の差」を生む、絶対的な極意なのです。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月14日
学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)
#保護者面談
#個別指導提案
#入試情報提供
#受験生意識付け
#塾テキスト推奨
#学習塾経営
#新年度カリキュラム
#春休み学習計画
#春期講習
#継続率向上

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目