簡易株価評価の算定方法(①):M&Aにおける売り手との交渉に役立つ基礎知識
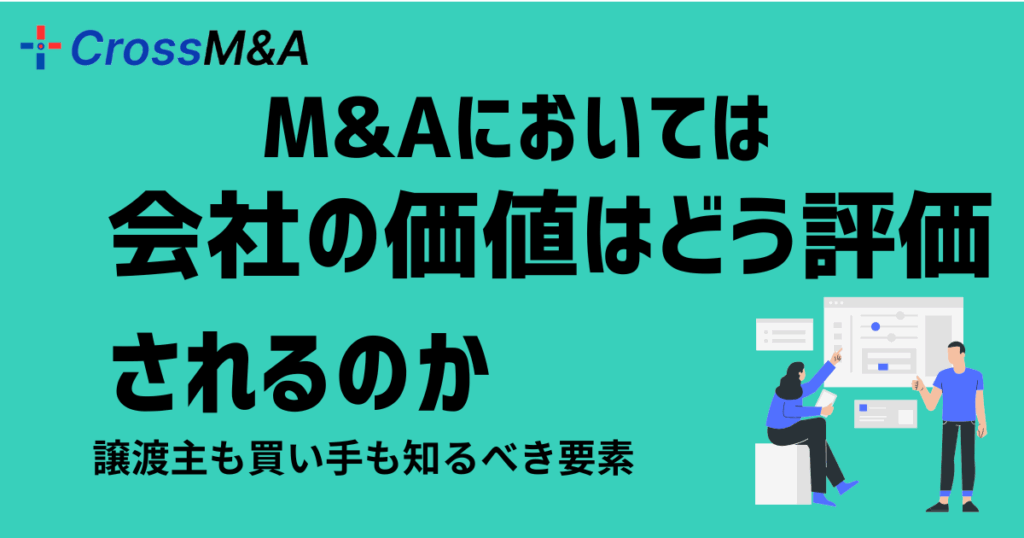
M&A(企業の合併・買収)を検討する際、会社の価値、つまり株価をどのように評価するかは非常に重要です。特に、中小企業の場合、売り手の希望する譲渡額が、会社の客観的な価値と乖離しているケースも少なくありません。
そこで今回は、M&Aにおける初期の段階で、売り手との交渉をスムーズに進めるために欠かせない「簡易株価評価の算定方法」について、その全体像から具体的な計算方法までを解説します。
1. 簡易株価評価のステップ:全体像を把握する
簡易株価評価は、以下の3つのステップで進めていきます。
- 決算書の確認(特に貸借対照表):会社の帳簿上の資産・負債・純資産を把握します。
- 重要な科目のヒアリング:帳簿上の金額と実際の価値(時価)に乖離がありそうな項目を特定し、詳細な情報を収集します。
- 実態純資産の算定:ヒアリングで得た情報をもとに、帳簿上の純資産を修正し、会社の真の価値である「実態純資産」を計算します。
この実態純資産こそが、簡易株価評価の基礎となる金額です。
2. ステップ1:決算書の確認(貸借対照表の純資産を把握する)
その前に、貸借対照表とは何か?ちょっと復習してみましょう
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)を理解する
貸借対照表は、会社の「健康診断表」や「家計簿」のようなものです。
ある特定の時点で、会社が「どのような財産をどれだけ持っているか」、そして「その財産をどうやって手に入れたか」が一目でわかる書類です。
では以下に簡単なサンプル表を示します。
おもちゃ屋さんの貸借対照表
| 借方(左側) | 貸方(右側) | ||
| 資産(財産) | 金額 | 負債(返済義務のあるお金) | 金額 |
| 現金 | 200万円 | 銀行からの借入金 | 200万円 |
| 商品在庫 | 100万円 | ||
| 純資産(返済義務のないお金) | |||
| 資本金 | 100万円 | ||
| 合計 | 300万円 | 合計 | 300万円 |
貸借対照表は、大きく3つのグループで構成されています。
- 資産(しさん)
- 負債(ふさい)
- 純資産(じゅんしさん)
左側は「資産」のグループ
貸借対照表の左側には、会社が持っている「財産」が並びます。
これは、現金や預金、会社が所有する建物や土地、そしてお店に並んでいる商品など、お金に変えることができるものすべてを含みます。
| 資産(財産) | 金額(円) |
| 現金 | 200万円 |
| 商品在庫 | 100万円 |
| 合計 | 300万円 |
右側は「負債」と「純資産」のグループ
右側には、左側の「財産」をどうやって手に入れたかが示されています。
負債(ふさい)グループ
「負債」は、他人から借りたお金です。いわば、「いずれ返済しなければならないお金」のこと。銀行からの借入金や、仕入先への未払い金などがここに含まれます。
| 負債(返済義務のあるお金) | 金額(円) |
| 銀行からの借入金 | 200万円 |
| 合計 | 200万円 |
純資産(じゅんしさん)グループ
「純資産」は、返済義務がない会社のお金です。社長が出資したお金(資本金)や、会社が営業活動で稼いで積み立てた利益などがこれにあたります。
| 純資産(返済義務のないお金) | 金額(円) |
| 資本金 | 100万円 |
| 合計 | 100万円 |
貸借対照表は「バランスシート」
貸借対照表は、英語で「Balance Sheet(バランスシート)」と呼ばれます。これは、左側の「資産」の合計金額と、右側の「負債」と「純資産」の合計金額が、常に同じになるためです。
まるでシーソーのように、常にバランスが取れています。
- 左側(資産):300万円
- 右側(負債200万円 + 純資産100万円):300万円
このバランスは、貸借対照表を理解する上での最も重要なポイントです。
貸借対照表でわかる会社の「健康状態」
貸借対照表を読み解くことで、その会社の財務状態、つまり「どれくらい健全か」を把握できます。
たとえば、負債の割合が多い会社は、借金が多い状態です。もし業績が悪化すれば、借金の返済が困難になるリスクがあります。
一方、純資産の割合が高い会社は、借金が少なく、経営基盤が安定していると言えます。
貸借対照表をチェックすることで、その会社が「借金に頼らず、自力で事業を回せているか」を判断する材料になるのです。
実際の貸借対照表は、上のように項目が少ないわけではありません。しかしながら、左側は資産、右側は負債と純資産という構図は、項目が多くても同じです。
貸借対照表を入手する
さて!貸借対照表(バランスシート)の基礎を見ていただいたところで、次に進んでまいりましょう。
まず、M&Aの対象となる会社の決算書を入手し、貸借対照表を確認します。貸借対照表は、会社の財政状態を把握する上で最も重要な資料です。
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
| 現金預金 | XX円 | 買掛金 | XX円 |
| 売掛金 | XX円 | 借入金 | XX円 |
| 建物・土地 | XX円 | 負債合計 | XX円 |
| 資産合計 | XX円 | ||
| 資本金 | XX円 | ||
| 利益剰余金 | XX円 | ||
| 純資産合計 | XX円 | ||
| 負債・純資産合計 | XX円 |
この貸借対照表の右下にある「純資産の合計額」が、評価の出発点となります。
帳簿上の純資産は、資産の合計額から負債の合計額を差し引いた金額であり、会社の帳簿上の価値を示しています。
しかし、この金額はあくまで過去の取引を帳簿に記録したものであり、現在の市場価値(時価)を反映しているわけではありません。
そこで、次に、この帳簿上の純資産を時価に近づけるための作業を行います。
帳簿上の純資産と実態純資産のイメージ
1. 純資産が減るパターン
- 資産の時価が帳簿価額より減少:売掛金の中に回収不能なものが含まれている、建物や機械の価値が帳簿上の金額よりも下落している、といったケースです。
- 負債が帳簿価額より増加:退職金規定がないため退職給付引当金を計上していない、といったケースです。
このような場合、帳簿上の純資産は実態よりも過大に評価されていることになります。
2. 純資産が増えるパターン
- 資産の時価が帳簿価額より増加:土地の含み益がある、といったケースです。
この場合、帳簿上の純資産は実態よりも過小に評価されていることになります。
今回の簡易株価評価では、特に前者の「純資産が減るパターン」に着目して評価を進めていきます。
3. ステップ2:金額の大きな科目をヒアリングする
次に、帳簿上の純資産を実態純資産に修正するために、貸借対照表の中でも特に金額が大きく、時価と乖離しそうな科目に着目して、詳細なヒアリングを行います。
具体的なヒアリングの対象となるのは、主に以下の項目です。
- 資産:売掛金、建物、土地、長期貸付金、保険積立金
- 負債:退職給付引当金
ここでは、それぞれの項目について、ヒアリングのポイントを解説します。
1. 売掛金:回収可能性を徹底的に確認する
売掛金は、売上として計上されているものの、まだ顧客から代金を受け取っていない金額です。これがすべて回収できるとは限りません。
ヒアリングのポイントは以下の3つです。
- 相手先の内訳:売掛金の相手先を確認し、金額の大きい先から優先的に、回収不能なものが含まれていないかを確認します。
- 時系列の比較:過去3期分の決算書を比較し、金額に変動のない売掛金がないかを確認します。長期間、金額が変化していないものは、回収不能になっている可能性が高いと考えられます。
- 回収可能性の判断:上記をもとに、回収不能と思われる金額を特定します。
2. 建物・土地:所有権と時価を把握する
建物や土地は、会社が所有しているかだけでなく、その時価が帳簿上の金額と大きく異なるケースが多いため、注意が必要です。
ヒアリングのポイントは以下の2つです。
- 所有権の確認:まず、建物や土地の所有権が本当に会社にあるのかを確認します。中小企業の場合、社長個人が所有しているケースも多いため、必ず登記簿謄本などで所有者を確認します。
- 減価償却の状況:償却資産の実在性を確認するため、減価償却明細書をチェックします。また、償却の過不足がないかも確認します。
- 土地の時価評価:帳簿上の土地の金額は、購入時の価格(簿価)のままになっていることがほとんどです。これを時価に引き直す必要があります。時価評価には、固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額などを参考にします。一般的に、固定資産税評価額は時価の7割程度と言われているため、評価額を0.7で割り戻すことで、おおよその時価を把握できます。
3. 長期貸付金:回収可能性と貸付理由を確認する
長期貸付金も、売掛金と同様に回収可能性が重要です。
ヒアリングのポイントは以下の3つです。
- 貸付先と理由:誰に、どのような理由で貸し付けたのかを確認します。特に、代表者や関係会社への貸付金は、回収可能性が低い場合があります。
- 法人税申告書の確認:法人税申告書の別表11-1を確認し、貸倒引当金が設定されている貸付金がないかチェックします。
- 時系列の比較:売掛金と同様に、過去の決算書と比較し、金額に変動のない貸付金は回収不能になっている可能性を疑います。
4. 保険積立金:解約返戻金を確認する
保険積立金は、会社の帳簿には支払った保険料が計上されていることが多いですが、時価で評価する場合は解約返戻金の金額で評価します。保険会社に問い合わせることで、評価基準日時点の解約返戻金を確認できます。
5. 退職給付引当金:退職金規定と支給実態を確認する
退職給付引当金は、将来従業員に支払う退職金を引当金として計上するものです。中小企業の場合、退職金規定がないケースも少なくありません。しかし、規定がなくても過去に退職金の支給実績があれば、将来の支払いに備えて引当金を計上する必要があると考えられます。
計算方法は以下の通りです。
- 要支給額の算出:退職金規定に基づき、全従業員が自己都合で退職した場合に必要となる総額を計算します。
- 計算例:基本給 × 勤続年数に応じた支給倍率 × 従業員数
- 年金資産の差し引き:中小企業退職金共済(中退共)など、外部に積み立てている年金資産があれば、その分を要支給額から差し引きます。
- 引当金計上額の確定:要支給額から年金資産を差し引いた金額が、退職給付引当金として計上すべき金額となります。
4. ステップ3:実態純資産を算定する
ステップ2のヒアリング結果に基づき、帳簿上の純資産を修正し、実態純資産を算定します。
実態純資産 = 帳簿上の純資産 ± 修正額の合計
例えば、以下のような修正項目が判明したとします。
- 回収不能な売掛金:-100万円
- 退職給付引当金の計上不足:-700万円
- 土地の含み益:+500万円
この場合、合計の修正額は「-100万円 – 700万円 + 500万円 = -300万円」となります。
帳簿上の純資産が4,000万円であれば、実態純資産は「4,000万円 – 300万円 = 3,700万円」となります。
このように、実態純資産を算定することで、会社の真の価値を把握でき、売り手の希望譲渡額との乖離を客観的に議論する土台が整います。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略