夏期講習の売上ダウンは学習塾にとって「死活問題」である!
夏期講習の季節が巡り来るたび、学習塾の経営者の皆様は期待と不安が入り混じった複雑な心境を抱かれることでしょう。特に、今年の夏期講習の売上が思わしくないという状況に直面しているオーナーの方々は、その焦燥感を誰にも理解してもらえないと感じているかもしれません。
なぜなら、学習塾は慈善事業ではないからです。
そして、夏期講習の売上は、多くの学習塾にとって単なる「上乗せ」ではなく、事業継続のための「生命線」であり、その売上ダウンは、塾の将来を左右する死活問題になりうるからです。
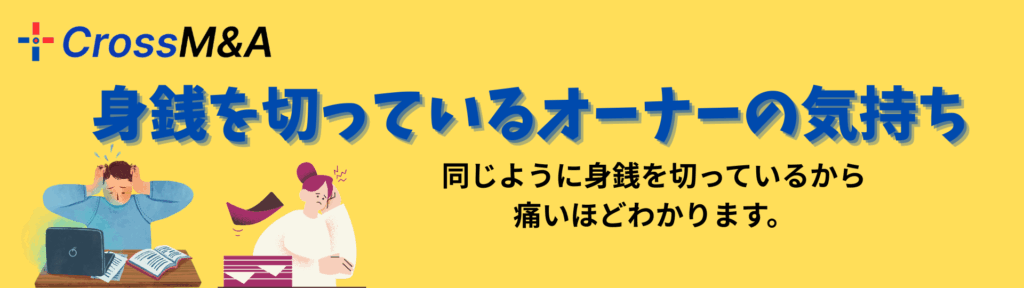
学習塾はボランティアではない:身銭を切るオーナーの覚悟
「教育は崇高なものだから、お金儲けを前面に出すべきではない」
このような美辞麗句を耳にすることは少なくありません。
しかし、学習塾を経営するということは、まぎれもなく事業を運営するということです。
従業員の給与、家賃、教材費、広告宣伝費、そして何よりもオーナー自身の生活費。これらすべてを賄うためには、安定した収益が不可欠です。ボランティアで塾を運営できるほど、この社会は甘くありません。
特に、学習塾のオーナーは、自身の貯蓄や退職金、あるいは借入金など、身銭を切って事業をスタートさせています。成功すればそれなりの見返りがありますが、失敗すればすべてを失うリスクを常に抱えています。
この「身銭を切る」という行為は、事業への覚悟と責任の重さを物語っています。だからこそ、売上が落ち込むことへの危機感は、身銭を切っていない「雇われ塾長」や「本部の人間」には決して理解できないレベルで深刻なのです。
彼らは、帳簿上の数字が多少赤字になったところで、個人の資産が減るわけではありません。
最悪の場合、別の部署に異動するか、転職すれば良いと考えるかもしれません。
しかし、オーナーにとっての売上ダウンは、まさに自身の懐からお金が流れ出ていくことを意味し、文字通り「身を削る」ような感覚を伴います。

「夏期講習の売上はいらない」という綺麗事は通用しない
「夏期講習は集客のためのものだから、売上は二の次で良い」
「夏期講習でしっかり指導して、正規入塾につなげられればそれで良い」
といった考え方をする場合もあるかもしれません。
もちろん、新規入塾への貢献は夏期講習の重要な役割の一つです。しかし、だからといって「夏期講習の売上はいらない」と言い切れるのは凄いと思います。
「あなた様はオーナーで身銭を切っている方ですか?」と聞いてみたいです。
多くの学習塾にとって、夏期講習は年間売上の中でも大きな比重を占める重要なイベントです。春期講習、冬期講習と並び、長期休暇を利用して集中的な学習機会を提供することで、普段の月謝収入だけでは賄いきれない部分を補完する役割があります。
これはこれで、多くのユーザーの心を捉えているし、必要とする生徒、受験生、ニーズを感じている人たちはとても多いです。
社会に対しての整合性は十分保っています。
また学習塾オーナー、経営者にとっても夏の売上は非常に重要で、運営の継続、継続企業が出来るかどうか(ゴーイング・コンサーン)という意味でも非常に重要です。
特に、夏期講習は期間が長く、提供できる講座数も多いため、年間を通しても最も高い売上が見込める時期と言えるでしょう。
ユーザー側とそのサービスを提供する学習塾、ベクトルが同じ向きなので、その関係性が十分に成り立っていますし、この二者の関係性に「ふにゃふにゃ、ぐだぐだ」と間に入ってくる外野意見は特に取り合わなくてもよいでしょう。
スマホを売る(利益を考えてプランをアレコレ考える)
スマホは必要、ほしい!(多少高くても使う)
この販売者側(製造者である場合もある)と購入者側は、売る側と買う側の関係性で、シンプルなのは、「使いたくない」「いらない」と思うなら買わなければいい、契約しなければいいという部分しかありません。
ここは単純でシンプルに考えていいでしょう
そして今、クロスマのアドバイザーは、困っているオーナー、学習塾を経営している社長、夏の売上がダウンして不安を抱えているオーナー兼教室長と
まったく同じ境遇でまったく同じ経験があり、まったくもって困り果てた経験もあるからこそ、書ける内容です。
ちょうど今、夏休みがスタートしました。
夏休みがスタートして、さてここから顧客が来るぞ!という期待感はほとんど持てないことは、もうご存知かと思います。
夏期講習はたいてい4月終わりから5月、遅くても6月頭までが商戦本尊だからです。つまり、今の段階で、ほぼ夏の売上は決まっているということです。
今年が初年度の方でしたら、週明け月曜日からさらに期待に胸を膨らませるのもわかります。
しかし2年目以降の方でしたら、もう理解しているはずです。
この夏期講習で売上が立たなければ、年間の事業計画に大きな狂いが生じます。
場合によっては・・・資金繰りが悪化し、従業員の給与支払いや家賃の支払いに支障をきたす可能性も出てきます。最悪の場合は・・・銀行からの借入金の返済が滞り、事業の継続自体が困難になることもありえます。
クロスマのアドバイザーは、経営者だからこそ抱える不安な気持ちを恥ずかしげもなく代弁することができます。
ときには仲間から連絡が入り、苦しい胸のうちを明かしてくれる人もいます。それは本音のトークです。美辞麗句で飾ることなど無意味であることは、身銭を切っているからこそわかります。そして、痛いほど理解します。
ではここで恒例の実例・実話コーナーです。
【実例(実話)】
Y教室長は、いつも明るく前向きで非常にバイタリティ溢れる人でした。
教室長になった2年目のことです。
初めてすべての業務をOJTなしの全権委譲で業務を行いました。
夏期講習前にはしっかりと資料を整え、保護者との面談、または三者面談のときのトークも準備し練習しました。しっかりとコツを覚えて、いわゆる「取りこぼし」などもほとんどなく、評価は満点を与えらえるぐらいの実績でした。
そして初めての冬期講習前の面談時期に、こう質問されました。
「オーナー、夏よりも冬休みのほうがかなり時間が短いですから、提案もそれなりに調整すべきでしょうか」
こう答えました。
「いや、夏と同じだけ提案して大丈夫だよ。8月から冬前にまた生徒来るから、たぶん夏よりもも2割から5割増しになるかもしれないよ?」
(一瞬間があり・・・)
「え?」
・
・
・
この話は実話です。そしてY教室長はその年度で全店1位になりました。
上の話にはまだ続きがあります。
その年度で、受験生は全員合格を果たしました。生徒、保護者、講師、そして教室長と大盛り上がりです。
さて、夏、何十年と続く個別指導塾でも光り輝く業績を残し、全員合格となり、口コミも拡大し、さらに次の年も安定「以上」の経営が出来た、その源泉はどこでしょうか。
もしこの教室が閑古鳥状態で、夏の売上も冬もボロボロだったら、保護者、講師、生徒とは早々にお別れしていたかもしれません。
利益を取ることが悪だと考えている人は間違っています。
利益が取れなければ継続企業の前提が失われていることになり、その場所から消えうせなくてはならないかもしれません。
そのときに、誰に迷惑がかかるのか・・・
これを考えればよくわかると思います。
そしてもう一つ、上の「実例(実話)」の中に、とんでもなく大きなキーポイントが隠されています。
それはどこだかわかりますでしょうか。

「夏期講習はサービス」という考え方も耳にしますが、申し訳ありません。そんな言葉を今私が耳にしたら、大嫌いな白いアスパラガラスを目にしたときと同様に、怖気走り、歯を食いしばって身震いすることでしょう。
講師の人件費、教室の冷暖房費、教材の印刷費、広告費など、目に見えないところで多大な費用が発生しています。
そのサービスを提供するためにもコストがかかっています。
これらのコストを回収し、さらに利益を生み出さなければ、塾は存続できません。

夏期講習の売上が立たない場合、カウントダウンは始まっているかもしれない
もし、今年の夏期講習の売上が、昨年度や目標を大幅に下回るようであれば、それは単なる一時的な不振として見過ごしてはなりません。
むしろ、あなたの学習塾にとっての「カウントダウン」が静かに始まっている可能性を真剣に考えるべき時が来ているかもしれません。
この「カウントダウン」が意味するのは、廃業か、あるいは事業の譲渡か、という究極の選択です。
売上不振が慢性化すれば、資金は底を尽き、やがて事業を継続することが不可能になります。その前に、体力があるうちに事業を畳むか、あるいは他の塾に事業を譲渡して、生徒や従業員の雇用を守る道を模索する決断を迫られるでしょう。
これは、感情的な問題ではありません。数字が示している厳しい現実です。
- 資金ショートの危険性: 売上が立たなければ、固定費(家賃、人件費など)を賄えなくなり、キャッシュフローが悪化します。
- 広告宣伝費の削減: 資金がなくなれば、集客のための広告宣伝費を削らざるを得なくなります。これはさらなる売上ダウンのスパイラルを招きます。
- 講師のモチベーション低下: 経営が不安定になれば、優秀な講師ほど離職を考え始めます。講師の質の低下は、指導の質に直結し、生徒離れを加速させます。
- 生徒・保護者の信頼失墜: 経営不安の噂は、保護者の耳にも入ります。大切な我が子を預ける場所として、信頼できない塾を選ぶ保護者はいません。
これらの悪循環が回り始めると、一度落ち込んだ売上を回復させるのは極めて困難になります。だからこそ、夏期講習の売上ダウンは、単なる一過性の現象として片付けるのではなく、事業継続の黄色信号、あるいは赤信号として受け止める必要があるのです。
身銭を切っているオーナーだからこそ、今、動くべきだ
この厳しい現実を最も痛感しているのは、他ならぬあなた自身、身銭を切っているオーナーです。
夜も眠れないほどの不安、将来への漠然とした恐怖、そして何よりも、これまで築き上げてきた塾がなくなるかもしれないという絶望感。
これらは、日々の給料をもらっている従業員や、会社から派遣されているだけの人間には決して分かり得ない感情です。
だからこそ、あなたは今、誰よりも早く、そして真剣に、この問題に対処しなければなりません。
具体的な対策は多岐にわたりますが、まず重要なのは現状の徹底的な分析です。
- なぜ売上がダウンしたのか?
- 競合の出現? 新規開校の塾は増えていないか?
- 少子化の影響? 地域の子どもは減っていないか?
- 広告戦略の失敗? 広告媒体やメッセージは適切だったか?
- サービスの魅力不足? 指導内容や合格実績は競合に負けていないか?
- 生徒募集活動の不足? 個別説明会や体験授業の実施状況は?
- 顧客満足度の低下? 生徒や保護者の声に耳を傾けているか?
- 講師の質の低下? 講師の指導力や生徒とのコミュニケーションは?
- 料金体系の見直しは必要か? 高すぎないか、安すぎないか?
これらの問いに対し、客観的に、そして正直に向き合う必要があります。感情を抜きにして、数字と事実に基づいた分析を行うことが、次の一手を見つけるための唯一の道です。
そして、分析結果に基づいて、迅速に具体的な行動計画を立て、実行に移すことです。
- 集客戦略の見直し: ターゲット層の再設定、効果的な広告媒体の選定、SNSを活用した情報発信、既存生徒からの紹介キャンペーンの実施など。
- 商品・サービスの改善: カリキュラムの見直し、新しい講座の開発、個別指導の強化、進路相談の充実など。
- コスト削減: 無駄な経費の洗い出し、光熱費の削減、業務効率化による人件費の適正化など。
- 生徒・保護者とのコミュニケーション強化: 定期的な面談、学習状況の細やかなフィードバック、悩み相談窓口の設置など。
- 講師の育成・モチベーション向上: 研修の実施、評価制度の見直し、働きやすい環境づくりなど。
- 事業譲渡も視野に入れた準備: もしもの時に備え、財務状況の整理、事業資産の棚卸しなど、M&Aに関する情報収集も始める。
身銭を切っているオーナーであるあなたは、この学習塾の舵取りをする唯一の存在です。誰もあなたの代わりに動いてくれる人はいません。
現状を直視し、迅速に行動を起こすことこそが、この危機的状況を乗り越え、学習塾の未来を切り拓く唯一の方法なのです。
「まだ大丈夫だろう」という楽観的な観測や、「なんとかなる」という根拠のない期待は、現状を悪化させるだけです。
「なんとかなる」という言葉は自分自身に言い聞かせるための自分のためだけの応援メッセージ宇です。
しかし、現実は、自らを応援すること「よりも」現実直視した対応策を考えることだと思います。
厳しい現実を受け入れ、オーナーとしての責任と覚悟をもって、今すぐ行動を開始してください。あなたの決断と行動が、塾の未来を、そしてあなた自身の未来を大きく左右するのですから。
CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡