M&Aの税務基礎知識:株式譲渡と事業譲渡の税務知識基礎編
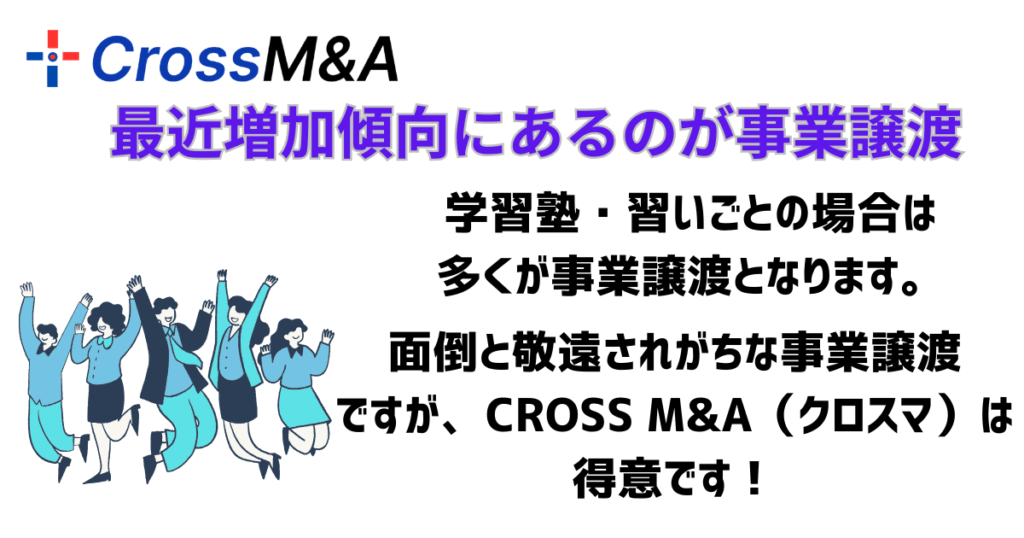
M&Aのトータル的な数値から、「学習塾・習いごと」に絞り込んでいきますと、「事業譲渡」の割合が増加しつつあります。
株式譲渡と事業譲渡では処理的な面で煩雑さが伴うのが事業譲渡です。税務的な面でも株式譲渡のほうが有利です。そのような視点で見ると「株式譲渡」のほうが良い・・・そう思われるかもしれません。
しかしながら、例えば学習塾や習いごと教室の場合は、個人事業主が多いです。
個人事業主がM&A(合併・買収)を行う場合には、基本的に事業譲渡(事業の譲受け)を行うことになります。
なぜなら法人とは異なり株式が存在しないからです。その事業を構成する資産や在庫、そこに存在する顧客や顧客リスト、そして従業員や、ウェブサイトなどを個別に買い手に譲り渡し、その対価を受け取る、そのような取引になります。
会社として学習塾や習いごとを運営している場合も例えば複数教室がある中で、選択と集中のために1教室を売却したい、そのような需要の際も事業譲渡となります。
多くのサイトで、
・株式譲渡のほうが簡単、有利
・事業譲渡は煩雑、税務面で不利
そのように書かれていますが、それは確かに事実であり、とは言え選択肢は限られるわけですから、とれる手法をとっていきましょう。
また、上記の有利不利の観点で言えば、上記は確かにそうだけれども、「閉校」という選択よりもはるかに資金的にも楽ですし、自分がクローズしなければいけない心労と苦労と比較することを考慮すれば、全くもって「閉校」よりも「譲渡」選択のほうが有利であることは間違いありません。
処理が比較的簡単、煩雑という観点で言えば、CROSS M&A(通称:クロスマ)扱いは、学習塾と習いごとに専門特化しているため、ほとんどが事業譲渡です。従ってその処理の煩雑さというのは、私個人の意見としていえば、整理してtodoリストを作って実施すれば、「煩雑」と感じるほどではありません。
少々、話が飛びましたが今回の主題に戻ります。今回は、「税務」中心です。
M&A(企業の合併・買収)は、企業の成長戦略や事業承継の有力な手段です。しかし、M&Aには税金が深く関わっており、その違いを理解しておくことも重要です。
特に、株式譲渡と事業譲渡は、課税関係が大きく異なるため、それぞれの税務上の特徴を把握し、自社にとって最適なスキームを選択するようにしましょう。
この記事では、M&Aにおける税務の基礎知識を、具体的な事例や表を交えながらわかりやすく解説します。
また、以下の記事も関連記事としてご確認ください。
・M&Aの成功を左右する!株式譲渡と事業譲渡、最適なスキームを見極めるポイント
Section 1: 税金とは何か? M&A税務の全体像
税金とは、国や地方公共団体が公共サービスを維持するために、国民から徴収するお金のことです。所得や財産、消費など、様々なものに課せられ、その種類によって税率や計算方法が異なります。
M&Aの分野では、主に以下の3つの税金が関係してきます。
- 所得税: 個人が事業や資産の売却などで得た所得に対して課される税金です。日本では、給与所得や事業所得など、様々な所得を合算して計算する「総合課税」が原則ですが、株式譲渡益など一部の所得は「分離課税」として他の所得と分けて計算されます。
- 法人税: 法人が事業活動によって得た所得に対して課される税金です。法人税には法人住民税や事業税も含まれ、これらを合わせた「実効税率」で課税所得が計算されます。
- 消費税: 商品やサービスの消費に対して課される税金です。M&Aにおいても、事業譲渡のように課税資産を譲渡する場合には、消費税が発生する可能性があります。
Section 2: M&Aにおける株式譲渡と事業譲渡の税務比較
M&Aで最もよく用いられる手法である株式譲渡と事業譲渡。
この2つは、取引の主体と課税対象が大きく異なります。以下にそれぞれの税務上の特徴を詳しく見ていきましょう。
株式譲渡の税務
株式譲渡とは、会社の所有者である株主が、保有する株式を買い手企業に売却することです。この場合、M&Aの当事者は「売主である株主個人(または法人)」と「買い手企業」になります。
【課税関係】
- 取引の主体: 売り手である株主個人または法人
- 課税対象: 株式の売却によって得られた譲渡所得(売却代金 – 取得費 – 譲渡経費)
- 発生する税金:
- 株主が個人の場合: 株式譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。この税金は、他の所得と切り離して計算される「申告分離課税」が適用されます。現在の税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合わせた20.315%の固定税率です。
- 株主が法人の場合: 株式譲渡益は、本業の利益など他の所得と合算して計算されます。課税される税金は、法人税、法人住民税、事業税です。中小企業の場合、これらの税金を合わせた実効税率は、およそ34%程度となります。
【具体的な事例:個人株主が株式譲渡する場合】
A社のオーナー株主(個人)は、A社を設立する際に株式を100万円で取得しました。その後、M&Aにより株式を1,000万円で売却しました。譲渡にかかった仲介手数料は20万円でした。
- 株式譲渡所得: 1,000万円(譲渡対価) – 100万円(取得費) – 20万円(譲渡経費) = 880万円
- 税額: 880万円 × 20.315% = 約179万円
この事例からもわかるように、個人株主の株式譲渡益は、約20%の固定税率で計算されるため、他の事業所得などと比べて税負担が軽くなるのが大きな特徴です。
事業譲渡の税務
事業譲渡とは、会社が特定の事業に関する資産(例:店舗、設備、在庫など)や負債を、買い手企業に売却することです。この場合、M&Aの当事者は「売主である会社」と「買い手企業」になります。
【課税関係】
- 取引の主体: 売り手である会社(法人)
- 課税対象: 事業譲渡によって得られた事業譲渡益
- 発生する税金:
- 法人税: 事業譲渡益は、会社の所得として他の事業の利益と合算され、法人税の課税対象となります。このため、譲渡益が大きくなると、法人税等の負担が重くなる可能性があります。
- 消費税: 事業譲渡では、譲渡される資産のうち、土地や有価証券などを除いた消費税の課税対象資産(建物、設備、在庫、ソフトウェア、そしてのれんなど)に対して、消費税が課されます。
【税務上の「のれん」】
事業譲渡では、譲渡対価が譲渡事業の時価純資産額を上回る場合、その差額は税務上の「のれん(資産調整勘定)」として扱われます。この「のれん」は消費税の課税対象となります。
買い手側にとっては、この「のれん」を5年間(60ヶ月)にわたって償却できるため、その分だけ課税所得を減らす効果があります。一方で、売り手側は消費税の納税義務が生じるため、譲渡対価に消費税分を上乗せすることが一般的です。
【具体的な事例:事業譲渡する場合】
A社は、飲食事業を売却することを検討しています。飲食事業の時価純資産額(資産2,000万円 – 負債1,500万円)は500万円です。この事業を買い手企業に1,000万円で売却することになりました。
- 事業譲渡益: 1,000万円(譲渡対価) – 500万円(時価純資産額) = 500万円
- 法人税等: 500万円 × 34%(実効税率) = 170万円
- 消費税:
- 課税対象資産の合計額(仮に建物、設備、在庫、ソフトウェアの合計が500万円)
- のれんの金額: 1,000万円(譲渡対価) – 500万円(時価純資産額) = 500万円
- 消費税の課税標準: 500万円 + 500万円 = 1,000万円
- 消費税額: 1,000万円 × 10% = 100万円
この事例では、A社は法人税等170万円と消費税100万円を納税する必要があります。消費税は買い手から受け取るため、最終的な手取り額に影響を与えることになります。
Section 3: 株式譲渡と事業譲渡の税務比較表とまとめ
株式譲渡と事業譲渡の税務上の違いを、以下の表にまとめました。この表は、M&Aを検討する際の重要な判断材料となります。
【株式譲渡と事業譲渡の税務比較】
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
| 取引主体 | 株主個人または法人 | 会社(法人) |
| 課税対象 | 株式の譲渡所得 | 事業譲渡益 |
| 発生する税金 | 株主が個人: 所得税等(20.315%固定)株主が法人: 法人税等(実効税率34%程度) | 法人税等(実効税率34%程度)消費税(課税対象資産に対して) |
| 税務上ののれん | 買い手側での償却は不可 | 買い手側で5年間償却可能 |
| メリット(売り手から見て) | 税負担が軽い(個人株主の場合)手続きがシンプル | 特定の事業だけを売却できる 赤字事業の損失と相殺可能 |
| デメリット(売り手から見て) | 会社の全事業を売却することになる 個人株主の税負担が重い(法人の場合) | 消費税の負担が生じる 手続きが複雑 |
まとめ
M&Aの手法は、企業の状況や経営者の意向によって様々ですが、その選択には税務上の影響を十分に考慮する必要があります。
- 株式譲渡は、個人株主にとっては税負担が軽くなるメリットがありますが、会社の事業全体を譲渡することになります。
- 事業譲渡は、特定の事業のみを売却できるメリットがある一方で、消費税の負担が生じる点に注意が必要です。また、手続きが複雑になる傾向があります。
M&Aの成功には、税務知識の理解が不可欠です。ご自身の状況に応じて、専門家と相談しながら最適な手法を選択することが、望ましい結果への近道となります。
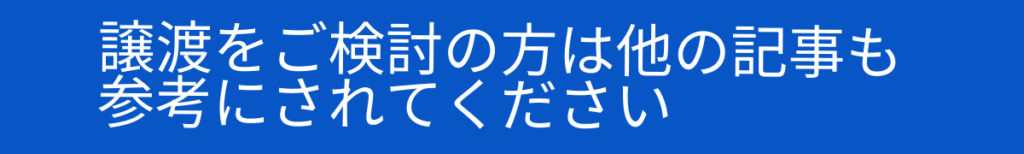
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡