塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について
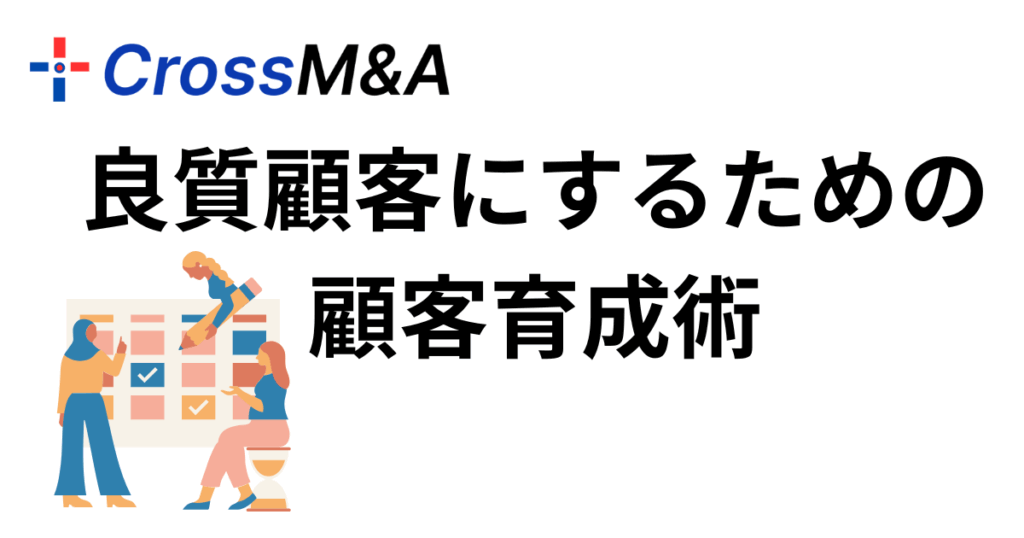
学習塾を成功させるための要素はいくつもあるのですが、今回は「顧客」という観点で述べさせていただきます。
ん?顧客の質?と一瞬思われるかもしれませんが、この論点は噛むほどに味が出るイカのようなもので、素通りはできない内容です。
意外や意外の重要な要素の一つである「顧客の質」について。
ここでいう「顧客」とは、生徒さん側よりも「保護者」だと思ってください。良質顧客は、わが子の勉強に対しての熱度が高いことだけを指すのではありません。
学習に対しての熱度が高いことが、良質顧客とイコールになることは正直あまりありません。
答えとしては、【塾との健全な関係性を築き、維持していく上で不可欠な要素】これを土台に整理していきます。
では、具体的にどのような顧客が「良質顧客」なのでしょうか?
それは、塾が設定するルールや期限を尊重し、約束事を守れる顧客です。
これは一見当たり前のことのように思えますが、なかなかそうではない実例が非常に多くあります。
実際には、わが子に「期限を守って宿題を出しなさい」と叱っているシーンがありましたが、保護者自身が塾との約束を守れていないことので、その場面を見て、私自身がひっくり返りそうになったことがあります。
ひとに対しては約束を守れと言い、自分は守らない・・・これってある意味すごいです。
いま、こちらの記事を縁あってご覧いただいている方で、現在教室運営をされている方がいらっしゃったならば、「ああ、あるある」と同意いただけるのではないでしょうか。
なぜ「期限」が最も重要なのか?
学習塾の運営において、様々な場面で「期限」という概念が登場します。
- 入塾契約: 「〇日までに契約書のご提出をお願いします」
- 季節講習の申込み: 「講習参加の有無を〇日までにご連絡ください」
- 定期面談: 「〇日〇時までにご希望の日時をお知らせください」
これらの期限は、ただの事務手続きではありません。塾全体の運営を円滑に進めるための重要な「信号」のようなものです。期限を守れない顧客が増えると、以下のような問題が生じてしまいます。
1. 教室運営の停滞: 期限内に回答や提出物がないと、塾側は何度も催促の連絡を入れる必要が出てきます。これにより、本来やるべき教材準備や生徒指導の時間が削られ、業務効率が著しく低下します。
2. 不確実性の増大: 特に季節講習やイベントの参加人数を確定する際、期限を守れない顧客がいると、正確な人数を把握できず、教材や座席の準備が困難になります。結果として、他の真面目な顧客にも迷惑がかかる可能性があります。
3. 講師陣への悪影響: 期限を守らない顧客が常態化すると、塾全体がルーズな雰囲気に陥る危険性があります。これは講師にも伝染し、「期限を守らなくても大丈夫」という認識が広がりかねません。
「一事が万事」という言葉があるように、期限を守れない顧客は、その他の面でもルーズな傾向があることが少なくありません。
彼らが増えれば増えるほど、塾運営は常に綱渡り状態となり、余計なエネルギーを消耗することになります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
今回のまた恒例の実例(実話)を披露いたします。
仮称(Aさん)の事例。
Aさんは、息子さんが高校3年生で一般受験をする生徒の保護者です。冬期前の面談の案内はまだ夏の暑さが残る9月早々に、紙面、保護者へのメール、再度紙面にて案内しました。
◆受験生の場合には、三者面談でお願いします
◆面談の実施期間は〇月〇日(金)までです
このような内容は案内の都度述べておりました。
なかなか面談の返事がもらえず、生徒や保護者に都度連絡をしていましたが、生徒側は困り切った様子でした。
そうです。親子の意志疎通がほとんど出来ていないケースです。
そのため、保護者にメールをして面談について再度お願いしました。
最終的には、上記指定の期日の先の日程提示でした。
私のほうから断りました。
このようなパターンで、あなたならどうしますか?
①相手が指定してきた期日を超えた日程で面談を実施する
②再度、期日内日程を打診する
多分、どちらかだと思います。
②はまだいいと思いますが、①を方法を迷わず選択された方は、ちょっと要注意要素があります。
これ、大きなサービスサイトとか、大きな企業だと、①の選択はないです。
何故なら
「木を見て森を見ず」のやり方をずっとやっていけば、いずれ早晩自分の首を絞めることになるからです。
そして、そのやり方が顧客へのサービスだと本気で思っているのであれば、多分以降にいろいろな顧客が言ってくる「外」案件を受けることになるでしょう。
それこそが一事が万事です。
Aという顧客へその例外を許した
Bという顧客がその事実を知り、例外を言ってくる
Cという顧客に対しても同じように例外を許した
これ・・・非常にまずい結末しか見えません。
皆さん、いかが思いますか
もちろん、上記については教室の考え方、教室長の考え方がそれぞれ異なるでしょうから、これが絶対正しい方法というものはありません。
しかし、期限とか約束というのは、破る前提ではなく、守る前提で今まで生きてきましたので、やはり相当気になるのです。
そうならないように・・・
ある日、ふと思いました。
やはりお客さんにも協力依頼をしなければだめだ、ならばお客さんを育てていくスタンスでやってみよう!
このある日の思いがきっかけです。
「顧客育成」のススメ:理想の顧客と関係を築くための3つのステップ
顧客を「育成する」という言葉は、少し上から目線に聞こえるかもしれません。しかし、これは決して保護者を軽んじるものではなく、お互いが気持ちよく、健全な関係を築いていくための「ルール」を共有するプロセスだと捉えてください。
具体的には、以下の3つのステップを通じて「顧客育成」を図ります。
ステップ1:入塾前の「口頭伝達」で期待値を設定する
顧客育成は、入塾前の段階から始まっています。新規面談の際、塾のシステムや理念、そして「ルール」について明確に伝えることが重要です。
この時、以下の点を強調して伝えましょう。
- 塾の指導方針: どんな生徒を育てたいか、どんな学習習慣を身につけてほしいかを具体的に話します。
- 期限の重要性: 提出物や返信の期限を守ることが、円滑な運営に不可欠であることを丁寧に説明します。例えば、「期限を設けているのは、他の生徒さんの授業準備を万全にするためです」といった理由を添えると、納得感が得られやすいです。
- 保護者の役割: 子どもの学習をサポートする上で、保護者の協力が不可欠であることを伝えます。
この段階で、塾のルールを尊重できないと感じる顧客であれば、入塾を見送るという選択肢も視野に入れるべきです。最初の段階でしっかりとした「基準」を示すことが、後のトラブルを防ぐ第一歩となります。
ステップ2:入塾後の「文書伝達」でルールを明文化する
口頭での説明は、時間が経つと忘れられてしまうことがあります。そのため、入塾時には必ず塾のルールを明記した文書を渡しましょう。
- 規則や規約: 入塾申込書や契約書に、塾のルール(振替授業のルール、欠席連絡の期限など)を詳細に記載します。
- 年間スケジュール: 各種イベントや講習の申込期限などを明記した年間スケジュールを配布します。
文書として残すことで、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐだけでなく、顧客自身もいつでもルールを確認できるようになります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
文書は曖昧にしないほうがいいという実例です。
CROSS M&A(通称:クロスマ)のアドバイザーは現役の塾オーナーでもあります。それがゆえに学習塾とか習いごと分野が大得意です。
今でもたくさんんの気づきとか、新しく変わった内容を文書にまとめたりとか資料を作成するに及び、やっぱり知識が毎日ついてきた印象を実感出来ます。
また、継続して塾オーナーを続けていることで、買収とか譲渡をご検討の方により専門的でより深い内容のお話が出来ることも最大の強みだと思っております。普通の専門ではないM&A会社の方でしたら、絶対に気づかない内容まで簡単に全貌がわかるぐらいになっていますので、CROSS M&Aを通した譲渡買収はどちらも安心だと思います。
そして、買い手が譲渡された後に困らないようにしていくことも使命だと思っておりますのでアフターサービスにすごく力を入れています。
その段階で、これがあったら困らない!という各種ツールとか資料がたくさんあるのです。
ここでいうところの「文書は曖昧にしないほうがいい」というのは、その文の通りです。
なんだかんだ言っても、こんなこと言ったら怒られますが、学習塾運営の人たちは個人でやっている人も法人でやっている人も「脇が甘い」ように思います。
だからトラブルが起こるのです。
私、15年やっていますが、トラブルと言えるトラブル(実際はとても小さい内容)は2回しかありません。
そのうち一回は、顧客からの資金回収トラブルでしたが、アフリカ系の方でしたので、あきらめました。
私が作成した「重要事項説明書」を使っての契約であれば、トラブルなど起きないと自負しているものを当方の関連教室長たちには使ってもらっています。
つまり本部が作成したものは使っていないということです。
それぐらい自信があるし、それぐらい重要なことなのです。
この重要事項説明書はどの学習塾でも応用して使えますし、習いごと教室でも使えます。コツがあります。それは
学習塾の場合には、その内容を「重い」ととられないような文章の書き方です。
これがしっかりとできていて、内容のツボを押さえておくことが出来ているかがポイントです。
CROSS M&A(通称:クロスマ)を通しての譲渡契約成立の場合は、学習塾の買い手様には、こういった、資料も提供いたしますので、かなり安心だと思います。
ステップ3:定期的な「メール伝達」でリマインダーを行う
期限が近づいてきたら、メールやメッセージでリマインダーを送ることも効果的です。
これは、顧客がルールを守れないことを責めるのではなく、「うっかり忘れてしまう」ことを防ぐためのサポートだと考えましょう。
- 簡潔なリマインダー: 「〇日締切の〇〇について、ご確認をお願いいたします」といったように、シンプルで分かりやすい文面にします。
- 締切日の一週間前と前日: 余裕をもってリマインダーを送ることで、顧客に十分な準備時間を与えます。
これらの伝達方法を組み合わせることで、顧客は「塾はルールを大切にしている」というメッセージを何度も受け取ることになり、次第にルールを尊重する意識が育まれていきます。
このリマインドメールの送信は小さい技かもしれませんが、けっこう有効です。文章的にはさして凝ったものじゃなくてもいいので、試してみてください。
タイトルのところに
【リマインド】〇月〇日(〇)の面談、どうぞよろしくお願いいたします
などと入れてもいいです。
今、メールを受信する場合は、多くがgmail です。gmailの場合にはスマホでも普通に受けることが出来ますし、今やほとんどの方がスマホでのやり取りがメインです。
従いまして、「タイトル」で工夫したほうがいいのです。
講師の「育成」も同様に重要
顧客だけでなく、講師の質もまた、塾の運営を大きく左右します。講師もまた「期限」を守れない人がいると、塾全体に悪影響を及ぼします。
- シフト表の提出: 翌月のシフト表を前月中に提出させることは、円滑な授業運営に不可欠です。
- 提出物の期日: 生徒の成績報告書や面談シートなど、提出期限を設けて管理しましょう。
もし期限を守れない講師がいる場合、その背景には何か理由があるかもしれません。個別に話を聞き、状況を改善するためのサポートをすることも重要ですが、「期限を守る」という基本姿勢を徹底させることは、プロとしての自覚を促す上で欠かせません。
それと一点知っておいてください。
↓
期限を守れない講師は、シフトへの責任も軽めです。当日欠勤など、より深刻な問題に繋がることも少なくありません。
人物は面接だけで見極めるのは難しいかもしれませんが、これも最初が肝心で、約束や時間を守ること、および期限を守ることは社会人として当たり前のことだということをしっかりと伝えて、仕事の心得的なことを植え付けておくことが肝要です。
まとめ:良質な顧客と安定した塾運営を両立させるために
学習塾の成功は、単に優れた指導内容だけでは決まりません。塾の理念やルールを共有し、共に成長していける「良質顧客」との関係を築くことが不可欠です。
そのためには、「顧客育成」という視点を持ち、入塾前から継続的に、口頭、文書、メールという3つの伝達手段を駆使して、塾のルールを明確に伝え、尊重してもらう努力を怠らないことが重要です。
これは、時に毅然とした態度を求められることもありますが、結果として、真面目な生徒や保護者が安心して通える環境を作り出し、塾の成長を長期的に支える強固な基盤となるはずです。
これから学習塾を始められる方も、既に運営されている方も、この「顧客育成」という視点を見つめ直し、より良い塾運営を目指していきましょう。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月14日
学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)
#保護者面談
#個別指導提案
#入試情報提供
#受験生意識付け
#塾テキスト推奨
#学習塾経営
#新年度カリキュラム
#春休み学習計画
#春期講習
#継続率向上

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目