塾の成功は「講師の質」と「情報共有」が鍵を握る! 生徒を伸ばす黄金方程式
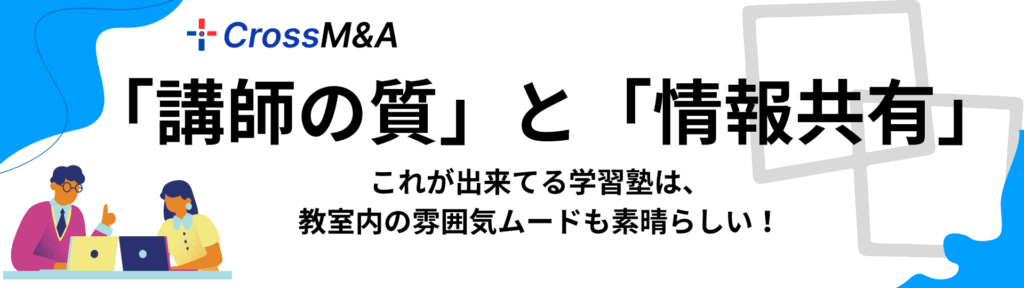
塾選びで重視される点の一つに、「講師の質」が挙げられます。
しかし、どれだけ素晴らしい授業をする講師がいても、それだけでは生徒の学力は飛躍的に伸びません。実は、もう一つ塾の成功を左右する重要な要素があります。
それが、「教室内における密な情報共有」です。
今回は、この「講師の質」と「情報共有」がいかに塾の成功に不可欠であるか、そして、それらをいかにして最大化していくかについて、詳しく掘り下げていきます。生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出すための「黄金方程式」を、具体的な事例を交えながらご紹介致します。
3か月以上通塾の生徒 保護者へのアンケート
下のグラフは、3か月以上通塾している生徒さんの保護者様へのアンケートです。何故、当方の塾に通って頂いていますか?という内容で複数回答可したものです。

↑
選択できる項目が複数であったために、お一人お一人の本音部分を完全に汲み取れているかどうかはわからないですが、このような結果があります。
・自宅から通いやすい
・学習計画が信頼できる
・体験授業で子どもが気に入った
・授業がわかりやすい
・成績向上が見込めそう
・子供の状況を把握している
・合格実績、指導実績
・講師との相性
・授業料が安い
・知り合いの勧め
・テスト対策がしっかりしている
・教室長との相性
・学校情報が豊富
今回の記事の主旨に合うものとしては、上の赤字にした部分だろうと推測します。
この中でもっとも注目して頂きたいのは、「子供の状況を把握している」という回答です。
これは、ものすごく気を付けている点です。

「講師間の情報共有」がもたらす相乗効果
どれだけ素晴らしい授業をする講師がいても、その情報が他の講師や塾全体で共有されていなければ、生徒の学習効果は半減してしまいます。
塾における「講師間の情報共有」は、まさに生徒の成長を加速させるための「潤滑油」のような存在です。
生徒理解の「点」を「線」にする
一人の生徒は、複数の科目を複数の講師から教わるのが一般的です。
例えば、数学はA先生、英語はB先生、国語はC先生といった具合です。
それぞれの講師は、自分の担当科目における生徒の学習状況を把握していますが、それだけでは生徒全体の学習状況を立体的に捉えることはできません。
ここで重要になるのが、講師間の情報共有です。
A先生が「この生徒は数学の応用問題で計算ミスが多い」という情報を共有すれば、B先生は英語の長文読解で似たようなケアレスミスがないか注意して見ることができます。C先生は、国語の論述問題で論理的な思考力が不足していると感じた際に、数学での論理的思考の訓練状況をA先生に確認するといったことも可能です。
このように、それぞれの講師が持つ生徒情報を共有することで、個別の学習状況が「点」ではなく、全体像として把握できる「線」となります。これにより、生徒の強みや弱みをより深く理解し、多角的な視点から効果的な指導を行うことが可能になります。
一貫性のある指導で生徒を混乱させない
もし、講師間で情報共有が全く行われていないと、生徒は混乱してしまう可能性があります。例えば、ある講師が「この問題はこう解くのが良い」と指導したのに、別の講師が「いや、もっと効率的な方法がある」と異なる解法を教えるようなことがあれば、生徒はどちらの方法を信じて良いのか分からなくなってしまいます。
適切な情報共有があれば、このような事態は防げます。例えば、特定の単元で複数の解法がある場合、事前に講師間でどの解法を推奨するか、あるいは生徒の理解度に合わせてどの解法から教えるかなどを話し合っておくことができます。
これにより、生徒は一貫性のある指導を受けることができ、安心して学習に取り組むことができます。
また、生徒の学習態度や集中力についても共有が必要です。
「〇〇さんは最近少し元気がない」「〇〇さんは集中力が続きにくい傾向がある」といった情報が共有されていれば、講師はそれぞれの生徒に合わせた声かけや指導方法を工夫することができます。これにより、生徒は常に最適な環境で学習を進めることができます。
塾全体で生徒の成長を支える「チーム」としての意識
情報共有は、単に生徒の学習状況を把握するだけでなく、塾全体が「チーム」として生徒の成長を支えるという意識を高めます。
一人の講師が抱え込むのではなく、全員で生徒の課題を共有し、解決策を検討することで、より多角的で質の高いサポートを提供できます。
例えば、ある生徒が特定の科目で伸び悩んでいるとします。その場合、担当講師だけでなく、他の講師もその生徒の学習状況について意見を出し合ったり、自身の経験からアドバイスを送ったりすることができます。これにより、担当講師は一人で抱え込むことなく、様々な視点から打開策を見出すことが可能になります。
また、情報共有は、講師自身のスキルアップにも繋がります。他の講師の指導方法や生徒への接し方を知ることで、自身の引き出しを増やすことができます。
成功事例を共有したり、課題解決のために議論したりすることで、講師一人ひとりの専門性を高め、結果的に塾全体の指導力向上に貢献します。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
それでは、CROSS M&A(通称:クロスマ)のアドバイザーが運営している学習塾における情報共有についてです。
どの学習塾でもやっていることだと思いますが、生徒ごとのファイルがあります。このファイルは色分けされていて、高校生は赤、中学生は青、小学生は緑色のファイルを使うようにしています。
一番最初の面談のときには、教室長が徹底してヒヤリングを実施いたします。生徒さんの学習状況はもちろんのこと、部活動の状況、内申点、出欠席、委員会活動から生徒会活動、学校の先生からの指摘事項とか、友達との関係性、ご自宅での過ごし方やお子さんの性格、趣味、好きなことなど、とにかく細かいところまで、お話してくださる内容はメモします。
その初期段階のメモを入れたり、学習上の相談シートを入れたり、模試や定期テストの結果、内申点(通知票)や個票などのコピー、検定試験の受験予定などなど、それはそれは細かくです!
講師はこのファイルをもって授業ブースに向かい、生徒の状況の把握に努めます。
センシティブな内容も共有します。例えば、ご両親ではなくお父さんだけのご家庭、お母さんだけのご家庭もあるでしょうし、ご本人が何かしらの障害をお持ちの場合などもあります。
教室責任者だけがこのような重要な情報を知っていて、講師が知らない・・・ということになると、うっかりした一言が生徒を傷つけてしまうこともあるのです。
ですから、細かいところまで「共有」します。
この共有は、教室長からだけの一報通行ではなく、担当した講師たちが自分たちが得た情報であるとか、見聞きした状況、及び授業を進めていく中での気づきなども提供されるため、教室長と講師の、講師同士の共有につながります。
そうすることで、1人の生徒さんの状況を全スタッフが知るようになります。
講師同士が生徒さんの授業方針を打合せしたり相談したりする場面をよくみます。この情報共有がしっかりしてくると、実は講師の中にも連帯感が生まれ、教室長と講師の相談の場もうまれ、教室内の風通しがとてもよくなるのです。

なぜ「講師の質」が重要なのか
塾に通う生徒にとって、講師の授業はまさに学びの核心です。
学校の授業とは異なり、塾の授業には特有の役割があります。それは、生徒一人ひとりの理解度や学習進度に合わせて、より深く、より効率的に知識を定着させることです。
知識を「理解」から「習得」へ
学校の授業は、どうしてもカリキュラムに沿って進められます。そのため、一度つまずいてしまうと、そのまま理解が追いつかずに置いていかれてしまう生徒も少なくありません。
しかし、塾の講師は、生徒のつまずきを見逃さずに、その場でフォローすることができます。
例えば、数学の応用問題で手が止まっている生徒がいれば、講師はすぐにその生徒がどの基礎概念でつまずいているのかを見抜き、丁寧に解説し直すことができます。単に「公式を覚える」のではなく、「なぜその公式が成り立つのか」「どのように活用するのか」といった本質的な理解を促すことで、生徒は知識を単なる暗記から、思考力を伴った「習得」へと昇華させることができます。
苦手克服と得意伸長を両立させるプロの技
生徒の学力は均一ではありません。ある科目は得意でも、別の科目は苦手という生徒は多くいます。塾の講師は、生徒の得意・不得意を正確に把握し、それぞれに合わせたアプローチを採る必要があります。
苦手な科目に対しては、問題を解かせるだけでなく、つまずきの根本原因を探り、基礎から徹底的にやり直すことが重要です。
例えば、英語の長文読解が苦手な生徒には、単語力だけでなく、文法や構文解析の基礎が不足している可能性もあります。講師は、その生徒の弱点をピンポイントで強化するための個別メニューを組むことで、苦手を克服へと導きます。
一方で、得意な科目を持つ生徒には、さらにその才能を伸ばすための挑戦を促すことも大切です。例えば、すでに学校の授業内容を理解している生徒には、より難易度の高い問題に挑戦させたり、発展的な内容を教えたりすることで、学習意欲を刺激し、さらなる高みを目指すきっかけを与えます。
「わかった!」を引き出すコミュニケーション力
授業の質は、知識の伝達だけでなく、講師と生徒の間のコミュニケーションによっても大きく左右されます。
一方的に教えるだけでは、生徒は飽きてしまったり、質問しにくさを感じたりすることがあります。
優秀な講師は、生徒が「わかった!」という手応えを感じられるように、工夫を凝らします。
例えば、難しい概念を身近な例に置き換えて説明したり、生徒に質問を投げかけ、考えさせる時間を作ったりすることで、能動的な学習を促します。
また、生徒が小さな成功体験を積み重ねられるように、適切なタイミングで褒めたり、励ましたりすることも、生徒の学習意欲を高める上で非常に重要です。
「情報共有」と「講師の質(授業の質)」を最大化する具体的な方法
では、実際に塾において「情報共有」を円滑に行い、「講師の授業」の質を高めていくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
1. 講師の採用と育成におけるこだわり
「講師の授業」の質は、まず講師の採用段階から始まります。
単に学力があるだけでなく、生徒と良好な関係を築けるコミュニケーション能力、生徒の疑問に寄り添える共感力、そして何よりも生徒の成長を心から願う情熱を持った人材を採用することが重要です。
採用後も、
指導スキルだけでなく、生徒への声かけの仕方、学習モチベーションの引き出し方、保護者との連携方法など、多岐にわたる業務を覚えてもらうことで、講師一人ひとりの能力を最大限に引き出します。
学生講師だから・・・という感覚は持たなくていいですし、
アルバイトであっても、「スタッフ」として接して、どんどん仕事を覚えさせていったほうが彼らのモティベーションは上がります。
また、ベテラン講師に新人講師を育成させることを敢えてやらせることでも実践的な指導力を身につけさせることも効果的です。定期的な授業見学やフィードバックを通じて、講師自身の指導を客観的に評価し、改善点を見つける機会も設けるべきです。
個人的には、
彼らのその後を決める一番の地点は、「最初」にあると思います。
つまり、面接時からその直後です。
2. 定期的な情報共有の場を設ける
情報共有は、偶発的に行われるものではなく、仕組みとして定着させることが重要です。
- 個別生徒の進捗共有シート: 各生徒について、学習目標、現在の進捗状況、課題点、次回の指導方針などを記録する共有シートを作成し、全講師が閲覧できるようにします。これにより、担当外の講師でも生徒の状況を把握しやすくなります。
- オンラインツールを活用: 講師へのツール利用を許可するのであれば、Discordや、Slackやチャットワークなどのコミュニケーションツールを活用し、リアルタイムでの情報共有を促進します。急な生徒の状況変化や、指導中に気づいたことなどをすぐに共有できる環境を整えることで、迅速な対応が可能になります。
- メンター制度の導入: 経験豊富なベテラン講師が、若手講師のメンターとなり、日々の指導における悩みや疑問に答えたり、情報共有の重要性を教えたりする制度も有効です。
3. 個別面談と三者面談の徹底
生徒一人ひとりの学習状況を深く理解するためには、定期的な個別面談が不可欠です。生徒との面談では、学習の進捗だけでなく、学校での様子、悩み、将来の目標など、多岐にわたる話題に触れることで、生徒の「人となり」を理解することができます。これにより、単なる教科指導だけでなく、精神的なサポートも可能になります。
また、保護者を交えた三者面談も非常に重要です。保護者から家庭での学習状況や、生徒の興味関心などを聞くことで、塾での指導に活かせる情報が得られます。塾と家庭が連携し、一体となって生徒の学習をサポートする体制を築くことで、生徒は安心して学習に集中できる環境を得られます。これらの面談で得られた情報も、当然ながら講師間で共有されるべき貴重な情報源となります。
4. 生徒の学習データ分析と活用
現代の塾運営において、生徒の学習データを活用することはもはや常識です。単なる点数だけでなく、各単元の正答率、苦手な問題の種類、学習時間などをデータとして蓄積し、分析することで、生徒一人ひとりの「学習の癖」や「つまずきポイント」を明確にすることができます。
これらのデータは、講師間の情報共有の強力なツールとなります。例えば、「この生徒は図形問題で特定のパターンに弱い」「計算速度が遅い傾向にある」といった具体的な情報が共有されることで、各講師はより的確な指導プランを立てることができます。また、塾全体として、どの単元で多くの生徒が苦戦しているかといった傾向を把握することで、カリキュラムの改善や教材の見直しにも繋げられます。
生徒を伸ばす塾が持つ「あたたかい」雰囲気
これまで、「講師の授業」と「情報共有」が塾の成功に不可欠な要素であることを述べてきました。しかし、これら二つの要素が真に機能するためには、もう一つ重要な要素があります。それは、塾全体の「あたたかい」雰囲気です。
生徒が安心して学び、質問できる環境がなければ、どんなに優れた講師の授業も、どんなに密な情報共有も、その効果を十分に発揮できません。講師と生徒の間に信頼関係が築かれ、生徒が「ここは自分の居場所だ」と感じられるような塾は、生徒の学習意欲を最大限に引き出します。
あたたかい雰囲気は、講師同士の円滑なコミュニケーションからも生まれます。講師たちが互いを尊重し、助け合い、生徒の成長を共に喜ぶ姿勢があれば、そのポジティブなエネルギーは生徒にも伝わります。塾全体が「生徒を伸ばす」という共通の目標に向かって協力し合う「チーム」となることで、生徒は安心して学習に没頭できるのです。
まとめ:生徒の可能性を解き放つ塾へ
塾の成功は、「偏差値を上げる」ことだけではありません。生徒一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出し、学習の楽しさを伝え、将来へと繋がる力を育むことにあります。その鍵を握るのは、やはり「講師の授業」と「講師間の密な情報共有」です。
優れた講師による質の高い授業は、生徒に知識と思考力を授けます。そして、講師間の情報共有は、その知識を生徒の全体像に即して定着させ、一貫性のあるサポートを可能にします。この二つの要素が密接に連携し、さらに塾全体が「あたたかい」雰囲気で包まれるとき、生徒たちは安心して、そして意欲的に学び、飛躍的な成長を遂げることができるでしょう。
私たちは、これからも生徒一人ひとりの個性と可能性を信じ、最高の教育を提供するために、講師の育成と情報共有の仕組みを磨き続けていきます。生徒たちの未来を、共に力強く切り拓いていくために。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

