学習塾の教材選び:なぜ「プリント依存」が学力低下を招くのか?
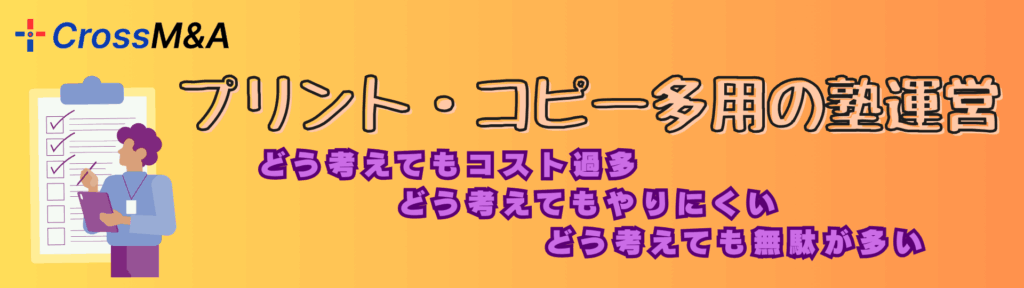
学習において、体系的にまとめられたテキストは不可欠です。
テキストは単に情報を羅列したものではなく、学習内容を論理的に構成し、段階的に理解を深めるための道筋を示しています。例えば、数学の参考書であれば、基本概念から応用問題、そして発展的な内容へとスムーズに移行できるよう、工夫された構成になっています。
生徒はテキストを通じて、自分が今何を学んでいるのか、そして次に何を学ぶべきなのかを明確に把握できます。これは、学習全体の見通しを立て、自己管理能力を養う上で極めて重要です。
章や目次、索引などは、生徒が知りたい情報を効率的に探し、既習事項との関連性を理解する手助けとなります。まるで地図のように、目的地への経路を明確にし、迷うことなく学習を進めることができるのです。
また、テキストは一貫性のある情報源として機能します。
異なる教師が指導しても、同じテキストを使用していれば、生徒は常に同じ基準で情報を得られます。これにより、学習内容の理解にずれが生じることを防ぎ、安心して学習に取り組むことができるのです。
さらに、良質なテキストは、学習内容の定着を促すための工夫が凝らされています。重要なポイントが強調されていたり、図やイラストが豊富に使われていたり、練習問題が適切に配置されていたりします。これらは、生徒が単に知識を詰め込むだけでなく、理解を深め、記憶に定着させるための手助けとなります。
プリントの「手軽さ」が招く混乱
一方で、多くの塾で用いられているプリント学習には、その手軽さゆえの弊害が潜んでいます。一枚完結型のプリントは、一見すると特定の単元や問題に集中できるため、効率が良いように思えます。しかし、その裏側には、生徒の学習を混乱させる多くの要因が含まれています。
1.学習の断片化と全体像の喪失
プリントは、多くの場合、特定のテーマや問題に特化して作成されます。これは、その日の授業内容に焦点を当てる上では有効ですが、学習全体の流れや各単元の関連性を見失わせる危険性があります。生徒は、個々のプリントに記された情報を断片的に吸収するだけで、それらがどのように結びつき、より大きな知識体系を構築するのかを理解しにくくなります。
例えば、数学で「方程式の解き方」のプリント、次に「関数のグラフ」のプリント、さらに「図形の証明」のプリントと、それぞれ独立した形で提供されたとします。
生徒はそれぞれのプリントで与えられた問題を解くことはできても、それらが数学という学問の中でどのように関連し、どのような位置づけにあるのかを把握することが困難になります。結果として、知識が体系化されず、応用力や思考力が育ちにくくなります。
2.情報の散逸と管理の煩雑さ
プリントは、その性質上、散逸しやすいという決定的な弱点があります。
授業ごとに配布される大量のプリントは、生徒にとって管理が非常に困難です。バラバラになったプリントは、紛失したり、順番が入れ替わったりしやすく、後で見返そうとしても必要な情報が見つからない、といった事態が頻繁に発生します。
「あの問題、どうやって解くんだっけ?」
「前にやったこれ、どこに載ってたかな?」
と生徒がプリントを探し回る時間は、決して学習の時間ではありません。本来、知識の定着や問題解決に費やすべき時間を、情報の整理という非生産的な作業に奪われてしまうのです。また、必要なプリントが見つからないというストレスは、学習意欲の低下にもつながりかねません。
3.復習効率の低下と学習履歴の不明瞭さ
体系的なテキストと異なり、プリントは復習の効率を著しく低下させます。特定の単元を復習しようとしても、どのプリントにその内容が書かれているのかを特定するのに時間がかかります。また、プリントの種類によっては、解説が簡略化されていたり、問題がランダムに配置されていたりするため、効率的な復習が難しい場合があります。
生徒は自分がこれまで何を学習してきたのか、どの分野を重点的に復習すべきなのか、といった学習履歴を把握しづらくなります。これにより、弱点の特定や克服が遅れ、学力向上の妨げとなる可能性があります。
4.手書きによる視認性の低下と学習効率の悪化
プリントへの直接の書き込みは、一見便利に見えますが、視認性の低下という問題を引き起こすことがあります。特に小学生や中学生の場合、まだ文字がきれいに書けないことも多く、書き込んだ文字が読みづらくなったり、図やグラフが見にくくなったりすることがあります。
また、限られたスペースに書き込むため、内容がぎゅうぎゅう詰になりがちで、後で読み返したときに内容を理解しにくい、という状況も生まれます。これは、結局のところ、学習効率の悪化につながり、せっかくの学習内容が十分に定着しない原因となります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
いつもの実例(実話)コーナーの時間です。
このプリント学習の弊害は、以下に書く以外にもたくさんあります。
たくさんの弊害事例
①渡したプリントを几帳面にまとめている生徒は1割もいない
たいてい、カバンの中でぐちゃぐちゃになっています。ファイルに整理してくれて、きちんと教科ごとに管理してくれていた生徒は、多分相当少数派になります。学習したプリント内に間違えがあったときに、ノートに解き直すなどして、ノートに整理する・・・そこまでの習慣づけが出来ればプリント学習も活きると思います。
②プリントの課題指示は、次回の講師が困る場合が多い
テキストの場合には、使用テキストとページ数、問題番号の記載があればすぐに課題や宿題の箇所を探し当てられますが、プリントの場合、その問題をどこからプリント、またはコピーしたのか、どの単元なのか、などをより細かく書いてくれないと次に担当する講師が困ります。
また、プリントの宿題を出した際に、前の講師が「解答・解説」までプリントしてくれれば、まやりやすいですが、それらがないと、次回に担当した講師が全部用意しなくてはなりません。
実に時間のロスも多く、講師のストレスにもなるでしょう。
③プリントは書き込みがゆえに、一回の学習で終わりがち
通常は、渡されたプリントには解答欄があります。したがって書き込み式です。そうすると、直接書き込んでしまっていますので、解き直しができません。
間違った答えを直す場合もプリントへ直接記入ですから、直すことが作業化してしまいます。
コスト面での無駄が多い

これはもう、単純な話です。
生徒がテキスト学習をすることを塾側で徹底している場合と、プリント学習する場合の塾側の負担コストはどのようになるでしょうか?
生徒がテキスト学習をする場合:
塾側の負担はゼロです。
プリント学習をする場合:
コピー代、紙代、塾側の負担です。
仮に一か月平均、複合機メンテ料金方式で、生徒向けのプリントとして平均10,000円のコストがかかっとします。年間12万円です。5年で60万円です。
一番やめたほうがいいのは、教材会社の〇トレなど
これは、驚くほどのコスト高です。
年間で30万円から35万円になります。5年で150万円から175万円です。ipadが35台以上買えます。良質なテキストが800冊ぐらい買えます。
そして、この教材会社の〇トレは、途中解約ができません。年度契約です。つまり、4月に契約して、例えば6月に解約としても、年度契約なので解約できません。残り9か月分、支払わなくてはなりません。
これは、教材会社のスタンスとしていかがなものでしょう。
もし、今契約されているのでしたら、一考を要する良い機会です。
よく考えてみてほしいのです。
100万題だとか、150万題だとかある、
それが保護者の入塾の決め手になりますか?
ならないです。
今まで、それが決め手だったと聞いたことは45000時間以上の実務時間で一度もございません。
つまり、それは、塾側のちょっとした自己満足、自己肯定材料でしかありません。
生徒目線、講師目線、保護者目線に立った時、
CROSS M&A(通称:クロスマ)アドバイザーは、塾経営もやっておりますが、はたと気づいてしまいました。
なので、一斉に解約しました。年間180万円のコストカットです。
塾がテキストを積極的に使うべき理由
まず最初に コストカットに繋がる!
まずはきれいごとを言う前に、テキスト主体の運営にした場合には、想像以上のコストカットになります。
たしかに最初に教室用のテキストを購入する必要がありますし、教科書の切り替えがあれば、新版の用意も必要です。しかしそういう場合、早く手配した場合の早割であったり、セット購入をした場合には半額で購入できるなどの塾ならでは特典もあります。
それらは必要経費ですので、それすらもコストカットしたい!という話になると、それは難しいです。
赤本や過去問などを揃える場合は、新品を購入してもいいですが、ブックオフやネットで、年度落ちでしたら、それもコストカットになります。

そして、
生徒が使用するテキストは、生徒側が用意することになりますので、(通常は購入してもらいます)塾が生徒のテキストを負担することはありません。
したがって、最初の塾用テキストを用意したら、あとは教材関連で、時折新規購入をしたり、中古でストックを増やすぐらいのコストにしかなりません。
学習効果で考えてみましょう!
上記のようなプリントの弊害を考慮すると、塾は体系的なテキストを積極的に導入し、その活用を徹底すべきです。テキスト中心の学習には、以下のような明確な利点があります。
1.体系的な学習の促進
テキストは、学習内容が論理的に構成されているため、生徒は順を追って知識を習得し、理解を深めることができます。各単元がどのように関連しているのか、次に何を学ぶのかが明確であるため、学習全体の流れを把握しやすくなります。これにより、知識が点ではなく線でつながり、より深い理解と応用力が育まれます。
2.情報の集約と管理の容易さ
すべての学習内容が一冊のテキストに集約されているため、生徒は必要な情報を簡単に見つけることができます。バラバラになる心配もなく、管理の手間も大幅に削減されます。これにより、生徒は情報の整理に時間を費やすことなく、純粋な学習に集中できる時間が増えます。
3.効率的な復習の実現
テキストは、章立てや索引がしっかりしているため、効率的な復習が可能です。苦手な単元や、過去に学習した内容をすぐに探し出し、集中的に復習できます。また、解説が充実しているため、生徒が自力で理解を深める手助けにもなります。
4.自学自習能力の育成
テキストは、生徒が自力で学習を進める能力を育む上で非常に有効です。疑問点が生じた際に自分で調べたり、練習問題を解いて理解度を確認したりする過程を通じて、主体的な学習態度が養われます。これは、塾を卒業した後も、生涯にわたって学び続ける上で不可欠な能力です。
5.講師の指導の一貫性
塾内の複数の講師が同じテキストを使用することで、指導内容の一貫性が保たれます。生徒は、どの教師から教わっても同じ質の情報と指導を受けることができ、学習の混乱を防げます。
プリントを全く使わないわけではない
もちろん、プリントが全く不要だというわけではありません。例えば、以下のようなケースでは、プリントは有効な補助教材となります。
- 直前の演習問題: 試験直前の総復習として、特定の分野の演習問題をまとめたプリントは有効です。ただし、これも過去に学習したテキスト内容と関連付けて使用すべきです。
- 補充問題や発展問題: テキストだけではカバーしきれない、生徒のレベルに合わせた補充問題や、さらに思考力を深めるための発展問題は、プリント形式で提供することも考えられます。
- 時事問題や最新の情報: テキストの改訂では追いつかないような、時事問題や最新の入試傾向に関する情報は、プリントで補うのが適切です。
しかし、これらの場合でも、あくまでテキストを主軸とした学習の「補助」として位置づけることが肝要です。プリント単独で学習を進めるのではなく、テキストの該当箇所と関連付けながら使用することで、その効果を最大限に引き出すことができます。
まとめ
学習塾が提供すべきは、知識の断片ではなく、体系的な学習の枠組みだと思います。
その中心に据えるべきは、良質なテキストに他なりません。手軽さゆえに多用されがちなプリントは、生徒の学習を断片化し、混乱を招く原因となりえます。
塾は、生徒が学習の全体像を把握し、効率的に知識を定着させ、自ら学び続ける力を育むために、テキストの活用を最優先すべきです。プリントは補助的な役割に徹し、生徒が迷うことなく、着実に学力を向上させられる環境を整えることが、塾の責務であると言えるでしょう。
あなたの塾では、テキストとプリントの役割分担は明確になっていますか? 生徒が学習の全体像を見失っていないか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク
関連記事

2026年02月05日
学習塾において、春期面談時に押さえるべきポイント ◆◆◆8つの重要項目について
#会場模試
#保護者面談
#学習塾
#授業計画
#教材選定
#新受験生
#春期講習
#春期面談
#継続確認
#英検対策

2026年01月14日
学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)
#保護者面談
#個別指導提案
#入試情報提供
#受験生意識付け
#塾テキスト推奨
#学習塾経営
#新年度カリキュラム
#春休み学習計画
#春期講習
#継続率向上

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導