定期テストと高校入試の大きなギャップ:その差を埋めるための徹底攻略ガイド
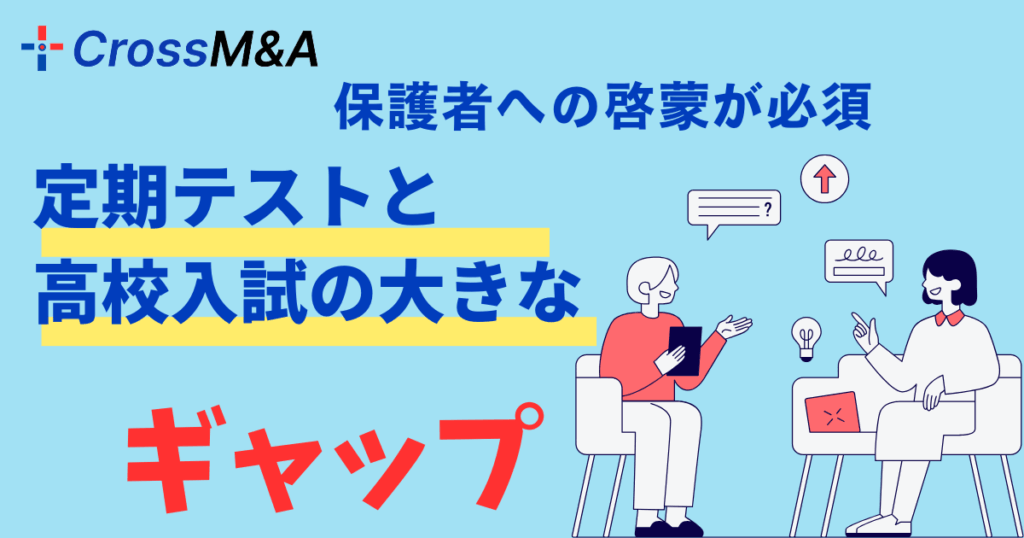
高校受験を控える生徒や保護者の皆様へ面談をする時期です。
保護者が塾に通わせる判断をし、塾通いを開始した後でも、保護者はわが子の成績が本当に上がるのだろうかと心配し続けます。
例えばこんな悩みに声を聴いたことはありませんか。
「定期テストではいい点が取れるのに、模試や過去問になると、どうしてこんなに点数が下がってしまうのだろう…」
実は、これは多くの受験生が直面する、ごく一般的な現象です。
なぜなら、定期テストと高校入試には、私たちが想像する以上に大きなギャップが存在するからです。
このギャップを正しく理解し、適切な時期に適切な対策を講じることこそ、志望校合格への最短ルートとなります。
そして、オーナーや塾長、教室長は、このギャップについて、極力早めに保護者へ「啓蒙」すべきです。
何故なら、保護者たちが子供のころと、今の子供の時代とでは、教育環境は大きく変化しているからです。
いわゆる
「お父さん、お母さんたちの時代とは、こんな風に変わっていますよ」
「お父さん、お母さんたちの時代と比べてこのようなことが加えられています」
「お父さん、お母さんたちの時代と比べて難易度面ではこのような変化があります」
そのギャップの正体を明らかにし、きちんと示して、さらに具体的な対策法について提示する!ここまでを徹底して面談の際でも実施していくようにしましょう。
定期テストと入試、何がそんなに違うのか?
まず、両者の本質的な違いを理解することから始めましょう。
生徒にも理解してほしいのはもちろんのこと、一番は「保護者に理解してほしい」からです。
定期テストは、あくまでも学校の授業の理解度を測るためのものです。出題範囲は限定されており、多くの場合、教科書や授業で扱った内容から出題されます。そのため、授業を真面目に聞いて、ワークを繰り返し解くことで、ある程度の点数は確保できます。平均点が300点前後と比較的高いのも、そのためです。
一方、高校入試は、中学校3年間の学習内容を網羅した総合的な学力を問うものです。ただ知識を覚えているだけでなく、その知識を使いこなす思考力、応用力、判断力が問われます。
出題範囲は広範にわたり、教科書を少しはみ出した内容や、複数の単元をまたいだ複合問題も頻繁に出ます。全国的な平均点が260点前後と、定期テストに比べて低いのは、入試問題がより高度な能力を要求している証拠です。
それでは、各科目で具体的にどのようなギャップがあるのか、詳しく見ていきましょう。
上記の件は、教室を運営されている全国のオーナー、教室長、塾長は百も承知で、釈迦に説法なのはよくわかります。
申し上げたいのは、その感覚と同等感覚になってくれるように保護者に啓蒙しなくてはいけないということです。これはマストであり、この発言や資料提供を端折ってしまったり、省略したりすれば、いずれ大きなしっぺ返しが必ずあります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
似たようなことが何度もあるため、一番インパクトがあったちょっとひどい事例を紹介します。
太郎君(仮称)は中学3年生で受験生。学校の成績はだいたい420点ぐらいでした。
面談に来られるのはいつもお父さんでした。お父さんは、かなり厳しい方で、太郎君に求めるものが大きかったです。
志望校は、学区内トップの学校を受けろ!点数は9割以下は許さん!
簡単にいうとこんなタイプの方でした。
ある日の面談で、社会の話題になったときに、
「社会なんてあんなものは暗記すればいいんだよ、覚えりゃ誰でも点数取れるんだよ!」と言いながら、太郎君の頭をポカポカと殴り始めたのです。
正直私は、これは何かのデモンストレーションなのだろうか?と思っていたのですが、その殴る音がだんだんと大きくなってきました。
よく芸人さんが相方の頭を平手うちするのがありますが、最初はあんな感じのペチッというぐらいでしたが、だんだん音が大きくなると、さすがに太郎君もかなり痛がっていましたので、
(これはもしかして家庭内ではこれ以上なのでは?虐待で通報したほうがいいだろうか・・)とまで考えたぐらいです。
家庭内のわが子に対しての指導方針はどのご家庭もあろうかと思いますが、さすがにひどいシーンを見せられましたので、思い切り話題を変えて殴るのをやめるように話しを誘導しました。
そうです。お父さんの時代と太郎君の時代ではかなり違うのですが、お父さんの時代感覚で、テストで9割、100点取れないのはおかしいというものがありありと残っていたのです。
太郎君の感覚はいつも
「親に叱られるからやる」というものでした。
私はこのシーンを見てから、必ず小学生であれ、中学生、高校生であれ、今の教育環境はこんなに違う!という関連記事をしっかりと初期面談でも伝えるようにしています。
要するに、親御さんたちに、今の状況をしっかりと理解してもらうことで、必要なプランや必要な時間などを具体的に提示できるようになるのです。
そして、最も大きな使命としては、例えば学校のテストで420点、430点・・・440点と取れていても
それはあくまでも
・範囲が細かく指定された
・本当に楽な定期テスト上での
・とれるべくしてとれた点数
ではなかろうか、という観点を持っていないと、ギャップは永遠に埋まりません。
例えば、普段から保護様に伝える報告内容で、
「よくできています!」
↑ ↑ ↑ ↑
この報告のリスク値の大きさは、オーナー、塾長、教室長は絶対に知っておいたほうがいいでしょう。
もし?
この「よくできています」が保護者にとって響きの良い言葉で安心を誘うものだとして多用しているのならば、今すぐやめたほうがいいです。
よくできていますの連呼を普段からしていて、定期テストでこけたら、保護者の不信感はマックスを飛び越えてしまいます。
下手したらブチ切れです。
子どもの良い部分の報告って楽ではないですか?
「花子さんは今回も小テストがよくできていて、素晴らしいです!」これ言いやすいですよね。(書きやすいですよね)
言う(書く)ほうも気分がいいですし、聞く(読む)ほうも気分がいいです。
このような報告を100万回しても何にもならないです。
逆です。
出来ていないこと、課題として残ること、
これを報告すべきだと思うのですがいかがでしょう。
もし、普段から「よくできています」を連呼してしているのでしたら、それが定期テスト後に修羅場になる教室の特徴です。
どんなに優秀な子でも課題を報告するようにしたほうが 今回の重要テーマである「ギャップ」はそうそう生まれません。
普段から、悪い報告から逃げていたり、伏せていたり、隠していたり、オブラートに包んだり、事実を捻じ曲げている場合には、保護者が本質、本当のことをつかめないまま、定期テストとかのいわゆる保護者にとっての本番(※または準本番)を迎えるのですから、そのギャップが大きいほどに、
今度は保護者のモードが「信用できないモード」になってしまいます。
ちなみに一度信用できないモードになりますと、信頼回復のための苦労を倍しなくてはいけません。
よいことなど、全部後回しにして
悪いことをピックアップして、丁寧に説明しケアしていく計画を立てる!このことが重要です。
それでは、今度は
各教科の「ギャップ」についても見ていきましょう。
英語:教科書を飛び出す世界
定期テストの英語は、教科書の本文や単語、文法事項が中心です。例えば「New Horizon」や「SunShine」といった教科書に掲載されている単語や文法をしっかり覚えれば、高得点も取れます。
しかし、高校入試の英語は全く異なります。
- 未知の単語:教科書にはない、より高度な単語や熟語が平気で出題されます。これは、単に「習ったことだけ」ではなく、「文脈から意味を推測する力」を試されているのです。
- 長文読解の質と量:定期テストの長文は、多くても数百語程度ですが、入試の長文は1,000語を超えることもあります。単に文章が長いだけでなく、テーマも環境問題、社会問題、科学技術など多岐にわたり、抽象的な内容も含まれます。
このギャップを埋めるには、日頃から教科書以外の英文に触れる習慣が重要です。ニュース記事や洋書(児童向けからでもOK)、英語の雑誌などを読み、未知の単語に臆することなく、文脈から意味を推測する練習を繰り返しましょう。
【実話】
実際、日本全国で見ても英語については定期テストにおいて「教科書外出題」が増加しています。それは何故かというと、教科書内容を出題すれば、軽く暗記しただけで点数が取れてしまうからです。
また単語は教科書に載っていない単語も入試で出るようになっています。
大学入試の問題が共通テストに代わって大きく変わりましたので、その内容を踏襲した形で高校入試などにも波及しているのがわかります。
数学:基礎問題では歯が立たない応用問題
定期テストの数学は、多くが教科書の例題や類題です。「この問題はあの公式を使う」とパターンを覚えていれば、ほとんどの問題に対応できます。しかし、入試問題は違います。
- 複合問題:一つの単元だけで解ける問題はほとんどありません。例えば、「二次方程式」と「図形」や「関数」が組み合わさった問題が出題されます。複数の単元の知識を横断的に使いこなす力が求められます。
- 思考力・発想力:公式を当てはめるだけでは解けない問題が多数出題されます。問題文を深く読み解き、自分で解法を組み立てる「発想力」が必要です。特に、証明問題や、グラフと図形を組み合わせた問題では、この力が試されます。
このギャップを埋めるには、ただ公式を覚えるだけでなく、「なぜその公式が成り立つのか」「どのような問題に応用できるのか」を深く考えることが重要です。一見難しそうに見える問題でも、実は基本問題の組み合わせで解けることがほとんどです。
【実話】
共通テスト2年目の数ⅠAにおいて、平均点が過去最低の38点台という衝撃の結果がありました。数学においては、日本という国が技術大国のはずだったのに、この失われた30年で思い切り米国や中国におかぶを持っていかれたそのツケが大きすぎると言えます。
官僚でも民間でも大学でも「理系人材」を欲しがっています。
しかも高度な数学を武器に世界に勝負をかけられるような人材をです。
従って、いつからか「一に数学、二に数学、三に数学」という数理資本主義を掲げるようになったのです。
数学の問題がかつてのゆとり時代のように簡単になることは、二度とないでしょう。これからどんどん低学年でも高度な内容を習うように変わっていくはずです。
国語:教科書を離れ、未知の世界へ
定期テストの国語は、教科書の本文から出題されます。事前に内容を読んでいれば、登場人物の心情や表現技法も予測できます。しかし、高校入試の国語は、受験生にとって全くの初見の文章で勝負しなければなりません。
- 文章量の増加:入試の長文は、定期テストの比ではありません。小説や随筆、論説文など、多岐にわたるジャンルの文章を、限られた時間で正確に読み解く必要があります。
- 深い読解力:ただ文章の内容を理解するだけでなく、筆者の主張や意図を正確に読み取る力が求められます。表面的な理解ではなく、「行間を読む」力が重要です。
- 多様なジャンル:小説や随筆だけでなく、論説文や説明文も出題されます。特に論説文は、抽象的な概念を扱うことが多く、論理的な思考力が問われます。
このギャップを埋めるには、日頃から様々なジャンルの本や新聞、雑誌を読み、読解力を養うことが不可欠です。また、文章の構造を意識して読む訓練をしましょう。「筆者の主張はどこか」「根拠となる部分はどこか」と意識しながら読むことで、初見の文章でも要点を素早く掴めるようになります。
【実話】
圧倒的な文章量を読ませる問題、これはもうデフォルトだと思っていいです。
読むスピードが普通であればお話にならないぐらい解き終わりませんので、速読の技術もすでに必要な世の中になっています。
国語については、例えば
定期テストで太宰治の走れメロスの内容が範囲と指定されたならば、100%教科書内容が本文として登場して、傍線が引かれ、その問いが作成されます。
著作権の問題があるため、類題として、他の作者の似たような文章とかを持ってくる・・・なんていうこともないです。
ところが、入試問題は現代文であれば、古典であれ、たいてい初見の問題になります。普段の国語学習で初見問題での練習を徹底している生徒などそうそういません。したがって、もっともギャップを感じる教科になるかもしれません。
理科:一問一答では通用しない「なぜ」の理解
理科の定期テストは、用語の暗記や一問一答形式の問題が多い傾向にあります。「イオン」「化学反応式」「天体」などの単語を暗記すれば、ある程度の点数は取れます。しかし、入試では、このやり方だけでは通用しません。
- 実験・観察問題:実験の手順や結果を読み取り、考察する問題が頻繁に出題されます。ただ知識を覚えているだけでなく、その知識を実験の場面で応用できるかが問われます。
- 計算問題:物理分野の「電気」「力学」や化学分野の「化学変化と物質の質量」など、計算を伴う問題の正答率が低くなりがちです。公式を覚えるだけでなく、問題の状況を正しく理解し、適切な公式を当てはめる「思考力」が必要です。
- 分野横断:例えば、地学と生物学が組み合わさった問題のように、複数の分野の知識を統合して解く問題も出題されます。
このギャップを埋めるには、「なぜそうなるのか?」を常に考える学習スタイルに切り替えましょう。用語をただ暗記するのではなく、その原理や仕組みを理解することが重要です。また、問題集を解く際も、計算問題は解法を丸暗記するのではなく、「どういう思考プロセスでこの式にたどり着いたのか」を意識して解き直しましょう。
社会:暗記だけでは点は取れない
社会の定期テストは、歴史の年号、人物名、地理の地名、公民の制度名など、暗記が中心です。しかし、入試では単なる暗記力だけでは太刀打ちできません。
- 資料の読み取り:統計グラフ、写真、古地図など、多様な資料から情報を読み取り、解答する問題が増えています。
- 因果関係の理解:歴史上の出来事や社会制度の「なぜそれが起こったのか」「その結果どうなったのか」という因果関係を問う問題が頻繁に出題されます。単なる暗記ではなく、歴史の流れを物語として理解する力が重要です。
- 論述問題:ある事柄について、複数の要素を関連付けて説明する論述問題も出題されます。論理的な文章構成力と、知識を統合する力が求められます。
このギャップを埋めるには、教科書の太字部分だけを覚えるのではなく、行間の文章までしっかり読み込みましょう。歴史の流れを年表で整理したり、地図と結びつけたりして、知識を点ではなく、線や面で捉えることが重要です。
【実話】
理科と社会については、暗記要素も多くありますが、暗記すれば点が取れる・・・という時代ではなくなりました。
例えば理科については、入試問題をよく分析するとわかりますが、生徒さんたちの正答率の高い順番にソートしていくことで見えてくる課題があります。
それは計算が絡んだ問題です。
つまり、理科という分野では、物理・化学が弱い生徒さんが全国的に多いということを示唆しています。
この内容からしても暗記が奏功する問題ではなくなっているのがわかります。
社会においても、ステップ数が多い問題が多くなっているのがわかります。
例えば、一問一答式の問題をステップがひとつの問題としますと、その考えるステップが2段階、3段階になっているということです。
徹底攻略!入試対策はいつから、どう始めるべきか?
定期テストと入試のギャップを理解したら、いよいよ具体的な対策に入ります。遅すぎると手遅れになる可能性もあります。
対策開始のベストタイミングは?
結論から言うと、中学2年生の冬から始めるのが理想的です。
この時期は、中学1・2年生で習った基礎が固まり、かつ高校受験を本格的に意識し始める時期です。部活動も徐々に落ち着き、まとまった勉強時間を確保しやすくなります。この時期から、定期テスト対策だけでなく、入試を意識した学習にシフトしていくことで、大きな差をつけることができます。
具体的な対策方法
1. 中2の冬:基礎の総点検と応用への挑戦
- 弱点科目の洗い出し:中学1・2年生の定期テストの成績や、実力テストの結果を分析し、自分の弱点科目を特定します。
- 基礎固めの徹底:弱点科目の教科書や問題集をもう一度解き直し、曖昧な知識をなくすことが最優先です。
- 応用問題への挑戦:教科書の発展問題や、入試の基礎レベルの問題集に少しずつ挑戦し始めましょう。
2. 中3の春~夏:入試レベルへの本格シフト
- 問題集の切り替え:定期テスト対策用の問題集から、入試レベルの問題集に完全に切り替えます。特に、「分野横断型」や「思考力養成」を謳う問題集を積極的に選びましょう。
- 演習量の確保:苦手な科目だけでなく、得意な科目も入試レベルの問題をたくさん解いて、応用力を高めます。
- 模試の活用:定期的に模試を受け、自分の実力を客観的に把握しましょう。模試は、弱点を発見する最高のツールです。間違えた問題は、なぜ間違えたのか、どうすれば解けたのかを徹底的に分析してください。
3. 中3の秋~冬:志望校に合わせた最終調整
- 過去問演習:いよいよ志望校の過去問を解き始めます。まずは時間を測らずに解いてみて、志望校の出題傾向、難易度、時間配分を体で覚えましょう。
- 弱点の再強化:過去問演習で浮き彫りになった弱点を徹底的に潰します。例えば、特定の分野の正答率が低いなら、その分野の問題集を重点的に解き直します。
- 時間配分の練習:時間を測って過去問を解く練習を繰り返します。本番で力を出し切るためには、時間配分が非常に重要です。
まとめ
定期テストと高校入試のギャップは、決して超えられない壁ではありません。「定期テストは知識の確認、入試は知識の応用」という本質的な違いを理解し、中学2年生の冬から入試を意識した学習を始めることができれば、合格はぐっと近づきます。
大切なのは、「なぜ?」を常に考える学習姿勢です。単に答えを覚えるだけでなく、その背景にある原理や仕組みを理解しようとすることで、思考力と応用力は自然と身についていきます。
さあ、今日から入試対策を始め、定期テストとは一味違う「本当の学力」を身につけ、志望校合格を掴み取りましょう。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目

2025年09月26日
塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について
#入塾面談
#塾の成功
#塾経営
#塾講師
#学習塾
#学習塾運営
#期限厳守
#生徒指導
#良質顧客
#顧客育成