事業譲渡と株式譲渡の基本:M&Aにおける法務知識
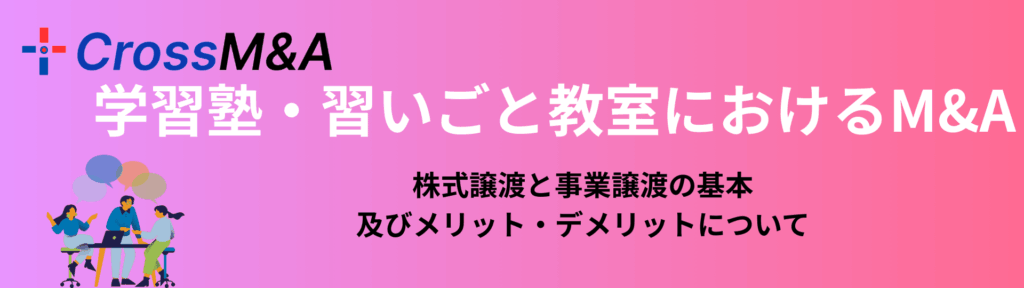
M&A(企業の合併・買収)を検討する際、特に中小企業にとって重要な選択肢となるのが事業譲渡と株式譲渡です。
これらはどちらも会社の売却を目的としますが、法的な手続き、税金、そして売り手・買い手双方に与える影響が大きく異なります。今回は、M&Aの実務に携わるCROSS M&A(通称:クロスマ)が、これらの手法の基本を法務の観点から解説します。
M&Aの基本構造
M&Aは、会社全体を売るのか、それとも特定の事業だけを売るのかによって、その手法が大きく変わります。この違いを理解することが、M&Aを成功させるための第一歩です。
私どもCROSS M&A(クロスマ)は学習塾・習いごと専門、特化型のM&Aサービスを行っておりますので、譲渡主、オーナー様の状況に応じて最適な方法を提案し、スムーズな手続きをサポートします。
学習塾、習いごとのM&Aは、規模的に言えば「小規模M&A」に属することが多いです。何をもって小規模かと言うと、売上高規模です。数千万円から2億円ぐらいは大方「小規模」に属します。そして、学習塾や習いごとは、法人が運営している場合もありますが、個人経営のところも多くあります。
これらの実情からすると、事業譲渡の選択が多くなります。もちろん、規模感の違いによって、及び状況の違いによって、それぞれのスキームにはメリットとデメリットがありますので、まずはその点を押さえておきましょう。
株式譲渡のメリットとデメリット
株式譲渡は、会社の株式をすべて、または過半数譲渡することで、会社の経営権を買い手に移転するM&Aの手法です。売り手にとっては手続きがシンプルで、会社法上の手続きが不要な点、また個人に譲渡益が発生するため、税率が低いという大きなメリットがあります。
どちらかというと、売上高規模で言えば中規模M&A(4億円から20億円ぐらい)の場合には、8割が株式譲渡を選択されます。
株式譲渡のメリット
- 手続きの簡便さ: 会社全体を譲渡するため、個別の資産や負債を一つひとつ移転する手続きが不要です。株主間の合意があれば、比較的スピーディーに取引を進められます。
- 税制上の優遇: 売り手となる株主(個人)は、株式の売却によって得た所得(譲渡所得)に対して、約20%の申告分離課税が適用されます。これは、個人の総合所得にかかる累進課税よりも低い税率であることが多く、売り手にとっては大きなメリットとなります。
- 従業員の雇用維持: 会社そのものが買い手の傘下に入るため、従業員の雇用契約や労働条件はそのまま引き継がれるのが一般的です。これにより、従業員の不安を軽減し、円滑な組織移行を促せます。
株式譲渡のデメリット
- 簿外債務のリスク: 株式譲渡は、会社の資産だけでなく、すべての負債(簿外債務を含む)も引き継ぐことになります。買い手は、貸借対照表に記載されていない隠れた債務(未払いの残業代、係争中の訴訟費用など)を抱えるリスクを負います。このため、買い手はデューデリジェンス(買収監査)を厳格に行い、リスクを特定する必要があります。
- 偶発債務の引き継ぎ: 株式譲渡では、将来的に発生する可能性のある偶発的な負債(保証債務など)も引き継がれます。
- 株主間の複雑な関係: 複数の株主がいる場合、全員の同意を取り付けるのに時間や労力がかかることがあります。また、少数株主の存在がM&A後の経営に影響を与える可能性もあります。
事業譲渡のメリットとデメリット
事業譲渡は、会社の特定の事業(事業部門、営業資産など)を切り出して売却するM&Aの手法です。事業譲渡は、会社全体ではなく、特定の事業のみを売却したい場合に適しています。
CROSS M&A(クロスマ)では、事業譲渡を行う譲渡主、オーナー様に対して、どの資産や契約を譲渡するかの検討をサポートし、法務・税務面でのアドバイスを提供します。
事業譲渡のメリット
- 譲渡範囲の限定: 売り手は、売却したい事業を自由に選択できます。これにより、不採算事業や将来性の低い事業のみを切り離すことができます。
- 簿外債務の回避: 売り手は、負債を承継させないという契約を締結できます。これにより、買い手は簿外債務のリスクを限定することができます。ただし、個別の債務については債務引受の契約が必要となります。
- 税制上の優遇: 法人税の観点では、譲渡益に対して法人税が課されますが、その後のキャッシュの使い道に柔軟性があります。
- 雇用契約の再構築: 従業員の雇用契約は自動的に承継されず、個別に同意を得る必要があります。これにより、買い手は必要な人材だけを雇用できます。
事業譲渡のデメリット
- 手続きの煩雑さ: 事業譲渡では、売却する資産や負債、契約を個別に譲渡する手続きが必要です。不動産の登記変更、許認可の再取得、取引先との契約締結など、多岐にわたる手続きが必要となり、時間とコストがかかります。(※下記に説明)
- 税制上の注意点: 譲渡対象となる資産の種類によっては、消費税が課される場合があります。また、不動産が含まれる場合は登録免許税も発生します。
- 従業員との再契約: 従業員は自動的に承継されないため、買い手は個別に再契約を結ぶ必要があります。このプロセスは、従業員との関係構築に影響を与え、労務リスクとなる可能性もあります。
- 会社法上の手続き: 事業譲渡は、株主総会の特別決議が必要となる場合があります。また、事業譲渡に反対する株主は、会社に対して株式買取請求権を行使できる場合があります。
株式譲渡と事業譲渡の比較表
以下に、株式譲渡と事業譲渡の主要な違いをまとめました。
これはあくまで一般的なものであり、個別のケースでは異なる場合があります。CROSS M&A(クロスマ)は、それぞれのケースに合わせた詳細な分析とアドバイスを提供します。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
| 法的根拠 | 会社法上の手続きは不要(取締役会の決議が必要な場合あり) | 会社法(株主総会の特別決議が必要) |
| 売買の対象 | 会社の発行済株式のすべてまたは一部 | 特定の事業に関する資産、負債、権利、義務 |
| 譲渡の手続き | 比較的簡便。株主間の契約締結のみ。 | 煩雑。個別の資産や負債、契約の移転手続きが必要。 |
| 簿外債務 | 買い手がすべて引き継ぐ | 買い手が引き継ぐ範囲を限定できる |
| 税金(売り手) | 株主(個人)に譲渡所得課税(申告分離課税、約20%) | 法人に譲渡益課税(法人税等) |
| 税金(買い手) | 譲渡対象ではない | 譲渡資産の種類によっては消費税、不動産取得税、登録免許税などが発生 |
| 従業員 | 雇用契約は自動的に承継される | 雇用契約は自動的に承継されない(個別再契約が必要) |
| 許認可 | 変更不要な場合が多い | 原則として買い手側で再取得が必要 |
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
上記で、事業譲渡における手続きの煩雑さをデメリットとして挙げました。
少々一般論的な内容でしたので、資産や負債の譲渡とか、不動産登記や許認可の内容も含めせていただきました。
学習塾や習いごと教室の一般的事例では、実際はそこまで煩雑ではありません。
以下、通常の学習塾・習いごと教室における事業譲渡の実例として示します。
学習塾・習いごとの事業譲渡
①不動産契約
例えば自分の土地に建物を建てて塾や習いごと教室を運営している事例は小規模M&Aではほとんどありません。たいていは、賃貸借契約により、物件を借りて運営しているケースです。
従いまして、譲渡の際は、不動産管理会社に「譲渡をする」旨をなるべく早く伝えておくようにしてください。
そして実際には、譲渡主、オーナー様は現状の不動産契約を解約となり、新オーナーがあらたに当該物件の契約を結ぶことになります。
その際に、譲渡主、オーナー様が預けていた保証金、敷金の類は通常は全額手元に返還されます。
それは、譲渡だからです。
もし「廃業」「閉校」で物件を解約のみとした場合には、保証金や敷金から物件明けわたし前に、原状回復しなくてはいけませんので、まるごと手元に返還されることはまずありません。
②フランチャイズ契約
フランチャイズでの運営をされていた場合は、同様に早めにフランチャイズの本部の担当者に連絡を入れておきます。
この場合も不動産と同様、契約者がAからBへ移動することになるため、譲渡主、オーナー様はその屋号での運営権利を放棄して(解除して)新オーナーが本部との新しい契約を結ぶことになります。
③引落処理をしている決済代行会社との契約
通常、学習塾や習いごとの月謝等は銀行引落にしているケースが多いです。そのため、オーナーチェンジの際は、新オーナー側に引き落とされた売上が入るようにしなければなりません。
ただこれは、決済代行会社が処理方法を丁寧に指定してくれますので、大きな心配はいりません。
④電話やWi-Fi、プロバイダの契約
電話の場合は、長年つかってきた塾や習いごと教室の番号をそのまま引き継ぐのが普通です。譲渡契約が成立したタイミングで電話番号も変更する・・・となると、非常に処理が多くなりますのでオススメできません。
各種登録されている媒体のすべて、顧客、講師、看板変更、サイトの情報内容の変更、パンフレットや案内書類を作っている場合の番号変更・・・など、とにかく全部を変更する覚悟で取り組まないと漏れが生じてしまいます。
そして、電話番号をそのままで承継する場合には、NTTとのやり取りがあります。承継の場合は手続きするためも書類が多いですが、手順に沿って実施すれば問題なく承継できます。
その際に、Wi-Fiもセットであれば、その内容の引継ぎも忘れないようにしましょう。
また、プロバイダの契約においても新オーナーが新規で契約することになり、旧オーナー側は解約をすることを忘れないようにしましょう。
その際に、プロバイダのIDやパスワードを忘れてしまっていると、少々厄介です。
通信関連の書類は、わかりやすく管理しておくとよいでしょう。
この上記の①から④がとても重要です。
会場模試の会社とか、テキストの会社、その他サービスの会社のおいては、比較的融通も利きますし、処理面では応援してくれますので、さほど大変ではありません。
しかしながら、こまごまと「やるべきこと」は多いです。
その際、優先順位を決めるとしたら、やはり一番最初に着手すべきは、不動産会社への連絡です。
物件によって異なりますが、2から3か月前に通告する必要があるからです。
重要事項説明書と賃貸契約書というものが物件を借りた際に買わされる書類です。
※下のほうに譲渡における情報の記事リンクがありますので、お時間がある方は全部確認してみてください。
ここで念のために、不動産契約における重要な書類2つについて、概要を知っておいてください。
不動産賃貸契約における「35条書面」と「37条書面」は、それぞれ異なる役割を持つ重要な書類です。
重要事項説明書(35条書面)
- 役割: 賃貸契約を結ぶ前に、物件や契約に関する重要事項を借主が十分に理解するための書類です。
- 説明者: 宅地建物取引士だけが、借主に対して口頭で説明する義務があります。この説明は、対面だけでなくオンライン(IT重説)でも可能です。
- 交付時期: 説明後、契約が成立する前に借主へ交付されます。
この書類には、物件の権利関係、法令上の制限、設備、家賃、敷金、契約期間、解約条件など、契約内容の根幹に関わる情報が記載されており、トラブル防止の鍵となります。
賃貸借契約書(37条書面)
- 役割: 賃貸契約が正式に成立したことを証明する書類です。
- 説明者: 不動産会社の従業員であれば、宅地建物取引士でなくても説明できます。
- 交付時期: 契約締結後、遅滞なく借主へ交付されます。
重要事項説明書(35条書面)で説明された内容が、書面として契約書にまとめられます。これは、売主と買主、または貸主と借主が互いに合意した内容を証明する法的効力を持つ書類です。
重要事項説明書は、必ず宅建の資格をもった従事者が行うことになっています。まずはこの書類をしっかりと確認しておきましょう。
M&A実務における法務の役割
M&Aは、売り手と買い手の意向をすり合わせ、円滑に取引を成立させるための複雑なプロセスです。その中でも、法務は非常に重要な役割を担います。CROSS M&A(クロスマ)がM&A実務で重視する法務のポイントは以下の通りです。
1. デューデリジェンス(買収監査)
デューデリジェンスは、買い手が対象会社の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。特に法務デューデリジェンスでは、以下の項目を重点的にチェックします。
- 各種契約の精査: 取引先との契約、雇用契約、ライセンス契約など、M&A後の事業継続に影響を与える契約内容を詳細に確認します。契約の自動更新条項や、M&Aを理由とした解約条項がないかを精査します。
- 訴訟・紛争リスクの特定: 現在係争中の訴訟や、将来的に訴訟に発展する可能性のある紛争がないかを調査します。
- 知的財産権の確認: 対象会社が保有する特許、商標、著作権などの知的財産権が正当に保護されているかを確認します。
2. 譲渡契約書の作成
デューデリジェンスで特定されたリスクを踏まえ、売り手と買い手の合意内容を明記した譲渡契約書を作成します。契約書には、以下のような項目を盛り込みます。
- 譲渡対象の明確化: 株式譲渡の場合は株式数、事業譲渡の場合は譲渡する資産や負債のリストを明確に記載します。
- 表明保証: 売り手が対象会社の財務状況や法務状況について、正確であることを買い手に保証する条項です。
- 補償条項: 将来的に表明保証に違反があった場合に、売り手が買い手に対して損害を補償する責任を定めます。
3. 会社法上の手続き
株式譲渡と事業譲渡では、それぞれ会社法上の手続きが異なります。
- 株式譲渡: 株主総会や取締役会の決議が必要となる場合があります。特に、非公開会社では株主名簿の書き換えや、株券不発行会社における株主通知など、細かな手続きが必要です。
- 事業譲渡: 原則として、株主総会の特別決議が必要です。また、事業譲渡に反対する株主がいる場合は、会社に対して株式買取請求権を行使される可能性があります。
まとめ
株式譲渡と事業譲渡は、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが優れているということではありません。会社の経営状況、売却目的、そして買い手の意向によって最適なスキームは異なります。
CROSS M&A(クロスマ)は、これらの複雑な要素を総合的に判断し、クライアントにとって最もメリットのあるM&Aスキームを提案します。法務、税務、会計の専門家と連携することで、お客様が安心してM&Aを進められるようサポートします。M&Aは、会社の未来を左右する重要な決断です。専門家の助言を仰ぎ、慎重にプロセスを進めることが成功への鍵となります。
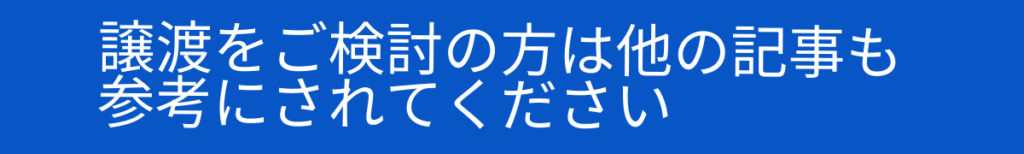
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
差し迫る「教育モデル改革」が学習塾譲渡の価値を劇的に高める理由

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡