差し迫る「教育モデル改革」が学習塾譲渡の価値を劇的に高める理由
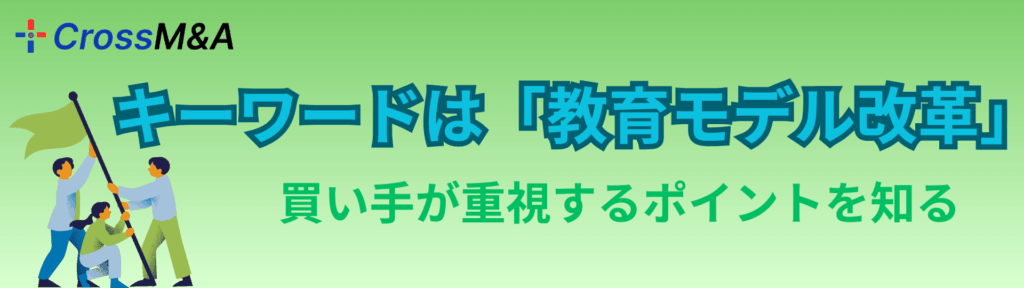
はじめに:なぜ今、学習塾の譲渡市場が活発なのか?
少子化による生徒数の減少、異業種からの学習サービス参入、そして何より教育モデルそのものの変革期。これらの要因が複雑に絡み合い、学習塾業界は大きな転換点を迎えています。
売り手市場?買い手市場?
※M&Aの買い手市場とは?=M&Aを検討している買い手企業の数よりも、売り手企業の数の方が多い状態を指します。簡単にいえば、買い手が有利な市場です。
※M&Aの売り手市場とは?=M&Aを検討している売り手企業の数よりも、買い手企業の数の方が多い状態を指します。簡単にいえば、売り手が有利な市場です。
経営者の中には、事業の継続に限界を感じ、譲渡を検討し始める方も増えているでしょう。実際に、学習塾のM&A市場では、「譲渡」を検討する経営者の検索数が「買収」を検討する企業を大きく上回る傾向にあります。これは、売り手側が圧倒的に多い、いわゆる「買い手市場」であることを示唆しています。
もしかすると、譲渡や買収を検討されている方が、学習塾や習いごと以外の内容からたまたまこちらの記事をご覧頂いた場合、「買い手市場」であるという上記に違和感を感じられたかもしれません。
そして実際に学習塾・習いごとの譲渡、買収経験がおありの方でしたら、仲介を依頼して対応された方が大半だと思いますが、実際に担当の方は、「買い手のほうが圧倒的に多い」という説明をされたのではないでしょうか。
なぜなら、「M&A全体」として見た場合、つまり・・学習塾や習いごと教室「以外」を全部包括的に見た場合は、確かに「売り手市場」だからです。さらに、学習塾、習いごと教室の譲渡案件を出すとそれなり買い手からの問合せがあるため、実態の数字の把握などする必要がないからです。
しかしながら、
特に学習塾の場合には、「譲渡」が「買収」の5倍検索されているのは紛れもない事実です。例えば「学習塾 譲渡」とか「塾 売却」を潜在的に検討されている方が多くなっているということを意味しているのです。
ここまでの内容は、本当に重要な点を指摘していますので、譲渡をご検討の方は是非最初にインプットしておいてください。
譲渡希望価格の強気設定
しかし、そうした厳しい市場環境の中にあっても、譲渡希望価格を強気に設定し、実際に高値で売却を成功させている事例が存在します。こうした成功事例には、単なる売上高や利益といった定量的な指標だけでなく、買い手の心を掴む「ある共通点」があります。
本記事では、この共通点を深掘りし、差し迫る「教育モデル改革」を味方につけることで、自塾の譲渡価値を劇的に高める具体的な方法を解説します。
成功事例に共通する譲渡価値を高める4つの要素
譲渡価格は、もちろん売上や利益といった財務諸表の数字がベースになります。しかし、それ以上に買い手が重視しているのは、「将来的な成長性」です。
この成長性を裏付ける要素こそ、高値譲渡を実現する鍵となります。
成功事例の分析から見えてきた、特に買い手が評価する4つの要素を見ていきましょう。
- 商品力に優れている:画一的ではない「独自性」の追求
多くの学習塾が提供するサービスは、集団指導か個別指導に大別され、カリキュラムや指導内容に大きな差がないのが現状です。しかし、高値譲渡を実現している塾には、独自の指導メソッドや、特定の層に特化したユニークなカリキュラムといった「商品力」があります。
例えば、「思考力を鍛えることを目的とした探究型学習プログラム」や「オンラインを活用した個別最適化された学習システム」など、他塾では真似できない強みを持つ塾は、買い手にとって非常に魅力的です。なぜなら、このような独自のプログラムは、新しい顧客層を開拓する可能性を秘めているからです。
単に「成績を上げる」だけでなく、子どもたちの好奇心や自発性を引き出すような、これからの時代に求められる教育モデルを商品として確立しているかどうか。これが、買い手側の評価を大きく左右するポイントとなります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
この「新しい顧客層の開拓」というのは、今までのヒヤリング経験からすると、買い手側の発想がとてもユニークで多岐に渡っているように感じます。
とりわけ今は、異業種からの参入希望が増加しているのは、外部から見た感想が以下のようなものが多いからです。
・学習塾は色々な面で遅れている
・学習塾運営で、もっとこうすればいいのに
・習いごと教室の管理が昔じみている
・教育業界全体の変化をリードする仕組みがあまりない
要するに、「自分ならこうする」という想定をしながら買収案件を模索しているのです。譲渡側は、今の仕組み、今の料金体系、今のシステム、今の運営の在り方がベストだと思い込んでいます。特に教育関連従事者は、自分のポリシーを強く持っています。
良く言えば強い信念を持っていると言えますが、悪く言えば時代の変化に若干取り残されているフシもあるのです。
ターゲット層においても
「このAという塾は、中学生をメインとした学習塾で個別指導を営んでいます」という概要を説明した際に、
「私立高校の無償化が始まる点と、中学受験が安定して人気が出ているため、私たちが買収さいた歳には、そのようなプランも組み込んでいきたいのです」
このように、すでに具体的な運営改造プランみたいなものを描いている方もいらっしゃいます。
- 商圏的に優れている:単なる「立地」ではない「潜在性」
良い立地とは、単に駅に近い、人通りが多いといった地理的な条件だけを指すわけではありません。買い手が着目するのは、その商圏が持つ「潜在的な成長性」です。
具体的には、以下の点が評価対象となります。
- 競合との差別化: 競合塾がひしめくレッドオーシャンではなく、特定のニーズを持つ層が手薄なニッチな商圏である。
- 地域の特性: 新しいファミリー層が増加している新興住宅地や、教育意識の高い家庭が多いエリアである。
- 地域コミュニティとの連携: 学校や地域団体と連携し、独自のイベントやワークショップを開催している。
単なる「良い場所」ではなく、その地域に深く根差し、独自のポジションを築いている塾は、既存の生徒数に加えて、将来的な生徒獲得のポテンシャルを高く評価されます。
この項目における潜在的成長性は、次の問合せ件数に関してのことにもつながります。
- 問い合わせ件数が多い:生徒獲得の「持続可能性」
生徒数が多いことはもちろん重要ですが、それ以上に買い手が重視するのは、その「生徒獲得モデルの健全性」です。
問い合わせ件数が多いということは、特定の時期に一斉に生徒を集めるのではなく、年間を通じて安定的に新規の入塾希望者や問い合わせが来ていることを意味します。これは、塾のブランド力やサービス内容が地域に浸透し、継続的な集客活動が機能している証拠です。
問い合わせ件数が多い塾は、広告費に過度に依存せず、口コミや地域での評判によって安定的に集客ができる仕組みを持っています。これは、譲渡後の経営におけるコスト削減と収益の安定性につながるため、買い手にとって非常に高い評価ポイントとなります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
ある譲渡、買収案件で、買収側の担当者が以下のように伝えてこられたことがあります。
「収支的に利益が出ていなくてもいいです。それよりも現在の生徒数と、お問合せがどういう経路で来るのかという点、またその実数を小中高別に知りたいです」
このことが、とどのつまり、生徒獲得の持続可能性の部分です。詳細を伺うと、この担当者はすでに学習塾を都内で運営しているため、教室の開校ペースを上げていきたい意向でした。
その際に、生徒数と問合せ数への拘りが一番と捉えていたのを覚えています。
また、
「多少赤字であったとしても、それなりに問合せがあればすぐに回復させることができますので、かえってそのほうがいいのです」という内容も伝えたこられました。
なるほど、この方は学習塾の運営の仕組みをよく知っている人だと思いました。
細かい点までここには書けませんが、実際その通りです。
問合せが多いということは、可能性が非常に高いということの裏返しで、その部分だけをとってみても運営手法を工夫することで急激に業績を回復させることが可能なのです。
- 教育モデル改革に向けた仕組みが整っている
これが、まさに今の時代において最も重要なポイントです。
教育の現場は、従来の詰め込み型、画一的な指導から、「個性を伸ばす」「自ら学ぶ力を育む」といった新しい教育モデルへと大きくシフトしています。
この変化に対応できる仕組みを、すでに構築しているかどうかが、譲渡価値を劇的に高める要素となります。
具体的には、以下の点が挙げられます。
- 個別最適化された学習システム: 生徒一人ひとりの理解度や進度に合わせてカリキュラムをカスタマイズできる仕組み。
- デジタルツールの活用: AIを活用した学習支援ツールやオンラインプラットフォームを導入し、学習効率を高めている。
- 教員の育成モデル: 教員が単なる「知識の伝達者」ではなく、「学習の伴走者」として機能するための研修や育成システムが確立されている。
新しい教育モデルへの対応は、一朝一夕でできるものではありません。しかし、すでにそのための土台や仕組みが整っている塾は、買い手にとって非常に大きなメリットとなります。なぜなら、買い手は譲渡後、すぐに新しい教育モデルの導入や展開に着手でき、市場での競争優位性を一気に高められるからです。
差し迫る教育モデル改革を味方につけるための具体的な行動
それでは、これらの要素を強化するために、日々の経営でどのような点に注力すべきでしょうか。
1. 独自の指導メソッドを言語化し、「商品」として確立する
あなたの塾が強みとしている指導法や考え方を、誰にでもわかるように言語化しましょう。例えば、「なぜこの教材を使うのか」「どのように生徒の意欲を引き出すのか」といった哲学を明確にすることで、他塾との差別化要因となります。これを譲渡交渉の際に提示することで、買い手はあなたの塾が持つ「商品力」を具体的にイメージできます。
2. 地域における存在感を高める活動を始める
地域のお祭りやイベントに積極的に参加したり、保護者向けの教育セミナーを開催したりすることで、塾の存在感を高めましょう。単なる学習塾としてではなく、地域の教育ハブとしての役割を担うことで、口コミや評判が集客の原動力となり、問い合わせ数の増加につながります。
3. デジタルツールを積極的に活用し、「新しい教育モデル」の基盤を作る
いきなり大規模なシステムを導入しようとすれば、構築とランニングで多くの費用が発生します。もちろん、買収側が、そのような仕組み、システム、スキルを持っているのであれば買収後に融合させていくことが出来れば非常に大きな武器になることでしょう。
しかしながら、アイディアはあるが、実際的にその構築には至っていない段階でしたら、既存のシステムが利用できるかどうか、または既にシステムを持った会社の仕組みを月額利用で利用できるものはないか、と言った模索が出来ます。
幸いなことに教育業界のサードパーティーとでも言いましょうか、そういうツール系統をサービス提供している会社はとても多くあります。
また、教材会社複数社との付き合いが開始されれば、自然とご案内が入ります。
個人的にオススメの方法は、
・授業を価値化するための手法
・授業1コマから得られる収入と支出バランスを今より有利にする方法
・生徒一人一人をもっと意識した手法
です。
新しい教育モデルは、発展的要素も含めればもっと自由な発想で取りくんでもよい課題ではないかと思います。今は、「そんなものは・・・」と即却下したくなるようなアイディアであっても、もしかしたらそれは宝の宝庫になるかもしれません。
おわりに:譲渡は「事業の終わり」ではなく「新しい始まり」
学習塾の譲渡は、これまで築き上げてきた教育モデルやノウハウを、次の世代へと引き継ぎ、さらに発展させるための「新しい始まり」なのだと思えばいいでしょう。
50年前の人たちの中で、誰が掌サイズのPCをだれもが持つ世の中になると思ったことでしょう。
これからの時代は、予想外のことだらけになって参りますので、新しい感性を持った若者たちにいい形でバトンを渡すという意味合いでも譲渡について、前向きな発想をもってみましょう。
買い手市場と言われる今だからこそ、自塾の強みを正しく見極め、教育モデル改革という大きな波を乗りこなせる「未来へのポテンシャル」をアピールすることが重要です。
本記事で解説した4つの要素を強化することで、あなたの塾は買い手にとって単なる「生徒が集まっている場所」ではなく、「将来の成長を約束する貴重な資産」へと価値を高めることができるでしょう。
または、今からオーナー自らが着手せずとも、新しい買い手に「こうするときっと良くなる!」という提案事項も譲渡時に用意する概要書の中に入れておくと、買い手の温度感も相当上昇するのではないでしょうか。
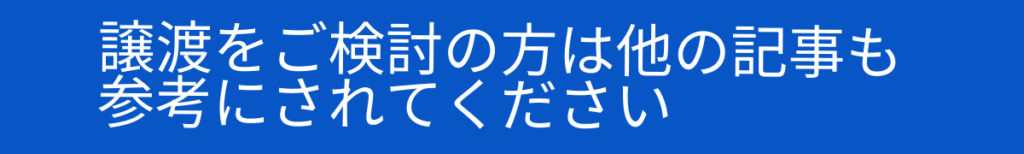
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡