初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(テキスト編)
初めての経営、特に初めて学習塾運営に挑戦される方にとっては、色々なことが新鮮であるとともに、色々なことが進行する度に緊張する場面もあるでしょう。
しかしそれは、新しいことへの挑戦の道中においては、誰もが通る道ですし習得するのに一か月も二か月もかかるような難易度高いものはありません。
やっていくうちに経験を積んで覚えていくものもありますので、プロになりきろうと背伸びする必要もないと思います。
今回は「~テキスト編~」と題してお送りいたします。
-1024x538.png)
教室運営では、「商品」として何かを販売する事業ではなく、サービスとして授業を提供して対価を頂く事業です。
しかしながら、教室という一つの箱物を任されている教室長や、そこで従事する講師たち、そこで提供するサービスのすべてが「商品なのだ」という認識を持つようにしましょう。
そうすれば、色々な気づきが加速度的に見つかることでしょう。
「教材・テキスト」は教室の「商品」そのものであり、成功を左右する最重要要素の一つです。内容の質はもちろん、使いやすさ、そして法的な側面まで、多角的な視点から注意点を解説します。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
さて、今回は最初から実例(実話)コーナーが登場しました。なぜなら、「テキスト?そんなに重要?」と思ってしまう方もいらっしゃるからです。
塾運営の大事な要素として挙げる際に、やっぱり最初に来るものは、立地や、講師、わかりやすい授業、内部の整理整頓などが最初の頃に出てくると思うのです。
ですが敢えて「テキスト」にしました。
では実例をご覧ください。
これは一度や二度の実例ではなく、「たいていはそうなるよ」という類のものです。
新規入塾の際や、季節講習の前には「面談」を実施します。話をしていればよくわかるのですが、保護者の方が前のめりになって話を聞いてくれるポイントが何点かあるのです。その中の一つは、間違いなくテキストです。
その際、
①教科書準拠型のテキスト
②入試まで活用できるテキスト
として、大きく2種類のテキストをご紹介します。どちらもグイッと身体を前に持ってきてみてくれます。
「テキストの話なんて、さして重要ではないだろう」
そう思った教室長の人は、一度試してみてください。テキストに関しての話だけでも30分は話が続きます。
1. 教室の「看板」となるテキストの設計・構成
テキストは、受講生が最も長い時間を共にし、教室の提供価値を実感する媒体です。単なる情報の羅列ではなく、学習効果を最大化するための戦略的な設計が求められます。
1-1. コンセプトと目標の明確化
テキスト作成の第一歩は、「誰に、何を、どのように提供し、どうなってほしいか」を明確にすることです。
- ターゲット設定(誰に): 対象の年齢層、既存の知識レベル、学習目的を具体的に設定します。「初心者向け」「経験者向け」「資格取得向け」など、受講生のプロファイルに合わせた内容とトーンを選びます。
- 達成目標(何を): そのテキストを終えた受講生が、具体的に「何ができるようになるか」を明確にします。抽象的な「理解」ではなく、「〇〇のスキルを使って△△を完成できる」といった具体的な行動目標を設定しましょう。
- 差別化要因(なぜ): 競合のテキストや市販教材にはない、あなたの教室ならではの強みや視点(ノウハウ、独自の事例、地域特化情報など)を盛り込み、付加価値を高めます。
1-2. 学習効果を高める構成と分量
テキストは「読み切れるか」「理解できるか」が鍵です。
- 段階的・体系的な構成: 受講生の理解を助けるため、必ず「基礎」から「応用」へと段階的に難易度を上げていく流れにします。
- 導入: 目的、メリット、全体の流れを示す(モチベーション向上)。
- 本編: 小項目に分け、一つのテーマが長くなりすぎないよう区切る(集中力維持)。
- 演習/アウトプット: 学んだことを試す実践的な課題を配置する(定着促進)。
- まとめ: 各章の重要ポイントを簡潔に再提示する(復習サポート)。
- 「インプット」と「アウトプット」のセット: 知識をインプットする解説ページと、それを実際に試す問題やワークシートなどのアウトプット用教材をセットで作成し、学習のサイクルを回せるようにすることが重要です。
- 1セッションの分量を意識する: 受講生が一度の学習で無理なく終えられる分量(例:1セッションあたり15分~30分程度で完結するボリューム)を目安に、細かく区切って作成すると、モチベーションが維持されやすくなります。
2. 読みやすさとデザインから「読みやすい」テキストを選定
内容が素晴らしくても、読みにくいテキストは学習意欲を削ぎます。プロフェッショナルな品質を追求しましょう。
2-1. レイアウトと視覚的な工夫
「見やすさ=理解のしやすさ」です。
- フォントの統一とメリハリ:
- フォント種類: 見出しと本文で種類が統一され、紙面全体に一貫性があるものはいいです。明朝体は書籍向き、ゴシック体は見出しやデジタル表示向きなど、特性を理解して選びましょう。
- 文字の大きさ: 文字は適度な大きさであることが重要です。特に小学生を対象とする場合は、より大きなフォントサイズを意識します。
- 装飾: 太字(ボールド)、色文字、下線などの強調は、重要ポイントに絞って使用され、あまりごちゃごちゃしていないほうが使いやすいです。
- 余白と行間の確保: 情報を詰め込みすぎると圧迫感が出て読みにくくなります。適切な余白(マージン)と行間が設定されていることで、視線移動がスムーズになり、理解度が高まります。
- 図表・画像・イラストの積極活用: 文章だけでは伝わりにくい概念や手順は、積極的に図表や画像で視覚化されていることが肝要です。文章の理解よりも、図の理解の方が直感的で早いため、説明を補強する意味でも図や表、グラフが適度に入っているテキストがわかりやすいです。
2-2. 表現と言葉遣いの注意
テキストの誤字脱字、表現のブレは信頼性の低下に直結します。
- 初版、第二版あたりは注意: 誤字脱字はもちろん、事実誤認、専門用語の統一、句読点の打ち方まで、テキストは第三者によるチェックを含めて複数回の校正・校閲が徹底されているのが普通です。
しかしながら、版が最初の方のテキストでは、ミスが多くありますので、注意しましょう。
よくあるのが、学習指導要領が改訂された後の「新テキスト」はミスが多いです。
生徒が間違った知識を得てしまう、誤字脱字や誤答内容を再度プリントで渡さなくてはならない、そのような問題が多く出てきますので、注意してください。 - 平易で正確な表現: 専門用語を使用する場合は、必ずその場で定義を説明するか、初心者にも分かりやすい平易な言葉に置き換えることを心がけます。そのため、そのような指導がしやすいような構成で作成されていることが望ましいです。
- 一貫したトーンと視点: テキスト全体を通じて、語調(「です・ます」調、「だ・である」調など)や、受講生への呼びかけ(「皆さん」「〜さん」「あなた」など)も統一されていることで、安心感と信頼感が維持されます。
3. 教室運営に不可欠な「ビジネス・法的」な注意点
教材は、作成・配布・販売において、経営と法律の観点から細心の注意を払う必要があります。
3-1. 著作権・知的所有権の遵守とリスク管理
営利目的である教室のテキスト作成においては、著作権の侵害リスクが最も注意すべき点です。
- 他者の著作物の利用は原則許諾が必要:
- 市販の書籍・問題集: 塾や予備校などの営利目的の教育機関では、学校法人と異なり、教科書や問題集を無断でコピー・スキャン・配布することは、著作権法上の「複製権の侵害」にあたります。
- インターネット上の画像・記事: フリー素材であっても利用規約を必ず確認し、出所の明記や商用利用の可否を遵守します。無断使用は厳禁です。
- 引用のルール: 他者の著作物を引用する場合でも、「引用部分が従、自作部分が主」「引用の必然性がある」「出所を明記する」など、厳格なルールを守る必要があります。
- 自作テキストの権利保護:
- 作成したテキストには著作権が発生します。受講生による無断複製や転載を防ぐため、テキストの奥付や注意書きに「無断複製・転載を禁じます」などの注意書きを明記します。
- 教室のノウハウを保護するため、営業秘密として管理することも検討しましょう。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
このテキストのコピーは、やってしまいがちです。
しかし、このことは塾経営においては、メリットにもなります。
それは・・・
①保護者からコピーを頼まれた場合
コピーをすることは、日常的行為ですので、保護者にも全く悪気はないと思いますが、何でもかんでもコピーしてほしいと依頼されるケースがあります。
問題を作ってほしいとか、〇〇問題集のコピーをしてほしい、などです。
②生徒からコピーを頼まれた場合
同様に生徒も多くあります。
たいていそれは受験生であることが多いです。塾での滞在時間が長くなることから、教室内部の仕組みがわかってくると、あれこれといじり出す生徒もいます。パソコンであったり、複合機であったりです。
そしてきっと、
「先生、これコピーしてください」
と言ってくるでしょう。
このシーンでは、断ったほうがいいです。
何故なら、1名の生徒に許したら、2人目、3人目と必ず同様の依頼が出てきます。
その際の、断る理由としては上記の通りです。
教科書や問題集を無断でコピー・スキャン・配布することは、著作権法上の「複製権の侵害」にあたります。
↑ これです。
「太郎君、ごめん、これをコピーすると複製権の侵害になるから出来ないんだ。テキストなんだけどさ、お母さんに勝ってもらって」
これが伝家の宝刀です。
以前、とある学習塾に見学に行ったときに、オーナー兼教室長の方が、新参者だった私にこう言いました。
「うちはコピー料金が1円なので、生徒には自由に何でもコピーしていいよってやってるんですよ。だいたい印刷代金で、月6万円ぐらいですかね・・・」
と言っていた方がいました。
ネットで見ると、自分の全体写真を載せて、時代の先端を言ってるかのような誤認せしめる内容でした。
こ、この方、堂々と違法コピーバンバンやってますって公言してるけれど大丈夫なのだろうか・・という心配と、月6万円の印刷費用?それって何の自慢にもならないのに、え?
そんな印象を持ちました。
印刷費用はリースなら、その200分の1の費用、買取りの複合機であれば、その10分の1の費用で足りるはずのところをそこまでかけるということは、私からみたら無駄なコストを垂れ流しているようなものにしか見えませんでした。
まぁ、これもやってはいけない!と言いつつ、たぶん日本全国、コンビニの数より多い学習塾の全てがコピーしていますから何とも言えない部分ではありますが・・・。
でも自由に生徒に複合機を使わせて、そのコストを塾が面倒みるというスタイルがすごいですね。
しかし、どう考えても1教室で年間60万円ぐらいの無駄で、10年間で600万の無駄だと思います。
余裕でベンツが買えます。
ちなみに、国内の有名な予備校も見学に行ったことがありますが、そこでは、生徒のコピーは1枚10円だか、5円だったか忘れたのですが、有料でした。
それが普通だろうなぁと思った次第です。
以前、あの分厚い赤本(確か、そのときは東洋大学の過去問)を全ページ印刷してほしいと言ってきた生徒がいましたので、
「キミ・・常識で考えなさい。その分厚い赤本を全頁コピーということは、その分のコストがかかり尚且つ、その時間を大量に消費しなくてはならない。我々にとっては時間もコストだから、とんでもない膨大な無駄遣いだよ。だったらAmazonでもう一冊買ったらよかろう?」
と伝えました。
基本、生徒の複合機利用は禁止すべきだと思います。
そのことを「あなたの塾はケチですね」と言わせないために、上記の法律をしっかりと伝えることが出来れば大丈夫です。
3-2. 自社作成テキストの価格設定と配布方法の戦略
自社で作成するテキストは収益源にもなり得る「商品」です。
- 原価計算と価格設定: 印刷費、デザイン費、作成にかかった時間(人件費換算)などの原価を正確に把握し、教室の提供価値に見合った価格を設定します。テキスト代を受講料に含めるか、別途徴収するかによっても受講生の心理的負担が変わるため、慎重に検討します。
- 配布方法と更新体制:
- デジタル vs 紙: 紙のテキストは学習に集中しやすいメリットがありますが、更新が難しく費用もかさみます。PDFなどのデジタル教材は更新が容易ですが、無断配布リスクがあります。教室の特性に応じて最適な形式を選びます。
- 更新サイクルの設定: 情報の鮮度を保ち、常に最新の情報を提供できるように、定期的なテキストの改訂・更新スケジュールを組み込みます。
3-3. 改善のためのフィードバック収集
テキストは「完成したら終わり」ではありません。
- 受講生のフィードバック: 実際にテキストを使用した受講生から、「分かりにくい点」「もっと詳しく知りたい点」「誤植」など、率直な意見を積極的に集めます。アンケートや個別ヒアリングを活用しましょう。
- 講師(あなた自身)の振り返り: 実際に授業で使用してみて、「説明に時間がかかりすぎた箇所」「テキストとの連動がうまくいかなかった箇所」などを記録し、次回の改訂に活かします。
最後の項目では、テキストの自社出版的な内容にも及びましたが、学習塾の中には自社で作成したテキストを持っているところが多いです。
何となくイメージとして自社で作成したものより、市販されているものや、教材会社が取り扱っているもののほうが信ぴょう性が高い感じにとらわれそうになりますが、
自社で作成したものが今までの過去の経験則などを踏襲した形で新傾向をしっかりと盛り込んだものとしてつくられたならば、内容次第では使えるテキストとして自分の中でインプットされます。
テキストは、複数種類を見比べてみましょう。
4. まとめ:テキストが語る教室運営の方向性
初めての経営でテキストを作成することは、非常に労力のいる作業です。しかし、このテキストは、あなたの教室の「教育理念」「専門性」「受講生への真剣さ」を無言で伝える最良のツールとなります。
単に情報をまとめるだけでなく、受講生の「成功体験」に直結するものとして、徹底的にこだわり抜いてください。初めは完璧でなくても構いません。上記のような注意点を意識し、作成・運用・改善のサイクルを回し続けることが、教室運営を成功へと導く礎となるでしょう。
4. おまけ:オススメの教材販売会社
ズバリ
中央教育研究所
育伸社
この2社です。
詳細の理由も全部書きたいところですが、他社さんに相当不利になるから書かないほうがいいでしょう。
この2社を選んでおけば大丈夫です。
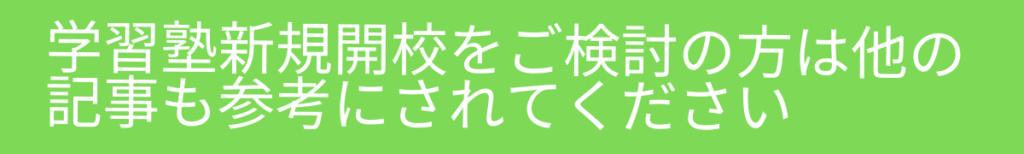
立地選定について
最適な物件選びの秘訣とは?
内外装計画と工事について
統一感のある什器・備品
教室長一日密着レポート徹底解説
失敗しない採用のための求人
見落としがちな掲示物の重要性!
開校時に用意しておく事務用品
商圏分析とネットリサーチ徹底攻略
塾講師採用 効果的な募集から採用
学習塾は単月赤字でも経営できる!
話し上手より「聞き上手」
テキスト選定と教材会社の選び方
塾の「儲けの仕組み」を徹底解剖!
学習塾選びの鍵!自習室の有無
立地で選ぶ塾の重要性
掲示物、パンフレット、のぼり旗
学習塾・習いごとの看板は集客の要

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備