学習塾サービスの未来予測:2026年からの5年間で激変する教育のカタチ

※この記事の最後のほうに「買収するならこのタイプの学習塾」についての完全回答と、この記事をご覧いただいている方で買収を真剣に考えている方向けの内容も記載ございます。
さて、それでは記事に参ります!
学習塾の運営を始めてみよう!
学習塾起業をご検討中の個人の方、法人の方、異業種からの参入検討の方、学習塾買収を考えている方に是非ご確認いただきい記事です。
よろしくお願いいたします。
世の中のあらゆるサービスが常に進化を続ける中で、学習塾の世界もまた、例外ではありません。かつての学習塾のカタチは、一言で言えば、学校番外編のようでした。
黒板とチョーク(ホワイトボードとマーカー)、そして熱弁奮いながら懸命に生徒たちに教える講師の姿が学習塾そのものの売り看板のような時代です。
時代は流れ、今ではテクノロジーの波に乗り、その姿を大きく変えてきました。本記事では、これまでの学習塾の歴史を簡単に振り返りつつ、今後5年間で何が起こるのか、そしてその変化が学習塾の運営にどのようなメリットをもたらすのかを深く考察していきたいと思います。
まずはじめに、軽く学習塾のサービスの歴史を追ってみましょう。
過去から現在へ:学習塾サービスの変遷
学習塾の歴史を紐解くと、その変化は時代のニーズを色濃く反映していることがわかります。
1. 集団塾の黎明期:教育機会の平等化
日本の高度経済成長期、学習塾は「集団塾」が主流でした。多くの生徒が一つの教室に集まり、一斉に同じ授業を受けるスタイルは、効率的に多くの生徒に教育機会を提供することを可能にしました。
カリスマ講師による熱気あふれる授業は、生徒たちの競争心を煽り、学力向上に直結しました。しかし、一人ひとりの理解度や進度に対応することは難しく、置いていかれる生徒も少なくありませんでした。
2. 個別指導塾の台頭:パーソナライズされた教育へのニーズ
2000年代に入ると、生徒一人ひとりの個性を尊重し、それぞれのペースに合わせた学習を求める声が高まってきました。これにより「個別指導塾」が急速に普及します。
生徒と講師が1対1、あるいは1対2で向き合い、苦手な単元を徹底的に克服したり、得意な科目をさらに伸ばしたりするパーソナライズされた指導は、集団塾では埋められなかったニーズに応えました。多くの集団塾も、個別指導部門を併設するようになったのはこの頃からです。
3. 映像授業の普及:時間と場所の制約からの解放
インターネットの普及により、「映像授業」が登場します。予備校の有名講師の授業を自宅で、好きな時間に繰り返し視聴できるこのサービスは、地方に住む生徒や部活動で忙しい生徒にとって画期的なものでした。質の高い授業を誰でも受けることができるようになった一方で、質問がしにくい、モチベーションを維持するのが難しいといった課題も浮き彫りになりました。
4. タブレット学習の台頭:デジタル化による学習の効率化
2010年代には、タブレット端末を活用した学習サービスが普及し始めます。ドリル学習、動画視聴、テストなど、様々な学習コンテンツをタブレット一台で完結できるようになったのです。自動採点機能や学習履歴の可視化は、生徒の自律的な学習をサポートし、学習塾にとっても、生徒の進捗管理が容易になるというメリットをもたらしました。
5. AIの活用とオンライン指導の深化:次世代の教育へ
そして現在、私たちは「AI」と「オンライン指導」の融合という、新たなフェーズに突入しています。
AIは生徒一人ひとりの学習データを分析し、最適な問題やカリキュラムを提案します。これにより、苦手克服から発展学習まで、その生徒だけにカスタマイズされた学習が可能になりました。また、新型コロナウイルスのパンデミックをきっかけに普及した「オンライン指導」は、地理的な制約を完全に撤廃し、全国の生徒が質の高い指導を受けられるようになりました。
Zoomなどのビデオ通話ツールを用いて、双方向性の高い授業を行う学習塾も増えています。
いかがでしょう。
ザっと駆け足で説明しますと、学習塾はこのような流れを経て参りました。もっとディテールを追っていけば、付加価値的にいろいろなサービスがありますが、大きな流れとしてはこのようなところです。
世の中のサービスは、常に変化、進歩しています。
新しく進化したものがいつか当たり前になり、次の新しいアイディアが具現化していくというのは、どの分野でも起こっています。
私たちは日頃意識しない中で、新サービスに自然に溶け込んでいきます。目新しいサービスに驚きつつも、少し時間がたつと、それがなくてはならない存在になったり、それが普通になったりするのです。
学習塾もきっとそうです。
それでは、また実例で見ていきましょう。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
CROSS M&A(通称:クロスマ)のアドバイザーは、現在も塾を運営しております。思えば大きなパラダイム転換のきっかけとなった出来事は、やはり新型コロナなのです。
あのとき・・・私たちは未曾有の時代だと気づくのにそう時間はかかりませんでした。
新型コロナウィルスに罹患する人たちが大勢いる中で、生徒や保護者、講師、関係者などそれはそれは毎日のように報告がありました。
いったいどうなってしまうのだろう・・・そんな不安がよぎることもありましたが、それでも教育の手を止めずに乗り切ることが出来たのは、
新しいツールがすでに準備されていたということに他なりません。
2019年です。
それまで私は、AIを使った授業形式なんて・・・という否定的な意見を持っていました。ましてやタブレット型で授業を進行して学力が向上するのだろうかという疑念も同時に。
たまたまですが、ためしに使ってみようという機運が高まり、マニュアルを見つつ実験をしてみることになったのです。
実験台はまずは自分でした。自分が実際に仮IDを使ってやってみること。及びほかの教室長にも触れてもらい、教室ごとに実験期間をもったのです。
正直、感動しました。
第一声としては「なんだこれ?すごいな」でした。
自分が作成したIDで、自分の学力診断をし、自分用にカリキュラムが瞬時に自動生成されながら解けば解くほどに自分用になるというコンセプト、、、
私は、単なるタブレット・・・と思い込んでいましたので、衝撃を受けたのです。
(これはいける)というのがそのときの印象です。
そして2020年コロナが蔓延し、2021年には世界のパンデミックは途方もない拡大をしていたのです。本当にたまたま2019年にいろいろ実験をしていた経緯もあって、新型コロナが拡大したときに、すぐにAIを使ったタブレット形式授業を生徒保護者に伝え、
・教室に来れる人は教室で
・来ることが出来ない場合は、自宅で
・休会されたい方は休会で
このような選択式の運営を実施したのです。
当時、ちょうど受験期と重なっていたこともあり、判断に悩みましたが、教室実施か自宅実施の選択制という形で運営を完全に止めることなく継続したのです。
マスク着用、手洗い励行、換気励行で冬でも換気をしながらでしたから、大変でした。
自宅学習を選択された方用には、説明も含めてzoomも同時に接続して、先生は教室から、生徒は自宅でというやり方をしました。
最初はzoomの接続とか、説明のやり方などに苦慮した部分もありましたが、さすが講師たちも慣れたもので、すぐに要領を得て、よどみなく授業を実施することが出来るようになったのです。
また、このzoom接続の際には、ほぼすべてのご家庭で、最初は保護者様と生徒が同時にzoom上に顔と声を出される形でしたので、不思議な感じでした。
でも保護者様も、コロナという大変な事態ではありながらも新形式のzoomを使ってAIを駆使した授業に興味深々で一緒に参加するという形が自然に出来上がったのです。
これはこれで、とてもいい経験になりましたし、保護者様の反応、生徒の反応もとてもいいものでした。
いかがでしょう。
何となく当時の塾内、教室内の様子などがイメージできますでしょうか。
マスクも品薄、ヘッドセットもネットで完売、売っているのは高いヘッドセット・・・マイクもなかなかなくて、手指消毒用の洗浄消毒液も品薄・・・
思い起こせばそんな時代でしたね。
しかし、そのどうしようもない時代の裏側で教育については、一気にそれまでの内容が大きく変化したのです。
この段階でのキーワードは、
「オンライン」
「AI」
だったのではないでしょうか。
2026年からの5年間:学習塾サービスの未来像
では、これらの歴史を踏まえた上で、2026年からの5年間で学習塾はどのような変化を遂げるのでしょうか。ここからのキーワードは
「ハイブリッド化」
「超個別最適化」
「コミュニティ形成」
の3つです。
1. サービス提供形態の「ハイブリッド化」
今後、集団、個別、映像、AI、オンラインといった既存のサービスが、どれか一つに収斂することはなく、それぞれが組み合わさり、より多様な形で提供されるようになるでしょう。
- 集団×個別×AI: 普段は集団授業で主要科目を学び、苦手な単元はAIが生成した個別演習問題で補強する。さらに、定期的に個別面談を実施し、学習進捗やメンタル面をサポートする。
- オンライン×リアル: 普段は自宅でオンライン授業を受け、定期的に塾の教室に集まり、対面での演習やグループディスカッションを行う。これにより、オンライン学習の利便性と、対面ならではのコミュニケーションやモチベーション維持のメリットを両立させる。
このハイブリッド化は、生徒が自分に最適な学習スタイルを柔軟に選択できることを意味し、学習塾側も、より多様な顧客層に対応できるようになります。
2. AIによる「超個別最適化」の加速
AIはもはや、単なる学習ツールではなく、生徒の「第二の先生」となり、学習の超個別最適化をさらに加速させます。
- AIによる学習経路の自動生成: 生徒の学習履歴、回答の癖、理解度をリアルタイムで分析し、次に解くべき問題、見るべき動画、読むべき参考書までを自動で提案します。これにより、生徒は無駄な時間を費やすことなく、最短ルートで学力向上を目指せます。
- AIチューターの誕生: 音声認識や自然言語処理技術の進化により、AIがリアルタイムで生徒の質問に答えたり、つまずいている点を指摘したりするようになります。これにより、生徒はいつでも、どこでも、わからないことをすぐに解決できるようになります。
この「超個別最適化」は、もはや集団塾や従来の個別指導塾では提供できない、唯一無二の価値を生み出すでしょう。
3. 学習の場から「コミュニティ」へ
学習塾は、単に学力を上げるだけの場所ではなく、生徒の居場所、仲間と切磋琢磨するコミュニティへと進化します。
- オンライン・オフラインでのコミュニティ形成: 共通の目標を持つ生徒たちが集まるオンラインサロンのようなコミュニティが形成されます。塾の垣根を越え、全国の仲間とオンラインで交流したり、進路相談をしたりします。また、リアルな教室では、グループワークやイベントを通じて、生徒同士の横のつながりを強化します。
- 保護者向けサービス: 塾が提供するサービスは生徒向けだけではなくなります。保護者向けのセミナーや情報提供、個別相談会を充実させることで、家庭での学習環境作りをサポートします。
このコミュニティ化は、生徒のモチベーション維持に大きく貢献するとともに、学習塾のファンを増やし、継続的な関係性を築く上で不可欠な要素となります。
今最も新しい学習塾サービス:AI×オンライン個別指導
現在、最も先進的な学習塾サービスとして注目されているのは、「AIを活用したオンライン個別指導」でしょう。これは、AIが生徒の学習データを分析し、苦手な単元や学習進度を可視化します。
その上で、オンラインで接続されたプロの講師が、AIの分析結果をもとに、生徒に合わせたきめ細やかな指導を行うというものです。
AIによる客観的なデータと、講師による人間的なサポートが融合することで、これまでにない質の高い学習体験を提供しています。
学習塾運営の変化とメリット
このようなサービスの変化は、学習塾の運営にどのような影響を与えるのでしょうか。
1. 運営効率の向上
AIによる自動採点や学習進捗管理は、これまで講師やスタッフが手作業で行っていた業務を大幅に削減します。これにより、講師は指導そのものに集中できるようになり、一人あたりの指導可能生徒数も増加します。また、オンライン指導の導入は、講師の採用範囲を全国に広げ、優秀な人材を確保しやすくなります。
2. 差別化と付加価値の創出
従来の「対面授業」だけでは、集客競争に勝つことは難しくなっています。AIやオンラインを組み合わせた新しいサービスは、他塾との明確な差別化要因となり、独自のブランドを確立できます。また、超個別最適化された学習プランや、学習コミュニティの提供は、生徒や保護者にとって大きな付加価値となり、顧客満足度を高めます。
3. コストの最適化
オンラインでのサービス提供は、大規模な教室を維持する必要がなくなるため、家賃や光熱費などの固定費を削減できます。また、AIを活用することで、一部の業務を自動化でき、人件費の最適化にもつながります。
4. データの活用による経営判断の高度化
AIが収集する膨大な学習データは、生徒一人ひとりの学習状況を把握するだけでなく、塾全体の学習トレンドや課題を分析する上でも役立ちます。これにより、カリキュラムの改善、マーケティング戦略の立案など、データに基づいた経営判断が可能となり、より効率的で効果的な塾運営が実現します。
買収するなら「このタイプ」の学習塾
自前でAIシステムの構築をすれば、莫大なコストを覚悟しなくてはいけません。
AIシステムの構築コストは、システムの目的や規模、機能によって大きく異なりますが、
小規模でもアベレージで300万円はゆうにかかります。
社内業務向けで500万円から1,500万円、大規模なシステムになりますと、1,500万円から3,000万円以上かかることもあります。
そしてこれらは開発のみの費用で、他にもデータ準備、AIモデル開発、既存システムとの連携、運用・保守など、複数の段階で費用が発生するため、予算計画と相見積もりの取得が重要ですし、自前でつくりあげるということは、よほどお金に余裕があるとか、肝が据わっていないと難しいと思います。
AIシステムの利点は上げればキリがなく、今後の展開を予想したときに、今よりももっともっと高度に発展していくことが明確です。
ですから、このAIを学習塾運営から切り離して考えるのは、少々無理があるように思います。
ずっとアナログでいくことも、それ相当の覚悟が必要になるでしょう。
時代の流れ、潮流、いわゆる新型だけどデフォルト路線になるであろう予想からしてもAIは切り離さないほうが無難だと思います。
そして結論です。
つまりは、AIとオンライン指導が実施できる商品ラインナップを備えた学習塾を買収するのが得策だということです。
現時点、個のサイトの「売り案件」にUPしておりませんが、
本記事をご覧いただいている方には、この記事内でお伝えしておきます。
優良案件がありますので、お問合せください。
まとめ
学習塾サービスは、過去の歴史を積み重ねながら、今、大きな転換期を迎えています。
集団、個別、映像、AI、オンラインといった様々な要素が複雑に絡み合い、それぞれの利点を生かしたハイブリッドなサービスが主流となるでしょう。
その中心にあるのは、AIによる「超個別最適化」と、学習塾が提供する「コミュニティ」としての価値です。
2026年からの5年間で、学習塾は、単に知識を教えるだけの場所から、生徒の学習をあらゆる面からサポートし、自己成長を促すためのパートナーへと進化します。
そして、この変化は、運営者にとって、効率化、差別化、コスト最適化、そして高度な経営判断といった、かつてないメリットをもたらします。
これからの学習塾は、テクノロジーを賢く活用し、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す、新しい教育のカタチを創造していくことでしょう。
そして最後に、
教育が止まることがないように、教育産業はなくなりません。
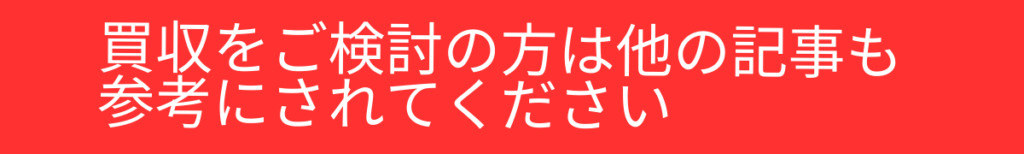
よい物件とのめぐり合い
顧客・従業員(講師)への最初の行動
フランチャイズと独自ブランド
なぜ今、学習塾がおすすめなのか?
見て触れて、深く理解するモデル教室
学習塾・習い事教室の運営は狙い目
学習塾の売上高は月間売上高の16倍
CROSS M&A(クロスM&A)の自信
学習塾とプログラミング教室のM&A
高校生指導ができる学習塾をM&A
60歳からの新しい挑戦!
国立大学最寄り駅の案件は即買い
小学生向け学習塾の料金相場徹底解説
M&A成功のコツ潜在的価値の見極め
【高収益案件を発掘!】小規模学習塾
あなたの既存スキルがM&Aで花開く
千葉県の学習塾買収
習いごとフランチャイズ買収ガイド
個別指導塾M&A成功秘訣と実践ガイド
人が変わると業績が変わる
未経験だからこそ成功率が高い!
簡易株価評価の算定方法(①)
簡易株価評価の算定方法(②)
デューデリジェンス基礎
労務リスクを見抜く専門ガイド
M&Aにおける不動産の基礎知識
保護者との信頼を築く授業報告
学習塾の新しい形:異業種参入歓迎
株式譲渡と事業譲渡、見極めポイント
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年02月03日
学習塾業界は変化を求めている:すべての受検で「安全志向」の時代へ突入!塾運営はこうなっていく!!
#バリューアップ
#リスク回避
#保護者ニーズ
#個別最適化
#塾M&A
#大学入試改革
#安全志向
#年内入試
#進路指導

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収