厳しい現実から目を背けない:塾・習いごと経営者が知るべき「撤退または譲渡」のタイミング
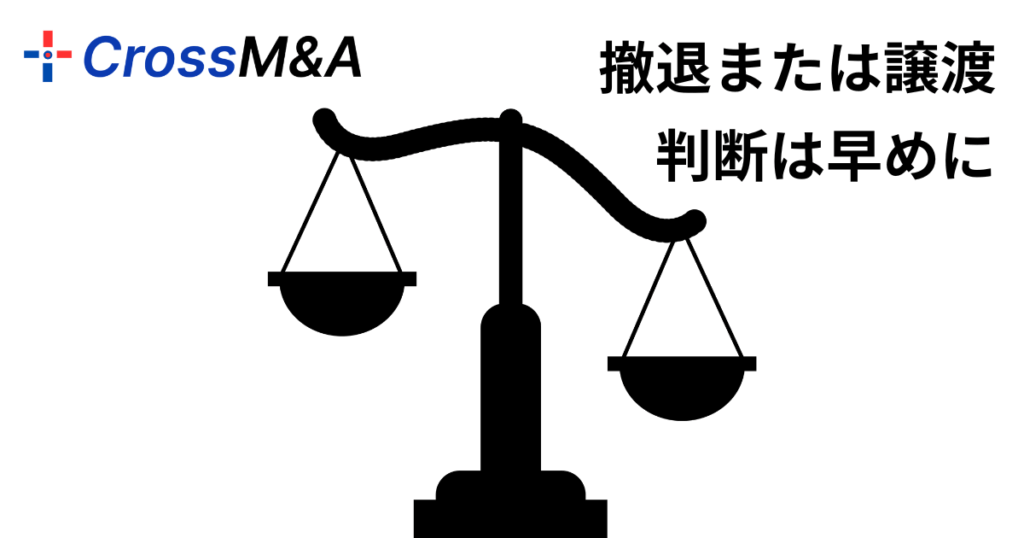
長年情熱を注いできた塾や習いごと経営。
「厳しい」と感じながらも、その場所を守り続けようと奮闘している方も多いでしょう。
しかし、ビジネスの世界は残酷なまでに自己責任です。誰かが優しく手を差し伸べてくれる奇跡は、残念ながら起こりません。負のスパイラルに陥り、心身ともに疲弊し尽くす前に、経営者自身が冷静かつ迅速に「撤退」または「譲渡」の決断を下す勇気を持つべきです。
経営が厳しくなる「兆候」を見逃すな
経営の悪化は、ある日突然訪れるわけではありません。
必ず、その前触れとなる「兆候」が現れます。重要なのは、これらのサインを「一時的なもの」「何とかなる」と軽視せず、客観的な事実として受け止めることです。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
最初に実例(実話)をご確認ください。
とても重要なことを書きましたので、読み飛ばしをせず是非、言葉の意味をグッと捉えながら読んでほしいです。
学習塾の場合、例えば法人で運営していても、個人事業主として運営していても、日本の学校は年度のスタートを4月にしているため、決算時期にかかわらず「4月スタート」から3月末までの一年をとらえます。
厳しくなる兆候は、その年ではなく前年度にすでにあらわれます。
一番わかりやすいのは、
夏(8月)が終わった後の9月から12月にかけて、受験生以外の生徒が何人導入されて、新年度の受験生が何人になりそうか・・・の読みです。
9月以降、例えば大学受験の高校3年生が入塾しても在籍は4~5か月です。
9月以降、例えば高校受験の中学3年生が入塾しても在籍は半年でしょう。
9月以降、例えば中学受験の小学6年生が入塾しても在籍は3~4か月です。
これらの生徒はカウントしません。
上記しましたように、新年度を迎えたときの「受験生」が何人9月~12月に導入されたかをカウントします。
1月、2月、3月はカウントしないのか?という疑問があるかと思います。
今回のテーマは、撤退するか、廃業するか、譲渡するかの判断をするための考え方ですので、遅くとも年内判断、年内決断をしていくほうが良いです。
12月で判断して、新年度を迎える前に撤退、廃業、譲渡のいずれが完成している状態にもっていくようにしましょう。
例えば・・・
気持ちの整理がつかない状態が長引いたり、2月、3月にまた生徒が入るかもしれないという期待感がが出たとします。
しかし、忘れてはいけないのは、1月、2月、3月は退塾が増加する季節でもあるのです。
結果、行って来いぐらいの生徒数であったり、さらに減少した「その結果」を見てからの撤退、廃業、譲渡の判断は、コスト的に考えてみても相当無駄なコストが発生してしまう可能性があるのです。
1. 心のゆとりがなくなる
最も危険な兆候の一つは、経営者自身の「心のゆとり」の喪失です。
- 授業や指導準備以外の雑務に追われ、生徒一人ひとりの変化に気づけなくなる。
- 保護者からの相談やクレームに対し、冷静に対応できず、イライラが募る。
- 新しい教育トレンドや指導法の研究、生徒募集のための企画を考える余裕が一切なくなる。
- 生徒指導における講師との打ち合わせ回数も減少する。
常に「しなければならないこと」に追い立てられ、経営の根幹である「教育」への情熱や喜びが薄れていくのを感じたら、それは黄色信号です。
リーダーの熱度の高さは、スタッフも講師も保護者も生徒も、ステークホルダーと言える業者もFC塾であれば、本部の人間も全員がわかります。
「心」は自然と表に出てしまうものなのです。
2. 現場の雰囲気に現れる「疲弊」
経営の厳しさは、現場の空気にもはっきりと現れます。
- 講師との前向きなディスカッションもなくなる: 以前は活発だったカリキュラムや指導法に関する意見交換がなくなり、業務連絡のみで終わるようになる。講師の疲労が蓄積し、新しい提案をする意欲が失われている証拠です。
- 生徒との談笑もなくなる: 教室がギスギスし、生徒たちが指導時間外に指導者と気軽に話したり、冗談を言い合ったりする姿が減ります。指導者が精神的に追い詰められ、笑顔や心の余裕を失っているため、生徒も萎縮してしまうのです。
この状況は、指導の質が落ち、ひいては生徒の満足度や成績にも悪影響を及ぼし、さらなる退塾へと繋がります。
3. 日常生活に侵食する「経営の重荷」
最も身近で、最も深刻な兆候は、経営者の心身の状態です。
- 業務が終わった後にため息が漏れる: 教室の戸締まりをした後、思わず深いため息をつく。それは、その日一日を乗り切った安堵ではなく、「明日もこの苦しさが続く」という絶望感の表れです。
- はつらつと次の朝を迎えることができない: 朝目覚めて、仕事に行くことに喜びや期待を感じられず、むしろ憂鬱さや重い義務感に苛まれる。睡眠の質も低下し、疲労が抜けないまま次の日を迎えるという悪循環に陥ります。
これらは、精神的な限界が近いことを示しています。教育事業は、経営者の「心のエネルギー」が非常に重要な要素です。
その源が枯渇し始めているなら、事業継続は極めて困難だと言わざるを得ません。
情熱が保てないことが、多分一番苦しいのでは・・・
塾を開講したときの「あのときの情熱」と今を比較すると、間違いなく大きな変化があるのではないでしょうか。
これはある意味、仕方のないことです。
順風満帆であれば、何も苦労もないですし、毎日が意気揚々と過ごせます。
しかしながら、周りの環境、制度、その他非常に多くの要素が絡んだ経営の世界では、何かが起こり、何かが消えていくというのは、日常茶飯事です。
例えば、小さいころに〇〇県〇〇市に住んでいたとします。
大人になって仕事の関係などで他県に引っ越しをして、10年、20年、30年と経ったならば、小さいころに育った〇〇県〇〇市は、大きく様相を変えていることでしょう。
時代の移り変わりとともに、どんどん変わっていく、それが普通です。
現状、そして今までオーナーは相当頑張ってこられたわけですから、あまり自分を責めないでいいです。
あまりにも純粋に、あまりにも真摯に、あまりにも責任重大に考えるようになると、自分を責めすぎてしまいます。
事業をすること、経営をすることは、流れがあります。決心して決断する場面が良きにつけ、悪きにつけあるものだという割り切りでいきましょう。
負のスパイラルを断ち切る「決心」と「決断」
これらの兆候を放置すれば、売上は減少し、支出は変わらず、資金繰りは逼迫し、経営者と従業員の精神はますます疲弊していく負のスパイラルに陥ります。
この悪循環から抜け出すためには、「決心」と「決断」が必要です。
思考の罠:「どうしたらいいだろう」の無限ループ
経営が厳しいと感じ始めたとき、人は自然と
「この先どうしたらいいだろう」
「これ以外で何で生きていけばいいのか」
と考えを巡らせます。
一見、前向きな思考のように見えますが、これこそが自分を追い込む思考の罠です。
現状の解決策が見えないまま、出口のない問いを繰り返すことは、不安を増幅させるだけで、具体的な行動には繋がりません。
体力と気力を消耗し、ますます判断力を鈍らせることになります。
このような形に陥ってしまうオーナーは非常に多いのです。ダメならダメでスパッと気持ちを切り替えていく判断、決断は責任者であるほど必要です。
撤退、廃業、譲渡の判断はそれぞれですので、状況判断していきましょう。
まずは「ゴールを決める」ことから
負のスパイラルを断ち切るために、まずすべきは「考えること」ではなく、「決めること」です。
- 撤退: 事業を畳む。
- 廃業: 法的な手続きを進め、完全に事業を終了させる。
- 譲渡(M&A): 経営権を第三者に引き継ぐ。
この3つの選択肢を自分自身に突きつけ、「どの道を選ぶか」を自分で決めることから始めましょう。
大切なのは、感情や執着を横に置き、残された体力と資金を最も有効に活用できるゴールを設定することです。
ゴールが見えれば、そこに至るための具体的なステップ(例えば、税理士への相談、フランチャイズ本部担当者への相談、M&A仲介会社への打診など)が見えてきます。
さて、相談を受けてくれた人は、本気の本気で親身になって考えてくれるかどうかです。
信じがたいかもしれませんが・・・
↓ ↓ ↓
誰も責任は取ってくれない:孤立した決断の重み
経営が厳しい時、誰かに相談したくなるのは当然の心理です。しかし、そこには残酷な現実が横たわっています。
例えば仲間に相談しても、フランチャイズ(FC)本部に相談しても、本気で寄り添った提案などしてくれるはずがありません。
これは、相談相手が冷たい人間だからではありません。
彼らは、「自分の発した発言の責任も怖いから」なのです。
例えば下の例を見ればわかります。
- FC本部: 「続けた方がいい」とアドバイスして、結果的に本部へのロイヤリティが増え、経営者が破綻すれば、責任を問われかねません。本部の真のゴールは、加盟店の維持とロイヤリティの確保であり、個別の加盟店の幸せではない場合が多いです。
- 経営者の仲間: 「頑張れば何とかなる」という精神論で励ましてくれるかもしれませんが、彼らはあなたの塾の負債や経営の責任を負ってくれるわけではありません。無責任な励ましは、決断を先延ばしにする毒にもなりえます。
- 税理士:一般的な会計や税務に関してのスペシャリストではあっても塾経営の細かなところまでは、さすがに把握しきれていません。
顧問税理士なのだからという押しつけも的外れだと思います。
真に経営者の人生に責任を持てるのは、経営者自身だけです。要するに最後は自分で判断しなくてはならないということなのです。
酷です・・・。
しかし、ここで、相談相手が必要だと思いましたら、さして気負われることなくご一報ください。
CROSS M&A(通称クロスマ)アドバイザーは、学習塾や習いごと教室の開校、閉校、閉鎖、譲渡、買収すべて経験があり、今もなお教室を運営しているオーナーでもあります。
ですから、皆さんの心の痛みはわかりますし、多角的視野でアドバイスできると思います。
ご相談は無料ですのでご安心ください。
撤退・譲渡は「敗北」ではない
「撤退」や「譲渡」は、決して「敗北」ではありません。それは、冷静な状況分析に基づいた、最も賢明で合理的な「戦略的判断」です。
- 撤退・廃業は、これ以上の損失拡大を防ぎ、経営者の心身を回復させ、次の人生への再スタートを切るための「英断」です。
- 譲渡(M&A)は、自分の築き上げた生徒やノウハウを、より安定した経営基盤を持つ第三者に託し、対価を得ます。事業承継、及び撤退廃業よりも圧倒的にコスト負担が少ない方策です。
いずれの道を選んでも、最も重要なのは「残された経営資源と時間を守ること」です。
資金が尽き、人としての尊厳を失ってからでは、選択肢は「自己破産」しか残らなくなります。
そうなる前に、
自らの直感を信じ、誰にも頼らず、誰にも責任を負わせず、自らの人生の次のチャプターを自分で決める。それが、塾・習いごと経営者に求められる、最後の、そして最も重要な「決断」です。(※繰り返しますが、私どものCROSS M&Aには頼ってくださって大丈夫です!)
この厳しい現実を直視し、一歩踏み出す勇気を持つことが、あなたの未来を切り開く唯一の鍵となるでしょう。
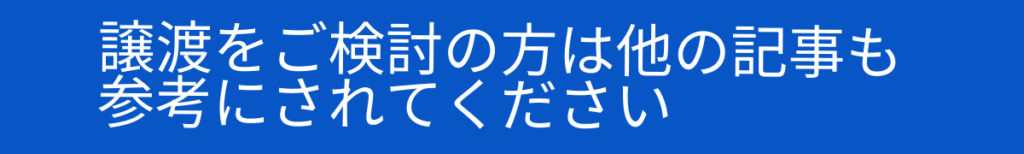
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡