学習塾の経営を成功に導く!利益最大化とコスト削減の全戦略
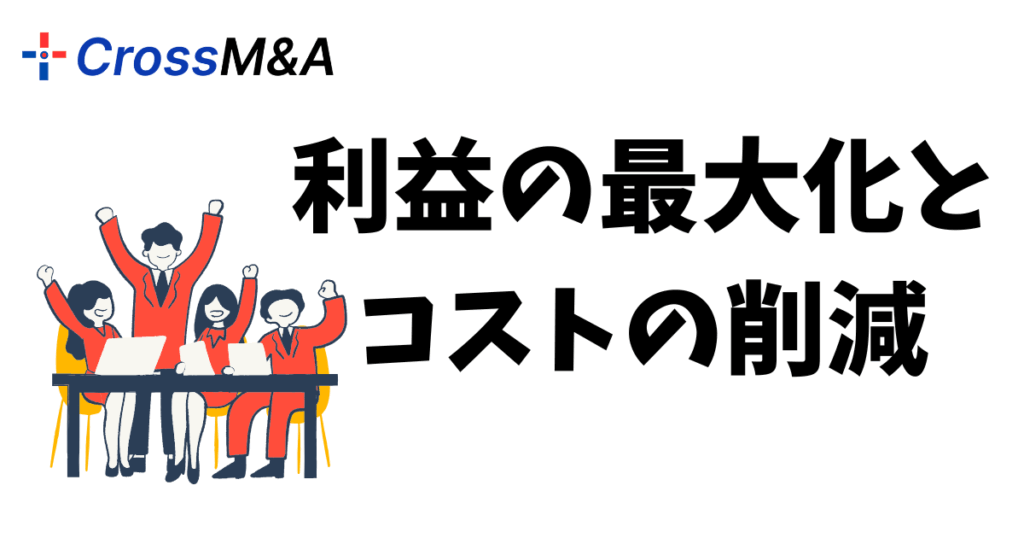
学習塾運営2年目以降の経営者、教室長向けの記事内容です。
学習塾経営は、子どもたちの未来を育むやりがいのある仕事ですが、同時に安定した収益を確保するための経営努力も欠かせません。売上を伸ばす一方で、コストをいかにコントロールするかが、経営の成否を分けます。
本記事では、学習塾経営で直面する主要なコストを分析し、特に大きな負担となりがちな人件費や消費税を削減し、利益を最大化するための具体的な戦略を解説します。
学習塾経営における収益構造の理解
学習塾の収益は、主に生徒から受け取る授業料から成り立っています。そして、この売上高からさまざまな経費が差し引かれ、最終的な利益が算出されます。
売上源泉として、テキスト代金や模試代金も入れて考えられるところもありますが、基本は授業料です。
売上高 – (地代家賃 + 人件費 + 社会保険料 + 教材費 + その他経費) = 利益
この構造を理解し、特にインパクトの大きいコストを特定することが、経営改善の第一歩です。そんなことを考える前に「売上高をあげればいいのだ!」という経営者もいますが、売上高をあげつつもコストを考える2段構えのほうがより実効性が高くなります。
CROSS M&A(通称:クロスマ)のアドバイザー視点では、まずコストからです。
学習塾の主要コスト:地代家賃と人件費
多くの学習塾経営者が「きつい」と感じるのが、地代家賃と人件費です。
1. 地代家賃
駅前や住宅街の好立地は集客に有利ですが、その分賃料が高くなります。固定費として毎月必ず発生するため、一度契約すると簡単には削減できません。契約前に周辺相場をしっかり調査し、必要以上の広さや利便性を求めすぎないことが重要です。
バーチャル空間で学習塾の運営が出来ればいいですが、現状、まだその域には達していないように思います。講師がいて、時間になったらしっかりと授業を行ってくれる、そんな環境がまだまだ必要です。そのため、「箱もの」としての物件契約は必要になります。
2. 人件費と社会保険料
講師の給与や事務スタッフの人件費、そしてそれに伴う社会保険料は、学習塾のコストの中で最も大きな割合を占めることが多いです。人件費は売上高の変動に左右されやすく、生徒数が減れば採算が悪化し、経営を圧迫する要因となります。しかし、裏を返せば、工夫次第で最も削減の余地があるコストでもあります。
つまり、最も変化させることが出来る可能性を秘めたコストであると言えます。
ひとりひとりに計算していく人件費が高すぎれば経営を圧迫しますし、低すぎれば従業員の募集や定着にも影響を与えてしまいます。
このコントロールは慎重に行う必要がありますが、適性コストが見出された「後」工夫してコストカットをしていくことは可能です。
人件費を削減する具体的な戦略
人件費を削減するためには、1人の講師が担当できる生徒数を増やすことが最も効果的です。個別指導塾であっても、集団授業であっても、この考え方は共通です。
個別指導塾の場合
- 1対2、1対3の指導形式の導入 完全なマンツーマンではなく、講師1人が複数の生徒を同時に指導する形式を取り入れることで、講師1人あたりの生産性を高めます。
- ティーチングアシスタント(TA)の活用 社員講師やベテラン講師がメインの指導を行い、大学生アルバイトなどをTAとして活用し、演習問題のサポートや質問対応を任せます。これにより、人件費を抑えつつ、質の高い指導を維持できます。
- 自立学習を促すカリキュラムの構築 生徒が自分で学習を進められるよう、デジタル教材や演習プリントを充実させ、講師が手取り足取り教える時間を減らします。これにより、講師1人でより多くの生徒を見ることが可能になります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
これは、私どもも実際にシミュレーションをして、計算して、尚且つ電光石火のごとく号令をかけて実務から得た経験として以下申し述べます。
個別指導塾の場合には、一回あたりの授業が60分、80分、90分、100分と様々ですが、この講師の授業コマにおける「コマ給与」をコストカットだからと言って、当初設定より下げることは、ほぼ不可能です。
例えば事例として、雇い入れたときのコマ給与が1,800円だとします。経営的にあまり芳しくないからといって、次月から1,600円に・・ということをすれば、その講師はとたんに辞めてしまうかもしれません。
人件費というのは、一度上げたらなかなか下げられないものなのです。
講師のコマ給与の昇給を年間1~2回実施するとすれば、確実に給与は上がってきます。準じて授業料をどんどん上げていけば、今度は顧客離れになってしまいます。
では、どうすればいいのか・・・?
個別指導の場合は、多くの場合、1:1の完全個別、1:2、1:3などで実施されています。
実際に上記の号令をかけた試みというのは、人が教える個別指導から、タブレットを使ったAI授業への一部シフト、及び導入です。
これによって、通常の個別指導と、タブレット型授業がハイブリッドで実施できるようになりました。タブレット形式のほうは、1:2とか1:1にする必要がなく、ときには1:4,1:6と一人の講師が見られる人数を増加させることが出来ました。
タブレット形式の授業のほうが授業単価が安くなる半面、一人の講師がみられる生徒数を増加させることで、いわゆる収益率は高くなるということです。
以下は、わかりやすくするため、個別指導の週2回の授業料金を35,000円、タブレット型授業の週2回の料金を25,000円と仮定します。
【1:2授業の場合】
一つの授業コマのところに、2名の生徒がいたならば、週2回=月間8回なので、1回の授業単価は4,375円になるため、これが2名いるということは、8,750円が授業一回に得られる収入ということになります。そこに1名の講師が1コマ授業を1,800円で実施しているのですから、差し引きで6,950円が想定粗利となります。
ここの意味はわかりますでしょうか。
収入は生徒からいただく授業料ですので、その授業料金の一回あたりの単価を求めて、そこにかかる講師コストがいくらかかっているのかという計算から想定粗利を求めているのです。
実際には、水道光熱費とか、通信費、その他費用に加えて地代家賃も日々案分しなくてはいけませんから、その想定粗利からさらにお金を引かなくてはいけません。
ただあまり複雑にするとわかりにくくなるため、敢えてシンプルにしてあります。
【タブレット授業の場合】
月間の授業料が個別指導料金より1万円ひくい25,000円での仮設定です。
そうすると、一回あたりの授業料が3125円です。このタブレット授業を4人の生徒が受けていたとします。売上高としては一回授業で12,500円で、講師費用が仮に1,800円だとしても想定粗利は、10,700円となります。これがもし講師1名に対して生徒6名でセットできると、3,125円×6名で18,750円の一回授業収入に対して講師費用は1,800円ですので、16,950円の想定粗利となります。
上記に書いた内容がイマイチ ピンとこない・・という場合には是非ご質問ください。
図を描きながら説明しますとたいていご理解いただけますので、何度でもわかりやすくご説明申し上げます。
集団授業塾の場合
- クラス人数の最適化 1クラスあたりの人数を適切に設定します。生徒数が少ないクラスは統合を検討するなど、講師の稼働率を最大化する工夫が必要です。
- 映像授業の併用 基礎的な内容は映像授業で学び、質問対応や演習に講師が集中する「反転授業」を導入します。これにより、同じ時間でより多くの生徒を指導できます。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
上の個別指導の事例をご覧いただければ、集団塾の利益構造も容易にご想像いただけるかと存じます。
つまり、1名の講師が一回に行う授業で生徒さんの数は3名とか5名ではなく、もっと多くいるわけです。20名とか30名となれば、一回あたりにいただける授業料金が計算によってかりに2,500円と、個別指導やタブレット型よりも安かったとしても人数がいれば講師にお金を支払っても十分に賄えるということです。
たとえば20名であれば、一回当たり50,000円です。30名であれば、一回当たり75,000円です。
だとすれば、講師に支払える授業対価も、個別指導講師よりも多く与えて大丈夫ということになるのです。
実は、先日、元集団塾の複数教室の教室責任者を歴任してきた方とお話をすることが出来ました。当初人数が2桁だったものを100名にし、300名を突破させるなど非常に有能な力を持った方でした。
独自のサービス視点を持っていて、実際には集団塾だからと大きなディスカウントをしないで運営されていたそうで、中学3年生でも37,000円ぐらいの授業料だったようです。
そうすると、一回授業単価が4,625円ですので、一回の授業での参加人数が40名ぐらいだとして、一回授業における想定粗利は185,000円です。とんでもない収益になっていたことが容易に想像できます。
全体に共通するポイント
業務効率化のためのITツール導入 :成績管理や保護者への連絡、スケジュール調整などにITツールを活用し、事務作業を効率化します。これにより、社員講師が指導以外の業務に費やす時間を減らし、本来の業務である指導に集中できるようになります。
このツール導入でも無駄なコストをかけないようにしましょう。
よくある月間コスト〇〇円で、生徒管理が楽ちん!!こんなの使う必要はないですし、無料でしかも顧客満足度が絶対に低下しない方法があります。
是非、お問合せください。
さて、続いては税金についてです。中でも消費税は、予定納税も含めて考えると、かなり痛い出費になるはずです。また痛い出費だと感じるはずです。
お客さんが支払ってくれた授業料やその他についての対価には消費税が入っています。
消費税というのは、一時受け取り側で預かっているだけのものですから、支払わなくてはなりません。
例えば売上高が約1億円あったとします。
これ、「売上高」だけをクローズアップすれば、約9000万円プラス消費税約900万円の合計ということです。つまりこの900万円は、消費税として税務署に納めなくてはならないものです。
こう考えるとかなり大きいです。10%は問答無料で持っていかれるのですから。
ただし、消費税というのは受け取り消費税と支払い消費税があります。つまり受け取ったものから支払ったものの差し引きを納める計算になります。
例えば、受け取った消費税は900万円だが、支払った消費税が400万円あれば、差し引きは500万円ということです。(500万円でも大きいですが・・・)
そこで下をよくご覧ください。
↓ ↓ ↓
消費税対策:経営拡大とコスト削減の両立
消費税は、売上にかかる「受け取り消費税」と、経費にかかる「支払い消費税」の差額を納税します。
納付額 = 受け取り消費税 – 支払い消費税
この仕組みを理解し、戦略的に経営を行うことで、納付額を抑えることができます。特に有効なのが、多店舗展開です。
多店舗展開による消費税対策のメリット
- 支払い消費税の増加 新規店舗の開設時には、内装工事費、什器備品購入費、広告宣伝費など、多額の初期投資がかかります。これらの費用には消費税が含まれており、支払い消費税が増加します。
- 納付額の軽減 支払い消費税が増えることで、受け取り消費税との差額が小さくなり、結果として納付する消費税額を軽減できます。
- 事業拡大によるスケールメリット 消費税対策を行いながら事業を拡大できれば、経営の安定と成長を両立できます。新しい教室が増えることで、教材の一括購入によるコスト削減や、ブランド力の向上といったスケールメリットも享受できます。
確かに2号教室、3号教室とつくっていくとなれば、その都度現金が減少しますが、支払い消費税は確実に減らせます。
そして、複数教室経営が成功すると、売上高が増大していきますので、消費税に対しての感覚的なものが低減できます。
多店舗展開の戦略的タイミング
既存の教室が軌道に乗り、安定的なキャッシュフローが確保できたタイミングで、次の店舗を検討します。これにより、新規店舗にかかる初期費用を、既存店舗の収益でまかなうことができ、資金繰りのリスクを抑えられます。
その他のコスト削減策と収益改善のヒント
- 広告宣伝費の見直し チラシやウェブ広告など、効果の測定が難しい広告は、費用対効果を定期的に見直しましょう。口コミや紹介制度を強化し、低コストで集客できる仕組みを作ることも重要です。
- 教材費の最適化 デジタル教材を導入すれば、印刷費や在庫管理の手間も削減できます。
- 補助金・助成金の活用 DX推進や従業員の雇用に関連する補助金や助成金は、経営改善に役立ちます。最新の情報を常にチェックし、積極的に活用しましょう。
【教材費について】
いずれかの回でも書きましたが、よくあるプリント型の教材システムを利用している場合は、それが本当に必要なものなのかどうかを精査されるとよいかと思います。
一か月に2万円から3万円ぐらいのコストをかけて『〇トレ』のようなシステムを導入するのであれば、良質のテキストを買ったほうが安上がりです。
例えば月間25,000円のシステム利用料金だとして、年間300,000円です。これが複数教室で利用していたならば、例えば5教室運営で年間1,500,000円です。
軽自動車が一台買えます。
ipadが37台買えます。
月3万円のアルバイト講師なら1年間4名雇えます。
結論:持続可能な経営を目指して
学習塾経営を成功させるためには、売上を伸ばすだけでなく、コストをいかに効率的に管理するかが不可欠です。特に、人件費と消費税は、戦略的なアプローチで大幅な改善が期待できます。
1. 人件費の最適化:1人の講師が担当できる生徒数を増やす工夫 2. 消費税対策:事業拡大と初期投資による支払い消費税の増加
これらの戦略を組み合わせることで、目先の利益だけでなく、将来にわたって安定的に成長できる強い経営基盤を築くことができます。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月14日
学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)
#保護者面談
#個別指導提案
#入試情報提供
#受験生意識付け
#塾テキスト推奨
#学習塾経営
#新年度カリキュラム
#春休み学習計画
#春期講習
#継続率向上

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目