学習塾・習いごと教室で、事業譲渡の価値を上げる方法
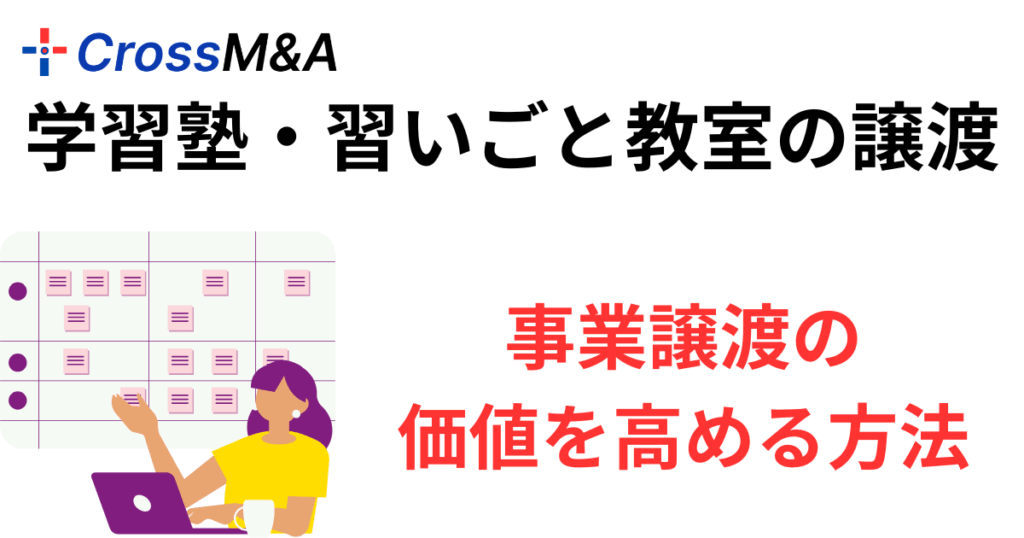
教育産業における事業譲渡の動向と価値向上の重要性
少子化、多様化する教育ニーズ、そして後継者不足という課題を背景に、学習塾・習いごと教室業界における事業譲渡(M&A)は、事業承継や事業拡大の有力な選択肢として年々増加しています。
事業の譲渡を検討する際、経営者にとって最大の関心事は「いかにして事業価値を最大化し、より良い条件で譲渡を成功させるか」という点でしょう。
学習塾・習いごと教室の事業価値は、固定資産や直近の財務状況だけで決まるものではありません。
・生徒の継続性
・講師の質及び継続性
・独自メソッドや教育ノウハウ
・地域におけるブランド力
といった無形資産が、M&Aにおける評価額を大きく左右します。
ここで買い手の気持ち(個人であれ、法人であれ)の立場、考え方に立ってみれば、望むものが何なのかが明確にわかります。
これは
・譲受後の「安定した収益性」
・「将来的な成長可能性(シナジー効果)」
です。この2つを重視するのです。過去じゃなくて、「これから」です。その予測をしながら買収を考えますので、買い手の気持ちを無視した交渉はできないということになるのです。
本稿では、学習塾・習いごと教室の事業価値を劇的に向上させるための具体的な戦略を、財務・非財務の両面から徹底的に解説します。
第1章:財務体質の強化と透明性の確保
事業価値の根幹をなすのは、やはり安定した収益性です。買い手企業が見るのは、過去数年間の財務諸表、特に営業利益(EBITDA)を重視します。
EBITDAとは?
EBITDA(イービットディーエー/イービッター)とは
「利払い前・税引き前・減価償却前利益」を意味する、企業の「純粋な収益力」を見るための財務指標です。
- 利息(Interest)、税金(Taxes)、減価償却費(Depreciation and Amortization)といった、金利水準、税制、会計基準の違いによって大きく変動する費用を取り除く(足し戻す)ことで算出されます。
- これにより、大規模な設備投資による減価償却費の大小や、借り入れによる利息の負担といった要素に左右されず、その企業が本業でどれだけキャッシュを稼ぎ出す力があるのかを比較・評価しやすくなります。
- 国際的な企業や設備投資が多い業種の収益力を比較する際などに特に重視されます。
EBITDA=営業利益+減価償却費
このように覚えておいてよいでしょう。
1.1. 収益性の向上と「非属人的な利益」の確保
- 適正な価格設定と客単価の向上(ARPUの改善): 近隣競合との価格比較はもちろん、提供するサービスの質や付加価値に見合った適正な月謝設定が重要です。さらに、季節講習、検定対策、プログラミング教育など、高付加価値なオプション講座を開発・提供することで、生徒一人あたりの単価(ARPU:Average Revenue Per User)を向上させます。単価向上は、生徒数の増減に左右されにくい安定的な収益基盤となります。
- コスト構造の最適化: 人件費、家賃、広告宣伝費のバランスを見直します。特に、生徒数の増減に応じた柔軟な講師のシフト・報酬体制を整えることで、人件費の効率化を図ります。また、ペーパーレス化やクラウドシステムの導入による業務効率化は、間接コストの削減に直結します。
- 「非属人的な利益」の証明: 社長(オーナー)個人の能力や人脈に依存した利益ではなく、システムや講師陣の指導力によって生み出されている利益であることを明確にすることが極めて重要です。属人的な利益は、譲渡後に消滅するリスクがあると見なされ、評価が大幅に下がります。
この点は、売り手としては悩ましいところかもしれません。
なぜなら、学習塾や習いごと教室の場合、大なり小なりオーナーの魅力、実行力、計画などがあったからこそ運営が出来ているという側面があるからです。
いゆゆるキーマンとなる人=オーナー、この構図である場合、当然ながら買い手は「自走できる案件ではない」と即断します。尚且つ人材手配やチーム構成などを考えなくてはいけません。そして、講師や先生と言われる人たちの継続の有無も重要です。基本合意、譲渡契約の前段階でこのあたりの人材の状況について、偽りなく買い手の報告をしないと問題が生じますので、要注意です。
1.2. 財務の透明性とクリーン化
- 適正な経費計上と「磨き上げ」: 譲渡前の数年間で、個人的な支出や事業とは関係の薄い経費を削減し、財務諸表を「クリーン」な状態にすることが望ましいです。
これをM&A業界では「磨き上げ」と呼びます。オーナー報酬が高すぎる場合は、一般的な役員報酬水準に調整することで、実態としての利益を明確化します。
しかし実際は「磨き上げ」をしている時間が許されないケースがあります。それはいわゆる急募ケースです。早く売りたいという場合です。すでに業績的にかなりまずい状態になっていますので、廃業(閉校)か譲渡かのギリギリ状態にある場合は、背に腹変えられない状態ですので、譲渡金額を安く設定してでも売りたいという意識が売り手側に働くことでしょう。
この場合でも売り手であるオーナーさんは、包み隠さず状況を知らせていくほうが無難(無難というか、そうしなければなりません)です。何につけても隠したらのちにトラブルになる可能性があるからです。
- キャッシュフローの安定化: 季節講習費などの一時的な大口収入に依存するのではなく、月謝を主軸とした安定的なキャッシュフロー構造を確立します。
- 固定資産の整理: 事業に利用していない資産や、老朽化して価値が低い設備などは、譲渡前に処分または売却することで、バランスシートをスリム化し、買い手側の煩雑さを軽減します。
第2章:無形資産の「見える化」とブランド力の強化
学習塾・習いごと教室の真の価値は、目に見えない無形資産にあります。これを体系化し、買い手企業に明確に伝えることが高額譲渡の鍵となります。
2.1. 講師・従業員体制の確立と非属人化
- 優秀な講師陣の確保と定着: M&Aにおいて、優秀な正社員講師の存在は大きな評価ポイントです。彼らがM&A後も継続して勤務する確約(アグリーメント)や、流出リスクの低い報酬・研修制度を構築することは、事業の継続性を保証します。
- 「指導ノウハウ」の体系化: 特定の人気講師に依存しない、標準化された指導マニュアル、カリキュラム、進捗管理システムを整備します。これにより、講師の入れ替わりがあってもサービスの質を一定に保てる「再現性」が保証され、価値が大幅に向上します。
- 組織図と業務フローの明確化: 教室運営、経理、集客といった業務の担当者とフローを明確に記録し、オーナー不在でも運営できる体制(自走力)を証明します。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
今まで自社及び他の譲渡案件に携わりましたが、譲渡することが従業員(雇っている教室長や講師)の退職につながった事例は実はゼロです。
また、逆のケースとして、CROSS M&A(通称クロスマ)アドバイザーが「買収側」として塾買収を行ったときにも それによって退職してしまったという事例がありません。ゼロです。
譲渡の際も買収の際も、かなり秘密裡に進行させて、基本合意がなされ、譲渡契約が終わって、いざいついつから新体制になるということが確定し、尚且つその日程までのカウントダウンが残り2週間ぐらいの段階で「実は・・・」という切り出しをメールとか手紙で実施することでもアルバイト従業員の退職はなかったということをここでお伝えしておきます。
それはたまたまだったのか?と問われると、決してそうではないと思います。
講師たちは、自分の慣れ親しんだ塾での勤務が嫌いではないので、ちゃんと継続して勤務してくれることが多いのでしょう。
教室長においては、さすがに2週間前の通告では、考える時間も何も与えないことになりますので、フェアではありません。
2~3か月前には通告して対話の時間を設けることが大切です。
突然の話では驚きますが、事前にしっかりと向き合って対話をしていき、尚且つ待遇面での変化は全くないということで安心感を与えてあげれば、運営者として継続して勤務してくれると思います。
譲渡が確定しました、では私も辞めますというのは・・・流れとしてはあまり想定できません。
しかし、何らかの原因でオーナーと教室長の折り合いが実は悪い状態だった・・・というケースとか、給与や待遇に不満を持っていた段階だったとか、新体制で給与や待遇が従業員にとって不利になるケースであれば、対話の内容によっては退職につながるかもしれません。
ですが、私は基本は対話重視だと思います。
アルバイト講師の採用は成功報酬形式のサイトで特別な広告を出さなくても採用は出来ます。しかし、教室長を雇用する場合には、そういうアルバイト講師採用のサイトでも出来なくはありませんが、相当の時間がかかります。
2~3か月で教室長を採用するのであれば、やはり大きな民間媒体を使うほうが効率がよく、尚且つ成功率が高いです。
そのかわり、その採用コストは、5万円、10万円・・・というのは、いくつものラッキーが重ならないと無理です。
教室長採用では、30万~60万円はかかるだろうというコスト計算もしておかなくてはいけません。
それは「買い手が負担」するコストになってしまいます。
従って、
従業員(教室長と講師)が残ってくれる場合には、それだけでも価値が高まり、逆の場合は価値が低くなるということを想定しておかなくてはなりません。
この点も正直ベースで買い手に情報提供することで、買い手側の安心と覚悟が高まります。
2.2. 教育コンテンツとシステムの優位性
- 独自のカリキュラム・教材開発: 他塾にはない、独自の指導メソッドや教材は、知的財産として高く評価されます。特に、AIツールやプログラミング、英会話、探究学習など、時代のニーズを捉えた新規分野への展開は、将来の成長性をアピールできます。
- デジタル化への対応と効率化: オンライン授業のプラットフォーム、生徒の進捗・成績をリアルタイムで保護者と共有するシステム、AIを活用した個別最適化学習ツールなどの導入は、サービスの質向上と業務効率化の両面で価値を生みます。特に、オンライン自習室や学習管理システム(LMS)は、物理的な教室のキャパシティを超えた収益機会と見なされます。
AIという言葉が出ていますが、これは買い手の方が興味をもってくれるキーワードです。AIは教育事業にとても親和性があり、今後も大きく発展していくものでしょう。
正直なところ、いまだにテキストのみの学習「のみ」の仕組みであれば、買い手に伝わるメッセージが相当弱まってしまいます。
かと言って、AIと使ったシステムをフルスクラッチで開発会社に頼めば、多分1000万単位でお金がかかり、新規参入の際の大きな障壁になってしまいます。
個人的にオススメするのは、AIツールの月額利用です。自社開発していくよりもコスト的にはかなり圧縮されます。得意なところを月額で使わせてもらうのが一番有効だと考えます。
- 顧客データとターゲティング: 過去の生徒の成績データ、退塾理由、成功事例などを分析し、今後の集客や指導に活かせるデータ資産として整備します。
2.3. ブランド力と地域密着性
- 実績の明確化と第三者評価: 進学実績(特に難関校)、定期テストの成績アップ事例などを明確に数値化し、ウェブサイトやパンフレットで公開します。また、地域での口コミや保護者アンケートでの高評価は、信頼性の高いブランド価値となります。
- 地域に根差した「固定ファン」の獲得: 創業からの年数や、地域イベントへの参加など、単なる実績だけでなく、地域住民からの信頼や愛着も、生徒の継続率と集客コストの低さにつながるため、評価されます。
- 多様な集客チャネルの確立: 口コミだけに頼らず、SEO対策を施したWebサイト、SNS、地域ポスティングなど、複数の集客チャネルが機能していることを示します。特にWeb集客で安定したリード(見込み客)を獲得できている仕組みは、譲渡後の成長期待値を高めます。
このWEB集客の補足をします。
業界的用語で、マーケティングだとか、コンバージョンだとか、上記にあるリードだとか、ちょっとわかりにくいかと存じます。
簡単に言えば、学習塾や習いごとは、例えば電話をかけまくって、訪問して顧客を獲得するのではなく、基本はウェイティング、待ち営業です。問合せがあった初めてそこから発展する可能性があるということです。
ということは、問合せが来る仕組みが確立されているかどうかは重要な指標になるのです。
塾業界であれば、自社サイトからの問い合わせはどうなのか?塾ナビからの問い合わせはあるのか?などの状況を数字面でアピールできるようになっていると尚良いでしょう。
第3章:事業譲渡に向けた準備と交渉戦略
価値を向上させるための施策と並行して、M&Aプロセスを円滑に進めるための戦略も重要です。
3.1. 法務・税務のコンプライアンス徹底
- 雇用契約と就業規則の整備: 講師との雇用契約、特に正社員・契約社員・アルバイト間の区別を明確にし、就業規則が最新の法規に準拠していることを確認します。未払いの残業代など、潜在的な法的リスクはデューデリジェンス(詳細調査)で必ず指摘され、価値が減額される要因となります。
- 契約書の整備: 教室の賃貸借契約、教材の著作権、フランチャイズ契約(FCの場合)など、すべての重要契約書を整理し、M&A後も買い手が円滑に事業を継続できる状態にしておきます。
- 個人情報保護の体制: 生徒・保護者の個人情報管理体制が適切であることを証明します。教育産業において、個人情報漏洩リスクは重大な懸念事項です。
上記はすべて書類関連にかかるものですが、財務管理、労務管理が軸になります。税理士が扱う範疇、社会保険労務士が扱う範疇ということです。
士業の方が顧問にいる場合は、それなりの書類がすぐに用意できると思いますが、個人事業主で、少々どんぶり勘定っぽい状況ですと、書類整備がなされていないことが多いため、このあたりの整理状況も把握しておく必要があります。
3.2. 買い手目線での「シナジー効果」の提示
M&Aの譲渡価格は、売り手事業の価値(企業価値)だけでなく、買い手がその事業を買うことで得られる「シナジー効果」の期待値によって大きく変動します。
- 立地の魅力と新規参入の容易さ: 買い手が未進出の優良な立地である場合、その地域への参入コストを削減できるというメリットは高く評価されます。
- 教育ポートフォリオの補完: 例えば、買い手が集団指導専門で、売り手が個別指導に強みを持つ場合、お互いの弱点を補完できる「サービスの多角化」というシナジーが生まれます。
- 顧客層の相互利用: 習いごと教室であれば、学習塾の既存生徒にクロスセルできる可能性など、顧客基盤を相互に利用できる提案は魅力的です。逆のケースもあります、学習塾が習いごとを買収する場合にもクロスセルが十分に可能です。
3.3. 専門家の活用
- M&A仲介会社・アドバイザーの選定: 教育産業に特化した知識とネットワークを持つM&A専門家を選定することで、適正な企業価値評価を受け、最適な買い手とのマッチング、そして複雑な交渉プロセスを有利に進めることができます。
結論:継続的な企業価値向上へのコミットメント
学習塾・習いごと教室の事業譲渡の価値を上げる方法は、一朝一夕に実現できるものではありません。それは、日々の経営努力を通じて、「オーナー個人に依存しない安定した収益を生み出す仕組み」、「再現性の高い指導ノウハウ」、そして**「地域社会からの高い信頼という無形資産」**を積み重ねるプロセスそのものです。
事業譲渡は、単なる資金調達や引退の手段ではなく、築き上げてきた教育理念と地域貢献を次世代に引き継ぎ、さらに大きな資本とノウハウのもとで発展させるための戦略的な選択です。
譲渡を検討し始めた時点から、本稿で述べた財務の透明化、非属人化の推進、無形資産の体系化にコミットすることで、事業価値は着実に向上し、経営者自身が納得のいく高額でのM&Aを成功させることができるでしょう。
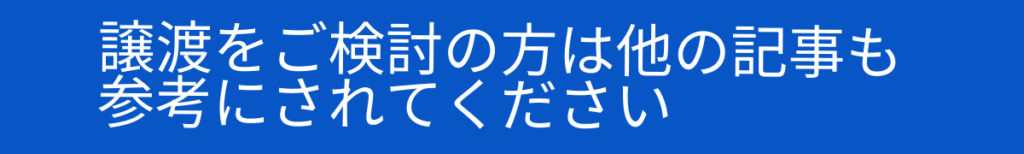
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡