子供の塾選びで失敗しない!立地で選ぶ塾の重要性と後悔しない選び方
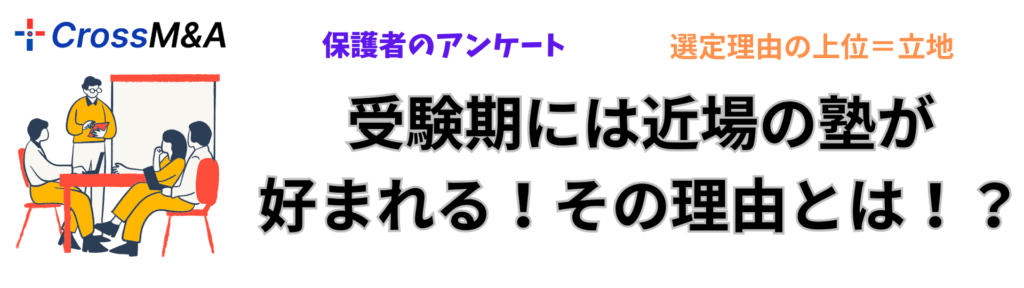
子供の塾選び、距離で悩んでいませんか?
アンケート結果を見ても、お子さんの塾選びで立地を重視している保護者の方が非常に多いことがわかります。
こんなケースもあります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
「今まで特定の駅の近くの塾に通っていたけれど、もっと家から近い塾を探しているんです」
「受験を控えて自習でも通いやすい塾に変えようかと思いまして・・・」
この2つは、2025年7月、まさに最近保護者様からダイレクトにお伝えいただいた内容です。その理由をおたずねすると、今まで通っていた塾に特段不満を持っているわけではなく、お子さんの学習効果をもっと高めたいという意向だということがわかりました。
つまり、塾の行き帰りの移動時間を短縮させたい、受験になるので頻繁に自習利用できる塾に転塾したいということです。
また同時に「ここは自転車は置けるのですか?」という内容もよく聞く質問ですので、その需要も多いことがわかります。
お子さんが安心して学習に取り組める環境を整える上で、塾の立地は非常に重要な要素です。単に「近いから便利」というだけでなく、お子さんの学習効率、さらには安全面にも大きく関わってきます。
なぜ塾の立地が重要なのか?
塾の立地が重要視される背景には、主に以下の3つの理由が挙げられます。もっと詳細に書きます。

1. 学習面での移動時間ロスをなくす
「今まで〇〇駅の近くに行ってたのですが、近場で探そうと思って」「受験になるので、自習でも通いやすいところを探しています」といった声は、まさに学習時間の確保と効率化を求める保護者の切実な願いを反映しています。
塾が遠いと、それだけで移動に時間がかかり、お子さんの学習時間が削られてしまいます。例えば、片道30分の移動時間が毎日発生すると、週に2回塾に通うとして月に4時間、年間で約48時間もの時間を移動に費やすことになります。この時間は、本来なら家庭学習や趣味の時間に充てられたはずの時間です。
特に受験期に入ると、1分1秒が惜しいほど貴重な時間となります。塾の行き帰りで疲弊してしまい、肝心の学習に集中できないという状況は避けたいものです。塾が近ければ、移動時間が短縮され、その分を予習・復習の時間に充てたり、苦手分野の克服に時間をかけたりと、より有効に時間を使えるようになります。
さらに、自宅から近い塾であれば、気分転換に一度家に帰ってから塾の自習室を利用したり、体調がすぐれない時にすぐに帰宅できたりと、柔軟な学習スタイルを確立しやすくなります。これもまた、学習の効率を高める上で大きなメリットとなります。
2. 自習利用のしやすさ
多くの塾では、生徒が自由に使える自習室を提供しています。この自習室をどれだけ有効活用できるかが、成績アップの鍵を握ることも少なくありません。
自宅から塾が遠いと、「今日は塾の自習室で勉強したいけど、行くのが面倒だな」「わざわざ電車に乗ってまで行くのは…」と、自習室の利用をためらってしまうことがあります。しかし、塾が近ければ、学校帰りや休日でも気軽に立ち寄って自習することができます。
ある保護者の方の口コミで
「家から塾が近いので、学校帰りに友達とそのまま自習室に寄って勉強する習慣ができました。わからないことがあればすぐに先生に質問できるのも助かっています」という声がありました。
(※学習塾選びの鍵!自習室の有無と活用法、そして生徒数から見る塾の質という記事も書いていますので、併せてご確認ください。)
このように、塾が近いことで自習室の利用頻度が増え、学習習慣の定着にも繋がるのです。
3. お子さんの安全面を確保する
塾選びにおいて、お子さんの安全は最優先事項の一つです。特に小学生や中学生の場合、夜遅くに塾から一人で帰宅することを考えると、塾の立地は非常に重要になってきます。
明るい通りに面しているか、人通りの少ない道を通らないか、治安が良いエリアにあるか、といった点は必ず確認しておきましょう。駅前であっても、繁華街の奥まった場所にある塾や、夜間になると人通りが極端に少なくなる場所に位置する塾は、避けた方が賢明かもしれません。
実際に、「塾から家までの道が暗くて心配なので、送り迎えをしています。もう少し明るい場所にあれば…」という保護者の声も聞かれます。お子さんだけで通塾する場合、塾までの道のりが安全であることは、保護者の方の安心にも繋がります。
塾の立地、どこまでが「近い」の基準?
「400m以内」「800m以内」「1.6km以内」と様々な検索キーワードがあるように、各家庭によって「近い」の基準は異なります。
実はこの400m以内や800m以内などは、全国の保護者様が学習塾を選定する際のロングテールキーワードとして、ワードに入れている言葉です。
その目安は、徒歩や自転車での移動時間ということになっています。
| 距離の目安 | 時間の目安(徒歩) | 特徴とメリット・デメリット |
| 400m以内 | 約5分以内 | メリット: 最も移動負担が少なく、急な用事や体調不良でもすぐに帰宅できる。自習室の利用頻度が高まる。デメリット: 選択肢が限られる可能性。 |
| 800m以内 | 約10分以内 | メリット: 徒歩圏内で十分に近く、多くの塾が選択肢に入る。自転車通塾も可能。デメリット: 交通量が多い場所では注意が必要。 |
| 1.6km以内 | 約20分以内 | メリット: 広範囲で塾を探せるため、希望の指導内容や費用で塾を選びやすい。自転車や公共交通機関を利用する。デメリット: 移動時間が長くなる。悪天候時の通塾が負担になることも。 |
リサーチすると、400m以内、800m以内が圧倒的に多いので、徒歩ベースで5~10分圏内を想定している保護者が多いということがわかります。
お子さんの年齢や性格、通塾方法(徒歩、自転車、公共交通機関)、そして塾に通う頻度などを考慮して、最適な距離を見極めることが大切です。
保護者の声から見る距離の重要性
あるアンケートでは、
「塾選びで重視した点」として「家からの距離」を挙げた保護者が非常に多かったという結果が出ています。具体的な口コミを見てみましょう。
- 「うちは小学生なので、学校から直接行ける距離で探しました。低学年のうちは特に、一人で電車に乗って塾に行くのは心配だったので、徒歩で通える範囲が絶対条件でしたね。」(小学4年生保護者)
- 「中学校の定期テスト前になると、塾の自習室にこもることが増えるので、自転車でサッと行ける距離の塾を選びました。おかげで、テスト期間中は毎日塾に通って勉強していましたよ。」(中学2年生保護者)
- 「電車通塾も考えていましたが、部活で帰りが遅くなることもあるので、駅から近い塾にしました。駅の改札を出てすぐの場所にあるので、夜遅くなっても安心です。」(高校1年生保護者)
- 「以前は遠くの有名な塾に通わせていましたが、移動で疲れてしまい、家ではなかなか勉強に集中できていないようでした。思い切って家の近くの塾に変えたら、見違えるように成績が伸びたんです。やっぱり、無理なく通えるのが一番だと実感しました。」(中学3年生保護者)
これらの口コミからもわかるように、塾の距離は単なる利便性だけでなく、お子さんの学習意欲や集中力、そして保護者の安心感にも大きく影響することがわかります。
自習率の高さは成績向上と比例することが多いです。
また保護者としても例えば、夏期講習の時期に午前の早い時間から塾で学習をしているとわかるだけでも安心できるのだと思います。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
実際、
現在運営中の学習塾でも中学受験のお子さんとか、一日10時間ぐらい塾にいます。さすがに小学生ですので、通しで10時間学習はやっていませんが、お弁当や水筒をもってきて、勉強しては休み時間をとって、また勉強して・・と自分で時間計画を立てて学習されている様子です。
中学受験は年内入試の通称「一志入試」があります。これは「第一志望入試」の略です。
年内、つまり12月ですので、学習意欲が7月、8月と下手したら高校受験の生徒さんより頑張る子もいるのです。
この生徒さんたちの保護者さんは、
口をそろえてこのように言ってくださいます。
「家だと集中できないことも多いので、塾でこうやって自習してくれると親としても安心です。」
ときおり、自習をしているときの様子をメールなどで報告することで、保護者さんとのコンセンサスがしっかりととれますし、
まさに長時間この場所にいることで、保護者さんが安心して任せてくださっているのが肌感覚でわかります。
立地以外の塾選びのポイントも忘れずに
もちろん、塾選びは立地だけで決まるものではありません。立地は選定要因のあくまでも一つですので、以下のポイントも合わせて検討されているのだということを是非知っておきましょう。
1. 指導内容とカリキュラム
集団指導か個別指導か、あるいはその両方を組み合わせた形態か。学校の授業の補習なのか、受験対策なのか。お子さんの学習状況や目標に合った指導内容を提供しているかを確認しましょう。体験授業に参加してみるのが一番です。
2. 講師の質
塾の講師は、お子さんの学習モチベーションに大きく影響を与えます。指導力だけでなく、お子さんとの相性も重要です。質問しやすい雰囲気か、熱意を持って指導してくれるかなど、実際に話を聞いたり、授業を見学したりして確認しましょう。
3. 費用
授業料、教材費、季節講習費、設備費など、塾にかかる費用は多岐にわたります。予算を明確にし、無理なく通わせられる範囲で検討しましょう。後から追加費用が発生しないかどうかも確認しておくと安心です。
4. 塾の雰囲気
塾の雰囲気は、お子さんが安心して学習に取り組めるかどうかに大きく影響します。活気があるか、静かで落ち着いているか、お子さんの性格に合っているかなど、お子さん自身と一緒に見学し、肌で感じることが大切です。
5. 進学実績(受験目的の場合)
もし受験が目的であれば、志望校への進学実績も確認しておきましょう。ただし、実績だけで判断せず、その塾がどのような指導をしてその実績を出しているのか、お子さんに合っているのかをよく見極めることが重要です。
これらの5項目は非常に重要です。
どれか一つでも生徒や保護者の感覚からずれていると、塾として選んでくれる可能性がダウンします。
後悔しない塾選びのための具体的なステップ
お子さんの塾選びで後悔しないためには、以下のステップで進めることをおすすめしています。
同時にこの項目では、
教室運営の教室長や、これから塾開業をされる方にも、保護者の気持ち、意向を知る意味でもぜひ押さえておいてください。
ステップ1:目的と優先順位を明確にする
- なぜ塾に通わせたいのか? (例: 成績アップ、受験対策、学習習慣の定着など)
- どの教科を強化したいのか?
- 集団指導と個別指導、どちらがお子さんに合っているか?
- 通塾の頻度や時間帯は?
- そして最も重要なのが、立地の優先順位です。どのくらいの距離までなら許容できるのか、お子さんと話し合って具体的な基準を決めましょう。
ステップ2:情報収集と候補の絞り込み
- インターネットで「地域名 塾」「駅名 塾」といったキーワードで検索し、自宅や学校から近い塾をリストアップします。
- 塾のウェブサイトを確認し、指導内容、費用、講師、雰囲気などの情報を収集します。
- SNSや教育系サイトで、実際に通わせている保護者の口コミも参考にしましょう。特に、立地に関する口コミは要チェックです。
ステップ3:複数の塾を比較検討する
候補に挙がった塾の中から、数ヶ所に絞り込み、資料請求や説明会への参加を検討しましょう。説明会では、疑問点を積極的に質問し、納得できるまで情報を集めることが大切です。
ステップ4:体験授業や面談に参加する
これが最も重要なステップです。お子さんと一緒に塾を訪問し、体験授業に参加させてもらいましょう。実際に授業を受けることで、塾の雰囲気や講師との相性を肌で感じることができます。体験授業の後には、必ずお子さんの感想を聞いてください。
ステップ5:最終決定と通塾開始
体験授業の結果と、これまでの情報収集を総合的に判断し、お子さんに最適な塾を決定します。
これは、「もし自分が親なら」という感覚でこの項目の内容を読んでいただければ、これらの5つのステップについてもご理解いただけるかと存じます。
体験授業が決め手になる!という方もいますが、資料請求をして、ネットで調べて、比較している段階では、なんとなく第一候補は決まっているものです。
体験授業は背中押しの役割みたいなものととらえてください。
以前、まだ新聞折込広告が隆盛の時代からすれば、今の選定基準は思い切り民意誘導型ですので保護者の情報整理によって8割は決まっていると言っても過言ではありません。
上記にヒントめいたものを書きましたが、
保護者が「遠いところから塾絵選びをする」ことはまれですから、「近場にあって安心できて、内部がしっかりと整った塾」であるならば、必ず選んでくれます。
まとめ:塾の立地は、お子さんの未来を左右する重要な要素
塾の立地は、単なる物理的な距離以上の意味を持ちます。お子さんの学習効率、自習の頻度、そして何よりも安全面に直結する非常に重要な要素です。
「学習面での移動時間ロスをなくしたい」
「受験に向けて自習でも通いやすいところを探している」
「夜遅くなっても安全に通塾させたい」
といった保護者の切実な願いに応えるためにも、塾選びの際には、立地を重視した選択を強くおすすめします。
お子さんの成長をサポートし、安心して学習に取り組める環境を提供するために、ぜひご家庭で最適な塾の立地について話し合ってみてください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備