【学習塾譲渡】失敗しないための仲介ガイド:知っておくべき手続きと業者の選び方
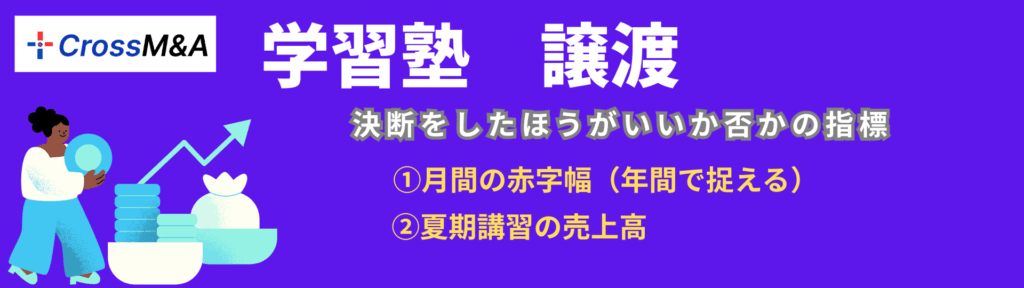
学習塾の譲渡、すなわちM&A(合併・買収)は、少子化や市場の変化が加速する現代において、多くの塾経営者が直面する可能性のある選択肢です。
「譲渡」「売却」「教室を売る」ことを考えたことがある方は、サイトを紐解いても
・なんだか難しそうだ
・色々と複雑で面倒だ
そのような感想をお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。
同時に
「売り手」と「買い手」が居るということは、そこにはやはり物品販売と同じ、需要と供給の関係性もあるということを感じ取られた方もいらっしゃることでしょう。
本記事では、学習塾の譲渡における具体的な流れ、留意点、そして成功へのポイントについて、なるべくわかりやすく、多角的な視点から詳しく解説します。事務的要素だけではなく、実例も挟みますので、最後まで読みやすい工夫を凝らしました。
1.学習塾の譲渡とは?M&Aの基本
学習塾の譲渡とは、経営者が自身の塾事業を第三者に売却することを指します。これは事業承継の一種であり、後継者不足の解消、事業の選択と集中、あるいは経営者のリタイアなど、様々な目的で行われます。
一般的なM&Aと同様に、学習塾におけるM&A案件は事業資産、顧客、従業員、ブランドなどを包括的に譲渡するケースが多いですが、中には特定の事業部門のみを譲渡するといった部分的なM&Aも存在します。
M&Aのメリット・デメリット
メリット
- 事業の継続と発展: 後継者が見つからない場合でも、事業を存続させ、さらなる発展の機会を提供できます。
- 創業者利益の獲得: 塾を売却することで、これまで築き上げてきた事業価値を金銭として受け取ることができます。
- 経営の効率化: 不採算部門の売却や、新規事業への集中など、経営資源を最適化できます。
- 従業員の雇用維持: 新たな経営者のもとで、従業員の雇用が維持される可能性が高まります。
- 個人保証からの解放: 事業売却によって、経営者が負っていた個人保証などから解放される場合があります。
【個人保証からの解放についての補足】
これは主に「会社を売る」つまり株式譲渡の場合の話です。通常、学習塾の場合は事業譲渡を用いられる場合が多いです。
事業譲渡の方が、譲受企業(買い手)にとってリスクを抑えつつ、特定の事業部門だけを取得できるメリットがあるためです。
株式譲渡の場合は、会社そのものを売ることになるため、会社の経営権は買い手側に移転します。しかしながら、売り手の個人保証は自動的に解除されるわけではありません。
そのため、買い手は、金融機関とやり取りをして売り手の個人保証を解除し、必要であれば買い手自身が新たに保証契約を結ぶという流れになります。
デメリット
- 売却価格への不満: 期待通りの価格で売却できない可能性があります。
- 従業員の反発: 譲渡に伴う不安から、従業員の士気が低下したり、離職につながったりする可能性があります。
- 顧客の離反: 新しい経営体制への不安から、生徒や保護者が離れてしまう可能性があります。
- 情報漏洩のリスク: M&Aの検討段階で情報が漏洩し、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 複雑な手続き: M&Aは法務、税務、会計など多岐にわたる専門知識が必要となり、手続きが煩雑です。
これらの「デメリット」は可能性として述べました。
しかしながら、これらいずれもが、段取り、準備、相談段階からの取り決めなどがしっかりされていれば防御できるものばかりです。
特に「人」の問題は、例えばM&Aであろうと、新規事業立ち上げであろうと、もっとも重視すべき問題です。
この問題と正面から向き合える方でしたら、デメリット要素はかなり少なくなるでしょう。
2.学習塾譲渡の金銭的側面:売上とコストの考慮
学習塾の譲渡における金銭的な側面は、経営者が最も関心を寄せる部分の一つです。売却金額がどのように計上されるのか、また物件取得時のコストがどうなるのかなど、具体的に見ていきましょう。
売却金額の計上:雑収入としての売上高
学習塾を売却して得られた金額は、会計上、基本的に雑収入として計上され、会社の売上高に含められます。これは、本業とは異なる収益源として認識されるためです。
売却金額は、塾の規模、収益性、ブランド力、保有資産(教材、設備など)、立地、教師陣の質など、様々な要素によって変動します。
売却金額が大きければ大きいほど、その年度の売上高が大きく計上されることになります。これは一見すると良いことのように思えますが、課税所得が増えるため、法人税などの税負担が増加する可能性があります。そのため、譲渡を検討する際には、税理士と連携し、税務上の影響を十分に理解しておくことが重要です。
物件取得時の敷金・保証金
学習塾が賃貸物件に入居している場合、物件取得時に敷金や保証金を支払っていることがほとんどです。これらの費用は、賃貸借契約が終了する際に、原状回復費用などを差し引いた上で、通常は全額返還される性質のものです。
そのため、廃業となり物件契約を解約する場合は、まず全額返金されることはありません。
しかし譲渡の場合は、新しい経営者がその物件の賃貸契約を引き継ぐ形となります。この場合、敷金や保証金の扱いは、売却価格に含めるのか、別途精算するのかなど、交渉によって決定されます。売却契約書にその旨を明記し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
もし、新しい経営者が物件を引き継がずに、現在の契約を解約する場合には、賃貸借契約に基づいて敷金・保証金が返還されることになります。
さて、続いては学習塾の経営状態が芳しくない場合の考え方についてです。
3.「損切り」の判断:赤字塾の早期売却の重要性
経営状況が芳しくない、特に赤字が続いている学習塾の場合、早期の売却を検討することは非常に重要です。これは、一般的に「売上を切る」という表現が使われる状況で、損失を最小限に抑えるための戦略的な判断となります。
「売上を切る」というネガティブな表現は、プラス発想的に言いかえれば、M&A市場でよく使われる「事業の選択と集中」です。
学習塾の場合、単月が収支トントンか、若干マイナスぐらいであれば、よほどのことがない限りは運営出来ます。学習塾は月間売上高の16倍の売上見込みが立つからです。

それではここで、「売上を切る」意味を知るために、具体的事例をみてましょう。
【実例(実話)】
上の内容で、学習塾は月間売上高の16倍の売上見込みが立つとありました。
しかし、
年度で回収できない赤字がある場合は、原因をしっかりと見極めて判断をしていく必要が出てきます。
例えば月間で50万円の赤字だったとします。
そうすると四半期で150万円弱のマイナスになります。
4月から年度の開始だとすると、
第1四半期の4月から6月では、講習がありません
第2四半期の7月から9月では、夏期講習があります。
第3四半期の10月から12月では、冬期講習があります。
第4四半期の1月から3月では、春期講習があります。
要するに上半期で夏期講習、下半期で冬期講習という稼ぎ頭があったとしても四半期150万、上半期で300万の赤字となれば、その分を夏期講習で賄えるかどうかがポイントになります。
同様に四半期150万、下半期で300万の赤字となれば、その分を冬期講習で賄えるかどうかがポイントです。
しかし、この借り計算は絵にかいたモチになりそうです。
何故なら売上的にここまでダウンすると、生徒数の減少または生徒がなかなか獲得できていない状況が読めるからです。
「売上を切る」というのは、とどのつまり、
売上高は月間で100万円、しかしながら月間コストが150万円、だからマイナス50万円、この状態における「月間売上高の100万円」を捨てるということです。
売上高が100万円あっても、コストが150万円であれば、運営すればするほど、赤字が拡大する状況になってしまうのです。
赤字が続く場合のダメージ
赤字が続いている学習塾は、月々に入ってくる売上高が、家賃、人件費、教材費などのコストを下回っている状態です。この状況が続けば続くほど、キャッシュフローが悪化し、資金繰りが厳しくなります。自己資金が減少するだけでなく、金融機関からの借り入れが増え、最終的には事業継続が困難になる可能性が高まります。
早期売却のメリット
赤字が続いている状況で早期に売却を判断することには、以下のようなメリットがあります。
- 損失の限定化: 損失が拡大する前に事業を手放すことで、それ以上のダメージを防ぐことができます。
- 新たなスタート: 経営者は、負のスパイラルから解放され、新たな事業や生活に集中できます。
- 従業員への影響緩和: 事業が破綻する前に売却できれば、従業員の雇用がある程度守られる可能性があります。
- 資産の保全: 残された資産(個人資産など)を、事業の失敗によって失うリスクを軽減できます。
そうすると、こんな疑問も出てきます。
「赤字の教室を買ってくれる人などいるのだろうか」
という疑問です。
いるのです。
まず、ご自身で運営されてきた学習塾で、売上が伸びなくなってしまった原因や理由などを考えてみると、
以前、しっかりと運営出来ていた時期と今とでは、何かしら変化があったはずです。
・以前はもっとアクティブにチラシを撒いたりしていた
・以前より少し体力的にダウンしている
・以前は、ちょくちょく実施していた定期テスト前イベントをやらなくなった
・以前よりも講師数を減らした
などなど、以前と比較した今の状況で、思い当たるフシがあれば、その見当は当たっているかもしれません。
このように、何かしらダウンしてしまった対応が、人が変わることで蘇る可能性はあるのです。その点をプラスに考えていくといいでしゅう。
判断の遅れが招く「深手」
この「売上を切る」という判断が遅くなればなるほど、ダメージは大きくなります。
- 評価額の低下: 赤字が続けば続くほど、塾の企業価値は低下し、売却価格が大幅に下がってしまう可能性があります。最悪の場合、買い手がつかないという事態にもなりかねません。
- 負債の増加: 資金繰りのために借入が増え、個人保証を負っている場合は、経営者個人の負担がさらに重くなります。
- 心身への負担: 事業の不振は、経営者にとって大きな精神的ストレスとなり、心身の健康を損なうことにもつながります。
夏の売上高に注目
学習塾業界において、夏期講習の売上高は非常に重要な指標となります。

もし・・・・
今年の夏の売上高が、前年や前々年と比較して明らかに悪いようなら、それは塾の経営状況が悪化している明確なサインと捉えるべきです。
この場合、
夏期講習後の落ち着いた時期に、本格的に譲渡の可能性を検討し始めるのが賢明な判断と言えるでしょう。
4.学習塾譲渡仲介のプロセスと成功の鍵
学習塾の譲渡は、専門的な知識と経験を要するプロセスです。そのため、M&A仲介会社などの専門家を活用することが成功への近道となります。
ご存じですか?不動産売買の仲介も営業力によって差が出ます
不動産の仲介では、400万円超過の不動産の場合は、速算式で金額×3%+6万円+消費税という計算です。
成功報酬として得られますので、売り手と買い手から得られます。
例えば5000万円のマンションであれば、上記の式であれば、171万6000円です。これを両方からもらえるので、343万2000円になります。
これは手数料上限ですので、営業によっては、「手数料を減額」というトークを発するかもしれません。また違う営業によっては、「手数料は減額が難しいですが・・・このような付加価値を」と提案するかもしれません。
そして、ストーリー仕立てのセールストークは、厚さでいうと、3センチから5センチぐらいにもなる資料でガッチリと説得するのです。
会社の規模よりも、営業マンの腕によって結果が異なるということです。
同様にM&Aの現場においても仲介する人間の力量によって結果が変わります。
ここで「譲渡をご検討の方に」
これだけは押さえておいてほしいポイントを御伝えしておきたいのです。
①M&Aの知識
と
②学習塾業界の知識
は
イコールではありません。
言い換えると、M&Aの知識が深くても学習塾業界の知識が浅ければM&Aを有利に進めることはできません。
通常、M&Aの仕事をしているわけですから、基本的な知識はどの会社のアドバイザーも持っています。
しかし、学習塾業界の知識を全員が同様に持っているかというと、それはないと思います。
従って、CROSS M&Aはその意味で、頭一つ抜けることで出来ていると自負しております。
譲渡仲介の一般的なプロセス
- 相談・アドバイザー選定: 譲渡の意向を固めたら、信頼できるM&A仲介会社やアドバイザーに相談します。
- 企業価値評価: 仲介会社が、塾の財務状況、事業内容、将来性などを分析し、客観的な企業価値を評価します。
- M&A戦略の立案: 譲渡の目的、希望条件、相手先のタイプなどを明確にし、戦略を立案します。
- 候補先の探索・選定: 仲介会社が持つネットワークを活用し、潜在的な買い手候補を探します。
- 秘密保持契約の締結: 候補先が絞られたら、情報の開示に先立ち秘密保持契約を締結します。
- トップ面談: 売り手と買い手の経営者が直接面談し、互いの理念や展望を確認します。
- 基本合意書の締結: 売却価格や条件、今後のスケジュールなどについて基本的な合意を形成し、基本合意書を締結します。
- デューデリジェンス(詳細調査): 買い手側が、塾の財務、法務、事業内容などを詳細に調査します。
- 最終条件交渉・最終契約書の締結: デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉を行い、最終契約書を締結します。
- クロージング(譲渡実行): 契約に基づき、事業資産や株式の引き渡し、代金の決済などが行われます。
☆何かが足りない一般路線!
やはり一般的な内容ですと、クロージング後の、アフターフォロー、アフターサービスはないです。
「売ったらおしまい」というスタンスではないクロスマの徹底アフターフォローつきのサービスを是非ご検討ください。
成功の鍵を握る要素
- 早期の決断と準備: 譲渡を検討し始めたら、できるだけ早く準備に着手することが重要です。資料の整理や経営状況の改善など、譲渡に向けた準備を怠らないようにしましょう。
- 透明性の確保: 買い手に対して、塾の経営状況を正確かつ正直に開示することが信頼関係構築の基本です。
- 専門家との連携: M&A仲介会社、弁護士、税理士など、各分野の専門家と密に連携し、適切なアドバイスを受けることが成功に不可欠です。
- 従業員への配慮: 譲渡のプロセスにおいて、従業員の不安を軽減するための情報共有やケアを怠らないようにしましょう。
- 強みの明確化: 塾の強み(特定の指導科目、合格実績、地域密着度、独自の教材など)を明確にし、買い手にアピールすることが、より良い条件での売却につながります。
5.学習塾譲渡の「明るい要素」:新たな可能性と未来
ここまで、学習塾の譲渡における現実的な課題やリスクについて触れてきましたが、譲渡は決して「負け」の選択ではありません。むしろ、新たな可能性を切り開き、未来を創造するための「明るい要素」*をたくさん含んでいます。
経営者の新たなステージ
長年にわたり学習塾を経営してきた方にとって、譲渡は人生の新たなステージへの転換点となります。
- リタイアメント: 安心してリタイアし、趣味や家族との時間を充実させることができます。
- 新たな挑戦: 譲渡によって得た資金や時間を使って、新しい事業を立ち上げたり、別の分野でのキャリアを追求したりすることも可能です。
- 健康と時間の確保: 経営のプレッシャーから解放され、心身の健康を取り戻し、ゆとりのある生活を送ることができます。
事業のさらなる発展とシナジー効果
買収する側にとっても、学習塾の買収は大きなメリットをもたらします。
- 事業規模の拡大: 既存の事業とのシナジー効果を生み出し、事業規模を拡大できます。
- 新規地域への進出: 未開拓の地域に進出する足がかりとなります。
- ノウハウの獲得: 譲渡される塾が持つ独自の指導ノウハウやカリキュラム、優秀な教師陣などを獲得できます。
- 顧客基盤の獲得: 既存の顧客基盤を一気に手に入れることで、新規顧客開拓の時間とコストを削減できます。
- ブランド力の向上: 異なるブランドを統合することで、より強力な教育ブランドを築き上げることができます。
例えば、地域密着型の小規模塾が、大手予備校グループに譲渡されることで、大手グループの持つ豊富な教材やIT教育システム、マーケティング力などを活用し、これまでは実現できなかった規模のサービスを提供できるようになるかもしれません。また、大手グループにとっても、小規模塾が持つ地域に根ざした生徒や保護者との関係性、きめ細やかな指導ノウハウは、新たな価値創造の源泉となり得ます。
教育機会の維持と向上
少子化が進む中でも、地域社会にとって学習塾は重要な教育インフラです。後継者不足などで閉鎖の危機に瀕していた塾が、新たな経営者に引き継がれることで、その地域の子どもたちが学習機会を失わずに済むという側面もあります。さらに、新たな経営者のもとでより質の高い教育サービスが提供されるようになれば、地域全体の教育レベルの向上にも貢献できます。
従業員の新たな活躍の場
譲渡によって、従業員は新たな経営体制のもとで、より安定した雇用や、スキルアップの機会を得られる可能性があります。特に、大手企業グループに引き継がれる場合、これまでにはなかったキャリアパスや研修制度が提供されることも期待できます。
6.まとめ:譲渡は戦略的投資
学習塾の譲渡は、単なる事業の「手放し」ではありません。それは、経営者、従業員、そして生徒たちにとって、戦略的な投資と言えます。
もちろん、そこには金銭的な考慮、赤字経営における早期決断の必要性、そして複雑な手続きといった現実的な課題が伴います。しかし、これらの課題に対して真摯に向き合い、信頼できる専門家のサポートを得ることで、譲渡は単なる損失の最小化に留まらず、事業のさらなる発展、経営者の新たな人生のスタート、そして地域社会への貢献といった、数多くの「明るい要素」をもたらす可能性を秘めています。
特に、経営状況が悪化している場合は、勇気を持って「売上を切る」という判断を早期に行うことが、最終的なダメージを最小限に抑える上で不可欠です。
そして、夏期講習の売上推移など、客観的な指標に目を向け、適切なタイミングで行動を起こすことが成功への鍵となります。
学習塾の譲渡は、複雑で感情的な側面も含むデリケートなプロセスです。しかし、その先に広がる新たな可能性に目を向け、ポジティブな姿勢で取り組むことが、最良の結果へとつながるでしょう。もし今、学習塾の譲渡についてお考えであれば、まずは一歩踏み出し、専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡