塾のM&A動向を徹底分析!「譲渡」が「買収」の5倍検索される驚きの背景と未来予測
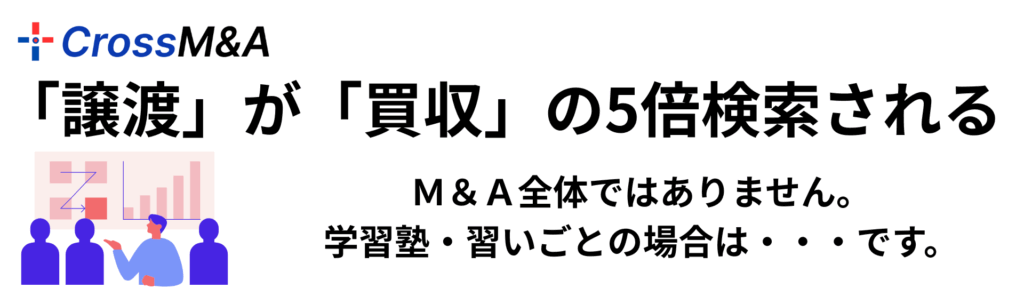
はじめに
塾業界におけるM&A(合併・買収)は、近年ますます活発化しています。その中で、興味深いデータがあります。
「塾の譲渡」というキーワードの検索数が、「塾の買収」というキーワードの検索数に比べ、およそ5倍も多いという事実です。
これは一体何を意味するのでしょうか。本稿では、この検索数の差が示す塾業界の現状を深掘りし、なぜ「譲渡」を検討する塾経営者がこれほど多いのか、その背景にある要因を多角的に分析します。さらに、2025年、2026年、2027年と、今後の塾業界のM&A動向がどのように推移していくのかについても予測を試みます。
「塾の譲渡」が「買収」の5倍検索される衝撃の真実
「塾の譲渡」と「塾の買収」という検索キーワードの比較は、現在の塾業界が抱える課題と、それに対する経営者の意識を鮮明に映し出しています。
単純に考えれば、事業を拡大したい、あるいは新規参入したいと考える「買収」側のニーズも相当数あるはずですが、実際には「譲渡」を検討する側の情報収集意欲が圧倒的に高いことが分かります。
この現象の裏には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
ここで誤解が生じないよう補足しておきます。
この現象は、『M&A全体』ではありません。
弊社が専門として実施している学習塾・習いごとという業種においてはという前提で以下をお読みください。
1. 経営者の高齢化と後継者不足の深刻化
最も大きな要因の一つとして挙げられるのが、塾経営者の高齢化とそれに伴う後継者不足の深刻化です。
長年地域に根差して塾を経営してきた経営者の多くが、引退時期を迎えつつあります。
しかし、少子化や多様な働き方の進展により、子供が事業を継承しないケースや、適切な後継者が見つからないケースが急増しています。
これまで築き上げてきた塾を閉鎖するのではなく、その教育理念や生徒たちへの思いを次世代に引き継ぎたいと願う経営者にとって、事業譲渡は最も現実的な選択肢となります。
学習塾・習いごとで譲渡を検討しているオーナーは、2つの側面で譲渡についての情報を収集しているのです。
一つは、果たして塾・習いごと教室は売れるのだろうかという純粋な疑問の答えを探すために。
もう一つは、「塾の譲渡」を早々に実行するため(またはその時期が来たという判断のため)に譲渡に関する情報を熱心に収集しているのです。
・・・・まさか「自分が閉鎖とか、売却、譲渡を考えるなんて」・・・長年、生徒と保護者のために地域貢献してこられたオーナーは、今の自分の考えが頭にふつふつと沸いてしまったことさえも、いまだ信じがたい思いかもしれません。
お店をつくることや、教室を開校することというのは、その当時一大決心だったはずです。荒波をいくつも超えて運営してきたのですから、色々な思いが交錯することでしょう。
しかしながら、現実の売上高の数字や、実際の自分自身の体力が以前より劣っている様子などを冷静に考えたとき、寂しいかもしれませんが、そう考えるのは特段不自然なことではありません。
2. 少子化による生徒数の減少と経営環境の厳しさ
日本の少子化は深刻な問題であり、学習塾業界もその影響を強く受けています。
かつては子供の数が増え続ける時代の中で、塾も自然と成長することができました。
しかし、現在の日本では、年々子供の数が減少し、それに伴い塾の生徒数も減少傾向にあります。特に、個人経営の小規模塾や、特定の地域に特化した塾は、生徒数の減少が直接的に経営を圧迫します。
生徒数減少への対応策として、新たな集客戦略の立案や教育内容の改革が求められますが、これには多大な時間とコスト、そして経営手腕が必要です。資金力や人材に限りがある塾にとって、単独での生き残りは非常に困難な状況となっています。
このような厳しい経営環境に直面し、事業の継続が困難であると判断した経営者が、事業譲渡によって新たな活路を見出そうとしているのです。
3. 大手・中堅塾との競争激化と差別化の困難さ
塾業界は、大手予備校や進学塾、さらにはオンライン学習サービスなど、多様な教育事業者がひしめき合う激戦区です。
大手塾は、資本力やブランド力、充実したカリキュラム、多様な学習ツールなどを武器に、生徒獲得競争を優位に進めています。
また、AIを活用した個別最適化学習や、オンラインでの双方向授業など、テクノロジーを駆使した新しい学習形態も台頭しており、これらに対応できない塾は生徒離れのリスクに直面します。
特に、地域密着型の個人塾は、大手塾のような大規模な広告宣伝や最新技術の導入が難しい現状があります。独自の強みや特色を打ち出し、差別化を図ろうと努力しても、その効果が限定的であると感じる経営者も少なくありません。
このような状況下で、将来的な成長が見込めないと判断した経営者が、事業譲渡を検討する傾向が強まっています。
4. 事業承継型M&Aへの意識の高まり
近年は、事業売却に対しての理解が急速に高まりつつあります。
事業売却はその事業を捨てることではなく、
譲渡側の思いや希望が汲み取れる仕組みが確立してきているため、
譲渡側とすれば
①投入すべき資本と選択を集中させることができるメリット
②事業をただ売ることが目的ではなく「事業承継」という明確な意思が実現できる
そんな観点から、事業売却が進めやすくなっています。
事業売却としてではなく、事業承継の一環としてM&Aを捉えることができることで、気持ちにのしかかる「長年培ったきた思い」「長年地域貢献してきたという自負」で、自分を責める必要がなくなります。
気持ちにのしかかる思いというのは、これまで築き上げてきた塾のブランドや教育理念、生徒や保護者との関係性を大切にしたいという思いがあるためです。
しかしながら、CROSS M&A(クロスマ)の実例でも、他所の実際例を伺ってもオーナーの思いが承継されていることが多いです。買収する側が譲渡オーナーの教育哲学を理解し、さらに発展させてくれているケースが非常に多いのです。
また、その土台をしっかりと承継したほうが、既存の生徒・保護者・講師たちもやりやすいため、買収側が急激に変更するリスクは負わない傾向です。
勿論、譲渡が完了して、1年、2年、3年と経過していけば、そこに存在する生徒・保護者などの顧客や、講師たちもメンバーの自然的な入れ替えがあることでしょう。
そのときには、内部も少しずつ変化しているはずですし、
教育業界全体も変化していきますので、その流れはきっと誰にも止めることはできないものとして、元オーナーも受け入れていくようにしましょう。
私たちM&A仲介会社や専門家も、大きな時代変化の中で、事業承継型M&Aの重要性を強調しております。
譲渡希望者と買収希望者の間で、単なる金銭的な条件だけでなく、塾の教育方針や理念の合致も重視するマッチングが進められています。これにより、譲渡側は安心して事業を任せられる相手を探すことができ、「塾の譲渡」に関する情報収集に積極的になっていると考えられます。
さて、続いては、「今後はどうなるのか?」という部分にフォーカスをあてます。
以下の記事を読まれるまでに
「M&A市場のパラダイム転換!「金利上昇」をきっかけに売り手市場から買い手市場へ!」
という記事を是非一度ご確認ください。
それでは、本論に行きます。
2025年、2026年、2027年、塾業界M&Aの今後はどうなる?
前述の要因を踏まえると、塾業界のM&Aは今後も活発に推移していくと予測されます。特に2025年から2027年にかけては、以下のトレンドが顕著になるでしょう。
2025年:高齢化と後継者不足がM&Aを加速させる年
2025年は、団塊の世代ジュニアが50代半ばに差し掛かり、その親世代である団塊の世代が70代後半から80代に突入する時期です。この世代交代の波は、多くの個人塾経営者に引退の時期を意識させ、後継者問題がより一層深刻化することが予想されます。
「塾の譲渡」に関する検索数は、依然として高い水準を維持し、実際にM&Aを実行する件数も増加するでしょう。特に、長年地域で信頼を築いてきた優良な個人塾の譲渡案件が増加する可能性があります。買い手側は、生徒基盤が安定しており、地域からの信頼が厚い塾を積極的に求める傾向が強まるでしょう。
また、少子化の影響で生徒獲得競争が激化する中、単独での生き残りに限界を感じる小規模塾の譲渡ニーズも高まります。この年は、「事業継続の選択肢としてのM&A」がより強く意識される年となるでしょう。
2026年:オンライン教育との融合と専門化が進む年
2026年には、塾業界におけるオンライン教育の浸透がさらに進み、M&Aの形態にも変化が現れると予測されます。オンライン学習プラットフォームを持つ企業が、オフラインの塾を買収し、そのノウハウや生徒基盤を獲得する動きが活発化する可能性があります。逆に、オフラインの塾が、オンライン教育の技術やコンテンツを持つ企業との提携や買収を模索するケースも出てくるでしょう。
また、学習塾の専門化もM&Aの重要なトレンドとなります。特定の教科に特化した塾、難関校受験に強みを持つ塾、あるいは不登校支援や発達障がい児教育に特化した塾など、ニッチな分野で確固たる地位を築いている塾が、その専門性を評価されて買収されるケースが増えるでしょう。これは、多様化する教育ニーズに対応するため、大手塾が自社のサービスラインナップを強化する目的で行われることも考えられます。
2027年:M&Aを通じた新たな教育モデルの創出が進む年
2027年には、M&Aが単なる事業承継や規模拡大のためだけでなく、新たな教育モデルやサービスの創出のための手段として、より戦略的に活用されるようになると予測されます。
例えば、学習塾とプログラミングスクール、あるいは学習塾とロボット教室といった、異業種間のM&Aが増加する可能性があります。これは、AIやSTEAM教育といった新しい学習トレンドに対応するため、あるいは子供たちの多様な才能を伸ばすための総合的な教育サービスを提供するためです。
また、地方の過疎化が進む中で、地域に根差した塾が、地域の教育インフラを維持・発展させるために、自治体やNPO法人、あるいは地元企業との連携を模索し、M&Aを通じてその連携を強化する動きも出てくるかもしれません。
この頃には、M&Aのプロセスもより洗練され、売却側、買収側双方にとって、より円滑で納得感のあるM&Aが実現できるようになるでしょう。M&Aは、塾業界が少子化や競争激化といった課題を乗り越え、持続的に発展していくための重要な手段として、その役割をさらに拡大していくと予想されます。
まとめ
「塾の譲渡」が「塾の買収」の5倍検索されるというデータは、塾業界が現在直面している経営者の高齢化、後継者不足、少子化、そして激しい競争という複合的な課題を明確に示しています。しかし、これは単なる困難を示すものではなく、M&Aという選択肢を通じて、多くの塾が新たな活路を見出し、その教育理念や生徒たちへの情熱を次世代へと引き継ごうとしている証でもあります。
今後数年、塾業界のM&Aはさらに加速し、高齢化による事業承継型M&Aの増加、オンライン教育との融合、そして専門性の高い塾の需要増といったトレンドが顕著になるでしょう。最終的には、M&Aが新たな教育モデルを創出し、塾業界全体の活性化に貢献していくことが期待されます。塾経営者にとって、M&Aは事業の継続と発展を実現するための、有力な選択肢の一つとして、今後ますますその重要性を増していくに違いありません。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡