塾売却、今こそ決断の夏!生徒数で未来を読み解く戦略的視点
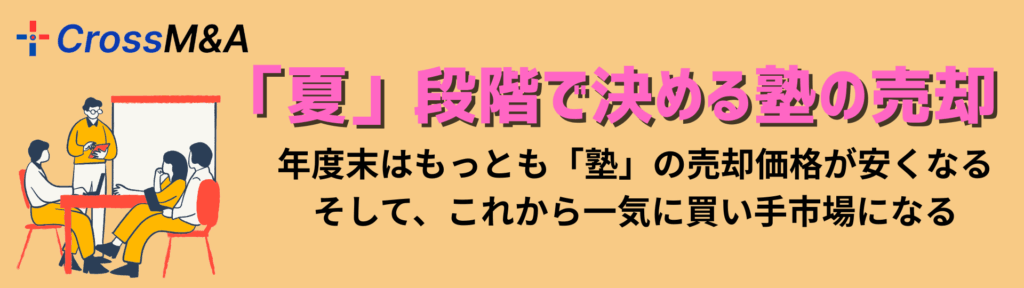
塾の売却について、「年度末」は多くの人が考える時期ですが、その時期の売却は需要と供給の関係から買い手有利になる傾向があります。
むしろ、夏の段階で「非受験生」の生徒数、特に高校2年生、中学2年生、そして中学受験を考えている小学5年生の人数を確認することが、売却決断の重要な指標となります。
「ときに経営はドライにならざるを得ない」という言葉が示すように、感情に流されず、数字に基づいて冷静に判断することが不可欠です。
今まさに夏を迎え、この時期に塾の売却について考えることは、非常に理にかなっています。
本日のテーマは、
塾売却、今こそ決断の夏!生徒数で未来を読み解く戦略的視点
学習塾の経営者の皆様、日々の生徒指導、募集活動、そして経営の舵取り、本当にお疲れ様です。
少子化が進む現代において、学習塾経営は決して平坦な道ではありません。時には事業の継続性について深く考えることもあるでしょう。その中で、「塾の売却」という選択肢が頭をよぎることもあるかもしれません。
以前であれば、小規模、中規模の会社や事業などは、潮時と思えば、「閉鎖」「閉店」「閉校」という選択のみでしたが、今では、まずは「譲渡」ということを考える人も多くなっています。
それだけ、M&A、譲渡、買収が一般的になりつつあるということです。
さて、とは言えM&Aと一言で言っても、そのタイミングや判断基準は非常に重要です。
多くの経営者が考える「年度末」での売却は、果たして本当に最善の選択なのでしょうか?
実は、塾経営者は奉仕の精神、滅私奉公精神にあふれた人が多いです。そのため、年度末では自分が不利になることを「知っていながら」も年度末の学年入れ替わりのタイミングにすることが多いのです。
年度末売却の落とし穴:なぜ買い手有利になるのか?
「年度末」という時期は、多くの学習塾にとって年度の締めくくりであり、新年度の準備期間でもあります。そのため、この時期に事業の売却を検討する経営者が増える傾向にあります。これは、「誰もが考える」タイミングであるがゆえに、ある現象を引き起こします。それが「需要と供給のバランスの微妙な崩れ」です。
年度末に売却希望の塾が増えれば、その分、市場には多くの売却案件が出回ります。一方で、塾の買収を検討している企業や個人は、その中からより条件の良い物件を選ぶことができます。
軽く2行ぐらいで書いてしまっていますが、実はこれ、考えてみるとけっこう売り手の不利度合いは大きくなります。
まず目を閉じてみてください。
そして売ろうとする案件は、日本にひとつ、世界にひとつ・・です。例えば譲渡しようとする教室が複数あろうと、その場所で、今の講師陣容で、今の電話番号を使って、運営している教室はたった「ひとつ」しかありません。
本当であれば、その「ひとつ」しかない案件特性は、売り手にとって有利なのです。
しかしながら、年度末になると、その案件に「似たような条件」または「もっと好条件」の案件が数の論理からして出やすくなる、目立ってきますので、買い手候補は自分の案件だけをめがけて走ってきてくれればいいのですが、実はそうではない状況が生まれやすくなります。
したがって、有利性が失われやすくなる。それが年度末なのです。
そして、売り手にとって年度を超えるということは、新年度のスタートということになりますので、年度末には決着をつけたい。その意識が強くなるほどに価格交渉で妥協が生まれます。
結果として、売却希望者側は買い手側の言いなりになりやすく、提示される価格も買い手にとって有利なものになりがちです。
例えば、物件が豊富にある中で、買い手は「他にも良い塾があるから、この価格では買わない」といった交渉がしやすくなります。
売り手としては、年度末という区切りで手放したい気持ちが先行し、多少不利な条件でも受け入れてしまう、という状況に陥りやすいのです。これは、不動産市場における「繁忙期」または、と似た現象と言えるでしょう。
誰もが売りたい、買いたいと思う時期は、往々にして価格競争が激化し、不利な状況が生まれる可能性があるのです。
しかし、この現象は、ある意味仕方のないことなのかもしれません。
塾のオーナーはその点の理屈はよく理解していて、それでも尚年度末までという意識が強く働きます。それは「受験」があるからです。受験生たちの合否動向です。
結果が12月、1月、2月、3月ですので、その最後の四半期が生徒たち、保護者との一つの区切りとして捉えがちです。
この塾を手放すにしても最後の受験生たちはきちんと結果を見届けたいという思いがあるのです。
とは言え、ときに経営はドライな判断をせざるを得ません。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
当方が運営している地域に、県下でも1・2を争う有名な塾があります。(ありました。)
昨年、2月に急遽、その地域の教室を閉校しました。
「3月ではなく、2月」ということろに意思を感じます。
近隣の生徒さんたちは、すでに11月、12月にはうごめきだして、当方の塾にも流れ込んできましたので、多分2月閉校を9月とか夏の終わりには全体告知していたのでしょう。
しかも、2月のラスト日ではなく、途中で全部がらんと片付いて誰もいなくなりました。徹底しています。
その塾は他にも多く教室を持っているのですが、もう一か所違う箇所で同時にクローズしていたようです。こちらも2月半ばには終わってしまっていました。
従業員、講師、生徒(受験生ではない非受験生も学年末テストがありましたので、けっこう大変だったのではないでしょうか)などもあったとしても経営判断として、ビシッと断行していました。
これの良し悪しは議論できません。
何故なら、継続するのもしないのも経営判断だからです。経営判断はときとして重いものがありますが、一番考えなくてはならないのは、従業員、他の教室の運営、傷を浅くということだと思います。
そこに、「今、閉校したら生徒がかわいそうだ」という感覚を持っていたら、自社の社員が路頭に迷うことになりかねません。自社が業績悪化店舗を見て見ぬ振りしたら、母体が危なくなります。
卵ではなく、鶏を守る、それが経営と言っても決して言い過ぎだ!とは、同じ経営の立場としては口が裂けても言えません。
さて、続いては かなりリアルで生々しく、判断したほうがいいのかを直感的に感じ取っていただくための項目です。
夏に「非受験生」に着目する理由:冷静な判断の要
では、いつが最適な売却決断時期なのでしょうか? 結論から言えば、それは「夏」、そして「非受験生の生徒数」に注目することです。
なぜ夏なのでしょうか? 夏は多くの塾にとって、夏期講習などのイベントがある一方で、新年度からの受験生以外の生徒が、本格的に受験モードに突入する前の比較的落ち着いた時期と言えます。
この時期だからこそ、冷静に塾の現状を分析し、将来的な生徒数の推移を見極めることができるのです。
特に重要なのが、「非受験生」の生徒数です。具体的には、以下の学年の生徒数に着目してください。
※以下の内容はものすごく重要です。
- 高校2年生:来年度には受験生となる学年です。この学年の生徒数が充実しているか否かは、来年度以降の塾の売上を大きく左右します。高2生が多いということは、来年度の入試を乗り越えた後も、高3生として塾に残る可能性が高いことを意味します。彼らは塾の未来の収益源と言えるでしょう。
- 中学2年生:こちらも同様に来年度には受験生となる学年です。地域の高校受験に大きく関わってくるため、中2生の数は塾の安定性を測る上で非常に重要です。彼らがそのまま中3生として塾に残れば、安定的な収益が見込めます。
- 小学5年生(中学受験を検討している場合):中学受験は年々増加傾向にあり、小5生は翌年には受験生となります。この層の生徒数が厚い塾は、中学受験塾としての価値が高いと判断されます。
これらの「非受験生」の生徒数は、塾の将来的な収益力を示す重要な指標となります。受験生は毎年入れ替わりますが、非受験生は来年度以降の売上を予測するための具体的な数字となるからです。
夏にこれらの生徒数を把握し、もしその数が思わしくない、あるいは減少傾向にあるのであれば、それは売却を真剣に検討する時期が来ているというサインかもしれません。
反対に、この層の生徒が充実しているのであれば、さらなる事業拡大や、より良い条件での売却を目指すことも可能でしょう。
「サイン・・・かもしれません」と控えめに書きましたが、本音を言えば・・・検討、決断すべきだと思います。
経営はときにドライにならざるを得ない:感情を排した客観的視点
「ときに経営はドライにならざるを得ない」。
この言葉は、学習塾経営において非常に重要な視点を提供します。
塾は、生徒の成長を間近で見守る喜びや、地域社会への貢献といった、感情的な側面が強い事業です。しかし、事業を継続し、さらに発展させていくためには、感情だけに流されず、客観的なデータに基づいて判断を下す「ドライな」視点も不可欠です。
生徒への愛情や、これまで築き上げてきた塾への思い入れは、素晴らしいものです。
しかし、それらが経営判断を曇らせてしまうことがあります。例えば、「もう少し頑張れば、きっと生徒は増えるはず」「ここまで続けてきたのだから、今手放すのは忍びない」といった感情は、時に現実的な判断を阻害する要因となり得ます。
売却という選択は、決して「諦め」ではありません。
むしろ、より良い形で事業を次世代に引き継ぎ、生徒たちが学ぶ場を守るための、戦略的な一歩と捉えるべきです。そのためには、以下の点を冷静に評価する必要があります。
- 生徒数の推移と将来予測:特に前述の非受験生の動向を重視します。
- 財務状況:収益性、キャッシュフロー、負債の有無などを客観的に評価します。
- 競合塾の状況:周辺地域の競合塾の動向、生徒募集状況などを分析します。
- 自身の健康状態や年齢:経営者自身の体力や年齢も、事業継続の重要な要素です。
- 後継者の有無:もし後継者がいない場合、事業承継の選択肢として売却を検討するのは自然な流れです。
これらの要素を感情を排して分析し、もし事業の継続に課題があると感じた場合、あるいは自身のライフプランとの兼ね合いで新たな道を考える時期に来ていると感じたならば、売却を真剣に検討する時です。経営判断において、「損切り」という言葉があるように、時には引くこともまた、大きな戦略の一つなのです。
今、考えることが最良の選択:後悔しないためのアクション
ここまで述べてきたように、塾の売却を考える上で「今」、つまり夏に具体的な行動を起こすことは非常に重要です。
なぜなら、年度末に売却を検討し始めると、時間的な制約から焦りが生じ、不利な条件を飲んでしまう可能性が高まるからです。夏に検討を開始すれば、十分な時間をかけて以下のプロセスを進めることができます。
- 現状把握と分析:
- 非受験生(高2、中2、小5)の生徒数を正確に把握し、過去の推移と比較します。
- 直近数年間の財務諸表(損益計算書、貸借対照表)を準備し、収益性や資産状況を把握します。
- 塾の強み(立地、指導内容、実績など)と弱み(生徒募集の課題、老朽化した設備など)を洗い出します。
- 近隣の競合塾の状況や、地域の人口動態などを調査します。
- 売却の選択肢の検討:
- M&A仲介会社への相談:専門知識を持つM&A仲介会社に相談することで、公正な評価や買い手探し、交渉のサポートを受けることができます。
- 事業承継の専門家への相談:売却だけでなく、親族内承継や従業員への承継といった選択肢も視野に入れる場合は、事業承継の専門家も有効です。
- 売却準備の開始:
- 財務状況の整理:買収側が評価しやすいように、財務資料を分かりやすく整理します。
- 契約書の整備:生徒や講師との契約状況を確認し、必要に応じて整理します。
- 設備の見直し:老朽化した設備があれば、必要に応じて修繕を検討します。
これらの準備を夏から始めることで、焦らずにじっくりと買い手を探し、より有利な条件で交渉を進めることが可能になります。もし売却を決断した場合、その手続きには一定の期間を要します。年度末に駆け込みで売却活動を始めると、準備不足や時間的制約から、望まない結果に繋がることも少なくありません。
まずは、「現状把握」からです。
現状把握というと、これも重く感じるかもしれませんが、シンプルに今、この夏の時期に「高2、中2、中学受験の小5」がいるのかいないのか!
これだけです。
・今はいないけれど、今は少ないけれど、きっとこのあと入ってくる
・今、受験生がそれなりに多いから先のことは考えなくてもいい
わかります。わかります。
ですが、それはとてもリスキーです。現状把握から逃げずに冷静に頭数を数えてみましょう。
1桁人数、3人、4人しかいない・・・
そんな状態でしたら、「即時」考えるべきだと思います。
結び:あなたの塾の価値を最大化するために
学習塾の売却は、経営者にとって人生における大きな決断の一つです。生徒たちの未来を考え、教え子たちとの思い出を大切にする気持ちは、何よりも尊いものです。しかし、その上で、ご自身の人生、そして塾の事業の継続性を冷静に見つめ、最適な時期に最適な判断を下すことが、結果として塾の価値を最大化し、次の世代へと円滑に引き継ぐことにも繋がります。
今、この夏に、改めてご自身の塾の状況を見つめ直し、特に非受験生の生徒数という具体的な数字に目を向けてみてください。そこに、あなたの塾の未来、そして売却決断の時期を判断するための重要なヒントが隠されています。
感情に流されず、冷静かつ戦略的に、あなたの塾の最良の選択を見つけてください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡