人が変わると業績が変わる:学習塾の買収、そして人材が織りなす成功の秘訣
学習塾業界におけるM&Aが活発化する中、「人が変わると業績が変わる」という現実は、多くの経営者が直面するテーマです。
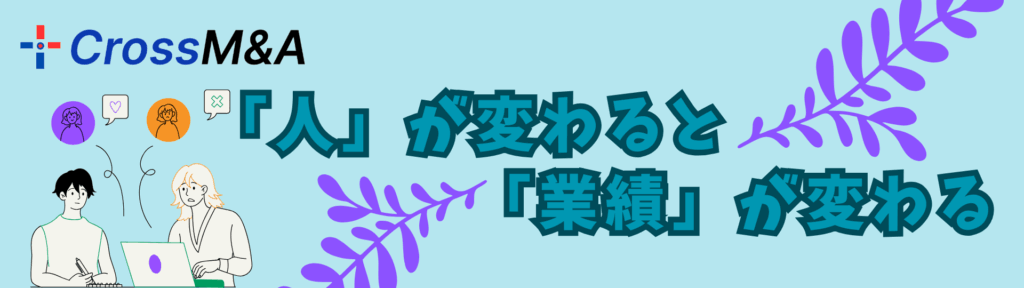
特に、買収後の業績向上を目指す上で、教室長や講師といった「人」の採用・育成は、単なるコストではなく、未来への投資としてその重要性が増しています。
本稿では、「学習塾 買収 社員募集 講師募集」というキーワードを軸に、人の持つ可能性と、それが業績に与える影響について、生々しい現実を交えながら深掘りしていきます。
生々しい現実というのは、とどのつまり、クロスマのアドバイザーであり、現学習塾のオーナーでもあるK部長の実例・実話込みの内容です。
この前文の中でM&Aで買収を考えている方に答えをお伝えするとしたら、以下のことになります。
「もし、買収したときに教室長がいない、講師が継続してくれないかも」という事態であっても慌てずに対応していきましょう。
そして、もしかしたらそのほうが、業績UPの近道になるかもしれません。
その意味は以下をご確認いただき、勇気を出してみてください。
実際のことですし、想像で伝えている内容ではありませんので。
教室長:業界経験者の落とし穴と未経験者の爆発力
学習塾の経営において、教室長の存在は教室の顔であり、業績を左右する最重要人物と言っても過言ではありません。
しかし、彼らの採用において、多くの経営者が陥りがちな落とし穴があります。
業界経験者が良い人材とは限らない理由
「業界経験者の方が即戦力になる」という考えは、一見理にかなっているように思えます。何か募集記事を書くときにも「経験者優遇」などの文字が躍っていることもあります。
これは応募する側がもし経験者であれば、琴線に触れるワードですし、「優遇」という文字に期待感を抱くことでしょう。
それが故に、この甘美なキーワードを入れた募集では、経験者からの応募も必然的にフックにかかってくるのです。
確かに、彼らは塾業界の仕組みや指導ノウハウをすでに持ち合わせており、OJTの時間を大幅に短縮できると期待されます。しかし、ここに大きな落とし穴があるのです。
①既存の成功体験への固執
長年業界に身を置いた経験者は、過去の成功体験に固執しがちです。
時代は常に変化しており、子供たちの学習スタイルや保護者のニーズも多様化しています。過去のやり方が通用しなくなっても、それを変えることに抵抗を感じたり、新しい手法を取り入れることに躊躇したりするケースが散見されます。
結果として、教室の成長が停滞し、むしろ業績を悪化させる可能性すらあります。
②新しい文化への適応の難しさ
買収された塾の場合、新しい経営体制の下で、これまでの文化や方針が大きく変わることがあります。業界経験者の中には、長年染み付いた自身のやり方を変えられない、あるいは新しい企業文化に馴染めない人もいます。これは、組織全体の足並みを乱し、教室の運営に支障をきたす原因となります。
③業界の常識という名の思考停止
業界経験者は、ともすれば業界内の「常識」にとらわれすぎることがあります。しかし、その常識が、実はイノベーションを阻害する要因になっていることも少なくありません。例えば、「塾はこうあるべきだ」「このやり方が一番効率的だ」といった固定観念が、新しい発想やサービスを生み出す妨げとなるのです。
【実例(実話)】
仕事柄も当然ですが、自ら15年間で1500人以上の面接を行ってきました。多いときには、一回の募集広告で100名以上のエントリーがあり、そのやり取りで業務が忙殺されてしまう事態に陥ったこともあります。
基本的には、zoomであれ、実際の教室内面接であれ、面接をすることによって、自分の勘のようなものが研ぎ澄まされて参ります。
結論から申して、目を見張る業績を上げた教室長は「全員」業界未経験者でした。
これも偽りのない事実で、何故なのかを検証したときに、上記の①②③のいずれかのケースだったということです。
元販売員、元法人営業、元学校事務、元化学メーカー、元電話オペレーター・・・こうやって書きながら過去を紐解いていくと、なるほど、業界経験者じゃない人が業績を上げているではないかと我ながら再確認のつもりではあっても驚きながら書いています。
業界未経験者が爆発的業績を残す可能性
一方、業界未経験の教室長候補は、育成に時間がかかると敬遠されがちです。しかし、彼らこそが、時に爆発的な業績を残す可能性を秘めているのです。
もし、今学習塾の買収を検討されている方はこの記事の真偽を私が運営する学習塾の業績で確認してもらってもよいです。
何故なのだろう?とまじめに考えてみました。
既存の枠にとらわれない柔軟な発想
業界未経験者は、既存の学習塾の「常識」にとらわれることがありません。彼らは顧客の視点に立ち、真っ白なキャンバスに自由にアイデアを描くことができます。例えば、異業種での経験から得たマーケティング手法や顧客サービス、人材育成のノウハウを学習塾に応用することで、これまでの塾にはなかった新しい価値を生み出すことがあります。
成長意欲と吸収力
業界未経験者は、自身の知識やスキルが足りないことを自覚しているため、成長意欲が非常に高い傾向にあります。新しいことを学ぶことに貪欲で、積極的に研修を受けたり、周囲の意見に耳を傾けたりします。この高い吸収力と成長意欲が、短期間での劇的な成長を可能にし、結果として教室の業績を大きく向上させる要因となります。
素直さと謙虚さ
業界未経験者は、成功体験に縛られない分、素直に新しい知識や指示を受け入れ、実践することができます。また、自分の意見を主張しつつも、周囲のアドバイスに謙虚に耳を傾ける姿勢は、チーム全体の協力体制を築き、教室を活性化させる上で非常に重要です。
なぜ、このようなことが起こるのか!?
この現象の根底には、このように文字として書いてみると・・・
「適応能力」と「創造性」という二つの要素が大きく関わっていることがわかります。
業界経験者は、これまでの成功体験が「学習性無力感」に繋がり、変化への適応を阻害する場合があります。
一方、業界未経験者は、既存の枠組みがないため、新たな環境や課題に対して柔軟に対応し、既成概念にとらわれない発想で創造的な解決策を生み出すことができます。
彼らは、失敗を恐れずに新しいことに挑戦し、その過程で得られた経験を糧に成長していく強さを持っています。
【実例(実話)】
ある時、クロスマのアドバイザーは、募集広告で「経験者優遇」の内容を一切書かず、
募集広告担当者の方には、
「未経験で素直で、全く業種が違ってもいいので営業をやっていた人」をターゲットにしたいという相談をしました。
「そうすると、最も熱度が高い人たちを避けてオファーすることになりますよ」
「いえ、構いません」
ということで、募集広告を開始しました。
これはヒットだったと思います。
「未経験なのですが自分は大丈夫でしょうか?」というちょっと自信なさげに伝えてくる人もいましたが、それなりに面接することが出来ました。
この時の募集媒体コストは税込みで55万円です。しかしながら、その後2年目のときには、その教室長は爆発的業績をあげてくれましたので、この55万円、そのときはけっこう痛い出費ではありましたが、成功したと言えます。
ちなみにオファーをかけていない方からの応募は当時4分の3が業界経験者でした。zoomや実際に会ってお話しましたが、皆さん、過去の職務経歴を一生懸命伝えてくださいました。
しかし、
「業績を上げるための方程式みたいなものはお持ちですか」
という質問を投げると、当時全員が黙り込んでしましました。
とても不思議な現象ですが、これが実態です。
講師:採用テストでは測れない人間性と、時代に合わせた育成
教室長と同様に、講師もまた学習塾の業績を大きく左右する重要な存在です。彼らの採用と育成には、従来の常識を覆すようなアプローチが求められます。
採用テストの結果だけでは計り知れない人間性
多くの塾が採用時に学力テストや適性検査を実施しますが、これだけで講師としての真の適性を見抜くことは困難です。
知識だけでなく、生徒との「共感力」が重要
講師に求められるのは、単なる知識の伝達だけではありません。
生徒一人ひとりの学習状況や性格を理解し、彼らの心に寄り添い、モチベーションを引き出す「共感力」こそが重要です。
これは、テストでは測ることのできない、人間性やコミュニケーション能力に深く関わる部分です。面接においては、学力だけでなく、生徒とどのように関わりたいか、どのような講師になりたいか、といった内面的な部分を深く掘り下げることが不可欠です。
困難に立ち向かう「粘り強さ」と「回復力」
生徒指導は、常に順風満帆ではありません。
生徒が伸び悩んだり、保護者からの厳しい意見に直面したりすることもあります。そのような困難な状況において、諦めずに生徒と向き合い、解決策を探る「粘り強さ」や、失敗から立ち直る「回復力」も、講師にとって非常に重要な資質です。
これらの能力は、テストでは測れませんが、過去の経験や挫折から何を学んだか、どのように克服してきたかといった質問を通じて見極めることができます。
【実例(実話)】
Yさんは、当方運営の学習塾で生徒として在籍されていて、卒業時大学進学が決まりアルバイト講師として採用試験を受けてみてはと声掛けをした方です。
高校は千葉県私立の中の上位で、理系の女子でT大学へ進学しました。
性格がとてもソフトな方でしたので、きっと生徒受けもよいだろうという読みがあったのですが、採用テストでは、当方が決めている及第点に届きませんでした。
数学で受けてもらったのですが、確かに内容としては高校生まで指導ができる講師を採用する方針でしたので難しいものではありますが、思ったより点数が低く少々その時点で、狼狽しました。
しかしながら、「この人はうちに塾に合う」という直感的なものがあり、少々御法度なのですが、採用を決定しました。
それからです。講師勤務がスタートしたYさんは、大学の学業も頑張りながら塾で教えるための学習も欠かさず、いつしか指名がわんさか入る超人気講師になってしまいました。
地域の口コミもあっという間に拡大し、その年度、ついに終盤は新規生徒を受け入れることが出来なくなるぐらいの満員御礼(多分満員をゆうに超えていました)になったのです。
特に女子生徒からの絶大な人気でしたので、当方も相当困惑しました。さすがにこのYさんだけで授業を組むのは無理だったからです。
そんな苦悩もついて回った人「財」だったのです。
社会人講師と学生講師の違い
両者にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、それぞれの特性を理解し、適切に配置することが重要です。
社会人講師の強みと弱み
強み:
- 指導経験と専門性: 自身の社会経験から得た知識や専門性を指導に活かすことができ、生徒に実践的な学びを提供できます。
- 責任感と安定性: 学生講師と比較して、責任感が強く、長期的な勤務が期待できるため、生徒指導の継続性が保たれやすいです。
- 保護者対応力: 社会経験を通じて培ったコミュニケーション能力や対応力は、保護者との円滑な連携において強みとなります。
弱み:
- 人件費が高い: 学生講師よりも高額な人件費がかかるため、コスト面での負担が大きくなる可能性があります。
- 時間の制約: 本業があるため、勤務時間や曜日が限定されることがあります。
学生講師の強みと弱み
強み:
- 生徒との距離が近い: 年齢が近く、生徒の気持ちを理解しやすいため、親近感を持たれやすいです。
- 学習内容への理解: 自身も最近まで学習者であったため、生徒がつまずくポイントや効果的な学習法をより具体的にアドバイスできます。
- 人件費が安い: 社会人講師と比較して人件費を抑えることができます。
弱み:
- 責任感のばらつき: 学業との両立やアルバイト意識が先行し、責任感にばらつきが生じることがあります。
- 経験不足: 指導経験が浅いため、指導力や対応力に課題がある場合があります。
重要なのは、両者の特性を理解した上で、例えば難関校対策には社会人講師を、基礎固めやモチベーション向上には学生講師を配置するなど、適材適所の人材配置を行うことです。
社会人講師が良い場合と学生講師が良い場合
これは保護者とのすり合わせで決定していくことを第一にとらえたほうが良いです。
なぜなら、保護者からの質問項目の中の「よくある質問」の上位に必ず顔を出す質問が
「こちらの講師は社会人ですか?学生ですか?」というものがあるからです。
この質問を投げてくる保護者は、十中八九社会人講師を望んでいます。
また、体験授業や実際の授業では、年齢の近い講師に生徒たちもなびく傾向があります。学生講師でも最近の入信を突破してきた講師たちは非常に優秀ですので、どうどうと保護者に紹介してもいいのです。
ちなみ誰もが知っているあの予備校でもチューターが学生アルバイトがこなしているという実態も知っておいてください。
諸々を考慮すると、教室内の陣容として社会人講師と学生講師がいると対応範囲がかなり広がるということも覚えておいてください。
研修に多くの時間を割く必要はない
さて、このテーマは「???」となってしまう方も多いことでしょう。研修は必要だろうと・・・。しかし、社会人講師であれ、学生講師であれ、紙面を読む力は持っていますので、クロスマのアドバイザーが塾オーナーとして兼任しているわけですが、研修をしっかりやったから優秀な講師になった事例は相当少なく、「覚えることに責任を持たせる形式として」彼らには、マニュアルを渡します。そのマニュアルを初回授業までにしっかりと呼んでおくことを、最初のミッションとして与えます。
これが私の研修です。
そして、初回授業前に30~40分ぐらいの機器使用のしかたを説明していざ初回授業となったときに、今まで失敗した!と感じてしまう要素はなく、きちんと回せています。
逆に言えば、マニュアルがしっかりしているという意味でもあります。
「研修は時間をかければかけるほど良い」という考え方も、実は時代錯誤かもしれません。
実践でしか得られない「本物の力」
講師の指導力は、座学の研修だけで身につくものではありません。実際に生徒と向き合い、試行錯誤を繰り返す中でしか得られない「本物の力」があります。必要なのは、過剰な座学研修ではなく、実践的なフィードバックと、改善のためのサポート体制です。
短時間・高頻度のフィードバックと OJT
長時間の座学研修よりも、短時間で頻繁に行われるフィードバックや、ベテラン講師によるOJTの方が効果的です。例えば、授業後に数分間の振り返りを行い、良かった点や改善点を具体的に伝える。あるいは、ベテラン講師の授業を見学させ、その指導法を学ぶ機会を提供する。こうした実践的な機会を増やすことで、講師は自身の課題に気づき、より早く成長することができます。
終礼後に残ってミーティングは時代錯誤
「終礼後に残ってミーティング」という慣習は、多くの塾で未だに残っていますが、これはもはや時代に合っていません。
したがって、一度も実施したことはありません。
効率性と生産性の追求
長時間労働が美徳とされた時代は終わりました。限られた時間の中で最大のパフォーマンスを発揮するためには、効率性と生産性を追求することが不可欠です。終礼後のミーティングは、講師の負担を増やし、疲労を蓄積させるだけでなく、家庭の時間を奪うことにも繋がります。
オンラインツールを活用した情報共有とコミュニケーション
現代には、ZoomやTeamsなどのオンライン会議ツール、DiscordやSlackやChatworkなどのチャットツール、Google Driveなどの共有ストレージなど、効率的な情報共有とコミュニケーションを可能にするツールが豊富に存在します。
これらを活用すれば、終礼後にわざわざ集まらなくても、必要な情報をリアルタイムで共有し、議論することができます。これにより、講師は自身の時間を有効活用でき、結果としてモチベーションの維持にも繋がります。
従って、弊社が採用した講師たちの中で、時間に関して不満を表明してきた講師は誰一人としていません。
礼節をもって接すれば礼節をもって返してくれる
講師との関係性において、最も重要なのは「礼節」です。
互いを尊重する関係性の構築
講師は、塾にとってかけがえのない財産です。彼らを単なる「雇われの身」として扱うのではなく、一人のプロフェッショナルとして、そして人間として尊重する姿勢が求められます。
挨拶をきちんとする、感謝の気持ちを伝える、意見に耳を傾ける、といった基本的な礼節を守ることで、講師は自分自身が大切にされていると感じ、塾へのエンゲージメントを高めてくれます。
これは一番最初の面接段階から今に至るまでずっと通したほうが良いでしょう。
親しき中にも礼儀あり!です。
信頼関係がパフォーマンスを最大化する
礼節ある対応は、講師との間に深い信頼関係を築きます。
信頼関係があれば、講師は安心して自分の意見を述べ、積極的に業務に取り組み、困難な状況でも協力し合おうとします。この信頼関係こそが、講師一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、ひいては教室全体の業績向上に繋がるのです。
教室長と講師、どちらが業績に大なる影響を与えるか
さて、
教室長と講師、どちらが学習塾の業績に大きな影響を与えるのでしょうか?
結論から言えば、どちらも不可欠であり、互いに密接に連携することで最大の相乗効果を生み出します。
しかし、
あえてどちらがより大きな「インパクト」を与えるかという視点で見れば、教室長の方がより大きな影響力を持つと言えるでしょう。
教室長の影響力:戦略と組織の舵取り
教室長は、教室全体の戦略立案と組織運営の責任者です。
- ビジョンの提示と方向付け: 教室長は、教室のビジョンを明確に示し、講師陣に進むべき方向を提示します。生徒募集戦略、カリキュラムの決定、サービス向上策など、教室運営の根幹に関わる意思決定を行います。
- 人材の採用と育成、配置: 講師の採用から育成、そして適材適所への配置まで、教室長が主導します。彼らの見極めや育成手腕が、講師陣の質を決定づけます。
- 組織文化の醸成: 教室長の人柄やリーダーシップが、教室の雰囲気を大きく左右します。風通しの良い、協力的な組織文化を築けるかどうかは、教室長の腕にかかっています。
- 危機管理と問題解決: 生徒や保護者からのクレーム対応、講師間のトラブル、突発的な事態など、あらゆる問題に対応し、教室運営の安定を図るのが教室長の役割です。
どれだけ優秀な講師が揃っていても、教室長が明確なビジョンを持たず、適切な指示を出さなければ、その講師の能力は十分に発揮されません。
また、教室長のリーダーシップが欠けていれば、組織は統制が取れなくなり、業績は低迷するでしょう。教室長は、まさに船の舵取り役であり、目的地を定め、嵐の中を進む判断を下す存在です。
講師の影響力:現場での直接的な顧客体験
一方、講師は、生徒と直接関わるため、学習塾のサービス品質そのものを提供します。
- 生徒の学力向上: 講師の指導力や生徒への向き合い方が、生徒の学力向上に直結します。
- 生徒・保護者満足度: 講師との相性や指導内容の満足度は、生徒や保護者の塾への信頼感、そして継続意欲に大きく影響します。
- 口コミと評判: 質の高い指導と親身な対応は、生徒や保護者からの良い口コミを生み出し、新規生徒獲得に貢献します。
講師のパフォーマンスが低ければ、どれだけ教室長が優れた戦略を立てても、現場での顧客体験は損なわれ、結果として退塾者の増加や新規入塾者の減少に繋がります。
相乗効果の重要性
最終的に、業績を最大化するためには、卓越したリーダーシップを持つ教室長と、高い指導力と人間性を兼ね備えた講師陣が、互いに連携し、相乗効果を生み出すことが不可欠です。
教室長が明確なビジョンを示し、講師がそのビジョンに基づいて最高の指導を提供することで、学習塾は持続的な成長を遂げることができます。買収後の成功は、単に資金を投入するだけでなく、人の可能性を信じ、適材適所の人材を配置し、彼らが最大限に力を発揮できる環境を整えることに尽きるのです。
学習塾業界における「人」の重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。買収後の業績向上を目指すならば、表面的な数字だけでなく、教室長や講師一人ひとりの「人間性」に深く踏み込み、彼らが輝ける場所を提供すること。それが、競争が激化する現代において、学習塾が生き残り、成長するための唯一無二の道であると言えます。
CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年02月03日
学習塾業界は変化を求めている:すべての受検で「安全志向」の時代へ突入!塾運営はこうなっていく!!
#バリューアップ
#リスク回避
#保護者ニーズ
#個別最適化
#塾M&A
#大学入試改革
#安全志向
#年内入試
#進路指導

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収