学習塾の「閉校」の具体的なやり方:生徒、講師、地域への責任ある幕引き

学習塾の経営者にとって、「閉校」という決断を下すことは、これまで築き上げてきた歴史と、信頼を寄せてくれた生徒・保護者、そして共に歩んできた講師たちへの責任を果たす、非常に重いプロセスです。事業を立ち上げる時と同じくらい、あるいはそれ以上に、誠実さと計画性が求められます。
本記事では、学習塾を円満に、かつ法的に適切に閉校するための具体的な手順と、特に配慮すべき倫理的な側面について解説します。
初めに「閉校」経験のあるCROSS M&A(クロスマ)アドバイザーからの心からのお願い
本記事をご覧頂いている方は何かしらお困りのことがあってのことかと存じます。私自身の経験ですので、たくさんある事例の中の一つと捉えて頂きつつも実際のところを知ってほしいです。
結論から申し上げて、「閉校」は経営者人生で、正直・・・一番きつかったです。
無理やり、「すっきりした」と思いこむようにしたものの、心の底からすっきりなどできませんし、自分を騙すような強引な心境でした。
何故なら、「弱り目に祟り目」という言葉がぴったり当てはまるぐらいですし、思い出しても奥歯を噛みしめるぐらいの嫌な感じです。
それでは実際にあった話で尚且つ、他人ではなく私自身が経験したことを公開いたします。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
基本的に、私が失敗したことを皆さんはやらなければ成功確率が非常に高くなる!それぐらい自信があるので、この失敗談は我慢して一読ください。
駅ロータリー極至近
駅ホームからも看板視認性良好
一日乗降者数が10万人超のターミナル
複数路線が行き交う駅
教室長継続案件
講師継続案件
生徒数は少な目だが15名
私はこのような案件を買収しました。当時は、とにかく「駅のホームから看板が見えて、すごい人通りもある!教室長も講師も残ってくれて、生徒数は少ないけど自分が巻き返せばいいだろう!」
そのぐらいの勢いで、買ったのです。金額は忘れてしまいましたが、とにかく「やれる」という気持ちしかなかったです。
自分がやらなかったことは何かというと、内部にもっと入り込んで状況把握することをしなかったという点です。
結果何が良くて、何が悪かったのか
【良いと思った点】
それは講師です。さほど数はいませんでしたが、その他教室を運営している私の目から見て残っている講師たちの質は極めて高いと判断出来ました。レベルが高かったですし、授業を少し聞いても非常にわかりやすく生徒の受けもよかったです。
【悪かった点】
・立地は最高ではなく、良くなかったのです。理由は雑居ビルでした。ターミナル駅でいろいろな業種が混在する駅でした。とても大きな駅であったけれども、「学習塾」が存在する駅として考えた場合、ロータリー内の選択は間違っていたと判断しました。
・教室へ上がるためのエレベーター付近、ビルの入り口付近は怖い印象でした。ゴミがよく散らかっていて、雑居ビル独特の何とも言えない怖さ(生徒目線、女性目線、保護者目線で見た場合の言いようもない怖さ)があったと言えます。
・自転車が全くおけない立地でした。大きなターミナル駅でしたので、電車通学の生徒もいましたが、やはり近隣にある中学生を生徒化するのに困難な感じでした。
市内の一番大きなマンモス中学が近い!ということで期待感を持っていたものの、過去データも確認せずに顧客導入できる「だろう」という根拠ない妄想が最悪の失敗です。
・前に在籍していた講師とのトラブルが残ったままでした。内容的にはどう考えても教室長に責任がある内容でした。その内容を最初に聞けておらず、後から問題としてわかった内容でしたので、前オーナーに連絡をしてこちらに火の粉が及ばないようにしたももの、当時の教室長の資質的なものに疑念を抱いた次第です。
自分が望む教室長像との乖離がだんだんと明るみになるにつけ、オーナーとしての私の気持ちと当時の教師長との気持ちは予想通り離れていきました。
結果、この教室は、終わりに向かっていったのです。
よく、立地が一番と言います。確かにそれは正しいのですが、「塾らしい佇まい」は必要だということを学びました。
また、何よりも教室長というのは、講師以上に運営実績にダイレクトに響くということを同時に知った次第です。
この実話は私がまだ学習塾運営初期段階のころの失敗談義です。
さて、この話はここで終わりか言うと、続きがあります。
ここからの内容が最も伝えたい内容です。
上記の教室は最終的に自分の中で終わったのですが、実は「譲渡」という形で幕引きしました。
そうです。実は閉校ではなく譲渡だったのです。
金額は、あまりピッタリ言うとよくありませんので少々オブラートに包み申しあげますと
約500万円弱です。
要するに、私は本来、閉校であれば物件の原状回復費用がかかったはずで、その他処理のために相当の手出し(コスト負担)を覚悟していたのですが、たまたま「買いたい」という人が突如現れて、そういう痛い負担はゼロで、それどころからお金を得て、本案件を何事もなく普通に譲渡できたのです。
思い切り準備をしての譲渡じゃなくて、自然発生的に生まれた譲渡でした。
閉校の場合は、推定マイナス200万円
でも
実際は譲渡でプラス500万円
従って、差異は700万円だということです。ちなみに物件の広さは20坪でした。いかがでしょう。これは実話ですし、
自分は「いらない」と思っていても他の人から見たら「ほしい」という案件だったということです。これは、メルカリなどもフリマと感覚的に似てます。
このときの経験は後に活かされているのが実態です。
それでは、ここからは一般論的になりますが、知っておいたほうがいい内容をお伝えいたします。
第1章:閉校を決断する前の最終検討と心構え
閉校は最終手段であるべきです。
その前に、事業譲渡(M&A)や規模縮小、オンライン化など、経営を維持するためのあらゆる選択肢を検討することが、経営者としての責務です。
特に、地域に根差した塾であれば、その閉鎖が地域の教育インフラに与える影響も無視できません。
1.1. M&A(事業譲渡)の検討 もし塾に一定のブランド力や生徒基盤、優秀な講師陣が残っているなら、事業譲渡が最善の道かもしれません。
生徒は学習環境を変えずに済み、講師の雇用も守られ、経営者は売却益を得られる可能性があります。居抜きでの譲渡であれば、内装や備品の処分コストも削減できます。
1.2. 経営再建の最後の試み 人件費の効率化、新たな教育サービスの導入(例:オンライン指導の強化)、コスト削減などを徹底的に行い、本当に閉校しか道がないのかを再確認します。
1.3. 経営者としての心構え 閉校は「失敗」ではなく、「責任ある撤退戦略」と捉えるべきです。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、生徒の学びの機会を途絶えさせず、講師の生活を守るための最大限の努力を払い、最後まで教育サービスとしての質を維持することが求められます。
第2章:閉校プロセスと法的手続き
閉校プロセスは、水面下の準備から始まり、公的な手続き、関係者への告知へと進みます。計画的かつ秘密裏に準備を進める時期と、誠実に情報公開を行う時期を明確に分ける必要があります。
この項目からラストにかけての「青い文字」で書いた箇所と、詳細記載の各項目は、順番として押さえておきましょう。
2.1. 【ステップ1:水面下の準備と日程決定】
まずは「水面下準備」ですから、あらゆる可能性を想定してほしいです。
その第一は、
事業譲渡の検討(並行して進行): M&A仲介業者などに相談し、売却可能性を探ってみてほしいです。上述のとおり、自分にとって「いらないもの」であっても他人から見たら「ほしいもの」である可能性があるのです。
この段階で「よし、相談してみよう」と思われた方は、
もちろんお急ぎの場合は、直接私へご連絡ください。
- 閉校日の決定: 学年の変わり目や受験が終わる時期など、生徒の学習に最も影響が少ない時期を選定します。通常、数ヶ月から半年前には決定しておくべきです。
- 資金計画の策定: 未消化の授業料の返金、・従業員への給与の支払い、賃貸物件の原状回復費用など、閉校に伴うすべてのコストを算出し、確実に支払えるよう資金を確保します。
2.2. 【ステップ2:従業員(講師・スタッフ)への対応】
- 告知のタイミング: 生徒や保護者に伝わる前に、まずは従業員に対して正式に伝達します。必要に応じて、労働契約や就業規則に基づき、解雇予告期間(通常30日前)を確保して行います。
- 退職金の精算と次の職のサポート: 雇用保険の手続き(離職票の発行、雇用保険適用事業所廃止届など)を確実に行い、可能であれば近隣の塾などへの再就職支援を検討します。モチベーション維持のため、最後まで質の高い指導を継続してもらうための配慮も必要です。
2.3. 【ステップ3:生徒・保護者への告知と対応】
- 告知文書の作成と説明会: 閉校の理由、閉校日、未消化授業料の返金方法、そして最も重要な「生徒の今後の学習サポート」についての詳細を記した文書を作成します。
- 未消化授業料の返金: 既に前払いされている授業料のうち、閉校日以降の未受講分は全額返金が原則です。トラブルを避けるため、計算方法を明確に示し、迅速かつ誠実に対応します。
- 転塾先の紹介・連携: 気持ち的に余裕があれば、生徒の学習機会を途切れさせないため、近隣の信頼できる塾と連携し、生徒の受け入れ先を紹介する仕組みを構築していくことも検討しましょう。
- 連携先との間で、生徒の成績や進捗状況などの情報引継ぎ(個人情報保護に配慮して)についても調整を行います。
第3章:物理的・法的な閉校手続きと資産整理
関係者への対応と並行して、教室の解約、備品の処分、そして行政への届け出といった物理的・法的な手続きを進めます。
3.1. 賃貸借契約の解約と原状回復
- 契約解除の予告: 賃貸契約に基づき、定められた期間(通常3~6ヶ月前)までに貸主に解約を通知します。
- 備品・資産の処分: 机、椅子、教材、PCなどの備品は、売却、譲渡、または処分を行います。特に内装が残る「居抜き」での売却を模索することで、原状回復費用を削減できる可能性があります。
- 原状回復工事: 契約に従い、内装などを入居時の状態に戻す工事を実施します。コストがかさむ部分であるため、事前に見積もりを取り、計画的な予算管理が必要です。
最後の項目に書きました「原状回復」は、物件の仲介を行う不動産会社によって、結果が大きく変わるポイントです。
まずはお手元に物件契約書、重要事項説明書を用意して書かれている内容を漏れなくチェックする必要があります。
・いつまでに解約通知をする必要があるのか
・敷金や保証金の返還についてはどのように規定されているのか
・原状回復の規定はどのようにされているのか
この3点は「閉校」であれ「廃業」であれ「株式譲渡」「事業譲渡」であれ、とにかくなるべく早めにチェックしてほしいところです。
3.2. 法的な廃業手続き
事業形態に応じて、以下の行政手続きを行います。
- 個人事業主の場合:
- 個人事業の開業・廃業等届出書: 廃業から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出。
- 都道府県税事務所への届け出: 各自治体の定める期限内に提出。
- 青色申告の取りやめ届出書(該当する場合)
- 法人の場合(会社解散・清算):
- 会社法に基づき、株主総会での解散決議、解散登記、清算人の選任、債権者保護手続き、官報公告、税務署等への解散届提出など、複雑な手続きが必要です。司法書士や税理士の専門的なサポートが不可欠となります。
3.3. 記録・情報の整理と保管
生徒の成績データ、契約書、会計帳簿などの重要書類は、法的に定められた期間(通常7年間)保管する義務があります。個人情報の漏洩がないよう、厳重な管理体制を維持し、不要な情報は確実に破棄します。
第4章:円満な幕引きと地域社会への配慮
閉校はネガティブな出来事と捉えられがちですが、これまでの感謝を伝え、最後まで責任を果たすことで、塾のブランド価値を毀損せずに幕を引くことができます。
4.1. 感謝の表明
生徒・保護者、そして地域社会に対し、これまでのご愛顧への感謝を伝える場を設けたり、しっかりとした内容説明のある手紙を送ることは、誠意を示す上で非常に重要です。
4.2. 教育者としての責任の完遂
閉校日までの残りの期間、サービスの質を決して落とさず、生徒の成績向上というミッションに対し、最後まで真摯に取り組み続けることが、教育者としての最後の責務です。
4.3. 閉校後の地域との関係
閉校後も、地域社会の一員として、元生徒や保護者との関係は続きます。最後まで誠実に対応することで、将来的な新たな事業展開や、地域貢献の可能性を残すことができます。
結論
学習塾の閉校は、単なる事業の終了ではなく、多くの人々の人生に関わるデリケートなプロセスです。経営者には、法的な義務を果たすこと、経済的な清算を行うこと以上に、「教育」という公共性の高いサービスを提供する責任として、生徒の学習機会を最優先に考えた行動が求められます。計画性、透明性、そして何よりも誠意をもって、これまでの感謝を込めた「最高の終わり方」を実現することが、学習塾経営の最終章となります。
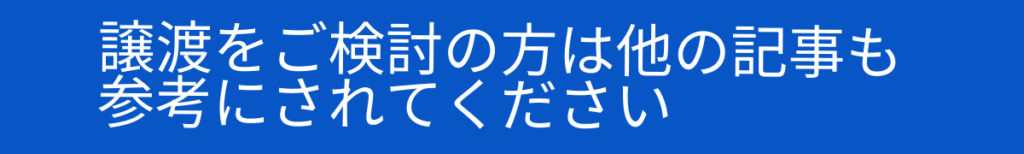
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月31日
なぜ「低単価・多人数」の塾は強いのか?長期繁栄を実現する経営戦略
#リスク分散
#一人当たり単価
#収益構造
#収益構造シミュレーション
#口コミの母数
#塾運営の標準化
#学習塾経営
#授業頻度の法則
#生徒数最大化
#経営の安定化
#講習平均単価

2026年01月19日
2026年1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト!ここから読み取る大学入試の変化
#2026年
#タイムマシン
#ベルサイユのばら
#入試改革
#大学入学共通テスト
#思考力
#探求学習
#文理融合
#新課程入試
#歴史総合

2026年01月13日
私立中学や私立高校で「大学へ直結する、思考型の学習」をテーマに学習カリキュラムを革新的に変更しようとする流れ!
#カリキュラム
#パラダイムシフト
#大学入試改革
#学習塾
#思考型学習
#探求学習
#教育の未来
#私立校
#総合型選抜
#非認知能力