初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(講師編)
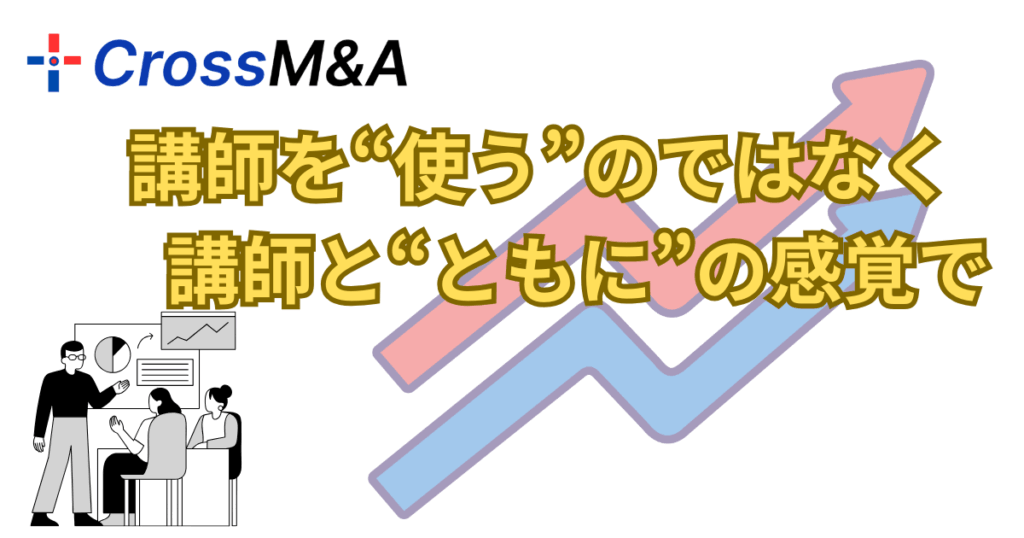
経営者として、そして教育者としての役割を初めて担うことは、大きな期待と同時に、乗り越えるべき課題も多くあります。
特に、学習塾や習いごと教室という「人」が核となる事業では、「講師としての質」と「経営者としての視点」のバランスが成功の鍵を握ります。
ここでは、「初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(講師編)」と題しまして、教える技術だけでなく、生徒と教室の未来を形作るために不可欠な要素を、徹底的に掘り下げていきます。
Ⅰ. 講師としての「指導力」と「人間力」の確立
講師は指導の前線に立つ人たちで、生徒との接点が多くなります。生徒からすれば、教室長・塾長よりも身近な存在になります。
英語にしても数学にしても、国語、理科、社会にしても生徒たちは、講師の特性を短時間でしっかりと感じ取ることが出来ます。
そして、
「あの先生は良い、あの先生はあまり良くない」
という生徒なりの講師評をするのです。
その講師評は、どうなるかというと・・・ほぼ確実に保護者に伝達されます。
伝達された内容は、教室長に伝わるという流れになるのです。
保護者からしたら、我が子が「あの先生はわかりやすい」「あの先生はわかりにくい」ということを言ってきたのですから、親の気持ちに中にしまっておくことはしません。
「〇日に指導してくださった先生が、息子がとてもわかりやすいと言っていました。
また、その前の日に教えてくださった先生は、息子には合わないようです。次回から変更して頂くことは可能でしょうか」
言い方は色々ですが、このように講師を変更してほしいというメッセージが届くことになります。
教室の看板になるのは、教科指導を行う講師です。生徒が「この先生から学びたい」と感じる指導力と人間力を磨くことが、何よりも重要です。
また、学習塾・習いごと教室の生徒のほとんどは、体験授業を経由します。
体験授業の成否は、講師の力量に左右されると言っても過言ではありません。
本記事は、これから学習塾や習いごと教室を開校される方向けですが、すでに2年、3年と運営をされた方でしたら、体験授業が要であることはわかると思います。
1. 「伝わる」指導法への徹底的なシフト
知識の量と教える技術は別物です。
「伝える」で終わらせず、「伝わる」ことを最優先する指導を確立しましょう。
- 正確さより「わかりやすさ」を優先する: 初心者にとって、専門的な正確さよりも、まずは全体像と基本ルールを掴む「わかりやすさ」が重要です。専門用語を多用せず、生徒のレベルに合わせた「翻訳」と「編集」を施しましょう。
- 例え話を効果的に用いる: 抽象的な理論や概念を、生徒の興味や実生活に結びつくような具体的な例え話を交えることで、理解度と記憶への定着率を飛躍的に高めます。「この知識が将来どう役立つか」を具体的に示し、学ぶ意欲を喚起します。
- 「インプットの5倍のアウトプット」を意識する: 自分が持っている知識を人に教えるためには、自分だけで理解しているレベルの何倍もの準備が必要です。常に「どうすれば生徒の行動が変わるか」をゴールに設定し、繰り返し、噛み砕き、実務に結びつけて伝える工夫を凝らしましょう。
2. 生徒の「学習進度と理解度」を知る技術
指導の質は、生徒の状態を正確に把握できるかにかかっています。一方的な講義にならないよう、常に生徒に目を向けましょう。
- 双方向のコミュニケーションを徹底する: 「わかった?」ではなく、「今、一番難しかったところはどこ?」「これをあなたの言葉で説明してみて」など、生徒がアウトプットすることで理解度を測る質問を投げかけましょう。
- 個別最適化への意識: 生徒一人ひとりの個性、これまでの学習経験、目標、そしてその日のコンディションに合わせて、指導方法や表現を変える柔軟性を持ちましょう。集団指導であっても、個別の進捗を把握する仕組みを持つことが不可欠です。
3. プロとしての「雰囲気作り」と「自信の演出」
生徒は、先生の話し方の内容だけでなく、雰囲気を敏感に察知します。プロフェッショナルとしての自信と熱意を示すことが、生徒の信頼につながります。
- 最初の3分間の重要性: 授業の導入部分は、その日の雰囲気と生徒の集中力を決める最も重要な時間です。入念に準備し、明るく、ハッキリとした声で、自信をもって授業を始めましょう。
- 視線と姿勢の管理: 落ち着いて会場全体を見渡し、背筋を伸ばした凛とした姿勢を保つことは、不安や準備不足を払拭し、生徒に安心感を与えます。
- 早口にならないよう注意: 緊張すると早口になりがちですが、これほど学習の妨げになるものはありません。意識的に話すスピードを適正に保つことで、生徒の理解を助けます。
- 熱意と楽しさの発信: 先生が「めんどくさそう」に話していると、生徒は授業を聞いてくれません。講師自身の「教えることが楽しい」という気持ちと、学ぶことの面白さを、明るく元気に伝えましょう。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
信頼されている講師、指導がわかりやすい講師、指導意欲が高い講師、生徒たちはあてずっぽうではなく、確信的に鋭い嗅覚でわかります。
教室運営をしているとよくわかるのですが、
一言で、「人気講師」になる講師は、コミュニケーションスキルが高いです。そういう講師のそばには、すぐに生徒が寄ってきます。
人気講師は、その振舞いが社交的で明るくて、楽しいから・・・「だけ」で寄ってくるのではありません。
「指導力」が伴っているから寄ってくるのです。
そのような講師が教室内に2人でもいたら、その教室はきっと新規顧客も取りやすくなるでしょうし、保護者との面談もスムーズに進むことでしょう。
講師は、大学生のアルバイト講師であれ、社会人講師であれ、良くも悪くも運営に大きな影響を与えるのです。
そして、これも知っておいてください。
良い講師を揃えると、紹介が入りやすくなります(断言)
紹介が減った・・・そう思ったら、講師の粒がそろっているかどうかを再確認したほうが良いでしょう。
Ⅱ. 経営者としての「講師」の役割と責任
個人教室の先生は、最高の講師であると同時に、最高の営業担当者であり、最高の広報担当者です。「講師」という立場を通して、教室の「経営」に貢献する意識を持ちましょう。
4. 講師が担う「集客」と「ブランディング」
個人教室において、先生のパーソナリティそのものが最高の集客ツールであり、教室のブランドとなります。
- パーソナルな情報の発信: 先生の経歴、教室を開業した動機、生徒への想い、そしてムリのない範囲での趣味や家族構成など、「先生がどういう方なのか」を積極的に発信しましょう。これにより、お客さまは信頼感と親近感を抱きやすくなります。
- 「顧客体験」のデザイン: 授業内容だけでなく、挨拶、受付での対応、教室の清潔感、保護者へのフィードバックなど、生徒や保護者が教室と接するすべての体験がブランディングの一部です。「教えに魅力がある教室」であると同時に、「心地よく通える教室」を目指しましょう。
- 生徒の成功事例の発信: 生徒の力が伸びたこと、目標を達成したことを、プライバシーに配慮しつつ積極的に発信することは、指導力の証明となり、新たな生徒を集める強い動機づけになります。
5. 教室の「ルールと時間管理」の確立
円滑な教室運営のためには、講師が中心となって共通のルールを確立し、守り抜くことが不可欠です。
- 教室内ルールの確立と徹底: 授業開始・終了時の挨拶、遅刻時の対応、宿題の提出方法など、教室で常時行う「決まりごと」を明確にし、すべての生徒に一貫した態度で接しましょう。新人でもベテランでも同じルールで生徒に接することが、教室の信頼性を高めます。
- 徹底した時間管理: 講師にとって最も避けるべき失敗の一つが「時間の超過」です。授業内容の優先順位を明確にし、ディスカッションなどで時間が押した場合にどこをカットするかを事前に決めておきましょう。黒板の隅にスケジュールを書いて、生徒と時間を共有するのも有効です。
6. 保護者・関係者との「信頼構築」
特に子ども向けの教室の場合、保護者との連携は不可欠です。大人を相手にする場合も、関係者との円滑なコミュニケーション能力が求められます。
- 定期的な進捗報告と対話: 生徒の成長や課題について、具体的な事実に基づいて定期的に保護者に報告する機会を設けましょう。教室への信頼は、「うちの子をちゃんと見てくれている」という安心感から生まれます。そのためには報告は非常に重要と言えます。
ビジネスのルールである「報告ー連絡ー相談(ほうれんそう)に通じるものがある、そう考えていくと、保護者との相談機会も大切であるということがわかります。 - クレーム・要望へのプロフェッショナルな対応: 講師の対応力が、教室の評判を左右します。生徒や保護者からの要望やクレームは、経営改善のチャンスと捉え、冷静かつ誠実に対応しましょう。相手を嫌な気持ちにさせない「対応力」を磨くことが必須です。どんな業種でもクレームゼロはありません。クレームを言ってくる保護者は性格的なこともありますが、誠実に対応すれば抜いた刀をきちんと納めてくれます。放置は絶対にダメです。
Ⅲ. 継続的な成長のため「講師に権限委譲」
初めての経営では、事務作業や集客など、すべての業務が教室長・塾長一人に集中します。ご自身が継続可能な状態を保つことが、教室の持続的な成功につながります。
そのために、どうしたらいいのか?
すべての業務を「自分がやったほうが早い」という感覚でアレもコレもとやってしまうと、教室のキャパシティーを自ら狭めてしまうことになります。
少し怖いかもしれませんが、講師に権限移譲していくことを強くオススメします。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
いつもの実例コーナーです。今回は「講師への権限委譲」についてです。
大学生講師、社会人講師いずれも最初面接をして、採用していきます。採用した直後の初回の研修や授業時、このときが一番のポイントです。
やってはいけないこと、やるべきことをしっかり明言し印象に残すように紙面に線を引いてもらったりして、きちんと伝えていきましょう。
さて、ここまではだいたいどの講師も平均以上です。
問題はその先。
講師はだんだんといい意味でも悪い意味でも「慣れて」くるのです。慣れの段階、例えば車の免許を取り立てのきわめて初期は大丈夫ですが、1年ぐらい経過した「ちょっと慣れたころ」が一番危ないのはご存じですか?そうです。事故が起こりやすいのです。
「慣れ」はスムーズな運営に必要である反面、何かしらのリスクが孕んでくる可能性があるととらえておいていいです。
例えば、
・遅刻が出てくる
・当日休みが出てくる
・挨拶が希薄になってくる
・生徒、講師からクレームが出てくる
・教室内で学習とは関係ない話をし始める
・授業の真剣さがダウンする
このような変化が出てきたら本当に要注意であることは肝に銘じておきましょう。
これらは、「慣れ」たことによって、講師の初期の緊張感が薄れていることに起因します。
CROSS M&A(通称クロスマ)のアドバイザーは学習塾、習いごとを経営しています。
そこでの学びは、『講師にはどんどん仕事を与えたほうがいい』ということです。
講師の中には、リーダーシップを発揮するタイプもいれば、バックヤード的な仕事に能力を発揮するタイプもいます。
彼らの良いところを活かして、仕事を与えていくのです。
例)
自分が教室の外に出なくてはいけない場面では留守を頼みます。
その間、当然ながら保護者が来たときの対応や、生徒が自習に来たときの案内、実際に授業がスタートした際の声掛け、システムによる各種確認など教室長がその時間行うべき業務を依頼するということです。
これらの権限委譲には、研修をしたり個別にシステム操作を教える時間が必要ですが、この「負荷」ともとれる仕事の増加は、講師にとって迷惑な話ではなく、その委譲に奮い立つ講師も多いのです。
そして重要で忘れてはいけないのは、
権限「委譲」であるとうことです。「移譲」ではありません。
つまり権限を委ねるものの責任は教室長・塾長が担うという考えでなくては講師も安心して委譲されることはありません。
この点をしっかりと講師に伝えることによって、今度は上司・部下関係としてみた場合の信頼関係が強くなります。
7. 業務の「効率化」と「固定費の管理」への意識
講師が疲弊してしまうと、指導の質が落ち、生徒の満足度が低下します。限りある時間を有効に使うための経営者視点が必要です。
- 教える業務と事務作業の分離: 授業の準備や指導以外の、報告書作成などの事務作業に費やす時間を把握し、ITツールを活用するなどして可能な限り効率化しましょう。
- コスト意識の徹底: 経営者として、教室の家賃、教材費、消耗品費などの固定費を常に意識し、無駄な出費がないかを見直しましょう。特に開業直後は、人件費(自分自身の給与を含む)や物件費を抑える工夫が重要です。
-1024x85.png)
【学習塾の報告書どうされていますか?】
・電話でまとめ報告
・面談のときにレポート提出
・一週間ごとに報告
・月間費用 人数×〇円という例のアレを使っている
などなど・・・どれもかなり時間とコストがかかります。弊社経由のM&A契約を行ってくださった方で、学習塾運営の買い手様には、
目からうろこどころから、、
本当に便利で!カスタムしやすく!無料で利用して、月額利用料金もゼロ円での報告システムを
ご希望の方には無料で設定補助していきます。
ものすごく!便利ですし、1件あたりの作業時間は、記録に挑戦してもいいですが、多分2秒とか・・・
これによって、
教室長・塾長勤務はとんでもなく時間短縮になります。
複数教室のオーナー様もいかがでしょうか!
8. 講師としての「自己研鑽」の継続
教える技術と知識は、時代とともに変化します。常に学び続ける姿勢が生徒に伝わり、指導の質を保証します。
- インプットの継続: 自分が教える分野の最新の知識や、効果的な指導法、教育トレンドについて学び続ける時間を確保しましょう。
- 他者のフィードバックの活用: 自分の授業を客観的に見つめ直すのは難しいものです。可能であれば、信頼できる同業者やメンターに授業を見てもらい、率直なフィードバックをもらう機会を持ちましょう。
9. メンタルヘルスと「燃え尽き」の予防
情熱を持って仕事をすることは大切ですが、無理は禁物です。
- 「完璧主義」からの脱却: 最初からすべてが完璧にできる人はいません。ミスを恐れず、「伝えることは目的ではなく手段である」ことを念頭に置き、「伝わったか」を基準に改善を繰り返しましょう。
- 適度な休息とリフレッシュ: 先生が心身ともに健康でなければ、良い授業はできません。趣味や家族との時間など、仕事から離れて心と体をリフレッシュする時間を意識的に設け、「授業をすることが苦痛にならない」状態を保つことが、長期的に生徒に向き合うための秘訣です。
よくあるのが、「夏休み後」です。
あまりにもハードな業務をさせてしまうと、まじめな講師ほど疲弊してしまいます。これは教室長や塾長も同様です。
オーナーや取締役の場合には、いわゆる時間で勤務する概念はなくなりますので、たとえ長時間勤務しようと自分の強い意志に基づくので全く平気なのです。
しかし従業員は違います。
夏休み後、つまり夏期講習の後に燃え尽き症候群が起こることが多いのは、講習のコマが多く勤務時間も相当長くなることによる弊害とも言えます。
この現象を効率よく防いで、しかも売上を確実にUPさせる方法!
これも弊社経由の譲渡契約成立の買い手様に伝授いたしますのでご期待ください。
終わりに
初めての経営と教室運営は、毎日が学びと発見の連続でしょう。成功の秘訣は、「先生の好きと、生徒の知りたいが一致する教室づくり」に尽きます。
今日お伝えした「講師としての質」と「経営者としての視点」を意識し、ご自身の教育への情熱と専門性を武器に、多くの生徒の成長を支える素晴らしい教室を築き上げていってください。
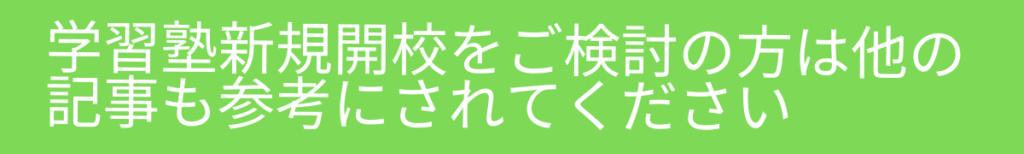
立地選定について
最適な物件選びの秘訣とは?
内外装計画と工事について
統一感のある什器・備品
教室長一日密着レポート徹底解説
失敗しない採用のための求人
見落としがちな掲示物の重要性!
開校時に用意しておく事務用品
商圏分析とネットリサーチ徹底攻略
塾講師採用 効果的な募集から採用
学習塾は単月赤字でも経営できる!
話し上手より「聞き上手」
テキスト選定と教材会社の選び方
塾の「儲けの仕組み」を徹底解剖!
学習塾選びの鍵!自習室の有無
立地で選ぶ塾の重要性
掲示物、パンフレット、のぼり旗
学習塾・習いごとの看板は集客の要

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日
特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。
#FC加盟
#ノウハウ
#塾起業
#塾集客
#学習塾経営
#守破離
#損益分岐点
#教室運営
#新年度開校
#経営基盤
#集客

2026年01月23日
初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資
#事業計画書
#創業融資
#創業計画書
#学習塾経営
#日本政策金融公庫
#書き方
#自己資金
#資金調達
#起業準備
#面接対策

2026年01月22日
会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~
#M&Aメリット
#パラレルキャリア
#副業オーナー
#合同会社設立
#塾買収
#学習塾経営
#教室長管理
#教育事業投資
#日本政策金融公庫
#脱サラ準備