学習塾・習いごと 閉鎖じゃなくて譲渡を最初に考えてください!売り手手数料無料。
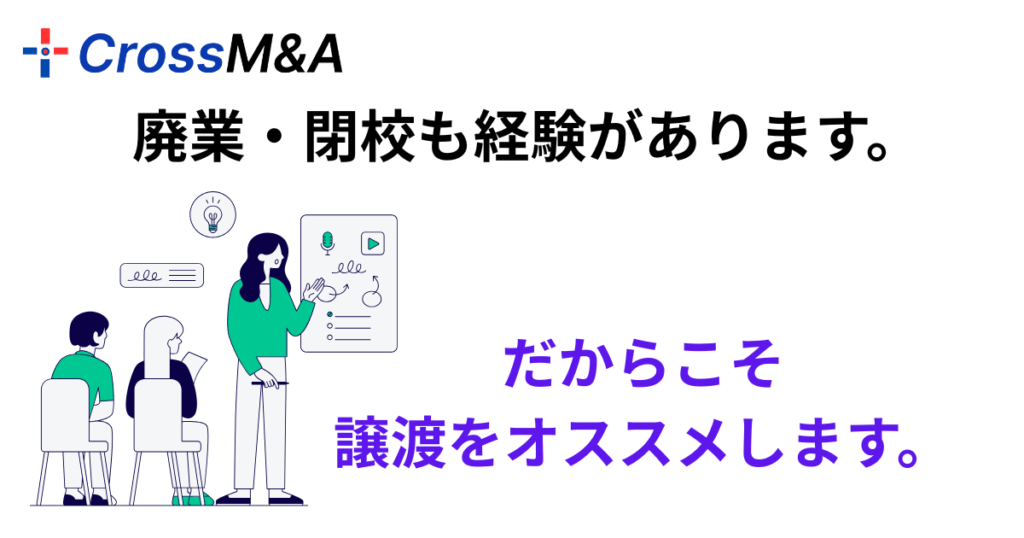
塾・習いごと事業の経営者にとって、事業継続が困難になった場合の選択肢は多岐にわたりますが、まず検討すべきは事業譲渡です。
閉鎖は最終手段であり、従業員の雇用、生徒の学習機会、そして築き上げてきたノウハウや資産を失うことになります。一方、事業譲渡は、これらの資産を次世代に引き継ぎ、新たな活路を見出すことができます。この記事では、学習塾・習いごと事業の譲渡を念頭に置き、来期の事業状況を占うポイントについて解説します。
以下の記事も参考になりますので、ご確認ください。

閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
個人塾の閉鎖、費用はいくら?
夏期講習の実施状況から占う来期状況
夏期講習は、学習塾・習いごと事業にとって来期を占う上で最も重要な指標の一つです。なぜなら、夏期講習は新規生徒の獲得だけでなく、既存生徒の継続意欲を測る試金石となるからです。
1. 新規生徒の獲得状況
今年の夏期講習で新規の問い合わせや入塾が例年よりも少なかった場合、来期も厳しい状況が続く可能性が高いでしょう。
これは、地域における少子化の進行、競合他社の台頭、あるいは自塾の広報戦略が時代に合わなくなっていることを示唆しています。特に、Web広告やSNSを活用した集客が弱点となっている場合、早急な対策が必要です。
2. 既存生徒の継続率
夏期講習は、既存の生徒が次期も継続して通塾するかどうかを見極める絶好の機会です。夏期講習の申し込みが少なかったり、講習後に退塾する生徒が増加したりした場合、生徒の満足度が低下している可能性があります。カリキュラムの内容、講師の質、あるいは保護者とのコミュニケーション方法に問題がないか、見直す必要があります。
3. 授業への参加態度
講習期間中の生徒たちの学習意欲や集中力は、来期への期待値を反映しています。夏期講習に積極的に参加し、課題に熱心に取り組む生徒が多い場合、学習成果が期待でき、保護者からの評価も高まり、継続につながるでしょう。一方で、欠席が多かったり、宿題を提出しなかったりする生徒が増加している場合、生徒が塾の価値を見いだせていない可能性があります。
これらの状況を客観的に分析し、
もし来期の生徒数の減少が避けられないと判断した場合、早めに事業譲渡を視野に入れた準備を始めることが賢明です。
事業譲渡を検討する際には、夏期講習の成功事例や参加人数、継続率などのデータを整理し、譲渡先に対して事業の潜在的な価値をアピールすることが重要です。
冬期講習の面談実施のアポイント状況から占う来期状況
冬期講習は、夏期講習に次いで来期を占う重要な指標です。特に、冬期講習に先立って実施される面談のアポイント状況は、保護者の期待値や塾への信頼度を直接的に反映します。
1. 面談のアポイント率
冬期講習の面談は、保護者が今後の学習計画について真剣に検討する機会です。面談のアポイントがなかなか取れない、あるいはキャンセルが増えている場合、保護者が塾の提供するサービスに満足していない、あるいは信頼を失いつつある可能性があります。特に、面談を拒否する保護者が増えている場合、深刻な問題があると考えられます。
2. 面談での保護者の反応
面談で保護者が熱心に質問したり、具体的な学習計画について積極的に意見を交わしたりする場合、塾への期待が高い証拠です。
一方で、保護者が受け身であったり、塾側の提案に無関心であったりする場合、信頼関係が構築できていない可能性があります。また、塾への不満や要望が面談で明確に示された場合、真摯に受け止め、改善策を講じる必要があります。
3. 講習への申し込み状況
面談後、冬期講習への申し込みがスムーズに進むかどうかも、来期を占う上で重要です。面談で好感触を得たにもかかわらず、申し込みにつながらない場合、料金設定やカリキュラムの内容が保護者のニーズと合っていない可能性があります。
冬期講習は、中学受験や高校受験を控えた生徒にとって、最後の追い込みの機会です。それにもかかわらず申し込みが少ない場合、生徒や保護者が塾にその価値を見出していないことになります。
これらの状況から、来期も生徒数が増加しないと判断した場合、事業譲渡のタイミングを早めるべきです。冬期講習の面談記録や申し込み状況は、事業譲渡における重要なデータとなります。これらのデータを適切に整理し、譲渡先に対して事業の将来性を論理的に説明できるように準備しましょう。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
アポイント率が低いことを、
(たまたまだろう)
(保護者も皆忙しいのだ)
などと流ちょうに思っていたら、非常にまずいです。
冬期講習前の面談は通常9月~10月に実施します。夏期講習の疲れが癒えない段階で、冬の打合せですから、けっこうハードです。
しかしながら、冬期講習前の面談は、入試本番や学年末テスト対策なども含むため、非常に重要度が高いのです。
それなのに、アポイント率が低いということは、黄色信号どころか赤信号です。
【既存保護者のアポイント率が低い理由】
新規の保護者の場合は、よくあるのが「塾ナビを経由してきた問合せだけど電話しても繋がらない」といパターンで、そもそも相手との会話が出来るかどうかも未知数です。よって新規の保護者とのアポの取りにくさと既存保護者とのアポの取りにくさは、次元が全く違います。
既存の保護者の場合は、すでに教室の顧客なのですから、それでもなかなか面談の約束が取れないのは、場合によってはとてつもなく大きな理由が潜んでいます。
- 単純に多忙である(それが本当なら)
- 子どもの成績があまり伸びていないので
- 面談をやってもただ講習の追加を勧められるだけだろうという思い
- すでに他塾を検討している
- すでに教室への信頼が落ちている
- すでに教室長への信頼がない
教室長や塾長、オーナー兼の責任者が声掛けしててアポがなかなか整わずに、面談が成功するというのは、ほぼないでしょう。
面談実施の期間を一か月間、たっぷりと準備したにも関わらずB教室は、結果面談率は、60%に留まりました。案の定、その40%の顧客の中からテスト後に辛辣なメッセージとともに退塾の知らせがありました。
それは序章に過ぎず、その後もダラダラと退塾が続く形になりました。
さて、この原因は何だったのでしょう。
答えは:保護者様との関係性希薄状態
です。
一番最初の段階から少し時間を経ると、保護者は塾の家庭への携わり方がわかってきます。
- マメな連絡があるのか
- テスト結果はどうなのか
- うちの子に対しての接し方は
- 教室の雰囲気は
- 自習に行ったときの教室のフォローは
など、です。
保護者からの信頼を失う一番のケースは、「報告」や「連絡事項」がないことです。
これは当然だと思います。
そして、最悪なのは、悪いことの報告・連絡をしないことです。
例えばテスト結果が悪かったときの、生徒や保護者へのフォローアップは、塾運営では最重要項目です。
この保護者との関係性を良好に保つ努力をしない教室長は、小さなきっかけでもすぐに保護者から嫌われてしまうのです。
「保護者」という存在を大切にしなければ、シーズンを経過するごとに徐々に信頼が失われるのです。
現時点の主要学年の状況から占う来期状況
学年ごとの生徒の状況は、来期の事業状況を予測する上で最も確実な手がかりとなります。
特に、
- 中学受験を控えた小学5年生
- 高校受験を控えた中学2年生
- 大学受験を控えた高校2年生
これらの「新年度に受験を迎える生徒」状況は非常に重要です!
少し詳細に見てみましょう。
小学5年生(中学受験)
小学5年生は、中学受験に向けて本格的な学習をスタートする時期です。この学年の動向は、来期の塾の収益を大きく左右します。
1. 外部模試の成績推移
外部模試の成績が伸び悩んでいる、あるいは平均点を下回る生徒が増えている場合、カリキュラムや指導方法が現状に合っていない可能性があります。また、受験を諦めてしまう生徒が増える可能性も示唆しています。この場合、カリキュラムの見直しや、個別の補習体制を強化する必要があるでしょう。
2. 宿題の提出状況
宿題の提出が遅れたり、提出しない生徒が増えている場合、学習意欲が低下している証拠です。保護者との連携を密にし、家庭での学習習慣を確立させるためのサポートが必要です。
3. 保護者の塾に対する期待値
この時期の保護者は、来年の受験に向けて不安を抱えており、塾に対して高い期待を寄せています。保護者からの質問や相談が少ない場合、塾の指導内容や進捗状況に満足していない可能性があります。定期的な面談や報告会を通じて、保護者との信頼関係を構築することが重要です。
中学2年生(高校受験)
中学2年生は、高校受験に向けた基礎学力を固める重要な時期です。この学年の動向は、来年の高校受験クラスの規模を決定づけます。
1. 定期テストの成績推移
定期テストの成績が伸び悩んでいる場合、基礎学力が定着していない可能性があります。この学年でつまずくと、高校受験での成功は難しくなります。個別の補習や、学習方法の指導を強化する必要があります。
2. 塾での出席状況
中学2年生は、部活動や友人関係など、学校外の活動が活発になる時期です。塾への出席率が低下している場合、学習へのモチベーションが低下している可能性があります。塾を「単なる勉強の場」ではなく、「居場所」として感じてもらえるような工夫が必要です。
3. 保護者とのコミュニケーション
思春期を迎えるこの時期、生徒とのコミュニケーションが難しくなることも少なくありません。保護者との連携を密にし、生徒の学習状況や精神的な変化について共有することが重要です。保護者との信頼関係が築けていない場合、高校受験を前に転塾されてしまう可能性もあります。
高校2年生(大学受験)
高校2年生は、大学受験に向けて本格的な対策を始める時期です。この学年の動向は、来年の大学受験クラスの規模と合格実績を決定づけます。
1. 模擬試験の成績推移
模擬試験の成績が目標とする大学の合格ラインに届いていない場合、学習計画の見直しが必要です。志望校のレベルに合わせた個別指導や、演習問題の提供を強化する必要があります。
2. 自習室の利用状況
自習室の利用率が高い場合、生徒の学習意欲が高い証拠です。一方で、自習室が空いている場合、生徒が塾を自習の場として活用していない可能性があります。自習しやすい環境を整備し、講師がいつでも質問に答えられるような体制を整える必要があります。
3. 保護者との進路相談
高校2年生の保護者は、生徒の進路について高い関心を持っています。定期的な進路相談会を実施し、保護者の不安を解消することが重要です。保護者との信頼関係が築けていない場合、生徒の進路選択に際して、塾への信頼が揺らぎ、転塾につながる可能性があります。
上記でいろいろ細かく述べましたが、
要するに簡易的な尺度としまして
夏の講習が終わった段階の新年度受験生がどのぐらいいるのか?
↑ ↑ ↑
これです。
事業譲渡を検討するタイミング
上記の分析結果から、来期の事業状況が厳しいと判断した場合、早急に事業譲渡の検討を始めるべきです。
理由は、事業譲渡は閉鎖と比べて多くのメリットがあるからです。ただし非常に重要なことが一つあります。それは・・・
時期とタイミングです。
①ギリギリの淵の状態まで運営状態がおかしくなったときは非常に厳しいです
②ほとんどの方が年度末を考えますが、そこは需給曲線を想像していただければわかると思います。
この2点を念頭に以下のメリットを見てみましょう。
1. 従業員の雇用維持
事業譲渡が成功すれば、従業員は新しい経営体制のもとで働き続けることができます。これは、長年苦楽を共にしてきた従業員の生活を守る上で、最も重要な点です。
2. 生徒の学習機会の確保
事業が継続されることで、生徒は引き続き同じ場所で学習を続けることができます。特に、受験を控えた生徒にとっては、学習環境の変化は大きな負担となるため、事業譲渡は生徒の学習機会を守る上で非常に重要です。
3. 築き上げてきたノウハウと資産の継承
長年にわたって培ってきた指導ノウハウ、カリキュラム、生徒情報、そして立地や設備などの資産を、新しい経営者に引き継ぐことができます。これは、経営者自身の努力が報われると同時に、地域社会への貢献にもつながります。
4. 借入金返済や引退後の生活資金の確保
事業譲渡によって得られた譲渡金は、借入金の返済や引退後の生活資金として活用することができます。閉鎖の場合、借入金の返済に困窮するケースも少なくありません。
事業譲渡の成功には、早めの準備と情報収集が不可欠です。事業の強みや価値を客観的に分析し、譲渡先が求める情報を事前に整理しておくことが重要です。専門家であるM&Aアドバイザーに相談することも、スムーズな事業譲渡を実現するための有効な手段です。
学習塾・習いごと事業は、地域社会の教育を支える重要な存在です。閉鎖という選択肢の前に、事業譲渡という道があることを知り、未来への新たな可能性を模索してはいかがでしょうか。
最後に、
仲介会社はたくさんあります。
しかし、私どもは
・現在も学習塾を運営している
・閉校、譲渡どちらも経験している
・モデルルームを運営している
・買い手に手厚いアフターサービスがある
・売り手の手数料は0円である
この強味を持ったサービスです。
きっとあなたの心強い味方になることでしょう。(自信あり!!)
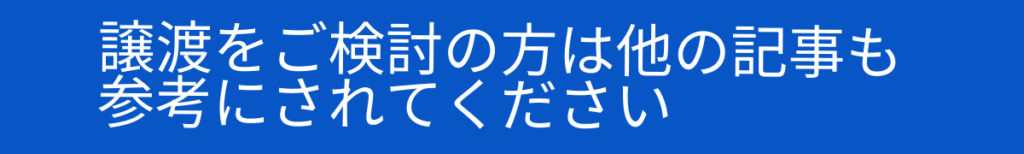
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡