塾経営は本当に「儲からない」のか?9月に検索が急増する理由と、収益を安定させるための具体的戦略
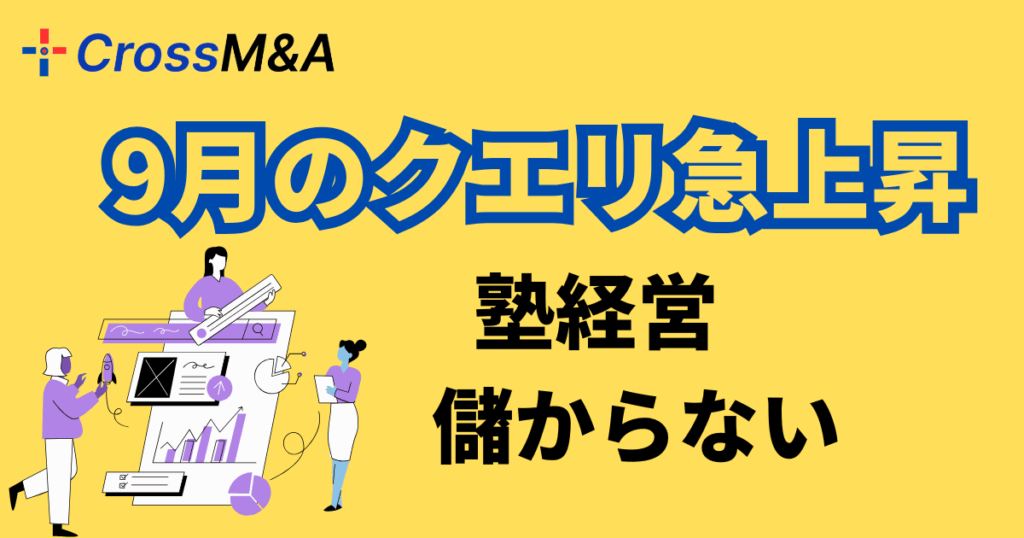
第1章:検索クエリ「塾経営 儲からない」の真実
1-1. そもそも「クエリ」とは何か?
検索エンジンにおける「クエリ」とは、単にユーザーが入力した単語や語句を指すものではありません。
それは、ユーザーが抱える疑問や解決したい課題そのものを如実に表していると言っても過言ではありません。つまり問いかける「質問」や「問い合わせ」そのものです 。
このクエリの背後には、ユーザーの深い「検索意図」が隠されています 。例えば、「浦安市 ホテル 安い」というクエリは、単に「浦安にある安いホテル」の情報を知りたいだけでなく、
「浦安の安いホテルに泊まりたい」という行動や、その背景にある「旅行の計画を立てている」という状況を内包しています 。
もしかしたら、東京ディズニーランド、ディズニーシーを思い切り楽しみたい!という計画をさらに思い出深いものにするための検索かもしれません。
それは家族の為であったり、恋人の為であったり、クラスメートの為であったり、色々な意図があるということです。
この観点から、「塾経営 儲からない」というクエリを分析すると、そこには単なるビジネス上の情報収集を超えた、より深刻な問いが込められていることがわかります。
この言葉を検索するユーザーは、単に収益を上げる方法を知りたいだけでなく、自身の努力が報われないことへのフラストレーションや、「もしかして自分の経営は間違っているのではないか」という根源的な不安を抱えています。
これは、金銭的な問題だけでなく、教育者としての自己肯定感にも関わる、いわば「事業継続の是非」を問うSOSの信号と解釈できます。
表面的な経営論だけでは、このユーザーの心に届くことはありません。まずは、彼らが抱える悩みが個人的な失敗ではなく、業界全体の構造的な問題であることを示すことで、問題解決の糸口を提示する必要があります。
1-2. なぜ今、この言葉が急浮上しているのか?
結論は9月だからです。
例えば夏期講習の成否から見て、比較的成功した部類だ・・と思えたとしてもそこで稼ぎ出した資金は、数か月ですべてコストとして消費されるものだということが大方のオーナーはわかっています。
それがゆえに、夏が終わったことによる恐怖感があるのです。
夏休みが終わり、新学期が始まる9月は、学習塾業界にとって独特な季節です。この時期に「塾経営 儲からない」という検索ワードが急増することには、業界特有のビジネスサイクルが大きく影響しています。
一般的に、夏期講習は大手塾にとって、通常の月謝だけでは賄いきれない経費を回収する重要な収益の柱と見なされています 。
しかし、個人塾や小規模塾の経営者にとっては、その現実は大きく異なります。夏休みという貴重な時間を投じ、連日膨大な労力をかけたにもかかわらず、期待したほどの収益が上がらなかったという現実に直面することが少なくありません 。
中には、時給換算すれば大幅に減少していると感じる経営者もいるのです。
夏期講習という大勝負を終え、その結果に落胆し、冬期講習や次年度の集客計画を立てなければならない正念場を迎える9月 。
この疲弊と落胆の狭間で、「なぜこれほど頑張っても報われないのか」という深い絶望感に襲われ、漠然とした不安が具体的な検索行動へと変わるのです。
1-3. この検索をしているのは「誰」なのか?
この検索クエリの主なユーザーは、教育への強い情熱を持つ、個人塾や小規模塾の経営者です。彼らは、大手学習塾のように分業された組織ではなく、教務指導、集客、財務、人事、校舎管理、清掃といったあらゆる業務を一人、あるいは少人数で兼任する「オールラウンダー」であることがほとんどです 。
彼らの多くは、生徒の成績が向上し、成長する姿を見ることに大きなやりがいを感じる教育現場の「プロフェッショナル」です。
しかし、ビジネスの成功がなければ、その情熱を継続できないという厳しい現実がのしかかっています。彼らは、生徒の学力向上には自信があっても、経営や集客といったビジネスの複雑な問題に直面したとき、誰に相談すればよいかわからず、孤独を感じやすい傾向にあります。
このジレンマを解決するためには、彼らの専門分野である「教育」を尊重しつつ、具体的な「経営」の知識を平易な言葉で提供する必要があります。
したがって、このテーマで情報を発信する際は、「儲け」という言葉を使いながらも、最終的には「教育事業を継続するための持続可能な経営」という、より高次の価値を提示することが不可欠です。
第2章:「儲からない」と感じる構造的な理由
2-1. 塾経営の収益構造と損益分岐点の現実
学習塾の経営は、「生徒数 × 月謝」という一見シンプルな収益モデルによって成り立っています 。
この売上から教室の賃料、人件費、教材費、広告費などの経費を差し引いた残りが利益となります 。この構造を正しく理解し、適切なコスト管理ができれば、個人塾の利益率は30〜50%が目安とされ、比較的高収益が見込めるビジネスモデルとされています 。
しかし、多くの経営者が「儲からない」と感じる最大の理由は、この収益構造における「損益分岐点」を明確に把握していないことにあります 。
損益分岐点とは、売上と費用が一致し、赤字でも黒字でもない状態となる生徒数のことです 。
個人塾の場合、生徒数が20〜30名で収支がゼロになることが一つの目安とされています 。しかし、この数字は経営者の給与や、賃料、広告費といった固定費の多寡によって大きく変動します 。開業初期に必要な投資資金 や、月々の家賃、人件費が経営を圧迫している現状を客観的に認識することが、「儲からない」という漠然とした不安を解消する第一歩となります。
表:塾経営の収益と費用の構造例
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 収入 | 生徒数 × 月謝 | 収益の大部分を占める |
| 支出(固定費) | 家賃 | 規模や立地により変動 |
| 人件費 | 講師の質と数に直結 | |
| 広告宣伝費 | チラシ、Web広告など | |
| 自分の収入 | 生活に必要な最低限の給与 | |
| 支出(変動費) | 教材費 | 生徒数に応じて変動 |
| 光熱水費 | 生徒数や利用時間で変動 | |
| 消耗品費 | 紙、文房具など | |
| 利益 | 収入合計 – 支出合計 | 適切に管理すれば30〜50%も可能 |
2-2. 激化する市場の「三重苦」
経営者が「儲からない」と感じる背景には、個別の課題だけでなく、市場全体が抱える構造的な問題があります。
まず、一つ目の要因は「少子化の進行」です。今後5〜10年で学齢人口は確実に減少し、新規生徒獲得の母数が年々縮小していくことが予測されています 。これは、努力だけでは埋められない、構造的な収益の圧迫要因となります 。
二つ目は「競合激化と淘汰の時代」です。縮小する市場のパイを奪い合う形で、大手塾やオンライン塾との競争が激化しています 。
東京商工リサーチの調査によると、2024年の学習塾の倒産件数は過去最多を記録し、その約8割が「販売不振」を原因としています 。これは、少子化という逆風の中、集客に失敗した塾が必然的に陥る結果であり、市場の激しい淘汰の時代に入ったことを示唆しています 。
三つ目は「生徒獲得コスト(CPA)の高騰」です。
激しい競争は、チラシのポスティングやWeb広告といった集客費用を押し上げます 。顧客獲得単価(CPA)が上昇し、顧客生涯価値(LTV)がそれを上回らなければ、赤字経営に陥る危険があります 。
経営者が「儲からない」と感じる悩みは、個人的な能力不足ではなく、制御不能な市場環境の激変に起因している側面が強いのです。
2-3. DXが遅れることの「見えない損失」
多くの塾経営者は、本来の教育業務以外のタスクに膨大な時間を費やしています。採点や宿題管理、保護者との連絡、事務作業など、これらの非効率な業務は「見えない人件費」として利益を圧迫しています 。
さらに、少子化は生徒数の減少だけでなく、将来の講師不足にもつながるため、アルバイトに依存しない運営体制の構築が喫緊の課題となっています 。
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単にテクノロジーを導入することではありません。
それは、AI教材やオンライン学習プラットフォームを活用し、事務作業を自動化することで、教育の質を保ちながら、限られたリソース(時間、人材)を最大限に活用するための経営戦略そのものです 。
事務作業から解放された経営者や講師は、本来の強みである教育、そして生徒一人ひとりへのきめ細やかなサポートに集中できるようになります。この効率化は、生徒の満足度を向上させ、低コストで最も効果的な集客手段である「口コミ」へと繋がります。
第3章:収益を確実に改善する「三つの鉄則」
3-1. 鉄則1:収益の多角化戦略
市場の縮小という課題に立ち向かうためには、既存の収益モデルに固執しない柔軟な戦略が求められます。
第一に、ターゲット層の見直しが重要です。多くの塾は中学生や高校生を主なターゲットにしていますが、少子化の中で生徒の母数が減ることを考えると、低学年層や不登校生徒など、新しい層にアプローチすることは、長期的な生徒確保と収益安定につながります 。
第二に、高付加価値サービスの導入です。単価を上げるために、プログラミング教室、探究学習、英検対策講座など、保護者のニーズに応える高付加価値サービスを開発・提供することで、客単価そのものを引き上げる機会を創出します 。
第三に、季節講習の価値向上です。夏期・冬期講習は短期間で収益を大きく向上させる絶好の機会です 。これを単なる収益確保の場ではなく、生徒の苦手克服や成績向上を約束する高付加価値な体験として設計し、既存生徒に対して追加受講を促す「アップセル・クロスセル」を積極的に行うことで、参加率を高めることができます 。
3-2. 鉄則2:デジタルとアナログを組み合わせた集客
生徒数増加は塾経営の要です 。高騰する広告費に対応するためには、費用対効果の高い集客戦略が不可欠です。
Webサイトやブログを活用したSEO対策は、塾の理念や教育方針を明確に示し、ターゲット層が知りたい情報(例:「〇〇高校合格」のための勉強法)を発信することで、信頼と権威性を築き、 Web広告を使わずに新規顧客を獲得する機会を増やします 。
また、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSは、勉強のコツや塾の日常を発信することで親近感や親しみやすさをアピールするのに適しています 。
そして、最も費用対効果の高い集客手段は「口コミ」です 。
日々の授業で生徒の自己肯定感を高め、保護者とのコミュニケーションを密にすることで顧客満足度を最大化することが、新規生徒獲得の最大の推進力となります 。
3-3. 鉄則3:時代に合った「独自性」の追求
大手塾と同じ土俵で「低価格」や「ブランド力」で戦うことは、小規模塾にとっては非常に困難です 。生き残るためには、独自の強みを打ち出す「差別化」が不可欠となります 。
個人塾の最大の武器は、「顔が見える」安心感ときめ細やかな対応力です 。講師や経営者と生徒、保護者の距離が近いという強みを最大限に活かし、生徒一人ひとりの個性に合わせた学習プランやメンタルケアを提供することで、大手には真似できない信頼関係を築くことができます 。
また、講師が教えすぎず、生徒の「やる気を引き出す」ことに注力する自立学習型指導は、人件費を抑えながらも高い個別対応力を提供する有効な戦略です 。このような指導法を確立し、生徒の学習への主体性を育むことは、競合にはない塾の強みとなり、顧客満足度の向上に直結します 。
第4章:迷いが生まれた時に取るべき「次の一歩」
4-1. 孤独な経営者の悩みに寄り添う相談先
経営の悩みは一人で抱え込まず、外部の専門家の力を借りることが、事業を立て直すための最初の、そして最も重要な一歩です。相談は決して「失敗」の証ではなく、あなたの事業を継続するための賢明な行動です。
まず、ビジネス上の課題解決に特化した専門家として、経営コンサルタントや中小企業診断士が挙げられます 。彼らはWebマーケティング、DX、資金調達など、幅広い分野で実践的な支援を提供し、事業の再建を伴走型でサポートしてくれます 。
また、地域の小規模事業者の「かかりつけ医」として、無料で経営相談を受け付けている商工会議所も有効な選択肢です 。
ここでは、創業や資金繰り、販路拡大といった多岐にわたる悩みに応じ、中立的な立場の経営指導員が助言を行います。
さらに、同じ悩みを抱える同業者が集うコミュニティも、非常に貴重な存在です 。外部には話しにくい悩みを本音で語り合える場であり、お互いの経験から学びを得ることで、孤独感を和らげ、実践的な知識を高めることができます 。
4-2. 相談から得られる本当の価値
専門家や同業者に相談する最大の価値は、あなたの悩みを「客観的に整理する」ことです。
経営者が抱える「儲からない」という漠然とした不安は、感情的な側面が強く、一人でいると「自分のせいだ」という自責の念に陥りがちです。しかし、外部に話すことで、その不安は「家賃の割合が高すぎる」「ターゲット設定がずれている」といった具体的なビジネス上の課題へと置き換えられます 。
この客観的な視点の獲得こそが、次の一歩を踏み出す原動力となります。専門家は、その変換を可能にするためのツールや知識を提供してくれる存在です。
このプロセスを通じて、経営者は「なぜ儲からないのか」という問いの答えを見つけるだけでなく、「どうすれば改善できるか」という具体的な行動計画を手に入れることができます。
「塾経営 儲からない」という検索の背後には、教育への情熱と経営上の現実のギャップに苦しむ、一人の教育者の存在があります。
この記事が、あなたの悩みを客観的に見つめ直し、事業を継続していくための確かな一歩を踏み出すきっかけとなることを願っています。
そしてもし・・・懸命に努力はしたが、一生懸命考えてみたが・・・どうしても気持ちが前に向かない、何となく気持ちが初期の頃と比べて後ろ向きになってしまっている(※初期とは開校時のことです)、1人になると不安感に襲われる・・・
月末時点の勘定をすると、本当にマズイ状況だということをあらためて認識する・・・
このような状況になっていたら、「譲渡」という選択肢もご検討頂くといいかもしれません。
筆者であるCROSS M&A(通称:クロスマ)のアドバイザーも「廃業・・・」という2文字が浮かんだときに、
ダメ元で譲渡をやってみようか、そう思ってから2か月間で譲渡契約が成立した経験があります。コスト的には、廃業に比べて300万円以上得になった計算でした。
学習塾・習いごと教室のオーナー経験があり、廃業も譲渡も経験しています。
従って今、この記事をふとしたきっかけでご覧になった方がもし同じように悩まれていたのだとしたら、是非相談相手に選んでほしいです。
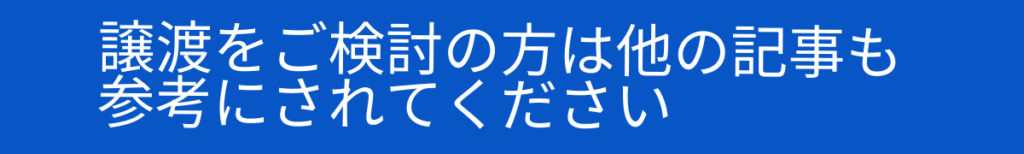
閉校・廃業を考える前に「譲渡」を
①仲介不動産会社への連絡
自分が望む金額でスピーディーに
習いごと教室の事業承継
②FC加盟の学習塾・習いごと教室
③スムーズ引継ぎ シート管理
買い手の心を掴む概要説明の極意
中学受験対応ができる場合の価値増加
BATONZの学習塾・習いごと専門家
学習塾の譲渡:ベストな時期はいつ?
学習塾譲渡:電話番号の引き継ぎ
売りっぱなしの時代は終わっている
後継者がいない学習塾オーナー様へ
習いごと教室の事業承継
個人塾の閉鎖、 費用はいくら?
英会話教室売却完全ガイド
学習塾の事業譲渡契約書
【学習塾譲渡】仲介ガイド
プログラミング教室のM&Aを
塾の譲渡、気になる「相場」は?
生徒数減少に直面した塾オーナー様へ
急募 不動産・FC契約更新間近
塾の譲渡は「面倒」じゃない!
塾の譲渡:理想の買い手を見つける
NN情報(ノンネーム情報)の重要性
売り手市場から買い手市場へ!
売却する際に準備すべき資料
企業概要書(IM)の作り方
売却、今こそ決断の夏!生徒数で
「譲渡」が「買収」の5倍検索される
【初心者向け】M&A簡易概要書
同族承継が第三者承継になる実情
「教育モデル改革」が譲渡価値UP
事業譲渡と株式譲渡の基本
株式譲渡と事業譲渡の税務
M&Aの税務基礎知識
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日
学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて
#不動産契約
#事業譲渡
#保証金
#名義変更
#大家承諾
#契約書条項
#承諾料
#賃貸借契約
#賃貸借譲渡

2026年01月05日
フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由
#AI教材塾経営
#フランチャイズ売却
#個人塾デジタル化
#塾オーナー出口戦略
#塾居抜き売却
#塾経営M&A
#学習塾事業承継
#学習塾再編淘汰
#学習塾譲渡
#学習塾閉校コスト

2025年12月22日
学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説
#M&A
#デューデリジェンス
#ページビュー
#事業承継
#個別指導塾
#営業利益
#売却価格
#学習塾
#実名商談
#成約期間
#譲渡