社会が苦手な生徒の保護者に「社会」の受講を断り、「英数」へのシフトを促すための対話術
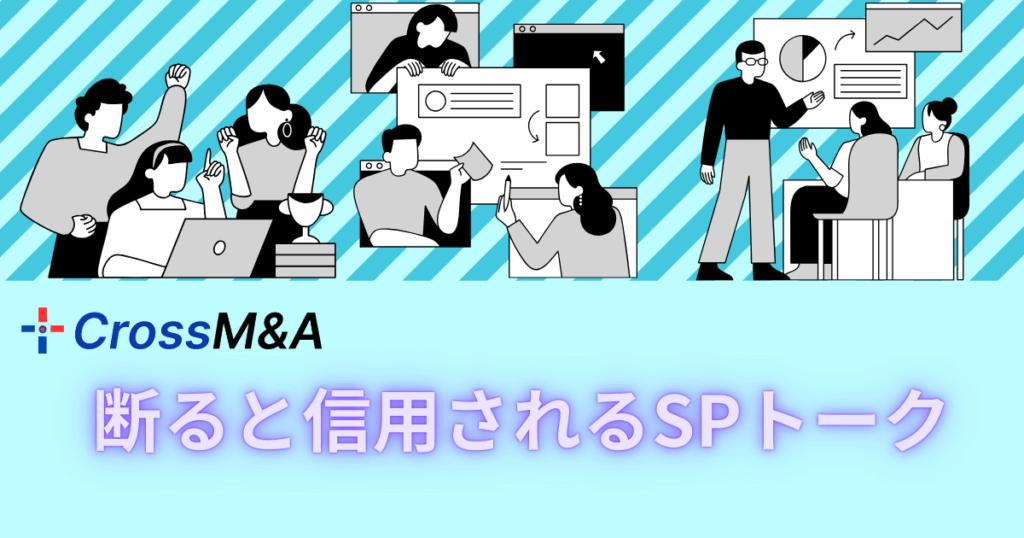
今回はほんの少し高等テクニックですが、トークを変に端折らないで忠実に再現してもらえたら保護者にきちんと伝わりますし、逆に信用度が高くなりますので、
是非取り入れてみてください。
社会科を苦手とするお子さんが「社会」の受講を希望した場合、多くの保護者は「せっかく本人がやる気になっているなら…」と考え、その選択を尊重しようとします。
しかし、塾や教室の責任者として、その選択が必ずしも最善ではないことを伝える必要があります。なぜなら、社会の学習は、単に塾で授業を受けるだけでなく、家庭での学習習慣が何より重要だからです。
この対話は、「社会の授業は不要です」と切り捨てるのではなく、保護者が抱える不安や期待に寄り添いながら、より効果的な学習方法を提案する機会と捉えるべきです。
この記事では、生徒が自ら「社会をやりたい」と希望してきた際の、保護者との対話術を具体的に解説します。生徒の主体性を尊重しつつ、最終的に英数に注力することがなぜ重要なのか、その理由を丁寧に伝え、保護者からの信頼を得るためのノウハウをお伝えします。
「断ると信用される」その仕組み、ニュアンスを感じ取ってみてください。
受講科目に「社会」を選んだ生徒との対話術
通常、受講科目は保護者と生徒が相談して決めるものですが、社会科を選択する場合、その多くは生徒本人の意志によるものです。お子さんが「社会が苦手だから、塾で教えてほしい」と訴え、それを聞いた保護者が「じゃあ、社会にしようか」と決めるケースが非常に多いです。
最初の起点は重要ですので、社会の受講という話が出てきたら、それが保護者主導なのか、生徒からの意志によるものなのかを探っておきましょう。
たいていは、保護者ではなく「本人」です。
この「苦手だから教えてほしい」という言葉の裏には、様々な気持ちが隠されています。
・「社会は暗記科目だから、誰かに教えてもらえれば楽になるはず」
・「歴史の流れや地理のデータが頭に入ってこない」
・「学校の授業だけでは理解が進まない」
・「暗記が苦手」
これらの気持ちに寄り添いながら、保護者に「社会の受講は必要ない」と伝えることは、一見、保護者の意向に反するように思えます。しかし、正しいアプローチをすれば、保護者はむしろ「この先生は、本当に子どものことを考えてくれている」と安心し、信頼関係を築くことができます。
なぜなら、保護者の多くは、内心で「社会の勉強にまでお金をかけるのはもったいないのでは?」と感じているからです。社会は英数に比べ、応用力や思考力を問われる機会が少なく、暗記が中心となる教科です。
もちろん暗記だけではなく、地理の時差計算や資料、史料の読み取りなどもあるため、単純ではない部分もありますが、それでも総じて暗記要素が圧倒的に多いです。覚えていなければ回答できない教科です。
社会は暗記なのだから、塾で授業を受けるよりも、自学自習で十分対応できると考える保護者は少なくありません。
あなたの役割は、この保護者の心の声を代弁することです。ただし、ただ「社会はやめましょう」と伝えるだけでは、保護者は納得しません。代案を提示し、具体的な行動プランを示すことが不可欠です。
ステップ1:生徒の「社会が苦手」を深掘りする
まず、生徒自身がなぜ社会が苦手だと感じているのか、その根本原因を探ります。
- 「歴史が覚えられない」:年号や人物名、出来事がバラバラで、繋がりが見えないと感じている可能性があります。
- 「地理の地名や産業が頭に入らない」:地図と情報が結びつかず、単なる文字の羅列に見えているかもしれません。
- 「公民の仕組みが理解できない」:専門用語や抽象的な概念に抵抗を感じている可能性があります。
これらの原因を突き止めることで、単なる「暗記が苦手」という表面的な問題だけでなく、学習方法そのものに問題があることを見抜くことができます。
ステップ2:保護者への「もったいない」を代弁する
生徒の苦手意識を把握したら、保護者に対して以下のように伝えます。
「〇〇くん(さん)が社会を苦手だと感じていらっしゃるのはよく分かりました。でも、正直にお話ししますと、私は社会の授業を今すぐ始めるのは、少々もったいないと考えています。」
この「もったいない」という言葉が、保護者の心に響きます。なぜなら、保護者が心の奥底で感じていることを、あなたが代わりに言葉にしてくれたからです。
ステップ3:代替案を提示し、具体的な学習方法を実演する
「では、どうすればよいのでしょうか?」という保護者の問いに対し、具体的な代替案を提示します。それが、「社会の効率的な勉強方法を無料で伝授する」というアプローチです。
このアプローチは、保護者に対して「お金をかけなくても、社会の苦手は克服できる」というメッセージを明確に伝えます。この段階で、保護者からの信頼は格段に高まります。
では、実例を踏まえて説明させていただきます。本記事の一番大事な部分で、実践していただければ必ず成功します。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
1.最適なテキストの選定と使い方
学校のワークや教科書は、情報が網羅的に記載されていますが、必ずしも初学者にとって分かりやすい構成とは言えません。そこで、市販の分かりやすい参考書を紹介します。
- 推薦するテキストの基準
- ビジュアルが豊富:図やイラスト、写真が多く、視覚的に理解しやすいものを選びます。
- ストーリー性がある:特に歴史では、出来事の因果関係がストーリーのように解説されているものが有効です。
- 単元が細かく分かれている:短い時間で一つの単元を完結できるような構成のものが、集中力を維持するのに役立ちます。
★関東圏でしたら、育伸社のiワークが非常に使いやすいです。
(※、育伸社の回し者ではありませんのでご安心ください)
2.デモンストレーションの実施
保護者と生徒の目の前で、実際にテキストを使った学習方法を実演します。
【歴史のデモンストレーション】 例えば、歴史の「江戸時代」の単元を使ってデモンストレーションを行います。
- 全体像の把握:まず、テキストの「江戸時代」のページを開き、「なぜ鎖国は始まったのか」「なぜ幕末に開国したのか」といった大きなテーマを提示します。
- ストーリーとして解説:教科書に出てくる出来事を、まるで一つの物語のように語ります。「秀吉が天下を統一した後に…」「家康が江戸幕府を開き…」といった流れを、人物の感情や思惑を交えながら話すと、生徒は興味を持ちやすくなります。
- 因果関係の理解:「〇〇が起こったから、××という出来事が起きた」というように、因果関係を明確にします。これにより、年号や出来事を単体で暗記するのではなく、流れの中で覚えることができるようになります。
【地理のデモンストレーション】 地理の「日本の工業」の単元を使ってデモンストレーションを行います。
- 地図との連携:テキストの地図を見せながら、「この地方はなぜ〇〇産業が盛んなのか」を解説します。
- 理由の提示:「太平洋ベルト地帯は、なぜ工業が発達したのか?それは、原料の輸入や製品の輸出に便利な港があるからだよ」といったように、理由を明確に伝えます。
- 具体的な例の提示:身近な製品や企業の名前を挙げ、「この車は〇〇県の工場で作られているんだよ」と話すと、生徒は自分ごととして捉えやすくなります。
このデモンストレーションを通じて、保護者は「社会の勉強は、ただ暗記するだけでなく、こうして理解を深めることが大切なんだ」と納得します。そして、生徒は「こんな風に勉強すれば、社会も面白そう!」と感じ、自学自習へのモチベーションが高まります。
デモンストレーションのときには、ご自身が得意な箇所でいいです。歴史か地理のうちのいずれかが良いと思います。公民でもいいですが、1ページに覚えるべき語句が公民の場合多いのと、公民の対象は中学3年生ですから、トークの打ち出しが出来る学年が3年生の春、夏(遅くとも)ぐらいまでに限定されてしまうからです。
たいていの教科書準拠版のテキストは、教科書の該当ページがテキスト内に書かれていますので、まずはそこを説明します。
以下のトークは覚えましょう。
①太郎君、お母さん、こちらご覧ください。テキストのこの部分に教科書の該当ページが書かれていますよね。太郎君、まずはね、この該当する教科書ページを我慢して読むんだ。その際、別に暗記しよう!なんて気負わなくていいので、普通に読んでくれていいよ。
②続いてお母さん、太郎君、こちらのページに重要な語句には赤とか青で色がついていますよね。この語句は重要な語句なのですが、これを意識してテキストのこの見開きのページを見るんだ。ノートにまとめなくていいよ。
見るときには、目力!眼力!みたいな感じで真剣に読んでみてね。
③そしたらね、お母さん、太郎君、次のページを開いてごらん。ここ、お母さん、空欄になっていますよね。ここの部分は「前のページを見ながらでもいいので」答えをノートに書いてほしいのです。
太郎君わかる?前のページを見て構わないから、解説ページのところから当てはまる答えを探してごらん。
④うん、いいね!その感じだよ。見れば答えがちゃんとあるから、気分的に楽だよね。なんだか答えを見て書いている・・・そう思う?いや、全然違うんだよね。自分で答えとなるところを探している段階から、すでに勉強がスタートしているからね。前のページは解答ではなくて、解説だから。
ここから答えになる部分を探し出すという感じだよね。
⑤はい、次にステップ!そしたらね、次のページを開いてごらん。
ここに20問の重要語句についての一問一答があるよね。これはね、ちょっと頑張って自分で考えて答えをノートに書いてみてほしいんだ。
お母さん、20問の問題ですが、最初は多分覚えきれていませんから、3分の1とか半分ぐらいしか書けないかもしれません。それでもかまいません。
そのあと、しっかりと解答をチェックして、間違えた問題とか書けなかった問題をノートに書くのです。
⑥次に標準問題というのがあるよね。これは飛ばしていい。ここは定期テストとかの前に学校のワークと一緒に解いて練習したほうがいいからね。
はい、ここまで!
どう、こんな感じで社会の勉強を、このテキストすっごくオススメなんだけど、これを使ってやると、今までよりも確実に結果の違いがでるよ。
お母さん、実際こんな感じです。いかがですか?
この一連の流れをやったときに、保護者から笑顔が見られないことは今まで一度もありません。
そして、次に進みます。
ステップ4:コストパフォーマンスを明確に提示する
デモンストレーションの後、金銭的な側面から「なぜ社会の受講がもったいないのか」をさらに具体的に説明します。
- 社会の年間受講コスト
- 授業料(例:月〇〇円×12ヶ月=〇〇円)
- テキスト代(例:〇〇円)
- 合計:〇〇円
「もし社会を年間受講されるとなると、これだけの費用がかかります。しかし、この費用を英数に回したらどうなるでしょうか?・・・と言いますか、私は社会にコストかけるなら、英語か数学にもっと回してもらったほうがいいと思うのです」
- 英数への費用投入のメリット
- 英数こそ、プロの指導が必要:英語の文法や数学の応用問題は、自力で解決するのが難しい場合が多いです。プロの解説や演習指導を受けることで、短期間で効率的に学力を向上させることができます。
- 英数こそ、コストをかけるべき:入試における英数の配点は、多くの学校で社会よりも高いため、英数の学力向上は合格に直結します。
この説明により、保護者は「社会にお金をかけるよりも、英数に集中させた方が、子どもの将来にとってプラスになる」と論理的に納得します。
まとめ:信頼を得て「英数」に誘導する
社会が苦手な生徒が「社会」の受講を希望してきた際、すぐに承諾するのではなく、以下のプロセスを踏むことが重要です。
- 生徒の「苦手」の根本原因を深掘りする。
- 保護者が心の奥で感じている「もったいない」という気持ちを代弁する。
- 「社会の学習方法」を無料で伝授する代替案を提示し、実際にデモンストレーションを行う。
- 金銭的なコストを明確に示し、社会にかける費用を英数に回すことのメリットを訴える。
このプロセスを通じて、あなたは単に塾のサービスを提供するだけでなく、生徒一人ひとりの学習状況を真剣に考え、最も効果的な学習方法を提案する「教育のプロフェッショナル」として、保護者からの信頼を獲得できます。
そして、この信頼関係こそが、長期的な生徒の定着と、教室の評判向上に繋がるのです。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2025年11月19日
学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ
#アルバイト募集
#リケジョ
#女性理系講師
#学習塾
#学習塾経営
#差別化
#理系講師
#講師採用
#集客
#高校生指導

2025年10月30日
開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略
#Googleツール活用
#コスト削減
#デジタル化
#ペーパーレス化
#効率化
#合理化
#塾経営
#塾運営
#時短
#時間的疲労
#無料ツール
#生産管理
#解消
#開校2年目

2025年09月26日
塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について
#入塾面談
#塾の成功
#塾経営
#塾講師
#学習塾
#学習塾運営
#期限厳守
#生徒指導
#良質顧客
#顧客育成