【重要】閉校・廃業時の原状回復トラブルのほとんどは対抗できる(小さくないコストカット)
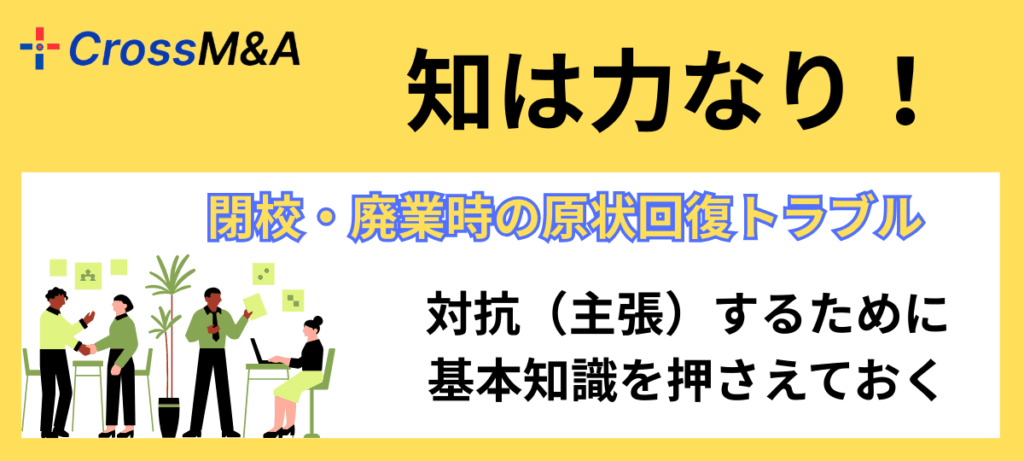
事業を閉じる決断は、決して簡単なことではありません。しかし、その決断を下したからこそ、最後の最後まで責任を持って、円滑に事を進める必要があります。特に、多くのトラブルが発生しがちなのが、オフィスの解約や店舗の閉鎖に伴う「原状回復」です。
初めに用語チェックをしておきましょう。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、賃貸物件を退去する際に、借主が「借りた時の状態」または「本来あるべき状態」に部屋を戻すことを指します。
たまに「現状回復」と記されていることがありますが、これは誤記だと思ってください。不動産契約で登場する「げんじょうかいふく」は「原状回復」です。
事業閉鎖、閉校という決断をしたら、まず何よりも先に「不動産賃貸借契約書」と「重要事項説明書」を確認しましょう。原状回復についての記載は、不動産賃貸契約書のほうに記載があるはずです。
【原状回復の例文】
「乙(借主)は、賃貸借契約が終了したときは、本賃貸借室内の物品等一切を搬出し、賃貸借室を本契約賃貸借期間開始日の原状に修復して甲(貸主)に明け渡すものとする」
こちらの文章は一般的なものですが、より細かく記載がある場合として特約項目を設けて書かれていたりするなどがありますので、やはりしっかりと確認しておくことが大切です。
最初の契約時のことを思い出そう
不動産の賃貸借契約書を交わすときには、決まったルールがあります。
①重要事項説明書は、宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に基づいて作成・交付されるため、「35条書面」と呼ばれます。賃貸物件を契約する際、賃貸借契約書に署名・捺印する前に「重要事項説明書」の説明が義務付けられています。説明は契約者本人に対して、「宅地建物取引士」が「宅建建物取引証」を提示の上、説明することが義務付けられています。
②不動産賃貸借契約書は、宅建業法37条に基づく契約書類となります。ここでは、宅地建物取引士の記名・押印をすることが義務付けられていますが、説明そのものは宅建士じゃなくても大丈夫です。
細かく書きましたが、
・契約前の宅建士が宅建取引証を提示して、重要事項説明書をきちんと説明し
・宅建士の記名押印がされた契約書を交わす
この概要と手順で行われたのかどうかを思いだしておいてください。これらのルールが守られていないことが明白であった場合、それは宅建業法違反となります。
不動産取引で重要事項説明(重説)が説明されていない場合、宅地建物取引業法違反となり、宅建業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは両方を併科される罰則があります。また、宅建業者は業務停止処分や免許の取消処分を受ける可能性もあり、違反した宅建士にも指示処分や業務停止処分が課されることがあります。
もし、万が一、例えば 重要事項説明書が郵送などでやり取りされていたとします。(対面で説明しなくてはいけないので)
その場合、原状回復などで揉めたときには、かなり借主が有利になります。昨今、不動産の原状回復に絡むトラブルがとても多いので、自分自身が有利になるポイントを見出すためにこの記載をしました。
つまり・・・数年前のことでなかなか記憶の糸を辿るのが難しいかと思いますが、不動産の賃貸借契約を結んだとき、重要事項説明書を取り交わしたときの内容を思い出しておいてくださいという主旨です。
原状回復でトラブルが多発する理由
なぜ、これほどまでに原状回復をめぐるトラブルが多いのでしょうか?その背景には、借り手と貸し手の認識のズレ、そして法律上の解釈の曖昧さが存在します。多くの事業主は、契約書の内容を深く理解しないまま「最後に綺麗にして返せばいいだろう」と安易に考えてしまいがちです。しかし、この「綺麗にする」という言葉の解釈こそが、トラブルの根源となります。
敷金・保証金の性質と返還されないケース
敷金・保証金とは?
そもそも、契約時に預け入れた敷金や保証金とは何でしょうか?これらは、賃料の滞納や建物の損害など、将来的に発生するかもしれない借主の債務を担保するために、貸主が預かるお金です。賃貸期間が終了し、すべての債務が清算された後に、残額が返還されるのが原則です。
以下の内容は、不動産会社と最後揉めてしまったときに、対抗できるかどうかの判断をするため、よく確認ください。
こういうときに使う「対抗」という言葉は、簡単に言うと民法用語なので、初めて見るといきなり争いごとか?と思ってしまうぐらい強い語気の言葉です。
なので「主張」と言い換えるとすっきりと頭に入ると思います。
敷金・保証金が返還されない・減額されるケース
しかし、以下のケースでは、敷金や保証金が返還されない、あるいは大幅に減額される可能性があります。
- 賃料の滞納がある場合 これは最もわかりやすいケースです。滞納分が敷金・保証金から差し引かれます。
- 解約の事前告知が遅れた場合 多くの契約書には、解約の数ヶ月前までに貸主へ書面で通知することが定められています。この告知が遅れると、規定された期間の賃料が違約金として徴収されることがあります。
- 原状回復費用が莫大になった場合 これが最も多いトラブルです。通常損耗を超えた建物の損傷や、内装の造作、設備を撤去する費用が、貸主が提示する見積もりによって高額になることがあります。この費用が敷金・保証金から差し引かれます。
- 契約書に「償却」の特約がある場合 事業用賃貸借契約では、契約期間の経過に伴って敷金・保証金の一部が返還されない「償却」という特約が付いている場合があります。たとえば、「敷金の20%は償却」と記載されていれば、20%は返ってこないことになります。
滞納があれば、敷金や保証金から引かれてしまうのは当然ですからこれはあきらめてください。
事前告知は、大方3か月前通知ですが、物件によって違いますから、これも契約書などでよく確認しておいてください。
問題は・・・原状回復として引かれてしまうお金と、契約段階で特約された償却項目があった場合です。
いずれも契約書上に文書として記載があります。
原状回復は下のライン以降に来ましたので、償却について軽く記載しておきます。
最高裁判決は、賃貸人と賃借人の間の情報や交渉力の格差を背景に、賃借人が一方的に不利益な負担を余儀なくされているケースが多いとして、敷引金の額が高額に過ぎる場合には、敷金償却の特約(敷引特約)が無効になり得るとしています。
これは、いわゆる償却として契約書上に記載があったとしても、あまりにも高額になる場合は、その特約そのものが無効に「なりうる」という内容です。
しかし注意してもらいたいのは、「なる」わけではなく、償却として記載された額や%表示が高すぎない場合には、有効となるのです。
しかしこれも考え方、規定のとらえ方ですので、トラブル要素の一つとなっています。
さて、では「原状回復」についての内容に入ります。
原状回復で絶対に知っておくべき3つのポイント
原状回復を巡るトラブルを避けるためには、以下の3つのポイントを事業開始時から、そして閉鎖を決めた今、改めて確認することが非常に重要です。
1. 契約時に重要事項説明書と契約書を徹底的に確認する
事業の夢と希望に胸を膨らませている契約時、多くの人は目の前の契約書を「とりあえず」と読み飛ばしてしまいがちです。しかし、ここにこそ、トラブルの芽は潜んでいます。特に、以下の項目を隅から隅まで確認してください。
- 原状回復義務の範囲 「貸主が指定する業者で原状回復を行うこと」といった特約がないか。「スケルトンでの引き渡し」が義務付けられているか。
- 敷金・保証金の「償却」に関する規定 償却の有無、償却率を必ず確認しましょう。
- 解約予告期間 「解約の6ヶ月前までに書面で通知」など、予告期間が定められています。
※今までの事例では、学習塾や習いごとなどの事務所仕様的なものの場合は、解約予告期間は2~3か月であることが多いです。(6か月前は・・・長すぎ・・・)
2. 更新時に不利な内容になっていないか確認する
事業が長くなると、契約を更新する機会が訪れます。この時、「契約書の内容が更新時に変更されていないか」を再確認することが非常に重要です。貸主から「更新契約書」が送られてきたら、前回の契約書と見比べ、原状回復に関する条項が厳しくなっていないか、償却率が上がっていないかなどをチェックしましょう。
3. 通常損耗の概念を理解し、不要な負担を避ける
裁判所の判例や国土交通省のガイドラインでは、「通常損耗」の概念が示されています。これは、賃貸物件を普通に使用し、経年劣化によって生じる損耗(例えば、壁紙の日焼け、家具の設置跡、画鋲の穴など)のことで、これらは貸主の負担とされています。
しかし、多くの貸主は、こうした通常損耗部分も借主の負担として請求してくることがあります。これが原状回復に関してのトラブルが多い理由なのです。(※この点重要です)
あなたは、この「通常損耗」と、借主の故意や過失によって生じた「特別損耗」(例:壁に開けた大きな穴、タバコによる焦げ跡、水濡れによるカビなど)を明確に区別し、通常損耗分の費用は支払う義務がないことを主張する必要があります。
解約時の具体的なアクションと注意点
原状回復を巡るトラブルを未然に防ぎ、スムーズに解約を完了させるためには、以下の手順を確実に踏むことが不可欠です。
1. 規定日時前の解約予告
契約書に記載された解約予告期間を確認し、定められた期限内に書面で解約の意思を通知します。口頭での通知はトラブルの元となりますので、必ず書面で行いましょう。
2. 解約時の立ち会いと記録
貸主または指定業者との立ち会いの際には、以下の点を記録します。
- 現状の写真撮影・動画撮影 室内のすべての箇所を、損傷箇所だけでなく全体をくまなく撮影します。特に、内装の汚れや設備の破損箇所は拡大して記録しましょう。
- 書面での確認 立ち会いの場で、原状回復の範囲や工事内容、費用について口頭で確認し、その内容を記録します。できれば貸主のサインをもらうのが理想的です。
3. 清算書の要求
解約後、貸主から「清算書」を必ず受け取りましょう。
清算書には、敷金・保証金から差し引かれた項目(賃料、原状回復費用など)とその金額が明記されています。不明瞭な項目や高額な請求がある場合は、この清算書を基に交渉します。
納得できない請求には「主張」を
もし、貸主から提示された原状回復費用や清算内容に納得できない場合は、泣き寝入りする必要はありません。正当な根拠を持って、しっかりとあなたの主張を伝えるべきです。
知っておきたい前知識:専門家の活用と交渉
- 原状回復の相見積もりをとる 貸主が指定する業者の見積もりが高すぎる場合があります。複数の業者から相見積もりを取ることで、適正な価格を把握できます。
- 内容証明郵便の活用 話し合いが進まない場合や、貸主からの連絡が途絶えた場合は、内容証明郵便であなたの主張を書面で送ることも有効です。法的な効力を持つ書面として、相手にプレッシャーを与えることができます。
- 専門家への相談 個人の力では解決が難しいと感じたら、弁護士や司法書士、原状回復専門のコンサルタントに相談することを検討しましょう。
事業を終えることは、新たな人生の始まりでもあります。最後のトラブルでつまづくことのないよう、冷静に、そして計画的に事業の幕引きを進めてください。この行動こそが、これまでの努力と成果を無駄にしない、最後の重要なステップとなります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
不動産契約(賃貸借契約)におけるこの「原状回復」に絡む敷金・保証金が返還されないトラブルは、非常に多いです。
CROSS M&Aのアドバイザーは、以前、譲渡ではなく「閉校」を選んだ教室がありました。自分が住む場所や事業用物件も含めると、それまで非常に多くの不動産賃貸契約を結んできた、または解約してきた経験があるため、そのときの経験は非常に大きなものとなりました。
結論から言えば、けっこう揉めて最後、当方が原告の裁判になりました。しかし結果はすぐに和解になり、原告である私どもの主張がほぼ認められた形です。こんな裁判になる前に、なぜ普通に当方の主張を受けてくれなかったのか、今でも不思議ですが、かなり強気の不動産会社もあるのだということです。
皆さんには、そんな経験はしてほしくありませんので、このサイトにおける記事や、記事内に記載した「実例(実話)」の箇所は生々しいリアルな話としてそのままストレートに受けていただければ幸いです。
ここであまり詳細を書くとさらに10,000文字ぐらい消費しそうですので、ザクっと概要を書きますと、最初の段階で清算見積をした段階では、ほとんど残金が戻らないという計算をされてしまったため、不服をメールなどで申し立てをしたのですが、不動産会社の担当が頑として譲らず、仕方なく専門家に相談し、内容証明を送り、きちんと自分が納得できる幕引きにしたというケースです。
これは、誰がどう見てもおかしなケースでしたので、わかりやすく、相手さんも当方も無駄な時間を削ったわけですが、先方の弁護士さんも最初から負けをわかっていたためか、丁寧に対応してくれました。
ポイントは、「通常損耗」です。
この言葉、ものすごい大きな意味を持つキーワードですので、是非覚えておいてください。
そして、実はこのときに、今までないぐらい困ったときの対応として今世紀一番を与えたい業者さんがいますので、トラブルになったときには無料で紹介いたします。
こちらの方がいたからこそ、最後まで力強かったですし、すごくためになりました。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月31日
なぜ「低単価・多人数」の塾は強いのか?長期繁栄を実現する経営戦略
#リスク分散
#一人当たり単価
#収益構造
#収益構造シミュレーション
#口コミの母数
#塾運営の標準化
#学習塾経営
#授業頻度の法則
#生徒数最大化
#経営の安定化
#講習平均単価

2026年01月19日
2026年1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト!ここから読み取る大学入試の変化
#2026年
#タイムマシン
#ベルサイユのばら
#入試改革
#大学入学共通テスト
#思考力
#探求学習
#文理融合
#新課程入試
#歴史総合

2026年01月13日
私立中学や私立高校で「大学へ直結する、思考型の学習」をテーマに学習カリキュラムを革新的に変更しようとする流れ!
#カリキュラム
#パラダイムシフト
#大学入試改革
#学習塾
#思考型学習
#探求学習
#教育の未来
#私立校
#総合型選抜
#非認知能力