学習塾は斜陽産業?【2025年版】新規開業・異業種参入で成功する戦略を徹底解説
はじめに:多くの人が抱く「学習塾=斜陽産業」という誤解
これから学習塾を始めようと考えているあなた、あるいはすでに塾を経営していて事業拡大を検討しているあなた。そうした方々からしばしば聞かれるのが、
・「学習塾はもう古いのではないか」
・「少子化で生徒が減る一方ではないか」
といった不安の声です。メディアでも「学習塾の倒産が増加」といったニュースが報じられ、漠然と「学習塾業界は斜陽産業だ」というイメージが広まっているかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか?
結論から申し上げます。学習塾業界は、決して「斜陽産業」ではありません。 むしろ、新たな可能性が次々と芽生え、多様なビジネスチャンスに満ちた、今まさに変革の真っ只中にある「成長産業」だと私は考えます。
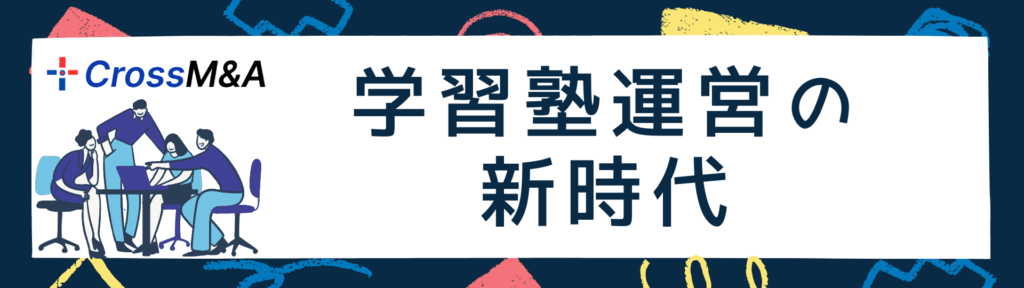
この業界が古い体質のまま停滞しているかのように見えるのは、固定観念にとらわれた古いビジネスモデルが機能しなくなっているに過ぎません。これからの時代に求められるのは、既存の枠組みを打ち破る新しい発想と、柔軟なビジネス展開です。
本記事では、なぜ学習塾業界が「斜陽」ではないのか、そして、これからこの業界で成功を収めるために必要な視点や具体的な戦略について、徹底的に解説していきます。
なぜ「斜陽」ではないのか?:データから見る学習塾業界の真実
まず、感情的な議論ではなく、客観的なデータを見てみましょう。確かに、日本の18歳人口は減少の一途をたどっています。これは事実です。しかし、生徒数の減少が即座に市場規模の縮小を意味するわけではありません。
関連記事として 数多くある譲渡案件の中で、なぜ今、学習塾がおすすめなのか? 未経験からでも参入しやすい「教育ビジネス」の魅力 わかりやすいグラフ記事内にありますので、こちらをご確認ください。
1. 教育への投資意欲はむしろ高まっている
少子化が進む一方で、一家庭あたりの教育費支出は増加傾向にあります。子ども一人にかける教育費は、親の教育熱心さや将来への不安から、年々高まっているのです。特に都市部においてはその傾向が顕著です。つまり、パイのサイズは縮小しても、1人あたりの単価が上がっているため、市場全体の売上は横ばい、あるいは緩やかに上昇しているという見方もできます。
2. 多様化する教育ニーズ
かつての塾は「学校の授業の補習」や「受験対策」が主な役割でした。しかし、現代の子どもたちの教育ニーズは非常に多様です。
プログラミング、ロボット工学、論理的思考力を養うSTEM教育、英会話、プレゼンテーション能力、さらには金融教育や起業家精神を育む教育まで、その内容は多岐にわたります。学校教育だけでは満たせない、こうした新しいニーズに応えることができる塾は、生徒や保護者から強く求められています。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】
プログラミングと学習塾
ロボット工学と学習塾
STEM教育と学習塾
英会話と学習塾
その他習いごとと学習塾
このように並べてみると、学習塾は入口ではなく出口である可能性が高いことに気付きます。
わかりやすく言えば、
小学2年生、3年生、4年生ぐらいの子供がプログラミングを習っていたとします。この子供は、絶対ではないにしても塾通いを始めます。
それが小学5年からかもしれません。6年からかも・・中学からかも・・・それはわかりませんが、プログラミングという習いごとが入口となって、最終着地として学習塾があるという意味です。
なぜ、「出口」が学習塾かと申しますと、「受験」があるからです。
・習字を習っていたけれど、受験なのでそちらにシフト
・サッカーのクラブチームに入っていましたが、受験期は一時お休みして塾で
・水泳と体操を習っていましたが、中学受験になるので塾一本に絞ります
・英会話を習っているのですが、もうすぐ受験なので塾の授業を中心に考えます
面談、新規対応をしていて思うのが、「塾」というのは出口なのだということがわかります。今は、習いごとの需要もかなり多いのです。
そして、習いごとを多くやっているご家庭では、「我が子にはこうなってほしい」という強い思いがあることがわかります。
さらに言うと、そのように習いごとをけっこう多くやっている(やらせている)ご家庭の場合、たいていは学習面でも遅れをとらせられないと考えている保護者が9割です。
つまり、総体的に教育に熱心なご家庭なのです。運動系もしっかりと習わせたいけれど、勉強面でも上位にいってほしい願いを持っている保護者さんが多いです。
上位志向がなかったとしても文武両道を目指しているフシがあります。
そして、習いごとを多くやっているご家庭のほとんどすべてが、受験期になると「受験」に対しての集約的な考えが増し、時間とコストを学習に全振りするのです。
ここに書かせて頂いたのは、15年以上に及ぶ学習塾運営で「実際に」経験してきたことです。
保護者の発言や、「実際に」習いごとから塾への大幅シフトをかけてきた実例ばかりですので、例としては100や200ではありません。
ほぼ全てなので、数千事例だと思ってください。
・中学受験期なのに、今やっている週3回の授業を減らしてサッカーを習いたい
・高校受験期なのに、プログラミングを極めたい
・大学受験期なのに、そろばんの級をとりたい
このような塾が入口で、習いごとに流れている事例はまずありません。
このことも少しヒントになるように思うのですがいかがでしょうか。
3. オンライン化の進展による「場所の壁」の消失
新型コロナウイルスの流行は、学習塾業界に大きな変化をもたらしました。その一つが、オンライン教育の普及です。これまでは、塾の立地が非常に重要でした。
しかし、オンライン授業が一般化したことで、地方に住む生徒が都市部の有名塾の授業を受けたり、逆に地方の特色ある塾が全国の生徒を対象にしたりと、地理的な制約がほとんどなくなりました。これにより、従来の地域密着型ビジネスの枠を超えた、新たなビジネスモデルが構築できるようになりました。
新しい価値創造の時代:3つの変革が未来を拓く
では、この新しい時代において、学習塾経営者はどのような視点を持つべきでしょうか。鍵となるのは、「新しいアイデア」「収益の多様化」「他業種との融合」という3つの変革です。
変革1:新しいアイデアで「塾」の概念を再定義する
これからの塾は、単に「勉強を教える場所」ではありません。子どもたちが自律的に学び、未来を生き抜く力を育む「成長支援の場」へと進化する必要があります。
- 学びの個別最適化: AIを活用した教材やアダプティブラーニングを導入し、生徒一人ひとりの進度や理解度に合わせた学習を提供します。これにより、生徒の学習効率を飛躍的に向上させることができます。
- 「探究」を軸にしたプログラム: 正解のない問いに自ら向き合い、思考し、表現する力を養う「探究学習」は、大学入試改革や新しい学習指導要領でも重視されています。こうしたプログラムを塾のカリキュラムに取り入れることで、従来の塾とは一線を画した価値を提供できます。
- 非認知能力の育成: 集中力、忍耐力、協調性、創造性といった、テストの点数では測れない「非認知能力」の育成に特化したプログラムも有力です。将棋、ボードゲーム、プログラミング、プレゼンテーション練習などを通じて、子どもたちの総合的な人間力を高めることができます。
変革2:収益を多様化し、経営基盤を盤石にする
従来の学習塾は、月謝という単一の収入源に依存しがちでした。しかし、これからの時代は複数の収益源を持つことが成功のカギとなります。
- イベント事業の展開: 春休みや夏休み、冬休みを利用して、特定のテーマに特化した短期集中講座や合宿イベントを開催します。普段の生徒だけでなく、新規顧客の獲得にもつながります。
- 教材やコンテンツの販売: 自社開発したオリジナル教材や、オンラインで配信できる動画コンテンツなどを販売することで、月謝以外の収益を生み出すことができます。
- コンサルティング事業: 長年の指導経験で培ったノウハウを活かし、学校や教育機関、他塾へのコンサルティング事業を展開することも可能です。
- フランチャイズ展開: 成功したビジネスモデルをパッケージ化し、フランチャイズとして他地域に展開すれば、一気に事業規模を拡大できます。
変革3:他業種との融合で新しい価値を創造する
学習塾という枠組みにとらわれず、異業種の知恵やサービスを積極的に取り入れることで、これまでにないユニークなビジネスモデルを構築できます。
- カフェやコワーキングスペースとの融合: 塾の機能を持ちながら、カフェやコワーキングスペースとしても利用できる空間を創出します。これにより、子どもだけでなく、その保護者や地域住民も集まるコミュニティの場となり、新たな顧客層を開拓できます。
- 学童保育との連携: 共働き世帯が増える中、学童保育のニーズは高まっています。塾と学童保育を組み合わせることで、放課後を安心して過ごせる場所を提供し、さらにその時間で学習サポートも行うことができます。
- スポーツやアートとの融合: 例えば、スポーツ教室と提携し、「運動+学習」をセットにしたプログラムを提供したり、美術教室と連携して「アート思考」を養うプログラムを開発したりすることも可能です。これにより、多様な才能を持つ子どもたちを惹きつけることができます。
新しい「学習塾」の黎明期:今こそ参入する絶好の機会
従来の「学習塾=受験勉強」というイメージは、もはや過去のものです。
新しい時代が求めるのは、子どもたちの多様な個性を尊重し、自らの力で未来を切り拓く力を育む、革新的な教育サービスです。
これから事業を始めようと考えているあなたは、既存の塾のあり方にとらわれる必要はありません。これまでの経験やスキル、そして何よりあなたのアイデアを掛け合わせることで、唯一無二の塾を創り出すことができます。例えば、
- IT業界で働いていた経験を活かして、プログラミングに特化した塾を開く
- 金融業界の知識を活かして、お金の教育に力を入れた塾を開く
- 接客業の経験を活かして、コミュニケーション能力を重視した指導を行う
といったように、異業種からの参入者こそ、この変革期において最も大きなチャンスを掴む可能性を秘めているのです。
そして、これらを融合する、または道筋を示すことで、上記にしめしたような「出口」=「塾」というリードが出来れば、収益の多様化も同時に叶います。
まとめ:学習塾は「アイデアと行動力」が未来を拓く成長産業
冒頭の問いに戻りましょう。学習塾業界は本当に「斜陽産業」なのか?
繰り返しますが、答えは「No」です。
少子化という逆風は、確かに存在します。しかし、それは同時に、「子ども一人ひとりに深く向き合い、より付加価値の高い教育を提供する」という、新しいビジネスモデルへの転換を促す追い風でもあります。
既存の枠組みにとらわれず、新しいアイデアを試し、収益源を多様化し、他業種との融合によって新しい価値を創造する。そうした柔軟な発想と行動力を持つ人にとっては、学習塾業界は無限の可能性を秘めた、まさに「成長産業」なのです。
「学習塾」という概念そのものが、今、大きく変わり始めています。この変革の時代に、あなたの新しい挑戦を始めることこそ、成功への一番の近道となるでしょう。
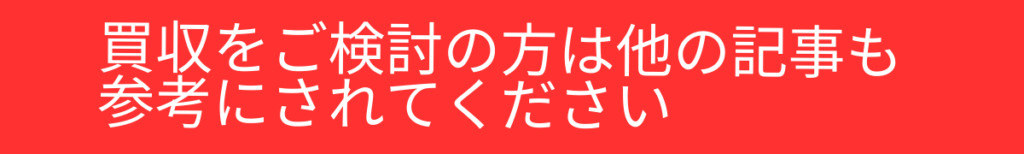
よい物件とのめぐり合い
顧客・従業員(講師)への最初の行動
フランチャイズと独自ブランド
なぜ今、学習塾がおすすめなのか?
見て触れて、深く理解するモデル教室
学習塾・習い事教室の運営は狙い目
学習塾の売上高は月間売上高の16倍
CROSS M&A(クロスM&A)の自信
学習塾とプログラミング教室のM&A
高校生指導ができる学習塾をM&A
60歳からの新しい挑戦!
国立大学最寄り駅の案件は即買い
小学生向け学習塾の料金相場徹底解説
M&A成功のコツ潜在的価値の見極め
【高収益案件を発掘!】小規模学習塾
あなたの既存スキルがM&Aで花開く
千葉県の学習塾買収
習いごとフランチャイズ買収ガイド
個別指導塾M&A成功秘訣と実践ガイド
人が変わると業績が変わる
未経験だからこそ成功率が高い!
簡易株価評価の算定方法(①)
簡易株価評価の算定方法(②)
デューデリジェンス基礎
労務リスクを見抜く専門ガイド
M&Aにおける不動産の基礎知識
保護者との信頼を築く授業報告
学習塾の新しい形:異業種参入歓迎
株式譲渡と事業譲渡、見極めポイント
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略