M&Aを成功に導く決算書の読み解き方:会社の価値を見抜くための徹底解説
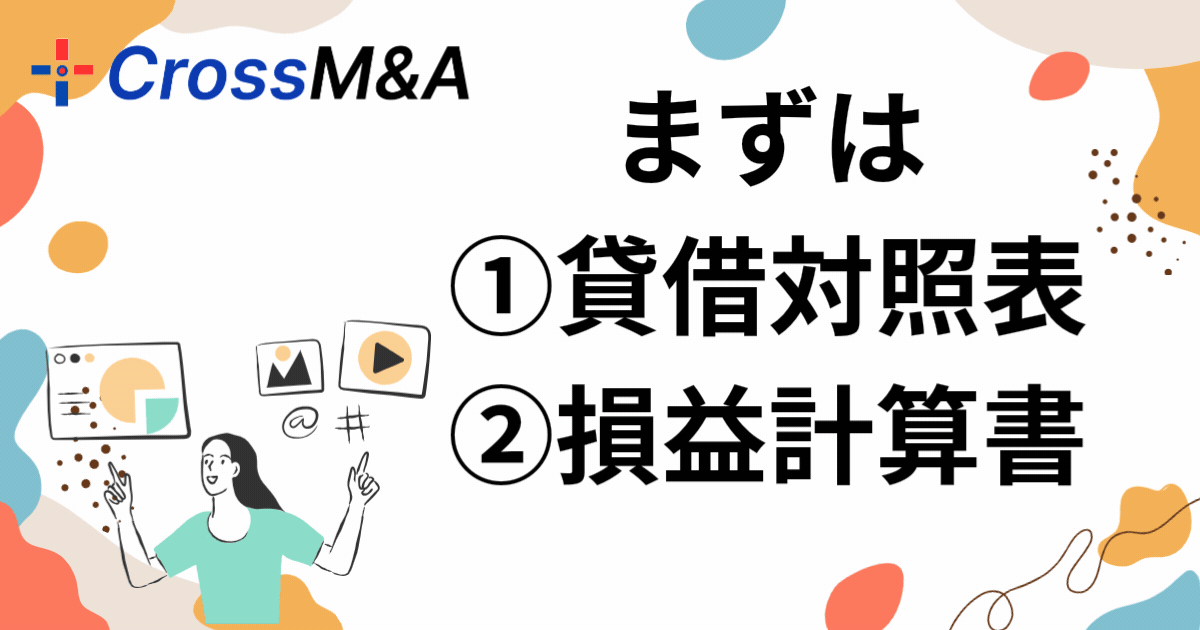
M&A(Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収)の成否は、対象企業の財務状況をどれだけ正確に把握できるかにかかっています。しかし、「決算書」という言葉に難しさを感じる方は少なくありません。この記事では、M&A担当者や経営者の方が、決算書から会社の本質的な価値を見抜くための実践的な方法を、専門知識がなくても理解できるように徹底的に解説します。
この記事で解説する内容:
- 会社の健康診断書、決算書とは何か?財務三表の基本構造
- 決算書から会社の「体力」と「稼ぐ力」を読み解く
- 数字の裏に隠された会社の「本当の実力」を明らかにする方法
- 日々の取引がどう決算書に影響を与えるか?仕訳との関係
1. 会社の健康診断書、決算書とは何か?財務三表の基本構造
決算書は、会社の財政状態と経営成績を数字でまとめたものです。これを読み解くことで、その会社が健全な経営をしているか、将来性があるかなどを判断できます。特に重要なのは、以下の3つの書類です。
- 貸借対照表(BS: Balance Sheet):「会社が今、どのような財産を持っているか」を示します。
- 右側:会社がどうやってお金を集めたか(借入金や資本金など)。
- 左側:集めたお金を何にどう使っているか(現金、建物、在庫など)。
- 左側の合計と右側の合計は常に一致します。まるでシーソーのようにバランスが取れているので「バランスシート」と呼ばれます。
- 損益計算書(PL: Profit and Loss Statement):「会社が1年間でどれだけ儲けたか」を示す成績表です。
- 売上高からさまざまな費用を差し引いて、最終的な利益を計算します。
- 本業の儲けを示す「営業利益」や、会社全体の儲けを示す「経常利益」などがわかります。
- キャッシュフロー計算書(CS: Cash Flow Statement):「会社の現金の流れ」を示します。
- PLが帳簿上の利益であるのに対し、CSは「実際に現金がいつ、どれだけ動いたか」を把握できます。
- 現金の増減が、本業(営業)、投資、資金調達(財務)のどの活動によるものか、3つの区分で示されます。
M&Aの分析では、主に貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)の2つが中心となります。この2つを正しく読み解くことが、企業の真の姿を理解する第一歩です。
まずは動画でBSとPLのアウトラインを知っておきましょう!
いろいろ動画がありますが、貸借対照表の動画は、以下の動画が一番わかりやすいです。超高速解説なのですが、それでも数回見れば頭がすっきりすると思います。
弥生会計はご存じ会計ソフトの会社さんですが、こういう動画はありがたいです。
それと、損益計算書の動画も弥生会計さんの公式より抜粋ですが、具体的な事例がわかりやすく小気味よいテンポですので、これまたわかりやすいです。
貸借対照表のわかりやすい動画
損益計算書のわかりやすい動画
2. 決算書から会社の「体力」と「稼ぐ力」を読み解く
M&Aの対象企業を評価する際、まずは貸借対照表(BS)で会社の「体力」を、損益計算書(PL)で「稼ぐ力」を分析します。
会社の「体力」:財務の安全性を確認する
財務の安全性とは、その会社が倒産するリスクがどれくらいあるかということです。以下の主要な指標を使って分析します。
| 指標名 | 計算式 | 意味 | 目安 |
| 自己資本比率 | 純資産 ÷ 総資産 | 会社の総財産のうち、返済の必要がない自己資金(資本金や利益の蓄積)がどれだけを占めているか。 | 40%以上が安全とされ、高いほど倒産リスクが低い。 |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 | 1年以内に現金化できる資産で、1年以内に返済すべき負債をどれだけまかなえるか。 | 150%以上が目安。200%以上あれば、資金繰りは非常に安全。 |
【具体例で学ぶ分析方法】
以下の架空の会社の貸借対照表を見て、財務の安全性を評価してみましょう。
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
| 流動資産 | 3億1,000万円 | 流動負債 | 8,000万円 |
| 固定資産 | 2億2,000万円 | 固定負債 | 1億4,000万円 |
| 総資産 | 5億3,000万円 | 負債合計 | 2億2,000万円 |
| 純資産 | 3億1,000万円 | ||
| 負債・純資産合計 | 5億3,000万円 |
- 自己資本比率:3億1,000万円 ÷ 5億3,000万円 = 58.5%
- 40%を大きく上回っており、会社の財務基盤は非常に安定していると判断できます。
- 流動比率:3億1,000万円 ÷ 8,000万円 = 387.5%
- 目安の150%を大きく超えており、流動負債を十分に返済できるだけの流動資産を持っているため、資金繰りの心配はほとんどないと言えます。
会社の「稼ぐ力」:収益性を確認する
収益性とは、会社がどれだけ効率的に利益を生み出しているかということです。これは主に損益計算書(PL)から分析します。
- 営業利益:会社の本業で得た利益です。M&Aでは、この営業利益が会社の**「実力」**を測る最も重要な指標となります。
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合で、会社がどれだけ効率よく儲けているかを示します。
【具体例で学ぶ分析方法】
以下の3社の損益計算書を比較してみましょう。
| D社 | E社 | F社 | |
| 売上高 | 20億円 | 10億円 | 2億円 |
| 営業利益 | 1億円 | 1億円 | 2,000万円 |
| 営業利益率 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
- D社とE社は営業利益が同じ1億円ですが、売上高はD社の方が大きいです。これは、E社の方がより少ない売上高で同じ利益を上げていることを意味し、E社の方が収益性が高いと言えます。
- F社は営業利益の額は小さいですが、売上高が少ないにもかかわらず10%という高い営業利益率を維持しています。これは、独自の強みを持つビジネスモデルか、非常に効率的な経営が行われていることを示唆します。
このように、利益の絶対額だけでなく、売上高との比較で「利益率」を分析することが、会社の真の収益性を見抜くカギとなります。
3. 数字の裏に隠された会社の「本当の実力」を明らかにする方法
決算書はあくまで過去の数字であり、M&Aにおける会社の本質的な価値をそのまま示しているわけではありません。決算書には載らない「隠れた価値」や「隠れたリスク」を見つけることが、M&Aを成功させる上で非常に重要です。
この隠された実力を明らかにするために、「正常収益力(正常利益)」と「実質純資産」を算定します。
- 正常収益力(正常利益):会社の「本業の本当の稼ぐ力」を把握するために、決算書の利益を修正して算出します。
- オーナーのプライベート費用:中小企業では、節税のためにオーナーの個人的な費用(高級車の維持費、社長宅の家賃など)を会社の経費としている場合があります。これらはM&A後に削減できるため、費用から除外して考えます。
- 生命保険料:節税目的で加入している保険料も、M&A後に解約できる可能性があります。
- 一時的な損益:災害による損失や、通常は発生しないような多額の修繕費など、臨時的・一時的な項目は、会社の継続的な収益力とは関係がないため、除外して考えます。
【具体例:決算書の利益を修正する】
| 決算書上の利益 | 修正項目 | 正常利益 | |
| 営業利益 | 6,000万円 | ||
| 修正項目 | オーナーのプライベート費用:+1,000万円<br>生命保険料:+600万円<br>大規模修繕費(一時的):+400万円 | ||
| 修正後利益 | 8,000万円 |
この場合、決算書上の営業利益は6,000万円ですが、M&A後に削減できる費用を考慮すると、会社の本当の稼ぐ力は8,000万円と判断できます。この正常利益こそが、M&Aにおける買収価格を算定する上での重要な根拠となります。
- 実質純資産:貸借対照表(BS)に計上されている純資産を、会社の「本当の財産価値」に修正して算出します。
- 土地の含み損益:BS上の土地の価格は、購入した時の金額(簿価)のままです。しかし、時価は変動します。もし簿価2億円の土地の時価が1億円に下がっていた場合、会社の純資産は決算書上の数字よりも1億円少ないと見なすべきです。
- 隠れた負債:従業員の退職金や未払いの給料など、決算書に計上されていない「隠れた負債」がないか確認します。これらは将来的に会社が支払う義務があるため、負債として加算する必要があります。
このように、決算書の数字を鵜呑みにせず、「実態」を反映した「実質純資産」や「正常利益」を把握することが、M&Aで後悔しないための重要なステップとなります。
4. 日々の取引がどう決算書に影響を与えるか?仕訳との関係
会社の財務状況を深く理解するためには、日々の取引がどのように決算書に反映されるかを知っておくことが役立ちます。会計処理の基本である「仕訳」と決算書のつながりを簡単な例で見ていきましょう。
例1:現金を借りる
- 取引:銀行から現金1億円を借り入れました。
- 仕訳:現金(資産)が1億円増え、借入金(負債)も1億円増えます。
- 決算書への影響:BSの現金と負債が同額で増加します。利益は発生しないので、PLや純資産に変動はありません。
例2:建物を購入する
- 取引:現金1億円で建物を購入しました。
- 仕訳:建物(資産)が1億円増え、現金(資産)が1億円減ります。
- 決算書への影響:BSでは、資産の項目内(現金と建物)で金額が移動するだけで、総資産額は変わりません。利益は発生しないため、PLや純資産に影響はありません。
例3:家賃を支払う
- 取引:1年分の家賃120万円を現金で支払いました。
- 仕訳:現金120万円が減り、家賃(費用)120万円が発生します。
- 決算書への影響:PLでは費用が発生するため、利益が減少します。BSでは現金が減少し、利益減少に伴い純資産も減少します。
しかし、もし会社が3月決算で、1月に1年分の家賃を支払った場合、3月末の決算では「今年の1月から3月までの3か月分」だけが費用として計上され、残りの9か月分は来期の費用として繰り延べられます。これを「前払費用」と呼び、BSの資産に計上します。
- 修正仕訳:家賃(費用)90万円が減り、前払費用(資産)90万円が増えます。
- 決算書への影響:PLの費用が減るため、利益が90万円増加します。BSでは前払費用という資産が増加し、利益増加に伴い純資産も増加します。
このように、日々の取引がどのように決算書の数字に反映されているかを知ることは、表面的な数字の裏側にある会社の活動を深く理解することにつながります。
まとめ:決算書から本質的な価値を見抜く
決算書は単なる数字の羅列ではありません。それは会社の財政状態と経営成績を映し出す重要な情報源です。
- 貸借対照表(BS)からは会社の「体力」を、損益計算書(PL)からは「稼ぐ力」を読み取ることができます。
- さらに、決算書には載らない「隠れた費用」や「含み損益」を修正し、会社の「正常収益力」や「実質純資産」を把握することが、M&Aにおける本質的な価値を見極める上で不可欠です。
これらの分析を通じて、M&Aの対象企業が持つ本当の価値を見出し、買収後の成長戦略を描くための確かな情報を得ることができるでしょう。ぜひ、この解説を参考に、決算書を深く読み解く力を身につけてください。
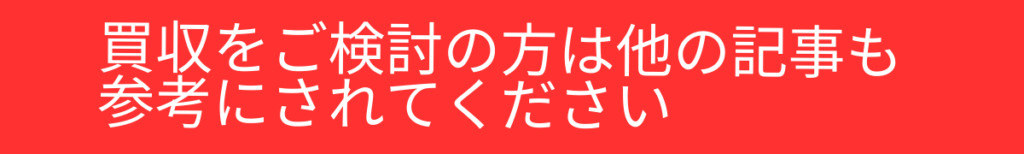
よい物件とのめぐり合い
顧客・従業員(講師)への最初の行動
フランチャイズと独自ブランド
なぜ今、学習塾がおすすめなのか?
見て触れて、深く理解するモデル教室
学習塾・習い事教室の運営は狙い目
学習塾の売上高は月間売上高の16倍
CROSS M&A(クロスM&A)の自信
学習塾とプログラミング教室のM&A
高校生指導ができる学習塾をM&A
60歳からの新しい挑戦!
国立大学最寄り駅の案件は即買い
小学生向け学習塾の料金相場徹底解説
M&A成功のコツ潜在的価値の見極め
【高収益案件を発掘!】小規模学習塾
あなたの既存スキルがM&Aで花開く
千葉県の学習塾買収
習いごとフランチャイズ買収ガイド
個別指導塾M&A成功秘訣と実践ガイド
人が変わると業績が変わる
未経験だからこそ成功率が高い!
簡易株価評価の算定方法(①)
簡易株価評価の算定方法(②)
デューデリジェンス基礎
労務リスクを見抜く専門ガイド
M&Aにおける不動産の基礎知識
保護者との信頼を築く授業報告
学習塾の新しい形:異業種参入歓迎
株式譲渡と事業譲渡、見極めポイント
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略