M&Aの成功を左右する!株式譲渡と事業譲渡、最適なスキームを見極めるポイント
はじめに
M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業の成長戦略や事業承継の有力な選択肢として広く知られています。
M&Aの推移を1985年まで遡ってみてみると、明らかに件数、規模、金額ともに上昇傾向にあります。

↑
こちらのグラフからも増加数が想像つかれると思いますが、日本企業が買い手となる国内外のM&A(合併・買収)は、2025年1~6月で過去最大です。
この時点で、金額は前年同期比3.6倍の2148億ドル(約31兆円)となっており、統計で遡れる1980年以降、半期として最大となりました。
Mergers and Acquisitionsを直訳すると「企業の合併と買収」となります。 一般的にM&Aという場合、「会社もしくは経営権の取得」を意味します。
一昔前は、M&Aと言えば、大企業、中企業だけが行うもので、そのほとんどが株式譲渡でした。しかし、時代とともに、M&Aがより一般的に実施されるようになり、民間、政府どちらも主導で様々な案件がM&Aの対象となってきたのです。
そして、
M&Aを検討する際に多くの経営者が直面するのが、「どのM&A手法(スキーム)を選ぶべきか」 という問題です。
特に、中小企業間のM&Aで頻繁に用いられる 「株式譲渡」 と 「事業譲渡」 は、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持っています。
これらの違いを理解せずに進めると、思わぬリスクを抱えたり、税金面で不利になったりする可能性があります。
本記事では、M&Aアドバイザーの視点から、株式譲渡と事業譲渡の主要な違いを徹底解説します。M&Aの目的から適切なスキームを選択できるよう、それぞれの特徴、手続き、そして見過ごされがちな注意点まで、具体的に掘り下げていきます。
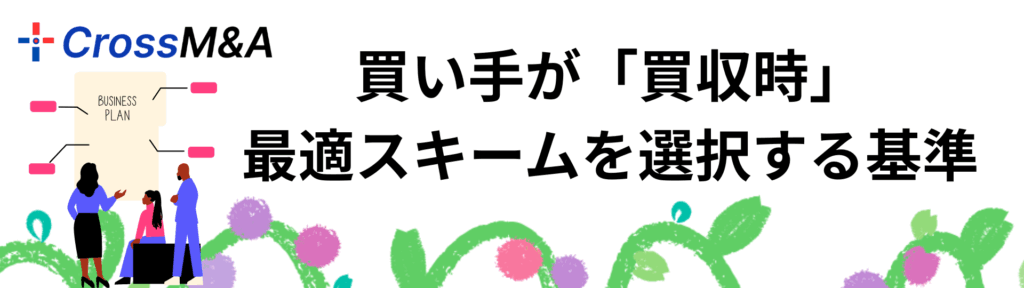
M&A手法の基礎知識:ストック・ディールとアセット・ディール
M&Aの2つの手法である株式譲渡と事業譲渡を少しカッコよく言うと「ストック・ディール」と「アセット・ディール」になります。
ストック・ディール(株式譲渡)
ストック・ディールとは、会社の「株式」を売買するM&A手法です。 売り手である会社の株主が、保有する株式を買い手企業に譲渡することで、会社の経営権が移転します。この取引の当事者は、あくまで「株主」と「買い手企業」です。
【取引のイメージ】
- 売り手: オーナー株主
- 買い手: 買い手企業
- 対象物: 売り手企業(A社)の株式
- 特徴:
- 会社全体がそのまま買い手企業のグループに入ります。
- 取引は株主間で行われ、会社自体は当事者になりません。
アセット・ディール(事業譲渡)
アセット・ディールとは、会社の「特定の事業」や「資産」を売買するM&A手法です。 会社が保有する特定の事業(例:飲食事業、IT事業)に関連する資産(店舗、設備、契約、従業員など)を、個別に買い手企業に譲渡します。この取引の当事者は、「売り手企業」と「買い手企業」です。
【取引のイメージ】
- 売り手: 売り手企業(A社)
- 買い手: 買い手企業
- 対象物: A社の特定の事業
- 特徴:
- 会社全体ではなく、特定の事業のみが切り離されます。
- 取引は会社間で行われます。
この2つの基本的な違いを理解することが、適切なスキーム選択の第一歩となります。
株式譲渡と事業譲渡の話題は、本サイトで何回も登場するのですが、とても大事なことだからです。
日本におけるM&A黎明期においては、株式譲渡(会社をまるごと売る)が主流で、今もM&Aの世界で、トータル的に見れば、株式譲渡が多いです。
しかしながら、売上高が2億円未満案件のいわゆる小規模案件になりますと、事業譲渡の率が高まる傾向で、半々ぐらいになります。
M&Aそのものがもっと日常的に実施されるようになってくると、事業譲渡の率がまた高まってくる可能性があります。
株式譲渡と事業譲渡のメリット・デメリット比較
M&Aの目的や状況に応じて、どちらのスキームが最適かは変わります。ここでは、それぞれのメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。
株式譲渡のメリット
- 手続きがシンプル: 株式譲渡は、譲渡制限株式の場合でも、株主総会や取締役会の承認プロセスを経ることで、比較的短期間で手続きを完了できます。契約締結と同時に決済(クロージング)を行うことも可能で、迅速なM&Aが実現しやすいのが大きな利点です。
- 法的な継続性 :対象となる会社は、法人格をそのまま維持します。そのため、許認可、取引先との契約、雇用関係、資産、負債など、すべての権利義務がそのまま買い手企業に引き継がれます。個別の契約巻き直しや手続きが不要なため、事業の継続性が高く、M&A後の事業運営がスムーズになります。
- 売り手(個人株主)の税負担が有利 :個人株主が株式を譲渡した場合、譲渡益は「申告分離課税」の対象となります。 これは、他の所得(給与所得など)と合算せず、所得税、住民税、復興特別所得税を合わせて約20.315%の固定税率で課税されるというものです。 総合課税で累進税率が適用される他の所得に比べて、税負担が圧倒的に軽くなるため、売り手の手取り額を最大化できる可能性が高いです。
株式譲渡のデメリット
- 簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスク :会社全体を引き継ぐため、貸借対照表(B/S)に計上されていない簿外債務(未払残業代、退職給付引当金など)や、将来的に発生する可能性がある偶発債務(訴訟リスクなど)もそのまま引き継いでしまいます。 買い手企業は、デューデリジェンス(買収監査)を綿密に行い、これらのリスクを事前に洗い出すことが不可欠です。
- 節税メリットが限定的 :買い手企業が取得した株式の取得価額は、資産として計上されます。 事業譲渡のように、取得価額と純資産の差額である「のれん」を税務上の費用(償却費)として損金算入するメリットがないため、買い手側の節税効果は限定的です。
※「のれん」とは?
「のれん」は、企業の営業権やブランドなどの無形資産から成り、M&A時に支払った価格と時価純資産との差額を指します。貸借対照表における勘定科目の一つで、具体的には譲渡企業の純資産(時価)と実際の買収価格の差額を指すことになります。
もっとわかりやすく言いますと、
例えば、ある企業の純資産が1億円の時に、2億円で買収した場合、1億円がのれんとして計上されます。最近の買収事例で有名なところでいうと、
ソフトバンクによる、英国の半導体設計会社ARM買収が挙げられます。
当時のARMの純資産はわずか2500万円だったのに対し、実際の買収額は3兆円に上りました。ARMという会社の持つ高い技術力やブランド力や世界的な顧客ネットワークなどが評価された結果です。
この大きな差額は「のれん」そのものです。
事業譲渡のメリット
- リスクを分離して承継できる :事業譲渡は、個別の資産や負債を特定して引き継ぐため、簿外債務や偶発債務のリスクを承継せずに済みます。買い手は、必要な資産・負債だけを承継し、不要なものを切り離すことが可能です。リスク遮断を優先したい場合に適したスキームと言えます。
- 税務上のメリット :事業譲渡の場合、買い手企業が支払う対価が、引き継ぐ事業の純資産額を上回る部分(いわゆる「のれん」)は、税務上の「のれん」として認識されます。この「のれん」を5年間にわたって損金算入できるため、買い手企業は節税メリットを享受できます。
- 部分的な事業譲渡が可能:会社全体ではなく、特定の事業部門のみを売却したい場合に適しています。複数の事業を営んでいる会社が、コア事業に集中するために不採算事業を売却するといったケースで有効です。
事業譲渡のデメリット
- 手続きが煩雑 :事業譲渡は、個別の資産・負債の移転手続きが必要なため、非常に煩雑です。 取引先との契約を1つずつ巻き直したり、許認可を再取得したり、従業員の雇用契約を結び直したりするなど、多くの手間と時間がかかります。
- 許認可が引き継げない: 事業に許認可が必要な場合、その許認可は法人に帰属するものであるため、事業譲渡では引き継げません。買い手企業は、新たに許認可を取得し直す必要があります。この再取得が難しい、あるいは不可能な業種では、事業譲渡は選択肢から外れることになります。
- 消費税が課税される: 譲渡される資産(事業用資産、営業権など)には消費税が課税されます。 買い手企業は、譲渡対価に加えて消費税を支払う必要があり、一時的に多額の資金が必要になります。
- 従業員の心理的負担 :従業員は、元の会社を退職し、新しい会社で再雇用される形になります。 この手続きは従業員の心理的負担が大きくなる可能性があり、丁寧な説明と配慮が不可欠です。 また、退職金の取り扱いについても、原則として元の会社で清算する必要がありますが、実務上は買い手企業が引き継ぐケースも見られます。
手続き面から見る株式譲渡と事業譲渡の違い
手続きの面でも、両者には大きな違いがあります。
株式譲渡の手続き
- 譲渡承認手続き: ほとんどの会社は、株式に譲渡制限を設けています。そのため、株主総会や取締役会で譲渡の承認を得る必要があります。
- 契約・決済: 手続きがシンプルであるため、契約締結と決済(クロージング)を同日に行うことも可能です。ただし、契約締結から決済までに、一定のクロージング条件(例:主要取引先との契約継続の確認など)を設定し、その条件が満たされた後に最終的な決済を行うケースもあります。
- 重要な子会社の譲渡: 2014年の会社法改正により、親会社が重要な子会社(総資産の5分の1を超える資産を持つ子会社など)を譲渡する場合、親会社の株主総会における特別決議が必要となりました。これは、重要な事業を譲渡する場合に特別決議が必要な事業譲渡とのバランスを取るために導入されたものです。
事業譲渡の手続き
- 株主総会の特別決議: 譲渡対象となる事業が会社の総資産の20%以上を占めるなどの「重要な事業」に該当する場合、株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上が賛成)が必要となります。
- 反対株主の株式買取請求権: 株主総会の特別決議に反対する株主は、会社に対して自身の株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。この手続きを考慮する必要があるため、契約締結から決済までには最短でも1ヶ月程度の期間を要します。
- 個別承継の手続き: 契約の巻き直し、許認可の再取得、従業員との雇用契約再締結など、多岐にわたる手続きが必要です。
まとめ:最適なM&Aスキームの選択
株式譲渡と事業譲渡は、それぞれ一長一短があります。どちらが優れているというわけではなく、M&Aの目的や現状に応じて最適なスキームを見極めることが重要です。
- 迅速さや手続きのシンプルさを優先したい
- 対象会社の事業継続性を重視したい
- 売り手(個人株主)の手取りを最大化したい ⇒ これらに該当する場合は、株式譲渡が第一の選択肢となるでしょう。
- 簿外債務などのリスクを遮断したい
- 特定の事業のみを切り離したい
- 買い手として節税メリットを享受したい ⇒ これらに該当する場合は、事業譲渡が有力な選択肢となります。
M&Aは、税務、法務、労務など、多岐にわたる専門知識が必要です。 専門家であるM&Aアドバイザーは、お客様の目的や状況を深く理解し、それぞれのメリット・デメリットを総合的に判断した上で、最適なスキームを提案します。
ぜひ、M&Aを検討する際は、専門家と相談しながら、成功への道筋を立ててください。
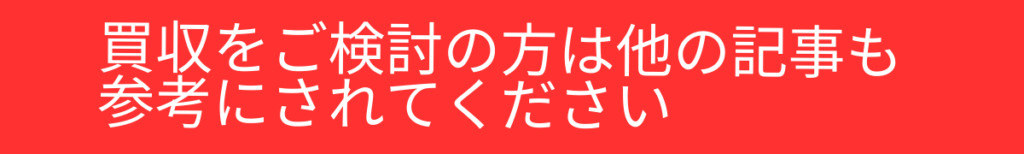
よい物件とのめぐり合い
顧客・従業員(講師)への最初の行動
フランチャイズと独自ブランド
なぜ今、学習塾がおすすめなのか?
見て触れて、深く理解するモデル教室
学習塾・習い事教室の運営は狙い目
学習塾の売上高は月間売上高の16倍
CROSS M&A(クロスM&A)の自信
学習塾とプログラミング教室のM&A
高校生指導ができる学習塾をM&A
60歳からの新しい挑戦!
国立大学最寄り駅の案件は即買い
小学生向け学習塾の料金相場徹底解説
M&A成功のコツ潜在的価値の見極め
【高収益案件を発掘!】小規模学習塾
あなたの既存スキルがM&Aで花開く
千葉県の学習塾買収
習いごとフランチャイズ買収ガイド
個別指導塾M&A成功秘訣と実践ガイド
人が変わると業績が変わる
未経験だからこそ成功率が高い!
簡易株価評価の算定方法(①)
簡易株価評価の算定方法(②)
デューデリジェンス基礎
労務リスクを見抜く専門ガイド
M&Aにおける不動産の基礎知識
保護者との信頼を築く授業報告
【CROSS M&A(クロスマ)からのお知らせ】
当記事をお読みの皆様で、当社の仲介をご利用いただいた学習塾・習いごとの経営者様には、ご希望に応じて無料でメール送信システムの作成をお手伝いいたします。システム作成費も使用料も一切かかりません。
安全かつ効率的な報告体制を構築し、保護者との信頼関係を強化するお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略