学習塾・習いごと経営者必見!男性講師と女性講師、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較
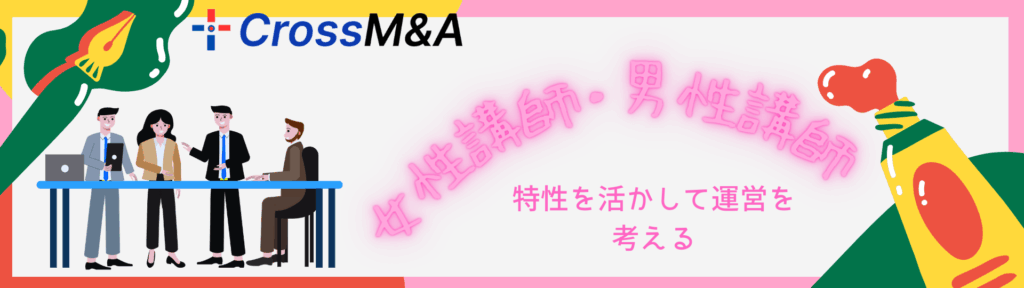
学習塾や習いごと教室を経営する上で、講師の採用は事業の成否を左右する重要な要素です。特に、男性講師と女性講師、それぞれを雇用することには独自のメリットとデメリットが存在します。この記事では、性別ごとの特性を深く掘り下げ、【実例(実話)】を交えながら、あなたの教室に最適な人材を見つけるためのヒントを提供します。
はじめに:なぜ性別で比較するのか?
現代社会において、性別による固定観念は薄れつつありますが、教育の現場では、講師の性別が生徒や保護者との関係構築、そして学習効果に少なからず影響を与えることがあります。
これは、性別そのものの優劣ではなく、社会的な役割や期待、コミュニケーションスタイルの違いから生じるものです。本稿では、あくまで一般的な傾向として、男性講師と女性講師それぞれの特性を分析し、より良い教室運営に役立てていただくことを目的とします。
男性講師を雇用するメリットとデメリット
メリット:リーダーシップと論理的思考力
男性講師の大きな強みの一つは、論理的で体系的な指導です。特に数学や理科といった論理的な思考を要する科目に強みを持つことが多く、複雑な概念をシンプルに分解して教えるのが得意な傾向にあります。
- リーダーシップと安定感: 生徒たちを引っ張っていくリーダーシップを発揮しやすく、特に思春期の男子生徒からの信頼を得やすい傾向があります。また、冷静沈着な対応は、保護者に対しても安心感を与えやすいでしょう。
- 専門性と熱意: 特定の分野に深く没頭し、その専門知識を熱意を持って伝える姿勢は、生徒の知的好奇心を刺激します。趣味や専門分野の話題で生徒との距離を縮め、学習意欲を引き出すことも得意です。
- 長期的な指導体制の構築: 結婚や出産といったライフイベントによる休職が少なく、長期的に安定した指導体制を築きやすい点も大きなメリットです。
デメリット:感情面への配慮とコミュニケーション
一方で、感情面への配慮や細やかなコミュニケーションに課題を抱えることがあります。
- 感情の機微を察する難しさ: 生徒の些細な変化や悩みを見過ごしてしまうなど、感情的なサポートが苦手な場合があります。特に、悩みを抱えやすい女子生徒への対応は慎重さが求められます。
- 威圧感を与えてしまう可能性: 体格や声の大きさから、生徒によっては威圧感を感じてしまうことがあります。特に小学生や内気な生徒には、より丁寧なアプローチが必要です。
- 家庭との連携: 保護者との密なコミュニケーションや、生徒の学習状況を細かく報告するといった業務が、やや苦手な場合があります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】男性講師編
男性I講師は、高校3年で大学進学が決定した後に、面接応募してくれました。文教大学教育学部で将来先生になりたいという希望を持った学生でした。とても誠実そうで、採用テストも優秀でしたので、その日のうちに採用を決定しました。
初回授業を最初は1:1で設定するはずだったのが、1:2設定となり、しかも1コマの予定が3コマ連続の設定になってしまいました。
そうです。当時は人手が相当不足していたときでした。
I講師は、その日から、大学を卒業するまでの4年間、膨大な数の授業をこなしてくれました。通常1年も居れば、少々図々しくなるところが、I講師は一貫して誠実で、一貫して生徒受けが良く、一貫して授業に真剣で、一貫して一度決まったシフトを自己都合で休むことはしませんでした。
このような講師との出会いは、多分10年に一度ぐらいしかないでしょう。
とにかくすごかったです。
推して知るべしです。このI講師が在籍してくれたことによる、塾の経済効果は非常に高かったのは間違いありません。
男性講師で、将来教員希望をされている場合は、経験上4年ラストまで在籍してくれることが多いです。尚且つ、塾の業務をどんどん教えていきリーダー的存在に育成していってもよいでしょう。必ず力になってくれると思います。
女性講師を雇用するメリットとデメリット
メリット:共感力と細やかな気配り
女性講師の最大の強みは、共感力と細やかな気配りです。生徒一人ひとりの心に寄り添い、安心感のある学習環境を提供することに長けています。
共感とは、他人の感情や思考を理解し、まるで自分のことのように感じたり、共有したりする能力のことを指します。同情するだけでなく、相手の立場に立って状況を理解し、感情を共有することで、より深い人間関係を築く上で重要な役割を果たします。
- 高い共感力と安心感: 生徒の悩みや不安を丁寧に聞き出し、共感することで信頼関係を築くのが得意です。特に、思春期の女子生徒にとっては、何でも話せる「お姉さん」のような存在になりやすく、学習だけでなく精神的なサポートも期待できます。
- 細やかな指導とマメな連絡: 生徒の学習進捗やノートの書き方、家庭学習の習慣など、細部にわたって丁寧に指導します。また、教室内部における他の講師とのコミュニケーションもこまめに行い、家庭と教室の連携をスムーズに進められることが多いです。
- 明るく温かい雰囲気作り: 教室全体を明るく、温かい雰囲気に保つのが得意です。学習の場でありながらも、生徒がリラックスして過ごせる空間を作り出します。
デメリット:ライフイベントと指導の厳しさ
一方で、ライフイベントの影響や、指導の厳しさに関する課題も考慮する必要があります。
- 体調不良その他による休み: これは男性講師にも当てはまりますが、比較的当日の急な欠勤が多いのは女性講師です。指導体制の継続性に影響を与えるため、代替講師の確保など、経営者として対策を講じる必要があります。
- 指導の厳しさ: 厳しい指導や叱咤激励が苦手な場合があります。生徒に嫌われることを恐れて、甘い評価や指導になりがちで、結果的に学力向上に繋がらないケースもゼロではありません。
- 感情的な不安定さ: 生徒や保護者との関係性が深まるあまり、感情移入しすぎてしまうことがあります。公平な評価や指導を保つために、プロフェッショナルな距離感を意識することが重要です。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】女性講師編
S講師は、とにかく共感の人でした。女性で理系講師は、そうそうポンポンと採用できるものではありません。東京理科大学の進学が決定し、当方に面接を受けに来てくれたときには、眼鏡をかけていて、いかにも理知的な女性という感じでした。
採用を決定して、少しすると、S講師は色々な生徒から慕われるようになりました。特に女の子の生徒さんからは絶大の信頼を得ていたようです。
ところがある日、S講師が出勤時間になっても来ないことがありました。
スマホが繋がらなかったため、仕方なく自宅へ電話するとS講師のお母様が出られました。
そのとき私は、衝撃の事実を知ったのです。
S講師は「ある病気」で病院通いをしていたのです。その日はものすごく体調が不良で家にはいるけれど出勤できそうにないということでした。
電話をすることも難しいぐらいの状況だったようです。
同日は臨時で講師の入れ替えなどをして対応していきました。その夜、再度S講師のご自宅へ連絡し、お母様と会話しました。病気のことは知らなかったとは言え、
「かえってS講師に負担をかけてしまっていたのではないでしょうか・・・」そうお詫びをしました。
ところがお母様からは予想外のお言葉がありました。
「いえ、塾での仕事は本人とても楽しいと言っています。どちらかというと塾の仕事があるから前を向けていますので、今後ともどうか宜しくお願いいたします」
「も、もちろんです!Sさんはすでに生徒から信頼を多くあつめ、とても人気のある先生です。ですからこれからももし、Sさんとお母様がよろしければ続けてほしいです」
そんなやり取りがあったのです。
Sさんが無事出勤できるようになって以降も、私はSさんの病気については一切触れず、自然にふるまいました。
以降、Sさんは病気のこともあるのに、長く勤務してくれました。S講師が書いてくれる生徒の報告書はいつでも丁寧でした。
生徒一人一人に対してとても真摯に真面目に向き合ってくれているのがよくわかりました。
上に二つ、男性講師、女性講師の実例(実話)を書かせて頂きました。いずれも今でも鮮明に覚えているからこそ、すんなり書くことができました。
今頃どうしているだろう・・・そんな風に思いを馳せたりしますが、きっと元気に頑張っていることでしょう。
大学生の講師は、アルバイト講師です。
アルバイト講師というと、保護者の中には怪訝に思われるかたもいらっしゃいます。社会人講師ではないことに不満を持たれる方も少なからずいらっしゃることでしょう。
しかし、私は堂々とこのように伝えます。
「お母様(お父様)、今の時代、予備校のチューターでも大学生が採用されている時代です。そして、社会人だから優秀、大学生講師だから優秀ではない・・ということは当てはまりません。
かえって、直近の共通テストをパスしてきた今の大学生のほうが採用テストでは高得点を取ります。当方が実施している採用テストは、界隈でも一番難しいテストです。
この内容で高得点をとれる人材は、50人から100人に一人ぐらいです。私どもはそんな講師を採用していますので、ご安心ください」
※実際、これはまやかしではなく本当にそうだからです。
採用戦略:男性と女性、どちらをどう活用すべきか?
結論として、男性講師と女性講師、どちらか一方が優れているということはありません。
重要なのは、それぞれの特性を理解し、教室の目指す方向性やターゲット層に合わせて、適切に配置することです。
1. 教室のターゲット層に合わせる
- 小学生や女子生徒が中心の教室: 女性講師が中心となることで、安心感のある学習環境を提供しやすいでしょう。優しく、きめ細やかな指導を求める保護者からのニーズに応えられます。
- 中学生や高校生、特に理系科目に特化した教室: 論理的思考力や専門性の高い指導を求める場合、男性講師が力を発揮しやすいです。リーダーシップを発揮して、生徒たちの学習意欲を強く引き出すことができます。
- 男女混合のクラス: 男性講師と女性講師をバランス良く配置することで、性別の偏りなく生徒たちの多様なニーズに応えることができます。例えば、男性講師がメインの授業を担当し、女性講師が質問対応やメンタルケアを担当するなど、役割分担を明確にするのも一つの方法です。
2. 指導科目や役割で使い分ける
- 男性講師: 数学、物理、化学、プログラミングなど、論理的思考が求められる科目の指導に最適です。また、進路指導や受験対策など、厳しさや戦略性が求められる場面でも強みを発揮します。
- 女性講師: 国語、社会、英語、芸術系など、感性やコミュニケーション能力が重要となる科目に適しています。また、生徒の学習習慣作りや保護者との連絡、教室の雰囲気作りといった裏方的な役割でも、その強みを発揮します。
さて、上記の1と2では、若干一般論的な見解ですが、講師一人一人にも性格がありますので、男性だから、女性だからというのが一概に当てはまらないこともあるのですが、一応・・・参考程度に以下の実例(実話)をご確認ください。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話)】男女講師どちらを?
採用すべきか・・・ですが、優劣はつけず、運営後にきっとあるであろう「とある現象」から
女性講師の採用を進めたほうが良いです。
「とある現象」とは、女性講師を求める現象ということです。これは特に女の子の生徒さんの保護者が希望してくることが多いです。勿論女の子の全員がそうではなく一部の事例ではありますが、それでも授業を組む際に、女性講師を指定されているのですから、いなければ組めないわけです。
集団塾の場合は、クラスがあって指導する先生は男性であれ女性であれ、そこは集団ですからほぼこの問題は起こりません。
個別指導塾の場合には必ず起こり得ます。
例えば、とある女子生徒Aさんが、女性講師を所望されたとします。Aさんは週2回の授業であれば、月に8回の授業は絶対に女性講師にあてがう必要が出てきます。
もしAさん以外にあと2人、女性講師希望の生徒さんが居れば、24回の授業箇所は女性講師に設定することになります。
組める曜日に女性講師の出勤があればいいですが、
・女性講師の都合が所望されている曜日と合わない
・一人ならまだしも2名、3名と女性講師希望の生徒がいた場合、設定がかなり厳しくなる
こうなります。
2名ぐらい・・3名ぐらい・・・と思いますでしょうか。
実際は曜日、教科、時間の都合が合致する必要がありますので、きっとこのケースであれば女性講師が1名では100%無理です。
たぶん、3名から4名ぐらいの女性講師がいなければ、希望を満たすことは出来ないでしょう。
えは、女性講師を3名確保できるまでにかかる日数は、運がよければ一か月、運が悪いと半年以上かかります。
それぐらい女性講師を採用していくのは難しいのです。
特に・・・女性の理系講師を採用するのは、最難関だと思ってください。
よって、女性を優先して採用したほうが良いのです。繰り返しますが、女性と男性の能力に差はありません。
保護者、生徒が望んでくるケースがあるということです。
「女性講師限定」のケースはあっても「男性講師限定」と言われるケースはありません(少なくとも私は経験がないです)
3. チームとしての相乗効果を狙う
最も理想的なのは、性別の異なる講師たちが互いの強みを活かし、弱みを補い合うチームを築くことです。
- 男性講師の論理的な指導と女性講師のきめ細やかなサポートを組み合わせることで、生徒は学習面でも精神面でも充実した支援を受けることができます。
- 講師会議や研修の場で、互いの指導法や生徒への接し方について意見交換することで、個々のスキルアップにも繋がります。
まとめ
学習塾や習いごと教室において、男性講師と女性講師の採用には、それぞれ独自のメリットとデメリットが存在します。男性講師は論理的な指導力とリーダーシップ、女性講師は共感力ときめ細やかなサポートが強みです。
経営者としては、これらの特性を理解した上で、教室の理念や生徒のニーズに合わせて戦略的に人材を配置することが求められます。性別にこだわらず、個々の講師が持つ多様な才能と個性を最大限に活かすことが、教室の発展に繋がるはずです。
採用活動を通じて、あなたの教室にぴったりの素晴らしい講師と出会えることを願っています。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月31日
なぜ「低単価・多人数」の塾は強いのか?長期繁栄を実現する経営戦略
#リスク分散
#一人当たり単価
#収益構造
#収益構造シミュレーション
#口コミの母数
#塾運営の標準化
#学習塾経営
#授業頻度の法則
#生徒数最大化
#経営の安定化
#講習平均単価

2026年01月19日
2026年1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト!ここから読み取る大学入試の変化
#2026年
#タイムマシン
#ベルサイユのばら
#入試改革
#大学入学共通テスト
#思考力
#探求学習
#文理融合
#新課程入試
#歴史総合

2026年01月13日
私立中学や私立高校で「大学へ直結する、思考型の学習」をテーマに学習カリキュラムを革新的に変更しようとする流れ!
#カリキュラム
#パラダイムシフト
#大学入試改革
#学習塾
#思考型学習
#探求学習
#教育の未来
#私立校
#総合型選抜
#非認知能力