【M&Aの前に必ず確認】労務リスクを見抜く専門ガイド:残業代・社会保険・退職金のチェックリスト
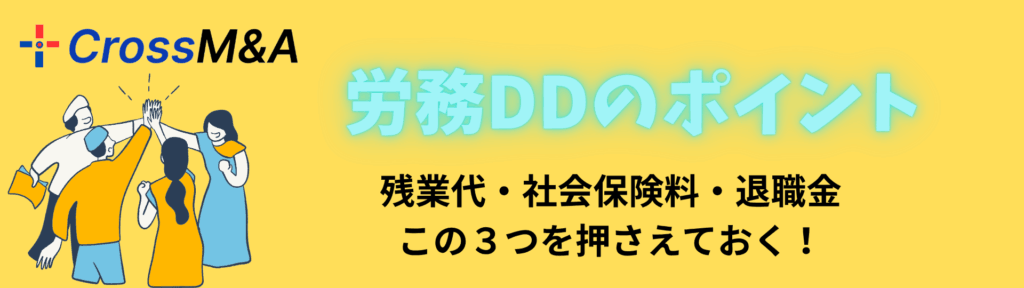
合併や買収(M&A)は、企業にとって大きな変革をもたらすイベントです。しかし、そのプロセスを成功させるためには、財務や事業戦略だけでなく、労務に関する詳細な知識と注意深い準備が不可欠です。
特に、M&A後に残業代の未払い、社会保険の未加入、退職金といった労務問題が発覚すると、予期せぬコストや法的リスクが生じ、事業運営に大きな支障をきたす可能性があります。買収後のトラブルを防ぎ、スムーズな事業統合を実現するために、M&Aにおける労務の基礎知識を解説します。
従業員と役員の違い:M&Aで押さえるべき基本
企業には、大きく分けて従業員と役員が存在します。
M&Aのプロセスでは、両者の違いを正確に理解することが重要です。
| 区分 | 従業員 | 役員 |
| 契約形態 | 雇用契約 | 委任契約 |
| 選任・解任 | 会社との合意に基づき雇用 | 株主総会での選任・解任 |
| 労働法規 | 労働基準法が適用される | 労働基準法は適用されない |
| 報酬 | 給与として支払い、期間の概念がある | 報酬として支払い、期間の概念はない |
| 残業代 | 残業代の支払い対象となる | 残業代の支払い対象とならない |
↑
従業員、役員ともに「契約」があるのだということを理解しておきましょう。
- 従業員は会社と雇用契約を結び、就業規則に基づいて働きます。労働基準法によって保護される立場にあり、正当な理由がなければ簡単に解雇することはできません。
- 役員は株主総会で選任され、会社から経営の委任を受けて働きます。労働基準法の適用外となるため、残業代は発生せず、株主総会の決議によって解任される可能性があります。
この違いを理解せずにM&Aを進めると、特に役員待遇で雇用されている実態が従業員である人物の処遇などで問題が発生することがあります。
就業規則と労働組合の注意点
M&Aでは、対象企業の就業規則の内容を十分に確認する必要があります。従業員数が10人以上の事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
就業規則は、労働時間、休日、賃金など、基本的な労働条件を定めたものです。特に、従業員にとって不利益になるような変更は、原則として従業員の同意がなければ行うことができません。
また、労働組合の存在も確認すべき重要なポイントです。M&Aの手法によっては、労働組合との協議が必要になるケースがあります。
- 企業内組合:通常、M&Aにおいて大きな問題になることは少ないです。
- 外部の労働組合:会社とは別の外部団体に所属する従業員がいる場合、買収後に団体交渉などの対応が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
株式譲渡の場合は、基本的に労働組合への説明義務はありませんが、事業譲渡や会社分割などの手法を用いる場合は、労働組合と協議の場を設ける必要があるため、専門家と相談しながら進めることが重要です。
残業代の未払いリスク:計算方法と法的リスク
M&Aのデューデリジェンス(詳細調査)で最も重要な論点の一つが残業代の未払いです。労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせることはできません。これを超える労働をさせる場合は、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれる時間外労働・休日労働に関する協定を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
残業代の計算方法
残業代は、以下の式で計算されます。
残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間
- 1時間あたりの賃金:基本給と諸手当(役職手当など)を合計した金額を、所定労働時間で割って算出します。ただし、家族手当や通勤手当などは除外します。この計算方法が間違っていると、未払い残業代が発生する原因となります。
- 割増率:労働基準法で定められた割増率を適用します。
| 労働の種類 | 割増率 |
| 時間外労働(法定労働時間超) | 25%以上 |
| 深夜労働(午後10時~午前5時) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
- 時間外労働と深夜労働が重複する場合は、50%以上の割増率を適用します。
また、2023年4月1日からは、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が、中小企業においても50%以上に引き上げられています。この変更にも注意が必要です。
未払い残業代が発覚した場合の対応
未払い残業代が発覚した場合、以下の対応が必要になります。
- 過去3年分(2020年4月1日以降に発生した賃金債権は3年分)の遡及支払い:法律上、残業代の請求権は時効があります。現在は3年に延長されていますが、将来的に5年まで延長される可能性があるため、注意が必要です。
- 遅延利息や罰則金の支払い:支払いが遅れた期間の利息や、悪質な場合は罰則金が科されることがあります。
M&Aにおいては、タイムカードや勤怠管理記録を詳細に確認し、正確な残業代計算が行われているかを調査することが極めて重要です。特に、15分単位で残業時間を切り捨てるような運用は違法となるため、注意が必要です。
働き方改革と社会保険の注意点
M&Aでは、働き方改革によって変更された法制度や、社会保険の加入状況も重要な確認ポイントとなります。
時間外労働の上限規制
働き方改革の一環として、長時間労働是正のため、時間外労働の上限規制が設けられました。
- 原則:月45時間、年360時間
- 特別な事情がある場合:年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内
以前は、労使協定によって上限を超えて労働させることが可能でしたが、現在は法的な上限が設けられています。この上限規制も、2020年4月1日からは中小企業にも適用されたため、買収対象企業が適正な労働時間を遵守しているかを確認する必要があります。
社会保険の未加入リスク
社会保険は、以下の5つから成り立ちます。M&Aの際には、これらの加入状況が適正であるかを確認しなければなりません。
| 保険の種類 | 負担割合 | 備考 |
| 労災保険 | 全額会社負担 | 業務上の災害時に適用 |
| 雇用保険 | 会社と従業員で負担 | 失業手当などに適用 |
| 健康保険 | 労使折半 | 医療費の自己負担を軽減 |
| 介護保険 | 労使折半 | 40歳以上の従業員が対象 |
| 厚生年金保険 | 労使折半 | 老齢年金などに適用 |
- 労働保険(労災保険・雇用保険):原則として法人であれば強制加入です。
- 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険):原則として法人であれば強制加入です。
パート・アルバイトの社会保険加入要件
特に注意が必要なのが、パートやアルバイトの社会保険加入状況です。
正社員は当然社会保険の加入対象ですが、パートタイマーも以下の要件を満たす場合は、加入義務が発生します。
- 所定労働時間・勤務日数が正社員の概ね4分の3以上
さらに、従業員数501名以上の大企業では、この要件がさらに拡大されます。小売業や飲食業など、パート・アルバイトが多い業種では、この加入状況が適正かを必ず確認しましょう。
未加入が発覚した場合の対応
社会保険の未加入が発覚した場合、以下のリスクが生じます。
- 過去3年間の遡及支払い:原則として、会社負担分と従業員負担分の両方を、会社が遡って支払うことになります。従業員に遡及請求するのは困難なケースが多く、実質的に会社が2倍の負担を強いられることが多いです。
- 追徴金の支払い:悪質な場合は、延滞金や追徴金が課せられる可能性があります。
M&Aの財務デューデリジェンスでは、社会保険の未払い分が偶発債務として計上されるかどうかを検討します。確定した債務ではないものの、将来的なコストを正確に把握しておくことが重要です。
退職金制度:M&Aにおける評価と財源
M&Aでは、退職金制度がどのように設計されているか、その財源が確保されているかを確認する必要があります。退職金の未払いも、買収後の大きなトラブルになりかねません。
退職金の財源と種類
中小企業でよく利用される退職金制度には、主に以下の種類があります。
| 制度名 | 概要 | 備考 |
| 中小企業退職金共済(中退共) | 国が運営する外部積立制度。会社が掛金を支払い、退職時に従業員に直接支払われる。 | 従業員300人以下などの加入条件あり。掛金は損金算入可能。 |
| 特定退職金共済(特退共) | 商工会議所などが運営する外部積立制度。 | 中退共との間の資産移管も可能。 |
| 建設業退職金共済(建退共) | 建設業向けの外部積立制度。 | 建設業特有の退職金制度。 |
多くの外部積立制度では、会社が毎月掛金を支払い、退職時にはその制度から直接従業員に退職金が支払われる仕組みになっています。これにより、会社のキャッシュフローに大きな負担をかけることなく、退職金の支払いを計画的に行うことができます。
M&Aにおける退職金の評価
M&Aの評価プロセスでは、退職金の引当金が重要になります。
退職給付引当金:従業員の退職金支払いに備えて、貸借対照表(B/S)に計上される負債項目です。
- 計算式:退職金規定に基づいて計算される総額 – 外部積立制度で積み立てられている金額
この計算式からわかるように、外部積立制度の利用状況によって、会社が将来的に負担すべき金額は大きく変動します。退職金制度が手厚い会社ほど、引当金の金額が大きくなる傾向があるため、買収対象企業の退職金規定や外部積立の状況を詳細に確認することが不可欠です。
まとめ:M&Aを成功させるための労務チェックリスト
M&Aにおける労務は、買収後の事業統合を円滑に進めるための重要な要素です。予期せぬトラブルを避けるために、以下のチェックリストを参考に、デューデリジェンスを徹底的に行いましょう。
- 従業員と役員の区分:雇用契約と委任契約の違いを理解し、実態と法的な位置づけが一致しているかを確認する。
- 就業規則:就業規則の有無、内容、従業員に不利益な変更がないかを確認する。
- 労働組合:企業内組合か外部組合かを確認し、必要に応じて対応を検討する。
- 残業代:
- 36協定が適切に締結・届け出られているか。
- 残業代の計算方法が正しく、未払い残業代がないか。
- 勤怠管理が適正に行われているか。
- 社会保険:
- 社会保険の加入義務がある従業員(特にパート・アルバイト)が適切に加入しているか。
- 社会保険の未払いがないか。
- 一人親方などの外部委託者の実態が労働者と見なされないか。
- 退職金制度:
- 退職金規定の内容を確認する。
- 外部積立制度(中退共など)の加入状況と積立額を確認する。
- 将来的な退職給付引当金の金額を正確に把握する。
これらの労務に関するリスクは、買収価格の調整やM&A後の経営計画に大きな影響を与えます。専門家と連携しながら、これらのリスクを事前に洗い出し、適切な対応を講じることがM&A成功の鍵となるでしょう。
この解説が、M&Aにおける労務の基礎知識を理解する一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。


↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略