簡易株価評価の算定方法(②):M&Aにおける売り手との交渉に役立つ基礎知識
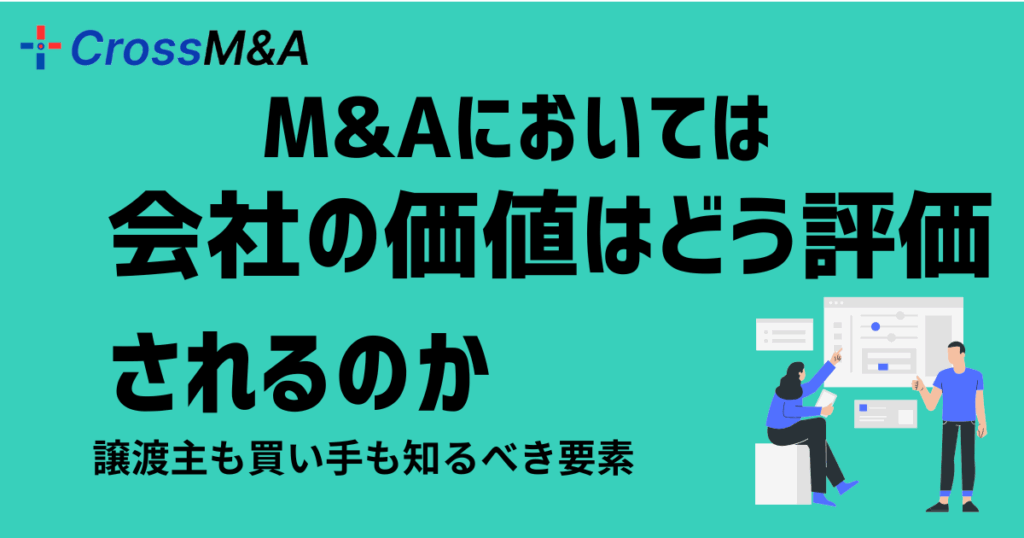
簡易株価評価の算定方法②:営業権(のれん)を考慮した株価評価
M&Aの交渉を円滑に進めるためには、売り手が希望する譲渡額が、客観的な会社の価値と大きくかけ離れていないかを確認することが重要です。
前回は、簡易株価評価の土台となる「実態純資産」の算定方法を解説しました。
しかし、会社の価値は、帳簿に記載された純資産だけでは測れません。
特に中小企業の場合、社長の経営手腕や長年の取引先との関係性、独自の技術力など、目に見えない強みが会社の価値を大きく高めていることがよくあります。
今回は、この目に見えない価値である「営業権(のれん)」を評価に加えることで、より実態に近い会社の株価を算定する方法を解説します。
簡易株価評価のステップ:全体像を把握する
簡易株価評価は、以下の6つのステップで進めていきます。今回は、ステップ4から6までを詳しく見ていきましょう。
- 決算書の確認(特に貸借対照表):会社の帳簿上の資産・負債・純資産を把握します。
- 重要な科目のヒアリング:帳簿上の金額と実際の価値(時価)に乖離がありそうな項目を特定し、詳細な情報を収集します。
- 実態純資産の算定:ヒアリングで得た情報をもとに、帳簿上の純資産を修正し、会社の真の価値である「実態純資産」を計算します。
- 決算書の確認(特に損益計算書):営業権(のれん)の計算に必要な情報を把握します。
- 営業権(のれん)の試算:会社の超過収益力から営業権の金額を計算します。
- 簡易株価評価の算定:実態純資産と営業権を合算し、簡易的な株価を算出します。
この評価方法を使えば、売り手の希望譲渡額の根拠をより客観的に説明できるようになり、買い手との交渉もスムーズに進められるようになります。
ステップ4:営業権(のれん)を試算する
営業権(のれん)とは、会社の「超過収益力」を数値化したものです。
平たく言えば、同業他社よりも多くの利益を生み出す会社の強みやブランド力、ノウハウといった「見えない資産」の価値を意味します。たとえば同業他社よりも優れた従業員の労働の質であったり、他社より優位な取引関係による営業権などがこれに含まれます。
M&Aの世界では、企業の買収価格が実態純資産を上回った場合、その差額が「のれん代」として扱われます。
今回は、こののれん代を逆算する形で、簡易的に営業権を計算してみましょう。
【営業権の計算式】
営業権の計算は、一般的に以下の式で行われます。
営業権 = 超過収益力 × 継続年数
この計算式を分解して解説します。
- 超過収益力
- 継続年数
1. 超過収益力の計算
超過収益力とは、「その会社が持つ強みによって、平均的な企業よりもどれだけ多くの利益を生み出しているか」を示すものです。以下の計算式で求めます。
超過収益力 = 修正後営業利益 - 正常な営業利益
それぞれの項目を見ていきましょう。
① 修正後営業利益
まずは、直近の決算書、特に損益計算書(P/L)を確認し、営業利益を修正します。
損益計算書は、会社の「活動報告書」のようなものです。一定期間の収益と費用を一覧にし、最終的にどれだけの利益が出たのかを示しています。
| 項目 | 金額(円) |
| 売上高 | 20,000,000 |
| 売上原価 | 10,000,000 |
| 売上総利益 | 10,000,000 |
| 販売費および一般管理費 | 8,000,000 |
| 営業利益 | 2,000,000 |
この営業利益には、M&A後に発生しなくなる費用や、会社独自の事情で発生している費用が含まれている場合があります。これらの費用を調整することで、その会社が本来持っている収益力を把握できます。
修正の対象となる費用(販売費および一般管理費)
- 役員報酬:特に中小企業の場合、社長個人の生活費も兼ねて過大な報酬を計上していることがあります。M&A後は、適正な報酬額に修正する必要があります。
- 代表者関連の経費:代表者個人の生命保険料や、自家用車を会社の経費として計上しているケースがあります。
- 福利厚生費:特定の人にのみ適用されている福利厚生費など、事業と直接関係のない費用があれば調整します。
これらの費用を調整することで、より実態に近い営業利益を算出します。
たとえば、営業利益が2,000万円の会社で、社長の過大な報酬が1,000万円含まれていた場合、修正後営業利益は3,000万円になります。
| 項目 | 金額(円) | 修正額(円) | 修正後(円) |
| 営業利益 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 代表者報酬 | +10,000,000 | +10,000,000 | |
| 修正後営業利益 | 30,000,000 |
② 正常な営業利益
正常な営業利益とは、「もしその会社に超過収益力がない場合、どれだけの利益を稼げるか」という、業界平均をベースにした営業利益です。
この計算には、前回算定した実態純資産を使います。
正常な営業利益 = 実態純資産 × 平均的な収益率(%)
平均的な収益率は、同業他社のデータを参考に設定します。ここでは、仮に収益率を**5%**としましょう。
実態純資産が3,700万円の会社の場合、正常な営業利益は以下のように計算できます。
正常な営業利益 = 3,700万円 × 5% = 185万円
この結果から、超過収益力は以下のように計算できます。
超過収益力 = 3,000万円(修正後営業利益) - 185万円(正常な営業利益) = 2,815万円
2. 継続年数
次に、この超過収益力が将来にわたってどれくらいの期間続くかを想定します。
これは一概に言えるものではなく、M&Aにおけるリスクや不確実性を考慮して判断します。
中小企業庁が提示している「事業承継ガイドライン」では、3〜5年程度を目安としています。今回は、一般的な3年で計算してみましょう。
但し、この数値がそれぞれの会社に当てはまるかと言えば、そうではないケースも多いため、計算は少な目にしてもよいでしょう(例えば、1年とか2年)
営業権の試算結果
上記の超過収益力と継続年数を使って、営業権を計算します。
営業権 = 2,815万円 × 3年 = 8,445万円
このように、超過収益力を算出することで、目に見えない会社の価値を具体的な金額として試算できます。
ステップ5:簡易株価評価の算定
ステップ3で計算した実態純資産と、ステップ4で試算した営業権を合算し、簡易的な会社の価値、つまり株価を算出します。
簡易株価評価額 = 実態純資産 + 営業権
前回算定した実態純資産が3,700万円、今回試算した営業権が8,445万円だった場合、簡易株価評価額は以下のようになります。
簡易株価評価額 = 3,700万円 + 8,445万円 = 1億2,145万円
この金額は、あくまで簡易的な評価額です。
しかし、この評価額があれば、売り手アドバイザーは売り手に対して「御社の客観的な価値は、約1億2,145万円です」と説明できるようになります。
ステップ6:譲渡希望額との調整
簡易株価評価額が算出できたら、売り手の譲渡希望額と照らし合わせます。
- 譲渡希望額 > 簡易株価評価額
- 譲渡希望額 ≒ 簡易株価評価額
- 譲渡希望額 < 簡易株価評価額
金額として考えられるケースは以上3つしかありません。
譲渡希望額が簡易株価評価額を大きく上回っている場合、その理由を客観的に検証する必要があります。たとえば、「事業のシナジー効果」や「将来の成長性」など、今回の簡易評価には含まれていない要素があるかもしれません。
一方で、売り手の希望額が市場の平均を大きく上回っている場合、交渉が難航する可能性があります。そのため、売り手アドバイザーは、この評価額をもとに売り手と冷静に話し合い、現実的な譲渡条件を設定できるよう促すことが重要です。
このように、簡易株価評価は、M&Aの初期段階で売り手と買い手の間で認識のずれがないかを確認し、スムーズな交渉の準備をするための強力なツールとなります。
コーナー-1024x154.png)
【実例(実話】
ここでは実例を示していきます。
この手の話は、実は周りにいくらでもあふれています。
・売り手はなるべく高く売りたい
・買い手はなるべく安く買いたい
通常の物品販売でもそうですし、大きなものでいえば、家やマンション、車などもそうです。
当然そうなるのですが、
しかし、「売れた!」ということと「なかなか売れない・・・」ということの違いは大きいです。考えてみたら、同じ品物なのに、金額が上下するので、やはり波はあるのでしょう。
先日、懇意にしている大手不動産会社の営業マンと話をする機会がありました。
「この地区は、去年までは坪単価200万円から240万円、つまり200以上で出ていたのですが、最近は、買い手がちょっと追いついてこない状態になっているんですよ」
最初、この「追いついてこない」という意味がわからなかったのですが、すぐに補足してくれました。
「金額に対して、気持ちがですね・・・」
「なるほど、不動産の世界でもやっぱり需給ですね」
「ええ、そうです。まったく。メディアで見たらどんどん買われている印象ですが、物件一つ、それなりの金額ですから、我々が営業していてわかるのは、なんとなくこの地域はこのぐらいが頭打ち価格だなという部分とかですね、なんか感じるんです」
・
・
・
このシチュエーションは、M&A、譲渡買収の世界でもあります。
そして、こんな事例です。
「〇〇オーナー、この案件、とてもいいと思うのですが、サイト見ると、同様案件が3つ、地域的に通勤圏内と言えるところで出ていて、これを平準化して考えると、オーナーの案件はちょっと高すぎるかもしれません。
ものは考えようなのですが、売れるまでの期間が1か月で済むのと、なかなか売れないで1年かかるのでは、そこで費やす時間的コストと、実際の費用コストを考慮したら、需給の際の部分に近い設定にして買い手がついたほうがいいと思うのです」
こんな提案をして、オーナーが理解納得してくれた経緯があります。
そうです。売れないで、数か月、一年と「いつかきっと現れてくれる買い手」を待つ段階でも家賃とか人件費だとかのコストがかかっているわけですし、希望金額との差異を考えても売れないことのデメリットのほうが圧倒的に大きいことを具体的な計算で理解してくださったのです。
早く決着をつけたい気持ちから出た提案ではなく、オーナーの「売りたい」気持ちを実現するための具体的な策をしっかりと提案したという経緯です。
これ、不動産営業の世界でも同じだと思います。
ある営業マンはこう言います。
「物件が売れるか売れないかは、会社のブランド力じゃないですよ。営業マンの腕です」
彼は、20年以上不動産の仲介をやってきたプロですが、はっきりと営業マンの腕と言いました。そして具体的には、
「物件を売りたい人の本音を、本当の気持ちを聞きだすスキルと、いち早く汲み取って提案する勇気と具体的な提案プランです」
こんな内容でした。
まったく同感です。
売りたい人には何種類かあるのです。
・本気で売りたい!しかもすぐにでも!
・売りたい!なるべく早く!
という売却意向のかなり強い方と
・売れるものなら売れてほしい
・もし買い手がつくなら売ってもいいだろう
・もし売れなくても、まぁいいか
こういう売却意向が実は薄めの方がいます。
それは、オーナー様の気持ちの部分の整理がついているかどうかという点と、実際的なお金の余裕の面です。
まとめ
今回は、前回解説した「実態純資産」に加え、会社の「超過収益力」を数値化した営業権(のれん)を考慮した簡易株価評価の方法を解説しました。
- ステップ4:損益計算書(P/L)から、役員報酬などの修正項目を調整して超過収益力を算出します。
- ステップ5:算出した超過収益力に継続年数を掛け、営業権を試算します。
- ステップ6:実態純資産と営業権を合算することで、より実態に近い簡易的な株価を算定します。
この簡易評価は、M&Aの交渉を円滑に進めるための土台となります。売り手は、自分の会社の価値を客観的に把握でき、買い手は、その価値を根拠とした納得感のある価格で交渉を進められるからです。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。
また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。
学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日
学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト
#2026年
#事業承継
#個別最適化
#入試対策
#公教育補完
#地域コミュニティ
#学習塾
#教育改革
#新時代開幕
#次世代経営

2025年12月26日
AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~
#AI指導
#EdTech
#M&A
#アダプティブラーニング
#コスト削減
#個別最適化
#塾経営
#学習塾
#教育ビジネス
#買収

2025年12月23日
買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い
#M&A
#事業承継
#収益開園
#塾経営
#学習塾買収
#投資回収
#教室運営
#早期収益化
#生徒集客
#経営戦略